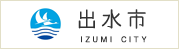令和4年出水市議会第3回定例会会議録第5号
-------------------------------------------------------
令和4年9月13日
-------------------------------------------------------
会議の場所 出水市議会議場
-------------------------------------------------------
出席議員 20名
1番 井 伊 健 一 議員
2番 迫 田 小百美 議員
3番 池 田 幸 弘 議員
4番 田 中 秀 一 議員
5番 宇 都 修 一 議員
6番 江川野 一 成 議員
7番 南 鶴 洋 志 議員
8番 鮎 川 浩 一 議員
9番 上須田 清 議員
10番 日 髙 信 一 議員
11番 北御門 伸 彦 議員
12番 吉 元 勇 議員
13番 土 屋 工 吉 議員
14番 鶴 田 均 議員
15番 田 上 真由美 議員
16番 杉 本 尚 喜 議員
17番 出 水 睦 雄 議員
18番 中 嶋 敏 子 議員
19番 道 上 正 己 議員
20番 髙 崎 正 風 議員
-------------------------------------------------------
地方自治法第121条の規定による出席者
椎 木 伸 一 市長
吉 田 定 男 副市長
冨 田 忍 政策経営部長
山 元 周 作 総務課長
大 田 直 子 財政課長
青 﨑 譲 二 企画政策課長
福 川 正 樹 企画政策課秘書監(係長)
柿 木 彰 保健福祉部長
宮 﨑 毅 市民部長
堂之上 健 二 生活環境課長
松 岡 秀 和 商工観光部長
揚 松 智 幸 農林水産部長
中 村 孝 文 農林水産整備課長
酒 本 祐 喜 農林水産整備課技術主幹兼基盤整備係長
小 原 一 郎 建設部長(水道部長併任)
小 村 郁 則 住宅課長
小田原 豊 道路河川課長
松 尾 善 博 道路河川課管理係長
大久保 哲 志 教育長
溝 口 雄 二 教育部長
住 吉 祐 一 教育総務課長
床 並 伸 治 学校教育課長
松 山 圭 水道課長
岩 本 秀 一 水道課業務係長
岡 本 賢 一 下水道課長
井 山 博 貴 下水道課管理係長
-------------------------------------------------------
議会事務局
春 田 和 彦 局長
華 野 順 一 次長(課長補佐級)
中 村 勇 士 主任主査
野 﨑 育 美 主査
北 紘 至 主査
-------------------------------------------------------
付議した事件
一般質問
午前10時00分 開 議
△ 開 議
○議長(田上真由美議員) おはようございます。ただいまの出席議員は19名であり、定足数に達しております。これより令和4年出水市議会第3回定例会第5日の会議を開きます。
-------------------------------------------------------
△ 議員遅刻の申出
○議長(田上真由美議員) 吉元勇議員から遅刻する旨の届出がありました。
-------------------------------------------------------
△ 議 事
○議長(田上真由美議員) これより議事日程により、議事を進めます。
-------------------------------------------------------
△ 日程第1一般質問 上程
○議長(田上真由美議員) 日程第1、一般質問を議題とします。
昨日に引き続き、一般質問を続行いたします。
質問順に従い、中嶋敏子議員の質問を許します。
○18番(中嶋敏子議員) おはようございます。9月議会、一般質問最終日の1番目の質問者であります。お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。
それでは、早速、通告に従って質問させていただきます。
まず、安倍元首相の「国葬」についてお尋ねいたします。岸田首相は安倍元首相の「国葬」を9月27日に行うことを閣議決定しました。今、多くの国民から疑問や反対の声が上がっています。世論調査でも、日を追うごとに反対が多くなり、9月11日付の地元紙が実施したアンケートでは、「評価できない」とする声が8割超に達したことを報道しています。このような世論には理由があります。1つは、個人の葬儀を国が行う根拠法が存在しないこと。2つ目が、特定の個人の葬儀費用を税金で執行する「国葬」が憲法14条の法の下の平等と19条の思想及び良心の自由を侵害すること。3つ目、安倍氏の政治的な評価が定まっておらず、むしろ、モリカケサクラ疑惑等行政の私物化などに厳しい批判があること。4つ目、加えて、連日報道されている旧統一協会との癒着の中心に安倍氏が存在していたことは、同氏の評価をさらに厳しいものにしています。こうした世論に押される形で、政府は弔意表明を各省庁に求める閣議了解を見送るとともに、地方自治体や教育委員会などへの協力も求めないとしました。
しかし、7月12日に行われた安倍氏の家族葬に当たって、全国で幾つかの教育委員会が弔意を示す半旗の掲揚を学校に求めたと報じられています。この事態は国葬にあたり、行政や学校などを通じて市民に弔意が強要され、基本的人権が侵害されるおそれを抱かせます。この件に関しては、8月29日に申入れをしておりますけれども、次の3項目について市長と教育長の見解をお尋ねいたします。1つ、安倍元首相の国葬に反対し、国に対し中止を求めること。2つ、公共施設や学校現場に半旗の掲揚や弔意を強制する指示や通達等を出さないこと。3つ、市民や市職員及び児童・生徒に弔意の表明を強制しないこと。以上の3項目です。
次に旧統一協会「世界平和統一家庭連合」及びその関連団体等との関係についてお尋ねいたします。連日、旧統一教会及びその関連団体と政治・行政との関係や、その被害の実態が報道され、閣僚はじめ多くの国会議員から地方議員までの関係も次々と明らかになり、政府は、今後は「関係を断つ」と表明せざるを得ない事態になっております。県内の自治体においても関連団体との関係が取りざたされ、行政として過去に後援したものを取り消すなどの対応に追われています。この件に関しても、8月29日、市長と教育長に申入れをしておりますけれども、本市と旧統一教会とその関連団体との関係について、次の3項目について、市長と教育長にお尋ねいたします。1つ、本市と旧統一教会「世界平和統一家庭連合」とその関連団体との関係はないか、あればその内容について明らかにしていただきたい。寄附金の受け取りや支出及び事業や催しに対する後援の有無なども含めて、お願いします。2つ目、旧統一協会とその関係団体とは、一切関係を持たないでいただきたいと考えますが見解を求めます。3つ、旧統一協会とその関連団体からの被害はないか市民に呼びかけるとともに、相談窓口を設けていただきたいと考えますが、答弁を求めます。
次に大きな3項目、教育問題について教育長にお伺いいたします。
まず1つ目、「小学校1年生、体重20キロの体重に5キロを超える重いランドセル。猛暑の炎天下の登下校、肩こりを訴える子供の負担を軽くできないか。」こうした保護者の訴えをどう受け止めておられるか、その認識と対策についてお伺いいたします。
2つ目、学校現場でのフッ化物洗ロの導入についてお伺いいたします。令和元年第3回定例会で、橋口住眞前議員がこの件で質問されています。その中で当時の溝口教育長が「今年度、」令和元年度のことかと思いますが、「出水市では、県から委託された「フッ化物洗口検討会」を実施している」と答弁されています。この検討会議の結果と今後の取組についてお伺いいたします。学校現場における集団フッ素洗口については、安全性、有効性、使用薬剤の安全管理体制等、幾つもの問題点が指摘されています。当時の答弁では、「児童・生徒の安全面を最重要視しながら、慎重に検討を重ねていきたいと考えている。」とされています。現時点ではどうなのでしょうか。実施の方向で検討されようとしているとすれば、中止も含めた慎重な対応を求めたいと考えますが、教育長の見解をお聞かせください。
次に、中2女子生徒自死事件についてお伺いいたします。独立行政法人日本スポーツ振興センターは、中村真弥香さんの自死は「学校の管理下において発生した事件に起因する死亡に該当する」と認め、死亡見舞金の支給を決定しました。この決定をどう受け止めておられるか、教育長の認識と見解をお伺いいたします。この決定や昨年、遺族との和解に際して、鹿児島地裁が提示した和解条項に照らした時、仮に、今、同じような事件が起こったとしたら、従前どおりの対応ではよくないと確認、認識する必要があると考えます。今後の対応についてお伺いいたします。
次に大きな4項目め、市営住宅の住環境の改善対策についてお伺いいたします。私は、毎年、市営住宅のアンケートを独自に実施しております。毎回、たくさんの要望が寄せられますが、今回は市内21の住宅・団地から切実な要望が幾つも寄せられています。特に、今回は生け垣や側溝、雑草処理など外回りの環境改善対策を中心にお伺いいたします。以上で、登壇しての1回目の質問を終わります。
○椎木伸一市長 おはようございます。中嶋敏子議員の御質問にお答えいたします。
まず、国葬については、政府が実施について閣議決定したものでありまして、私が意見を述べる立場にはないところでございます。また、黙禱や弔旗の掲揚といった弔意の表明につきましても、政府は、中嶋議員が御披瀝のとおり、地方公共団体や教育委員会に対し、協力の要望を行う予定はないとしているところであります。
また、世界平和統一家庭連合及びその関連団体との関係についてでありますが、本市では行事の後援等は確認されておりません。なお、中嶋議員から8月29日付で申入れのあった件につきましては、現在検討中であります。
次に、市営住宅の住環境の改善対策についてお答えいたします。市営住宅につきましては、1階の植栽帯・垣根等を含めた入居されている部分や、通路、公園等の共用部分についても、清掃や除草等の日常管理につきましては、入居者で行っていただいております。ただし、専門業者に依頼しなければならないような補修や危険を伴うような高い木の剪定や空き部屋の外回り等につきましては、市で業者に委託して行っております。各団地では、公園などの共用部分については、共同で作業をされたり、共益費を集めて業者に委託されるなどの管理をしていただいています。
1階の垣根などで、管理が不十分なところもあるようですが、今後は、住宅管理人等にも協力をいただきながら、巡回等により状況を把握し、市が管理する部分は計画的に業者に委託し、入居者が管理する部分につきましては、清掃や剪定などを働きかけ、適時適切な管理に努めてまいります。
○大久保哲志教育長 中嶋敏子議員の御質問にお答えします。
安倍元総理の国葬と、世界平和統一家庭連合及びその関連団体との関係については、先ほど市長が答弁したとおりでございます。
次に、登下校時の児童の負担を軽くできないかについてでございますけれども、教科書がカラー刷りでサイズも大きくなり、ページ数も増え、併せて教科数や教材も増えていることから、登下校時の負担が大きくなっていることについては認識しております。
児童の負担軽減については、教科書やその他の教材、体育用品等が過重になることで、身体の健やかな発達に影響が生じかねないことなどから、平成30年9月に文部科学省から「児童生徒の携行品に係る配慮について」の事務連絡がありました。
本市では各学校に「保護者等とも連携し、児童・生徒の携行品の重さや量について改めて検討の上、必要に応じ適切な配慮を講じるよう」指導し、家庭学習で使用する予定のない教材を机の中などに置いて帰ることや、学校で栽培した植物等を持ち帰る場合、児童の状況等を踏まえ、保護者が学校に取りに来ることとしました。
今後も、教科書やその他教材等のうち、何を児童・生徒に持ち帰らせるか、また、何を学校に置くこととするかについて、保護者と連携し児童・生徒の発達段階や学習上の必要性、通学上の負担等を踏まえた配慮を講じていきたいと考えています。
次にフッ化物洗口についてですが、令和元年度に2回、「地域フッ化物洗口推進検討会」を実施し、本市の保育園や幼稚園における実施状況の説明や導入する際の学校での取組について協議を行いました。令和2年度以降も引き続き検討することとなっていましたが、コロナ感染症拡大のため、検討会の実施を見送っているところです。
フッ化物洗口については、WHO世界保健機関のほか、我が国でも厚生労働省や日本口腔衛生学会、日本歯科医師会等が一致して、科学的・学術的に虫歯予防の効果が高く、かつ安全であるとし、その取組を推奨しています。しかし、導入にあたっては、薬剤の取扱いや保管、洗口液の調剤や実施に向けた周知等の課題もあることから、今後、コロナ感染症の拡大状況を見ながら、検討していきたいと考えています。
次に、独立行政法人日本スポーツ振興センターの決定についてですが、今回の死亡見舞金の支給に関しては、独立行政法人日本スポーツ振興センターが決定したことであり、特に見解を申し上げることはありません。
次に、今後の対応についてですが、和解調書のとおりであり、和解が成立していることから、回答はできません。
○議長(田上真由美議員) 中嶋敏子議員より、書画カメラの使用について申入れがありましたので、許可しております。
○18番(中嶋敏子議員) 国葬問題ですけれども、教育長は市長と同じだとおっしゃったんですが、申入れに対しては何とおっしゃったかな。「現在検討中」とおっしゃったわけですけれども、それは弔意の表明とか教育委員会に対するいろんな指示とか、そういうことについて今、検討していらっしゃるということとして受け止めてよろしいですか。
○椎木伸一市長 中身全体について検討中ということで、個々具体については申し上げられません。
○18番(中嶋敏子議員) この前、県内の状況で塩田知事は8月26日の定例記者会見で県独自で弔意を一般県民に求めることはしないと。県教育委員会も各市町村や県立学校に要請しておらず、事務局も実施予定はないと報道されております。県内43市町村と教育委員会に対する地元紙の聞き取りによれば、弔意掲揚や黙禱について、いずれも「未定」とか「予定なし」とか、「県から要請がなく検討していない」とかと回答されているようです。実施を決めているところはないようなんですけれども、出水市は答えられないという回答でありますけれども、南さつま市教育委員会だけは、要請があっても実施しない方針と報じておるようであります。
教育長も市長と同じ立場かなとおっしゃったんですけれども、もう1回、教育長の言葉で答弁いただきたいと思いますが。
○大久保哲志教育長 先ほど、市長がるる話をされたとおりということでございます。
○18番(中嶋敏子議員) 答弁ができないという答弁なんでしょうかね。
政府でさえ、今回は世論が沸騰してきているということもあって、最初に岸田首相が決められたのが、亡くなられた明くる日か明くる日ぐらいですかね。国民の皆さんが突然のああいう死に方に対してショックを受けた行動を起こされていたので、それをちょっと読み間違われたのではないかなという気もするんですけれども、何しろ、国会での議論、三権あるのに閣議決定でできるんだというのを、この前の説明会でもおっしゃったわけですけれども、国民の皆さんは、それは納得されていないと思うんですよね。だから、やっぱり反対意見のほうが強くなってきているんじゃないかなと思うわけですけれども、法的な根拠がないまま国の予算を出すということについて、いろいろ異論が出てきているんだと思うんですけれども、この時点で決めるのは国だといえばそうなんですけど、市長も教育長もそういう事態を受けての市としての対応というのについては、国待ちなのか、県待ちなのか、自分のところでは決めかねているということなんでしょうか。もう1回、御答弁をお願いします。
○椎木伸一市長 そもそも国葬につきましては、国が決定するべきものでございますので、私どもがどうこうというコメントを出すことはできません。議員も御紹介されたように、地方自治体あるいは教育委員会に対しての要請もございませんし、文科大臣、そして総務大臣の記者会見を聞いておりましても、そのようなことでございますので、要請はないものと判断しております。
○18番(中嶋敏子議員) このままいかれると、やっぱり後世にいろんな汚点を残すのではないかと考えます。今からでも遅くはないので、中止をされるか、あるいは少なくとも内閣葬等、自民党葬にされるのかですね、そういう対応をされたほうが賢明ではないかなと思うところですけれども、統一教会との間では関係はないということでありましたので、市民の皆さんから何か相談を持ちかけられたときには、しかるべき対応をしていただければと思います。
それでは、次の質問に入ります。ランドセルの問題ですけれども、書画カメラの1番をお願いしてよろしいですか。(議場内ディスプレーへの資料表示)教科書に副教材、タブレット、体操服、水筒、図書館から借りた本、これが通常日のランドセルの中身ですね。今、映していただいたのは、9月1日の始業式の日の小学1年生のある学校の「持って来てくださいよ」と言われた中身なんですけれども、初日ですので、いろいろな持ち物がたくさんあるのかなと思うんですけれども、これだけの物を保護者の皆さんもそろえるのも大変ではないかなと思ったことでしたけれども、たくさんの中身を背負わされているということかと思います。昨日でしたか、宇都議員のほうも同様の質問をされました。このことでは、特に低学年を持つ祖父母の皆さんからも、「肩こりで整骨院に連れて行った」とかですね、そういう声も寄せられております。相談した母親も、昨日の宇都議員と同じようなことを言っておられましたけれども、通学距離が3キロ以上ある地域からの通学は、まるで強制労働だと。20キロの体重で5キロの荷物というのは、45キロの体重の大人であれば12.5キロの荷物を持って3キロ歩けと言われているのと一緒だと。だから、ここではある日、バランスを崩して、子供さんが前のめりに転んだんだそうですね。大体、重いから後ろに転ぶというのが普通なのかな。そうしたらかばんがクッション材になるから、体をカバーをしてくれるのかなというのが一般論としてはあるんだけれども、何かお家の階段を下りるときに、バランスを崩して前から落ちたんだそうですね。自宅の近くだったからお母さんがすぐに気づいて、対応できたからよかったんだけれども、前のめりというのは想定していなかったので、びっくりしたと。この母親が子供さんに、「先生に相談してみる」と言ったところが、子供は「絶対、駄目と言うから言わないで」と言って、止めたというんですよね。教育長は先ほど、現場といろいろ相談しながらしているんだと言うけれども、現場は一人一人の子供さんにそういう対応をするというのは、なかなか難しいのかなというのも考えますけど、のっけから、子供さんは「駄目と言われるから、お母さん、言わないで」ということを言ったんだそうです。
猛暑の中で、いろんな方がこの登下校中は目が届きにくい通学路で、体調を崩す子供さんもいるので、保護者からの心配の声が上がっていると。行きがけは送っていくという方も結構、何人か聞くんですけど、下校時は大体一人で帰るというのが、ちょうど暑い時間ですよね。そこに、この重い荷物を背負って、熱中症なども心配じゃないかと思うんです。この対策のためにも、この重いランドセル対策というのは重要じゃないかなと思いますけど、教育長のお考えをもう一回お聞かせください。
○大久保哲志教育長 この児童の荷物が非常に重たいというのは、先ほど私も認識していると申しましたように、これは本市だけの問題ではなくて、学習指導要領で教科数が増えたり、あるいは資料集がカラー刷りになって紙質が良くなったもんですから、それで1冊当たりの重さが増えたりとか、そういったことで全国的に今話題になっていまして、昨日提案があったさんぽセルというんですか、そういった工夫もなされたりとか、様々しているというようなこともあって、学校ではそれぞれ課題として捉えてはおります。
今、個別の案件についてはということでしたけれども、やはり小学校の低学年においては、特にまだ成長段階の初期段階でしょうから、極端に重たい物を持って行くのは負担が非常に大きいというのは十分に分かりますので、そういったことについても、また改めて先ほど答弁しましたように、保護者の方々とも連携しながら、重さであったりあるいは必要な配慮を講じるということをしていきたいと感じています。
○18番(中嶋敏子議員) 先日の全国紙が1面でこのランドセル論争を書いていた記事があったんですね。ランドセルの必要性についての議論もあったんですけれども、重い中身について多くの方の意見が掲載されていたんです。その中の一部を紹介しますと、「とにかくランドセルが重い。教科書を学校に置いてきてもいいように先生にお願いしてみるから、と言っても、子供たちは駄目と言われるからと答える」と。一緒なんですよ、やっぱり。「置き勉が許されない」「教師の命令に従順な子供たちは自らを守る術を知らない」と。小学校の近くに住んでいると、体格の小さい下級生は後ろから見ていると、ランドセルが歩いているように見える。さらに、いろいろな下げ袋も一緒にぶら下げており、車に引っかけそうで危なくて見ておれない。時代はペーパーレスなので、ペンケースとタブレットだけ持って通学できるようにすべきだと。また、子供たちが体に負荷をかけることなく通学できる社会にすることが、大人の務めではないかと。体一つで通えてこそ、公教育。でも今は学校に置き場がないと。宿題もたくさん出るので、教材を毎日持ち運びしないといけない。詰め込まれる教材、子供たちの時間の中にもっと余白が必要なのでは。置き勉を認めさせるためには、そもそも教室に置くスペースがあるのかと。1学級の人数を減らさないと難しい学校もあるのではないかとか、ランドセル論争が思いがけず公教育の奥深い議論を巻き起こしておりますけれども、こうした声はどこにでも共通してあると思うんですね。教室にスペースがないとか、そういう問題も含めて、今現実はどうなのでしょうか、お聞かせください。
○大久保哲志教育長 まず、先ほど「置き勉」という言葉がありましたけど、学校に教材、教科書等を置いてはいけないという話ですけれども、これはもともと教科書でありましたり、その他教材等というのは、先ほど話がありました宿題、あるいは予習・復習など家庭での学習課題を適切に課すなど、家庭学習を視野に入れた上で指導をしていくということは重要であると、そういったことから必ず持ち帰るようにと指導がなされていたわけでございます。しかしながら、先ほど答弁の中でも申しましたように、今、文部科学省からも身体の健やかな発達に影響が生じかねないとかこういったことで、実際事務連絡も出ておりまして、実際に学校のほうでもこういった対策は具体的に取り組んでいるのがありまして、例えば、毎日持って帰らないといけないものでないもの、例えば、道徳が教科となりましたけれども、道徳の教科書等は1週間に1回しか授業がないので、しかも自宅学習は必要ないということで、棚の所に置いて、それを使って授業をするというのもあったり、あるいは荷物が多くならないような時間割で工夫するとか、あるいは荷物が多いときには保護者と一緒に持って来ていただくとか、出水市であれば家読の日というのがあって、読む本がかなり重たいですので、それを持ち帰る日には宿題を出さないようにしているとか、こういった個別の取組を出水市の学校がそれぞれ実情に応じてやっているという状況でございます。
それから、先ほど学校に置くスペースがあるのかという質問がありましたけれども、これも実際の例でございますが、例えば後ろにあるかばん棚の上にケースをずっと並べて、その中に特に持ち帰る必要がないものは入れて、保管してという学校があったり、あるいは教卓前のほうにある棚を使って、先ほど申したように毎日持って帰らなくていいような教材等は置いておくとか、そういった学校も実際にあります。
○18番(中嶋敏子議員) じゃあ、教室のスペースについては特別気を使わなくてもよろしいということで理解してよろしいでしょうかね。
○大久保哲志教育長 全ての学校がそうだといったわけではなくて、そのような例もあるというのでありまして、今、出水市の学校が全て教室のほうに余裕があって、置くスペースがあると申し上げたわけではございません。学校の実情によっては、例えば1つの教室にマックス40人入っているわけです。これに特別支援学級に配置されている児童が帰ってきた場合は、それを超える場合もあったりすると、大分教室が狭くなる場合もありますので、そういった場合にはまた別な方法を考えないといけないと思うんですけども、学校の実情に応じて、そういったものを考えていくというようなことでございます。
○18番(中嶋敏子議員) そういう学校については、生徒さんの数も多くて、また問題も多いかなと思いますので、ぜひ、また対策を別途考えていただければと思います。
熱中症対策で日傘は有効だよということで、日傘はいいということになっていますけどね、その上に日傘まで差すというのは、なかなか大変ですよね。でも、日傘は選択だとしても、雨の日はどうしても傘も差さないといけない。だから、やっぱり特に低学年で心配される方も多いかなと思います。私が相談を受けた江内の方からの相談については、3キロ以上の道のりでしたけれど、1回歩いてみようかなと思ったけど、そこまで私もしきりませんでしたけど、車ででしたけれども何回か往復してみたんですね。そうしたら急な坂道があったりとか、人家のない暗い林道みたいな道、道を間違ったのかなというくらいの所もあったりしてですね、小さな子供さんには危険もちょっと付きまとうんじゃないかなということを危惧したんですね。外国はスクールバスが当たり前になっているという、今幼稚園のバス通園のことでいろいろ問題にはなっておりますけれども、登下校中に暴漢に襲われる事件が起きたときに、ちょっと導入をどうかということを申し上げたこともあったんですけれども、場所によっては今後検討課題の一つになるのではないかなと思ったんですけど、いかがでしょうか。
○大久保哲志教育長 今おっしゃったのは、距離が長いときに、どうやって登校するかということでよろしいですか。
今、実際に登下校の様子を見てみますと、もちろん歩いて登校する子供もいますし、家庭の事情で仕事に行く途中に車に乗せて、途中で降ろしている例というのも実際にありますし、そこ辺りは発達段階に応じて、家庭で配慮をしていただいているのは、特にそれを禁じていることはないと思います。ただ、やはり送り迎えが非常に多くて、学校の周辺の交通の状態がよくなくて、警察のほうから指導を受けたりとか、昨日、この話の中でもちょっとありましたけれども、やっぱり子供たちは歩いて体を鍛えているんだというような子供も当然いますので、そこは発達段階に応じて歩く距離であったり、それから重さ、そういったものを考えていかないといけないのかなと考えております。
○18番(中嶋敏子議員) 体を鍛えるというのは昔の軍隊方式みたいな感じでね、今は暑さの程度も違うので、そこはちょっといかがなものかなと思うところです。
いろいろと、このランドセル問題からいろいろな課題が見えてきておりますので、学校現場の状況をぜひ見ながら、実効性のある対策をですね、子供たちが「先生に言っても無駄だよ、お母さん言わないで」と、そういうことがないように、ぜひ学校の現場で、先生方も大変かもしれませんけれども、手を打っていただければと思います。
次ですけれども、学校現場における集団フッ素洗口問題ですけれども、先ほどの教育長の答弁では、検討会議が2回でしたか、開かれて、そしてそのときにコロナが出てきて。
そのようなことで、今のところ実施を見送っているというか、検討しているという状況だということでしょうか。実施はしたいと、実施はする方向で検討はしていらっしゃるんだと。私も学校薬剤師をしているもんですから、学校薬剤師の先生方にも協力していただいて、現場の声を集めたりもしたんですけれども、現場は今はコロナで大変で、人手も足りずに、今は教師の成り手もいなかったりですね、長時間労働が問題になってきている現場に、またこの問題が持ち込まれると、お薬の管理、大体お薬自体は劇薬ですので、それを管理したり調整したりですね、一人一人子供さんが飲み込まないように最後まで見届けないといけなかったりとか、うがいをした後30分は水も飲んだらいけないとか、そういう管理まですると、子供の昼食時間がもっと短くなるし、先生方の負担ももっと重くなってくると。そういう声がうちの薬剤師の先生方からも何人も寄せられたんですね。だから、それでもモデル校を作って取り組んでいかれるのではないかという声もちょっと聞こえたもんですから、そこら辺について教育長、どうなのか。見解を聞かせてください。
○大久保哲志教育長 先ほど答弁の中でお話をしましたように、令和元年度に2回実施したわけですけど、まだ具体的に、その時点で、こういう形で進めていく、というところまで進んだわけではございませんので、これから実施をどのような形でできるのか、そういったことも含めて検討していくという意味で、まだ現段階でこのような形でやっていくというのを検討ができているということではございません。
○18番(中嶋敏子議員) 県の依頼で検討会議を開いたというのも、前の溝口教育長のときにあったんですけれども、県としてはこれを進めていってほしいというふうな要請がといいますか、そういう方向が示されているのでしょうか。
○大久保哲志教育長 昨年、今年、2年間の中でそういった文書が来たということは記憶しておりませんけれども、このフッ化物の洗口につきましては、取組の背景が私もいろいろ調べてみますと、国の自分の歯を大事にして、健康な生活を送るとか、そういった意味からの推進であったり、あるいは1回虫歯になれば、元にはもう戻らないという状況で、虫歯予防の取組は日本は非常に遅れていると、そういったこと。それから鹿児島県が全国と比較すると、この虫歯の状況は非常に悪いという、そういったことから鹿児島県としても少しずつフッ化物洗口に取り組むところは増えてきていると理解しています。
○椎木伸一市長 先ほど、県からの要請があったのかという話でございましたけれども、私が記憶している中では、令和元年だったと思いますけれども、県からではなくてですね、私ども地域の中で医師会、薬剤師会、それから歯科医師会、3師会の方々と意見交換をする地域医療の協議会がございます。その中で、先ほど教育長が答弁いたしましたように、フッ化物洗口につきましてはWHOの世界保健機関、あるいは我が国の厚生労働省とか日本口腔衛生学会、日本歯科医師会等が一致して、非常に効果が高くかつ安全であるということが推奨されているんだというようなことでしたので、教育委員会のほうでもいろいろ課題があるというようなことで、課題は先ほど議員がおっしゃったような薬の保管であるとかですね、あるいは調剤を誰がやるのかとか、いろいろ具体になればありますので、そういう具体的なことを協議しながら進めてまいりましょうということを、その協議会の中で協議した覚えがございます。そのあと、教育委員会のほうで先ほどありましたような検討をしておりましたが、コロナの関係でなかなか進んでいないというのが実情だと認識しております。
○18番(中嶋敏子議員) 県のほうに、うちの県議を通してちょっと確認したんですけれども、県のほうとしては現時点では特別推進の方向は示しておりませんと。県内でどれぐらいの自治体が取り組まれていますかと聞いたら、43自治体中で12自治体だと。そこはどこかというのは言えません、という回答をいただいております。
薬剤師会のほうは、歯科医の先生から指示書が来れば、薬を一応置いておいて、ミラノールというお薬なんですけれども、それを置いておいて、必要があったらあっせんするということで、備蓄センターのほうに備蓄はしております。だけど、事務局に聞いてみたら、令和元年度に1包か2包、1包100円か150円だそうですけれども、出ただけで、そのあとはもう来ていませんと、そういう回答でした。薬剤師会は特別推進をするということではないのかなというふうに思っています。先ほど、WHOの話もされましたけど、WHOは6歳以下の児童にはフッ素を使うなという指示を出しているようですけれども、それは御存じなかったでしょうか。
○大久保哲志教育長 今おっしゃったWHOが6歳未満の就学前の児童にフッ化物洗口を推奨されないという、その一文があるという話ですけれども、これはWHOのテクニカルレポートという中に、そういうものがあるというのは存じ上げております。これにつきましては、日本歯科医師会の見解によりますと、この一文が6歳未満の幼児が洗口液の全量を毎回飲み込むと仮定し、特に他のフッ化物である虫歯予防のための水道水のフッ化物濃度を適正にコントロールして、供給する方法、いわゆる水道水フロリレーションやフッ化物錠剤、他のフッ化物サプリメントなどを複合して使用した場合には容認できないとしており、水道水のフロリレーションやサプリメント等の全身応用は、現在我が国では存在せず、我が国の実態からかけ離れたものであるというふうに報告しているというのは聞いております。
○18番(中嶋敏子議員) フッ素についての否定的な見解をほとんどおっしゃらないんですけれども、私も薬剤師の端くれでございますから、いろいろと資料を取り寄せたり、勉強もしたりとかしているところですけど、WHOは1994年に6歳以下の子供へのフッ素洗口は強く禁止するという見解を出しているようであります。スウェーデン、ドイツ、オランダなどではフッ素の使用を禁止したと。フッ素予防の発祥地であるアメリカでも1990年代半ばからフッ素の人体に対する毒性だけでなく、環境に及ぼす影響も含めて議論が起こって、大きく方向転換をし始めていると、そういうふうな流れに、今なってきております。
今、日本消費者連盟等が学校での強制的なフッ素洗口等を推進しないよう厚労大臣宛てに要望書を提出しているとかですね。今、スーパーに行っても、私も昨日、ここちょっとガムを仕入れてきたんですけど、これには全部フッ化物添加、フッ素配合というのはみんな載っているんですね。だから、ほとんど家庭のほうではこういうものを使ってやっておられるわけで、家庭がさっき言ったように指示書を持って相談に来られる分については否定はしませんけれども、学校でやるということになるとちょっと問題が違ってくるんじゃないかと思うんですね。日本弁護士連合会も、市民団体等から虫歯予防のための集団フッ素洗口塗布の中止を求める人権救済の申立てを受けて調査検討をした結果、医薬品・化学物質に関する予防原則及び基本的人権の尊重を踏まえ、厚労省、文科省、各地方自治体及び各学校等の長に対して、学校等で集団的に実施されているフッ素洗口塗布の中止を求める意見書を2011年、平成23年1月に提出したというふうになっておりまして。90ページぐらいの資料なんです。これ、非常に逆の立場で勉強にもなるかなと思いますので、教育長、もし機会があれば読んでいただければと思います。
危険な問題としても、いろいろと指摘をされているのもあります。濃度次第では、いろいろな副作用的なものも出されておりますので、賛否両論いろいろある中で学校に持ち込むとなったら、なかなか先生方も拒否はできないし、また子供さんたちも嫌とは言えなくなったり、いろんな問題が持ち込まれてくるかと思いますので、ぜひ、そういう資料等も目を通しながら、慎重に検討を進めていっていただければと思います。今の段階ですぐということではないとお伺いしましたので、そこは確認をさせていただいておいときたいと思います。
それでは次の、女子生徒の自死事件についてですけれども、今、和解をしたので返事をしないと。スポーツ振興センターがやったことだと。でも、スポーツ振興センターというのは文科省の機関の一つですので、今度の補償金だって出水市を通して支給されていると思いますので、関係ないということは言えないんじゃないでしょうか。
日本スポーツ振興センター施行令の学校の管理下における災害の第4に、児童生徒等の死亡で、その原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、文部科学省令で定めるものとしてあります。今回の通知の中にある独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令第24条第3号は、「学校の管理下において発生した事件に起因する死亡」と規定しております。この中で「事件」とはどういうことを指すのかお答えください。
○大久保哲志教育長 今お話されたように、省令の中にある「発生した事件」という言葉があるということでございましたが、これは当該文書がそもそも独立行政法人日本スポーツ振興センターが作成したものでありまして、これは私どもが「事件」というのを作成したものではないことから、答弁することはできません。
○18番(中嶋敏子議員) これはお尋ねしますから、と言ってはおったんですけれども、それが答弁であれば、それでいいです。「事件」とは、児童・生徒等の安全な学校生活を妨げる特別な事実をいい、急激な事実であるか、継続性がある事実であるかは問わないと。ここでいう「特別な事実」とは、どういうことを指しているのかお尋ねしたいんですけれども、これもさっきの答弁と一緒でしょうか。よろしくお願いします。
○大久保哲志教育長 そちらも、先ほども申したように、これは独立行政法人が訴訟の相手方に発した文書でありまして、私のほうでは回答できません。
○18番(中嶋敏子議員) 学校と非常に関係の深いセンターだろうと思うんですよね。学校で起きた事故・事件は全部このスポーツ振興センターを通して被害補償していただいているわけですから。「特別な事実」とは、いじめ・体罰等を言うというふうになっております。真っ先に「いじめ」というのが出てくるわけですね。ここでは、体罰というのは考えられませんので、日本スポーツ振興センターは学校の管理下で起きた事件、つまり、ここではいじめに起因する死亡というふうにスポーツセンターは認めて、死亡見舞金の支給を決定したというものが妥当ではないかと考えますけれども、これについてはお認めになりませんか。
○大久保哲志教育長 その点については大事なことですので、日本スポーツ振興センターのほうに確認をしました。スポーツ振興の給付については、これはいじめを認めたものではなく、被災者の迅速な救済という災害共済給付制度の趣旨と併せて、総合的に勘案した結果であるということで、このような回答をいただいております。
○18番(中嶋敏子議員) 私はやっぱり、後で申し述べたいと思っていますけども、最初に事件があった3か月後に教育委員会が真弥香さんの自死については事実関連が確認できなかったと、そしてここでいじめはなかった、学校との関係はなかったとの結論を出しちゃっているわけですね。だから、安倍さんじゃないですけど、自分がモリカケやなんかに関係しとったら、もう総理どころか国会議員も辞めますよと言った、そのことから発して、ずっといろんなことが起きていますけど、ここで教育長が言い切っているわけですよ、「学校に問題はありません」と。裁判の和解にいく最後に教育委員会が出した意見陳述書では、学校にはほとんど問題はなかったと、家庭に問題があったんだと、両親が離婚していたとか、じいちゃんが厳しかったとか、そういうことから家庭に問題があったというのを最後の陳述書で出していますので、そこが教育委員会の言い分として、それをずっと通さざる得なくなってしまっているんじゃないのかなと、私は判断しているところなんですね。それで、教育長も署名を持って、何回かアンケートを開示してほしいということを言いに行ったこともありました。――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
私は、今回の件を無駄にしないためには、裁判所からおとがめがなくてよかったということで、終わらせないことが必要だと。和解条項に関して市教委の認識について、次の2項目についてお伺いします。1つ目は、和解で認定されたバックを蹴られた、いじめがあってあまり眠れないと、10項目ありました。いじめの判断を被害者の受け止めに委ねる現行法下では、十分にいじめに当たる事実と思われますけれども、教育長の見解をお聞かせください。
○大久保哲志教育長 この件に関しては、先ほど申したとおりですが、和解調書のとおりでありまして、和解が成立していることから回答はできないということでございます。
○18番(中嶋敏子議員) 和解調書の中でも、現行法に照らせば、いじめとしての対応が必要だったんですよといっているじゃないですか。和解調書は現行法等に照らせば、いじめの存在を想定して対応すべき状態にあったと規定していますよ。つまり、いじめの兆候を認識していたにもかかわらず、いじめの可能性を考えることをせずに、学校全体で組織として対応しなかったということを指摘をしているわけですよ。教育長は、この指摘に対して何も感じていらっしゃらないですか。
○大久保哲志教育長 この裁判所の和解調書というのは、裁判所でいえば判決のようなものですから、ここにあるものについてコメントはできないということを申し上げて、ここに書いてあるとおりだということを申し上げておきます。
○椎木伸一市長 質疑の途中ではあるとは思います。
この案件については、先ほど来、教育長が説明しておりますように、既に和解をしております。和解に当たっては、議会の議決もいただいております。和解という意味は、今後このことについては一切、両方、議論がないというか、ものを言わないということだというのが和解だというふうに我々は思っているところであります。そういった議会で議決された和解について、また議場の場で同じ和解した案件の内容についていろいろ問い出されるというのは、議会としていかがなものかなと思いますし、また先ほど、当時の職員に対する誹謗的なお話もございました。それについては、そういったことをこの議場で言っていいものかどうか。そこも含めて、議会に問いたいと私は思っております。
○議長(田上真由美議員) 中嶋議員に申し上げます。この件からは、違う観点での質問に移行してください。
○18番(中嶋敏子議員) 和解文書による補償の問題は、もちろん解決していますから、それを一切言う気持ちはありません。教育上の問題は、私は残されていると判断しているわけですよ。それで、和解条項の中でも指摘をされていることでもあるので、やっぱり今後、同じような事例が起きたりとかしたときには、あの事例と、真弥香さんの事例と同じような対応はしないと。違う対応をしてくださいよということも出ているので、教育上の問題点として、これは昨年の6月議会でも申し述べた上で、議論をさせていただいていると思うんです。それは、市長の見解でありまして、私どもはそこについては、きちんとしておかないと同じようなことがされたら、再発防止にはつながらないと、非常に、私は危惧しているものですから、その点にきちんと遺族に対しても謝罪をするところは謝罪し、きちんとした対応を求めていきたいということで取り上げてきておりますので。
○議長(田上真由美議員) 発言の途中ではございますが、中嶋議員に申し上げます。この質問につきましては、質問通告書を出される際にも、この和解条項に抵触するのではないかということで、私のほうからも申し上げました。その際に、答えられなければ答えないでいいというふうに答弁がありましたので、やむなく、これは受け付けた案件でございます。ですので、次の質問に移行していただきたいと思います。
ここで、暫時休憩とします。再開を午前11時15分とします。
午前10時58分 休 憩
午前11時15分 再 開
○議長(田上真由美議員) 再開いたします。休憩前に引き続き、会議を続行いたします。
中嶋議員に申し上げます。先ほどの溝口前教育長に関する発言については、地方自治法第132条に抵触いたしますので、地方自治法第129条に規定する議長の議場秩序維持権を行使し、発言の取消しを命じます。なお、取消しに応じていただけない場合は、同条の規定に基づき、本日の会議が終わるまで発言を禁止いたします。
中嶋議員、いかがなさいますか。何とおっしゃっているか、分かりません。
○18番(中嶋敏子議員) 取消しで結構です。
○議長(田上真由美議員) 取消しを認められるんですね。承知いたしました。
それでは、中嶋議員の質問を許します。
○18番(中嶋敏子議員) 私は和解条項の中身も今後のことがいってあるので、そのことを議論していたんですけれども、あなた方のそうした態度が、スポーツ振興センターが。
○議長(田上真由美議員) 中嶋議員に申し上げます。これと離れた質疑に移行してください。先ほど申し上げました。これ以上お続けになるようでしたら、発言の停止を求めます。
(マイクなしで発言する者あり)
○議長(田上真由美議員) そこから離れての質問に移行してください。
(マイクなしで発言する者あり)
○議長(田上真由美議員) それでは、発言の停止を求めます。
これで、中嶋議員の質問を終わります。自席にお戻りください。
次に、江川野一成議員の質問を許します。
○6番(江川野一成議員) 本日、最終日の2番目の質問者になりますが、よろしくお願いいたします。中嶋議員から3分いただきましたので、43分ということで、よろしくお願いいたします。今のは違います。
通告に従いまして、武本排水路の一部区間に防護壁等の設置ができないか、質問させていただきます。
今回、武本排水路という名称での質問項目になっていますが、地元では、汲ん川溝や大野田溝と呼ばれていますので、ここでは、地元の人たちが分かる汲ん川溝で話をさせていただきますので、御理解の程よろしくお願いいたします。
出水の水系は東に矢筈山、南に紫尾山、この二つの大きな山系によってできた大野原台地は、砂礫層で構成され、多くの河川は、水がしみ込みやすい土地を川が流れる、水が地中に潜り込むという現象、伏流水となり、地下水面は深くなっていることから、水に恵まれず、昔から、これに水を引こうとしたのが五万石溝であり、現在の出水平野開発土地改良の事業であります。
紫尾山系から流れている平良川を水源とした、先ほど言いました汲ん川溝ですが、これは人工溝で、平良川にある江川野の椎井手井堰が起点となり、野添の五万石溝に落ちるまで、おおよそ4キロメートル近くあり、6集落を縦断していて、水稲の植付けが近くなる時期からかんがいに使い、昔から、この溝には年間絶えることがなく常時きれいな水が、適当な勾配に従って、勢いよく流れていて、昔の人はこの流水を利用し、多くの水車、13か所あったそうですけれども、江川野に2か所、上中に3か所、下中に3か所、上屋に3か所、野添に2か所があったそうです。それが設置され、精米や製粉が行われていました。
また、汲ん川溝から各自の家の近くを流れるように引いて、我が家の洗れ川を作って、洗濯や洗い物に利用していたとのことです。大正14年頃、腸チフスという恐ろしい病気が蔓延し、各集落では毎日のように死人や葬儀と、大変な事件となったそうです。事件が収まってからも、元どおりこの溝を使っていましたが、昭和の初め頃になると、飲み水は井戸水に変わってきたようです。それでも、自然に決まった時間帯を守って、食器類や野菜類の洗い物とか、人や牛馬の水浴、子供たちの水遊びなどに利用され、地元にとって、なくてはならないものとなっていました。
現在も、水稲栽培の用水として利用し、枝線も含め、豪雨時の排水路としても機能し、地元の雨水対策として必要なものとなっています。
また、常時水量があることから、昭和55年度まで消防水利に認定されていましたが、消火栓設備の整備に伴い解除されました。しかし、現在も多くの水量が確保できることから、消防活動にも利用できると考えております。
このような貴重な財産を維持していくことが重要であり、地元の安全、安心に繋がることだと思っております。
今回質問しています区間は、清水集落内に架かっています橋の上下区間で、地山を6メートル以上掘り下げた素掘り水路となっているところで、経年等により何回となく崩落し、流れを塞ぎ、そのたびに大変苦慮しています。また、地元の4集落でつくっています大野田溝管理組合で、この溝の清掃区間割を行い、機能維持のために、危険を感じながらも草刈りや土砂上げの作業に取り組んでいますが、この崩落の危険がある区間に、水路の機能保全と地元の方々が安全に作業に取り組むことができるように、防護壁など何らかの対策が必要であると考えておりますが、市長の考えをお伺いし、壇上からの質問を終わります。
○椎木伸一市長 江川野一成議員の御質問にお答えいたします。
武本排水路につきましては、財産管理を市で行っておりますが、通常の維持管理につきましては、議員御紹介のとおり井堰からの農業用水路として使用されているため、原則として受益者の皆様方に除草や泥上げ等の協力をいただいているところであります。
また、本水路の一部区間は、のり高が約5メートルと高くなっておりますので、のり面が崩れ水路部分が閉塞するような事態には、用水路としての機能を回復するため、農業用施設単独災害復旧として市で対応しているところでございます。
農業用水路につきましては、受益者がいらっしゃることから受益者の負担はございますが、県営事業等や事業費の75%を市が補助する市単独土地改良事業、建設資材等の支給をする農業用施設整備地域支援事業により整備しているところであります。
防護壁の設置につきましても、事業の対象になると考えられますことから、これらの事業について受益者である水利組合に、情報を提供してまいりたいと考えています。
○6番(江川野一成議員) このことにつきましては、市民として、後ろに議員とありますけれども、担当部署が二転三転する中で再三となくお願いしていることでございます。それは御理解いただけると思います。
担当部署はどこですか。
○揚松智幸農林水産部長 現在、武本排水路となっておりますので、農林水産部の所管となっております。
○6番(江川野一成議員) それでは、排水路は行政財産ということで理解していいわけですね。
それでは、公の施設の設置及びその管理に関する事項は条例で定めなければならないということで、地方自治法の第244条で定められていますよね。ですから、出水市農道及び排水路の管理に関する条例を平成18年3月に設けておられると思います。
その条例に基づき、適正に管理されていると考えていますか。
○揚松智幸農林水産部長 先ほどの市長答弁でもありましたとおり、災害等、土砂崩れ等、地元の日常の維持管理以外のものについては、農林水産部のほうで対応をしております。
○6番(江川野一成議員) 通常、簡易な維持管理は、水稲栽培に利用させていただいておりますから、当然やっていることですけれども、「維持管理とは」ということでお聞きします。どういうことですか。
○揚松智幸農林水産部長 日常的な維持管理ということで、地元の受益者の皆様方にお願いしているのは草刈り、それから簡易な土砂上げと理解をしております。
○6番(江川野一成議員) 今、揚松部長が言われましたが、通常の維持管理等はお願いしてありますと。誰も受けたことないんですよね、そういう話は。だから、維持管理の方法とか、どの程度までが維持管理でしてもらうとか、そういう話を地元の組合でもいいんですけれども、そういう話をされたことがありますか。
○揚松智幸農林水産部長 私がしたことはありません。ただ、簡単に説明をすれば、もともとの青線、赤線と言われたところだと思います。そこについては、法定外公共物というところから始まっており、これは現在の地籍図の前、字図ができるときに、実際にそこがあった、それは税を負担をしないということから、国有地として認定をされたものであり、元来、地域の皆様方が御利用されているというところから、今の維持管理、通常の維持管理というふうになったと理解をしております。
○6番(江川野一成議員) 今、揚松部長からお話がありました法定外公共物でいいんですね。そういう理解でいいんですね。分かりました。だから、単独条例を作っていらっしゃると思います。単独条例を作って、財産経営は出水市であり、財産の機能管理は当然出水市がやらないといけない。簡易な除草、土砂上げ等は当然、利用させていただいておりますので地元がやるんですけれども、結局、機能管理をすることが市であって、その機能管理が損なわれるときには誰が調査をして、どういう形でやっていらっしゃるのか、よく理解しておりません。
○揚松智幸農林水産部長 機能保全という意味からいえば、例えば下流側に水が来ないなどなどあった場合には、当然、そこの原因を突き止め、必要であれば土砂を取り除いたりすることになります。今、言われたところについても、今年度、木が落ちてきたところがありまして、そこについては市のほうで除去をしたというところです。
○6番(江川野一成議員) 私が何でこういうことを言うかというのは、担当部署がはっきりしないんですよ。私が何回となく来て、道路河川にやられ、下水道にやられ、農林水産整備課にやられ、私もこんな条例を見てなかったから、よく分かりませんでしたけれども、結局担当部署が二転三転して、対応が遅れると。その挙げ句、排水路としては機能は満足しています。いや、そういう話を私はやっているんじゃないと。基本的に、そこに転石とかそういうものが落ち込んだときの対応は、地元で手作業でやる分はできないから、そこに落ちないようにしてくれという話をしているのに、排水路の容量は足りていますとか、そういう話をやっているんじゃないんですよ。
だから、記録からいきますと昭和46年から8回ほど崩落しているんですね。そして、また今年になっても何回か、その前も何回か。だから、それを地元のその辺の近くの住民が下りていって確認したり、石を抱えてやったり、それとか組合の連中の役員の方が行って、できないときは市役所にお願いし、市役所にお願いしたら、担当部署はどうじゃこうじゃといって言わない。そうしたら結局、処理してしまうまで何日かかかるわけですね。そういうことで、管理がしっかりできていますということは、言えないんじゃないか。担当部署も分からんのに、どうして管理がぴしゃっといっていると言い切りますか。
○揚松智幸農林水産部長 農業用用水、排水路というのは、市内全域、かなりの量があります。それを一つ一つずっと見て回ればよろしいんでしょうけれども、そういった時間もない。例えば、大雨の後、台風の後等については、そういう危険があるところについては見回りをしている状況だというところで御理解をいただきたいと思います。
○中村孝文農林水産整備課長 ただいま議員が言われた内容でございますが、今年度、木が水路の中に落ちたときも、通報を受けてその日のうちに段取りをしまして、即対応ということで行っていると考えております。
○6番(江川野一成議員) 中村課長、ありがとうございました。対応を早急にしていただきました、初めてです。だから、条例ができているのであれば、条例に基づいて適正に管理しないといけないんですね。それを地元任せにするんじゃなくて。それで危険箇所が普通のところの排水路とか用水路でしたら、そこの道路の近くを歩いて見えるんです。ここの場所は見えないから言ってるだけのことであって、現地を見に行かれましたか。
○揚松智幸農林水産部長 農林水産部長になってから、四、五回現地へ行っております。で、上のほうから下ってみたりとかしております。
○6番(江川野一成議員) すみません、どのように感じられていますか。地元の普通の人が、専門じゃない人たちが、あそこを下のほうから入ってきて、あの部分でやろうとします。草刈りとかマムシもいます。マムシの巣になっている部所です。隣のおじさんが言われましたけど、そこに石があるやつを一生懸命抱えて上げる所もないと。どうしたらいいんですかと言われました。
だから、そういうような地元が一生懸命やって、地元が助けを市にお願いしているのに、通常どおりでどうじゃこうじゃということに対して、どうですか。
○揚松智幸農林水産部長 通常どおりというか、他の箇所と同じように、我々は対応をしているつもりです。先ほどおっしゃられたように、落石があった場合に、それが人力ではどうしても無理、あるいは年齢的に厳しいものがあるということであれば、御相談がくればこちらで対応したりしております。そこについては、今までもやっておりますし、これからもやっていくつもりでございます。
○6番(江川野一成議員) この頃はやっていただいているんですね。何回かお願いすれば。だけど、以前は全然です。だから、なかなか対応はしていただけない。そこで今言われたように、地域の関係者の方々が高齢化しています。確かに、耕作者は高齢化しています。そして、市民の意識の変化ですか、それによって除草作業等も難しくなってきております。だから、今ここの区間は、上中集落の方が管理していただいております。今、要望している清水集落の所の上下区間は上中集落の区間割になっておりますので、上中でやっていただいております。なぜ、できないのかな。不思議でならないんですけど、行政財産を守る、交通、道路なら交通の用に供する。そうしたら、当然、交通の障害になれば対応します。それの話ですよね。今、水路がしたら、誰かから連絡が来れば対応します。そうしたら、道路は何回となく崩落がある場所は擁壁ができます。行政財産を守る上で、水路も一緒じゃないかなと私は理解しているんですが、あまり頭がよくないですから、そんな理解でいいですか。
○揚松智幸農林水産部長 ここ数年の話で申し訳ありませんが、今、ここ3年ほどの間に同じ箇所が崩落をしたという所はございません。場所がかなり違っておりましたので、またそれが同じ箇所が何度も何度も、ということであれば、そのときにはまた対応方を、それこそ地元、水利組合の皆さん方とも話をしなければならないことだと思います。
○6番(江川野一成議員) 同じ箇所じゃないんですよ。その区間のどこかが崩れるんですよね。先ほど言いました6メートル以上素掘りを掛けて、掘り下げて、素掘り水路になっている区間です。当然崩れます。だから、何らかの水路を守るため、それから通常の維持管理を地元にさせるのであれば、それらの対応を行政はやるべきだと思っております。
本当に、先ほど言いましたように、なぜできないのか、ちょっと思うんですよね。通常のところの考え方と危険性がある所に、地元に維持管理をしなさい。自分たちで災害で崩れた所を見に行って報告しないといけない。それが本当にいいんですか。命の危険、また崩れるかもしれない。そこに地元が調査に行くんですよ。それは行政側が行くべき仕事であって、私なんかが行って報告する、私は1回も入ったことないんですよ、マムシが怖いですから、そこに入ったことないんですけれども、上からしか見たことないです。あの、住宅がありますから、あっちの上から見たりとかしていますけれども、それでいいんですか。何かちょっと理解できないんですけれども。危険が伴うようなやつを、地元の維持管理でしていただいているんです。当然、部長が言われたとおり、昔造った人工溝ですよ。かんがいのためにつくった、先ほど壇上で説明しました、そのとおりだと思うんですよ。そのあと、国有になったのか、権限移譲で18年というとちょうど地籍でやって、法定外公共物とった時期ですよ。そのときに、条例を整備したんですよ。条例を整備したんであれば、条例に基づいて適正に管理するのが、行政だと思うんですよ。それを、怠ったという言葉はよくないな、地元に任せ切り。それじゃどうでしょうかね。
それともう1点。この質問書を出して、初めて農政が担当部署と言われたんですよ。それまでは二転三転しているんですよ、分かりますか。こんな対応を市民にしていたら、どうしようもないんですよ。だから、質問することになったんです。こんなことで質問することはないんですよ。まだ大きい皆さんが質問しているようなことをしたいんですよ。夢のあることをここで語りたいんです。だけど、これを質問しないと、どうしようもないと思って質問させていただいているんです。担当部署が変わることが、どうも分からないんですよね。法定外公共物だから、道路河川ですよ。排水路ですから下水です。そして用水ですから、農水です。こんな市役所の体制というのはいい加減なものかなと思っております。にこにこいつもしていますけれども、腹は相当はらけとったど。その辺、分かっていますか。担当部署が二転三転するのを、これを一般市民の方にやられたら、それは怒りますよ、みんな。分かります。どうですか、その見解を教えてください。
○揚松智幸農林水産部長 おっしゃることは本当によく分かります。そういうことがないようにということで、今地図情報なり何なりを整備しております。今回の件に関しましては、確かにここの溝が武本排水路ですか、平成18年に指定をされたというところも私は認識がありませんでしたので、それについてはおわびを申し上げます。
○6番(江川野一成議員) あと、先ほど市長が補助事業として取組は75%、地元25%、今崩れている所は清水集落内です。清水の人はその用水は使っていないんです。あくまで、用水の管理というよりも、防災とか排水とかの管理で地域が昔から守ってきた汲ん川溝ですから、対応されていると理解しております。そうしたら、下のほうに行ったら、上中と下中です。そうしたら、野添地区はほとんどしていないんですね、上中、下中で水稲栽培をよくしております。これも一時的なものです。5月頃から10月初旬までですか。ほかは何のために流れているかという話ですよ。大雨が降ったときは、井堰は自然に止まります。そして、管理組合の水門係が開けに行きます。だから、井堰が止まって、溝を空にして、今度は汚水排水のために利用されているんです。それを途中で崩れて止まっているということです。そして通常のときは、先ほど壇上からも言いましたけれども、消防水利にできるんじゃないかと。消火栓設備、あのど真ん中しか走っていませんから、それから集落というのは下に上にいっていますから。ですから、そういうことを考えたら、耕作者だけに負担を求める事業は、到底納得できないと私は思っております。ですから、それであれば理解しているんですよ、私も行政におったから。だけど、この案件については、当然市のほうで単独事業でもいいから、どうにか地元が管理しやすいように対応していただけないかなと思って、再三したんですけど、そんなふうで部署が変わり、しないための理屈を常に言われる。だから、市民が相談してきたときは、「してやる」つもりで勉強して、やるべきであって、その法定外公共物、道路河川が持っているんですよね。農政が持っているんですか。だから、それもはっきりしないんですよね。だから真剣味が足らないんですよね、相談に行って。だから、てげてげに思われていたんですよ、私を。だから、やっぱりちょっと対応が、どうも一市民の立場になれば、どうかなと。もう少し、市民に寄り添った対応をしてほしいなと思ってます。
単独事業で、市長、すみませんけど、できないでしょうかね。
○椎木伸一市長 先ほど来、部長も申し上げておりますけれども、この水路等の維持管理については、やはり市民の皆様と我々行政のほうとの協働、信頼関係の中での協働になると思いますし、また役割分担ということで、かねての維持管理、先ほどどこまでかという話がありましたが、維持管理をお願いしながら我々ですべきところについては、いろんな事業を導入しながらやっていくというのが基本的なことであろうと思っております。
江川野議員のほうに、大変所管のことで御迷惑をかけたことはおわびを申し上げたいと思います。今後も、そういったことで市民の皆様との協働、信頼関係を維持しながら取り組んでいかなければならないと思っておりますので、またお互いに意見交換をしながら、先ほど水利組合のほうとの話をするというようなことでもございますので、この「つくる」「つくらない」とか、事業を導入できるかどうかということについては、その場で協議をしながら対応していきたいと考えます。
○6番(江川野一成議員) 前向きに検討していただくのが、地域の方々にとっても安心できる話だと思うんです。これを一部の水稲耕作者の方に負担をさせる、それは用水はその一部しか使っていない。その代わり、清水集落の方々も水稲には使っていなくて、ボランティアというか、今農地・水でお金を払っていますけれども、今まではボランティアで清掃活動をやっていた。だから、皆さん、地域を守るために一生懸命やっていて、そして地域がどうしても危険が伴うとか、地域ではできないことは行政にお願いするしかないと私は思っています。そのときに、ああじゃこうじゃ、基本的にやらないための説明をされるよりも、「前向きにどうにか検討していきます」と。そして、それが2年かかろうと3年かかろうと、前向きに検討して結果が出ればいいわけです。それを、何か知らんけど、窓口で断られる。よっぽど嫌われていたんだなと思っておりますけどね。だから、とにかく行政という市民の代表である、市民のお金を運用する人たちです。そうしたら、市民が先ほど言いましたように、助けを求めているのであれば、それなりの対応を求めないといけない。そして、この前もちょっと言いましたら、「連絡くだされば、すぐ対応します」と。いや、そういう話じゃないでしょうと。連絡はするよと、その代わり、それを調査に行くのは地元の人ですよ。そうしたら、雨が降ったり、水稲を作るときは水が来なかったら、その人たちが中に入って見に行くんですよ。そうしたら、そこが崩れる危険性もある。そういうことを地元に人にさせていいのかというのもあるんです。だけど、用水を確保するために、地元は一生懸命頑張っていらっしゃいます。だから、井堰管理とか、平良川の砂利も落としたりします。手作業です。機械を入れないで手作業で今もやっています。水量を上げるために。だから、その辺を理解していただいて、行政が何とか対応してほしいというのが、私の意見です。だから、揚松部長の所管部だということですので、どうか前向きに検討していただいて、水稲栽培の耕作者だけの水路じゃないと。災害用の水路である。それから、火災用の水路である、ということを御理解いただければ、そこの部分だけでも何か対応ができるんじゃないかなと。理屈は付けられるんじゃないかなと思っております。どうですか。
○吉田定男副市長 行政経験豊富な元職員の江川野議員、水路であっても里道であっても、受益者がいらっしゃるところについては、受益者負担金というのは当然生じてくるというのは、御認識のとおりだと思います。ただ、先ほどから申していますように、災害等でのり面が崩れたりしたときには、当然、単独の災害復旧とか使ってやるわけですよ。議員さんたちが言われたから、そこだけを特別にとかいう話ではなくて、するのであれば、市内全域を見渡したところでの取組をしないと、議員さんが言えばできるとか、そういうのはやっぱり客観性に欠けると私は思いますので、するのであれば全体を見渡したところで検討していきたいと思います。
○6番(江川野一成議員) やっぱり、副市長が出てきたですね。通年ずっと続いて、受益者があるのであれば、ものすごく理解するんです。ほかの用途がなければ、ものすごく受益者負担というのは理解します。用水で限定的な用水、今言われる排水路です。私もびっくりしたんです。この前、一般質問を出したときに排水路になっているんだと。全然知りませんでした。用水路と思っていました。だから、要するに私どもが1年通して工事以外は全て流れている。だから、水稲栽培が6か月ぐらいしか要りませんから、あとは止めていいのかなという議論もやったことがあります。そうしたら、下の集落の方々が水路が臭くなると、ということは、家庭排水が流れていたり。ということは、それを流してくれということで、流さざるを得ない。これがただ用水だけの話で収まるという話ではないような気がしています。だから1年間、守りをしています、溝の役員を。だけど10月で終わりですよ、本当は。だけど1年間流さないと私どもがこの前、多面的でちょっと補修工事をしましたけれども、そのときも四、五日止めましたけれども、そのときも苦情がきました。だから、おかしいんですよね。だから純然たる最初は汲ん川溝といって、先ほど壇上で説明しましたように、用水としたりかんがいしたりとか、それから井戸がない時代の洗い物とかというもので造ったんだろうと、私は思います。だけど、今はちょっと変わって、防災と用水と限定されていると。だから、補助事業を市長のほうから答弁いただきましたけれども、なかなか受益者負担とかというのは考えにくいかなと。下のほうが少ないんです。耕作者がですね。だから、なかなか考えにくいんですけれども、このままずっと平行線でやるよりは、12時前ですので、もう終わりたいと思うんですけれども、どうにか地元の西出水地区の方のことを思って、そしてまた関係者の方々を思って、どうにか前向きな検討をお願いして、質問を終わります。ありがとうございました。
○議長(田上真由美議員) ここで昼食のため、暫時休憩いたします。再開は午後1時からとします。
午前11時53分 休 憩
午後1時00分 再 開
[吉元勇議員着席]
○議長(田上真由美議員) 再開いたします。休憩前に引き続き、会議を続行し、井伊健一議員の質問を許します。
○1番(井伊健一議員) 皆様、お疲れ様です。前回に続き、今回の一般質問を最後の登壇になりました。どうぞ、最後までよろしくお願いいたします。
それでは、通告に従いまして、質問に入らせていただきます。大きく2点です。1点目が学校教育の環境について、2点目が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用、公共料金の負担軽減についてになります。
まず最初の1点目の学校教育の環境についての1番目、屋内運動場の熱中症対策について質問していきたいと思います。今回、この質問は既に土屋議員がしていますので、2問目以降については質問していない部分についてお伺いしますので、よろしくお願いします。
今年の夏は、いつもの年にも増して暑い夏が続いています。9月中旬になった今でも最高気温が30度を超す日が続いており、熱中症による救急搬送も過去最多を記録している状況です。学校教育の現場、体育の授業や部活動でも、子供の熱中症対策が今も、そして、これから先の時代、来年以降も必要と思われます。そこで今回は、屋内運動場の現状と今後について質問します。
ア、本市の現在における夏場、特に5月から10月の屋内運動場使用時の熱中症対策はどのようにしていますか、お伺いします。
イ、屋内運動場使用時の熱中症対策として、強力スポットエアコンを導入する考えがないか、お伺いします。
2点目、学校トイレの現状と今後についてです。現在、コンビニや一般のお店等のトイレの手洗い場は、非接触型の自動水栓器を設置している所がほとんどですが、今後の感染症対策、衛生的なことを考慮して、本市の公共施設や学校等においても、全面的に手動式の蛇口タイプ、すなわち手で回すタイプから、非接触型の自動水栓器、センサー感知による自動水栓タイプに変更していくべきであると思います。そこでお伺いしたいと思います。
ア、現在の学校のトイレの手洗い場の蛇口、手で回すタイプは何%であるか、お伺いします。
イ、感染症防止・衛生面を考慮して、非接触型自動水栓器、センサー感知による自動水栓タイプに変更できないか、お伺いしたいと思います。
3点目、この質問については、既に吉元議員がされていますので、2問目以降は割愛させていただきます。
今から1か月前の8月9日に曽於市の高岡小学校で、校長先生が大イチョウの枝の下敷きになりお亡くなりになられた事故で、住民にとても愛された校長先生だったとのことで、非常に残念でなりません。改めて、御冥福をお祈りいたします。今後、同じような痛ましい事故がないように、再発防止をしていくことが重要だと思います。
ア、今回の曽於市の大イチョウの枝の下敷きになり死亡した事故で、本市として、同じような事故が起きないようにどのように考えているか、お伺いします。
イ、本市の幼稚園・学校で、古木・老木その他伐採したほうがいいと思われる木が、どれくらい、何本あるかお伺いします。
ウ、今後、古木・老木など、落下するおそれのある木を伐採等の対応をしていく予定など考えているかお伺いします。
大きい項目の2点目、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用、公共料金の負担軽減について質問します。政府は原油高騰を受けた今年4月の総合緊急対策で、地方創生臨時交付金に1兆円の原油価格・物価高騰対応分を新たに設けました。現在、各自で生活や事業を守る施策が進んでいます。本市においても、学校給食費の支援、生活困窮者支援や子育て世帯向け給付金、プレミアム付き商品券、マイナンバーカードの取得者への5,000円分の商品券、交通運輸事業者支援など、市民の生活を守る、事業者を守る施策、本当にありがとうございます。市民の皆様も家計が少し楽になったと喜んでおられると思います。
7月15日に行われた政府会合で、岸田首相が、地方創生臨時交付金の活用事例を紹介した上で、「自治体の実施状況を踏まえつつ、必要に応じて地方創生臨時交付金をさらに増額し、対策を一層強化していく」との方針を示しました。政府は8月15日、物価高への対応を話し合う「物価・賃金・生活総合対策本部」の会合を官邸で開いた。岸田首相は物価高騰対策などに充てる地方創生臨時交付金を、1兆円から増額することを指示したと表明しています。
そこで、今後、地方創生臨時交付金が増額等された場合、いろいろな活用のやり方があると思いますが、本市においては、公共料金、上下水道、電気、ガス等の減免に活用できないか。他の自治体の活用について紹介させていただきますが、本市においてもできないかお伺いします。
(1)下水道料金の基本料金分の減免に活用できないか。これにつきましては、福岡県福岡市では、8月から11月までの下水道使用料のうち、2か月分を免除するとのこと。福岡市においては、2か月に1回の検針分で約2,000円から3,000円分の減免をするそうです。本市においても、公共料金の減免に活用できないかお伺いします。
(2)水道料金の基本料金分の減免に活用できないか、お伺いします。これにつきましては、鹿児島県日置市では、水道料金の基本料金の減免を8月から1月までの6か月するとのことです。2か月毎の検針で、偶数月の検針の8月、10月、12月の方は、その検針の月に1,760円分を、奇数月検針の9月、11月、1月検針の方は、その検針月に1,760円分の基本料金分を免除するとのことです。本市においても、公共料金の減免に活用できないか、お伺いします。
(3)地方創生臨時交付金の活用については各地方自治体で検討して、いろいろな使い方がありますが、電気代・ガス代の減免にも活用できるとのことですが、基本料金の減免に活用できないか、お伺いしたいと思います。
○椎木伸一市長 井伊健一議員の御質問にお答えいたします。
私のほうからは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した公共料金の減免についてお答えいたします。まず、下水道の基本料金は1件当たり990円で、基本料金を1か月減免する場合、減免額の総額は約1,700万円となります。なお、下水道の市全世帯に対する接続率は、本年3月31日時点で59.9%であります。
次に、水道の基本料金は一般的な家庭で使用している口径で13ミリメートルの場合、495円、20ミリメートルの場合、638円となっております。基本料金を1か月減免する場合、減免額の総額は約1,600万円となります。なお、水道の市全世帯に対する普及率は、本年3月31日現在で98.7%となっております。
次に、電気料金・ガス料金の減免については、各家庭の電気、ガスそれぞれの契約の有無、契約の内容などを把握する必要がございます。なお、制度的には、交付金を公共料金の基本料金の減免に活用することは可能でありますが、地域経済への波及効果は限定的なものになるのではと考えているところであります。
一方で、プレミアム付き商品券は、公共料金を含めた家計全体の負担を軽減し、かつ、地域経済への波及効果も大きいと考えますので、現時点では、交付金を活用した公共料金の減免については考えていないところでございます。
○大久保哲志教育長 井伊健一議員の御質問にお答えします。
まず、屋内運動場の熱中症対策についてですが、屋内運動場の使用時は、風通しをよくするため、必ず、窓や出入口の扉を開放し、状況に応じて大型扇風機を利用しています。
また、体育の授業や部活動等の運動を行う場面においては、熱中症対策を優先し、児童・生徒にはマスクを外して活動させたり、運動が長時間にわたる場合は、活動前後に必ず水分補給を行わせ、活動中においてもこまめに水分や塩分を補給させたりしています。さらに、体が暑さに慣れていないときには、短時間で軽めの運動から始め、徐々に慣らすようにし、運動時の服装は軽装とし、素材は吸湿性や通気性のよいものにしています。なお、暑さに対する耐性は個人差が大きいことから、指導者は常に健康観察を行い、体調不良が見られる場合には、無理に運動をさせないようにしています。
また、熱中症対策としての強力スポットエアコンの導入についてですが、小型のスポットクーラーから大型の冷風機まで様々な機種があり、それぞれ効果や費用も異なることから、現状の対応を徹底しながら、強力スポットエアコンも含めた空調の設置について調査研究を進めていきたいと考えています。
次に、学校のトイレの手洗い場についてですが、全蛇口460か所のうち手動式蛇口は441か所で、95.8%となっています。非接触型自動水栓器(センサー式)の導入は、感染症予防等に効果があると思われますが、工事費や維持管理費の点から、他の施策との優先順位等を考慮し、進めていく必要があると考えています。
次に、曽於市で起きた大イチョウの枝の下敷きになった死亡事故について、本市で同様の事故が起きないための方策ですが、学校施設等の点検は毎月1回安全点検を行うこととなっており、樹木についての項目はありませんが、点検を実施している中で事故につながるおそれのあるものは、教育委員会に随時報告するようになっています。今後、樹木についても点検項目に加え、注意を払っていきたいと考えています。今回の事故を受けて、古木・老木に限らず将来的に生命、身体及び財産に損害を与えることが予見される樹木を調査したところ、小学校93本、中学校24本の報告がありました。
次に、今後、古木・老木など伐採の予定はあるかについてですが、これまでも教育活動に支障のある木については伐採等を行っており、今回の詳細な点検の結果に基づき、伐採等が必要な樹木を整理し、樹木医の診断を参考に進めていきたいと考えております。
○議長(田上真由美議員) 井伊健一議員より、書画カメラの使用について申入れがありましたので、許可しております。
○1番(井伊健一議員) 種々、御答弁いただき、ありがとうございます。
まず初めに、学校教育の環境についてから入っていきたいと思います。現在、屋内運動場はドアや窓を開けた状態で使用しているのもよく分かりました。また、水分補給、無理な運動はさせないということで、生徒あるいは児童に御配慮いただき、ありがとうございます。
大型扇風機、これについてお伺いしたいと思います。実際、大型扇風機を使用している学校の数、あと使用していない学校の数がどれぐらいずつあるか、よろしくお願いします。
○床並伸治学校教育課長 大型扇風機は、市内全校に配備をしてございます。体育の授業をはじめとして、学年集会とか、あるいは学校で行ういろんな講演会等の場において、大型扇風機を使用しております。
○1番(井伊健一議員) 学校も2学期が始まり、私先週、米ノ津中学校をちょっと見てまいりました。屋内運動場で体育祭の練習をしていたので見て来ましたけれども、すごい暑い状況でした。ちょうど、5分、10分見ていたら休憩時間になりましたので、生徒が出てきたので「実際、どうですか、体育館の中は」と聞いたら、「暑くてたまらない」その一言で、タンブラーに入っていた水、あれを美味しそうにぐびぐび飲んでいました。私も水を持っていなかったので、欲しいなとは思ったんですけど、そういう状態でした。熱中症で具合が悪くなったり、倒れなければいいかなと思って見ていたんですけど、改めて熱中症対策が必要だと感じました。
そこで、お伺いします。この暑い時期に、小学校・中学校の屋内運動場で、体育の授業あるいは部活動をしている児童・生徒を見て、教育長はどのように感じたか、お伺いしたいと思います。
○大久保哲志教育長 この暑い時期に、外も日差しが強くて大変でありますが、屋内は単に暑さだけではなくて湿気が籠っていたり、風が通らなかったりして、そういう意味では非常に大変であると。ですから、先ほど申しましたように、指導する教員については子供たちの健康観察といいますか、状態をしっかり見極めながら体育の授業を進めていると把握しております。
○1番(井伊健一議員) 熱中症ということを考えれば、大型扇風機だけではちょっときついかなと思うので、将来的に強力スポットエアコンというのは必要になってくるかなということで、種々、調整・調査研究しているということだったんですけど、ちょっと私なりに調べてきたので紹介させていただきたいと思います。
書画カメラの1をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)いろんなタイプの移動式の強力スポットエアコンということで、3種類ほど出しておりますけれども、安いものになると10万円ぐらい、高いものになると40万円、70万円とするんですけれども、私が推奨する強力スポットエアコン、教育長とか市長も御存じと思うんですけども、大量の冷風を送り込めるスポットエアコンです。メリットとしては移動式、下にキャスターがついておりますので、移動が楽で、また電気代も安くて済むという利点もあります。2点目としては、災害時にも避難所まで移動させて使える。3点目、天井が高く、解放空間のイベント会場でも使える、冷暖房がない体育館でも使える、配管工事等の必要がないという利点があります。
デメリットとしては、部屋全体を冷やすことができないというところもあるんですけれども、現状、こういった感染症やいろんなものがあるものですから窓・ドアを開けっぱなしなので、エアコンを入れているよりか、こういった移動式の強力のスポットエアコンを導入したほうがいいと思います。現状、大型扇風機よりも子供たちが熱中症にならないためには、学校の教室のエアコンが壊れたときでも移動して使えるという、そういう緊急時でも使えるという利点があるので、その辺も含めて、できれば早い段階で導入を検討していただければと思うんですけれども、その辺でお伺いしたいと思います。
○椎木伸一市長 予算的なこともございますので、私のほうから答弁をさせていただきます。
このスポットクーラーについては、今御披瀝いただきましたように広範囲の、全体のクーラーには適さないわけでございますけれども、現状の温暖化といいますか、夏の暑さというのは気象庁も異常気象ではなくて、温暖化の一つだということで、これからも常態化していくだろうという予測であります。そういった中で、私としては学校体育館についてもエアコンの必要性を強く感じているところであります。よって、まずは総合体育館に今回、エアコンをお願いしておりますけれども、それが終わった後にはスポットクーラーとかもそのつなぎとして考慮しながら、あるいは使い方の限定的な使い分けといいますか、そういったことで導入もしたいとは考えております。
そして、総合体育館が終わった暁には、災害時の避難所となっている小学校体育館等がございますので、中学校もですね、そういったところを優先して整備した上で、やがては全学校の体育館にもエアコンを設置すべきだと強く思っておりますので、今後、経済面、ランニングコスト、設置の効率といいますか、冷却の効率等も十分に勉強しながら、他自治体の設置等も見ながら、できるだけ早い時期に実現できるように対応していきたいと考えております。
○冨田忍政策経営部長 ただいま井伊議員のほうから丁寧なシミュレーションの上での御提案がございました。料金減免をできない部分については現金給付あるいは商品券給付ということでございます。それも一考かと思います。ただ、現実の事務手続の面でいいますと10円単位とか、あるいは「この人はこう」とか個別の対応というのは非常に事務効率と迅速性に欠ける部分があろうかなと考えております。
先ほど市長が申し上げましたとおり、減免がどうこうということではなくて、我々が考えているのは、その先の経済の波及効果、その部分だけでとどまることなく、端的に言えば商品券を配ればその分は他の経費を補う部分にも使えて、減免をして浮いたお金といいますか、それでほかに商品に回る、そこを自由に市民の皆さんが選択をしていただいて、自分が必要とする部分に商品券を活用していただく。なおかつ、商品券の場合は市内のほうで利用いただければ、その分地域経済の循環に回っていくんじゃないかなと、そういう考えでこれまで経済対策等には取り組んできております。非常に丁寧にシミュレーションしていただきましたけれども、事務上の問題等もございます。そこは御理解いただきたいと思います。
○1番(井伊健一議員) 分かりました。あともう一つ市民の方から言われたので。プレミアム付き商品券、今回5,000円分、マイナンバーカードを取得された方に商品券という形でいただいています。私もいただきました。大変、ありがとうございます。それで、ちょっと言われたのが、共通券と地元で使える地元応援券というがちょうど半分ずつという形できているんですね。よく言われるのが、地元応援券というのはなかなか使うところがなくて、若い方とかは特になんですけど、やっぱり共通券を使うところに行くという人が多いんですね、聞いていたら。その辺の割合をもし考えていただければありがたいなと思うんですけど、その辺はどう御見解でしょうか。
○松岡秀和商工観光部長 地元券の分につきましては、今回、こちらで考えたのがプレミアム分については、その分だけでも市内に本店があるところで使っていただこうということで、結果として半分ずつになったところでございます。今回から、地元にある本店というところの定義も少し見直しまして、コンビニ等で地元の方がやっていらっしゃるところは共通券、地元券両方とも使えるように検討したところです。
○1番(井伊健一議員) 分かりました。検討した上で、そうされているのであれば、今後ともよろしくお願いいたします。
私のほうからは以上になりますが、今後とも出水市の発展のために私も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
以上で、私の質問を終わらせていただきます。
○議長(田上真由美議員) 以上で、質問者全員の質問が終わりました。
-------------------------------------------------------
△ 散 会
○議長(田上真由美議員) お諮りいたします。本日の会議はこれで散会したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(田上真由美議員) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれで散会いたします。
第6日の会議は9月30日に開きます。御苦労さまでした。
午後1時33分 散 会
-------------------------------------------------------
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
出水市議会議長
出水市議会議員
出水市議会議員
出水市議会議員
- 221 -