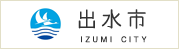令和4年出水市議会第3回定例会会議録第4号
-------------------------------------------------------
令和4年9月12日
-------------------------------------------------------
会議の場所 出水市議会議場
-------------------------------------------------------
出席議員 20名
1番 井 伊 健 一 議員
2番 迫 田 小百美 議員
3番 池 田 幸 弘 議員
4番 田 中 秀 一 議員
5番 宇 都 修 一 議員
6番 江川野 一 成 議員
7番 南 鶴 洋 志 議員
8番 鮎 川 浩 一 議員
9番 上須田 清 議員
10番 日 髙 信 一 議員
11番 北御門 伸 彦 議員
12番 吉 元 勇 議員
13番 土 屋 工 吉 議員
14番 鶴 田 均 議員
15番 田 上 真由美 議員
16番 杉 本 尚 喜 議員
17番 出 水 睦 雄 議員
18番 中 嶋 敏 子 議員
19番 道 上 正 己 議員
20番 髙 崎 正 風 議員
-------------------------------------------------------
地方自治法第121条の規定による出席者
椎 木 伸 一 市長
吉 田 定 男 副市長
冨 田 忍 政策経営部長
山 元 周 作 総務課長
戸 﨑 基 夫 くらし安心課長
益 山 剛 くらし安心課防災対策監(参事)
大 田 直 子 財政課長
青 﨑 譲 二 企画政策課長
福 川 正 樹 企画政策課秘書監(係長)
山 﨑 裕 樹 企画政策課総合政策係長
田 中 一 将 情報課長
柿 木 彰 保健福祉部長
谷 川 弘 之 健康増進課長
田 畑 幸 二 いきいき長寿課長
宮 﨑 毅 市民部長
松 原 淳 市 市民生活課長
堂之上 健 二 生活環境課長
松 岡 秀 和 商工観光部長
松 井 勉 商工観光部参与(文化財・ツル博物館担当、文化財課長兼補)
駒 壽 ひとみ 観光交流課長
濵 畑 信 一 市民スポーツ課長
揚 松 智 幸 農林水産部長
中 原 克 章 農政課長
小 原 一 郎 建設部長
小田原 豊 道路河川課長
松 尾 善 博 道路河川課管理係長
永 山 勝 久 道路河川課課長補佐兼建設第一係長
松 﨑 和 洋 道路河川課維持係長
大久保 哲 志 教育長
溝 口 雄 二 教育部長
床 並 伸 治 学校教育課長
川 添 直 生涯学習課長
-------------------------------------------------------
議会事務局
春 田 和 彦 局長
華 野 順 一 次長(課長補佐級)
中 村 勇 士 主任主査
野 﨑 育 美 主査
北 紘 至 主査
-------------------------------------------------------
付議した事件
一般質問
午前10時00分 開 議
△ 開 議
○議長(田上真由美議員) おはようございます。ただいまの出席議員は20名であり、定足数に達しております。これより令和4年出水市議会第3回定例会第4日の会議を開きます。
-------------------------------------------------------
△ 議 事
○議長(田上真由美議員) これより議事日程により、議事を進めます。
-------------------------------------------------------
△ 日程第1一般質問 上程
○議長(田上真由美議員) 日程第1、一般質問を議題とします。
これより9日に引き続き、一般質問を続行いたします。
質問順に従い、宇都修一議員の質問を許します。
○5番(宇都修一議員) おはようございます。本日一般質問3日目の1人目でございます。朝一ですので、爽やかに進めたいと思います。
さて、今回は、住みやすいまち出水市がさらに住みやすいまちになることをテーマに質問を行いたいと思います。
まず初めに、大項目1番、住みやすいまち鹿児島県ナンバーワンの出水市がさらに住みやすいまちになるためにの小項目1番、3年連続、鹿児島の住みやすいまちナンバーワンに選ばれたが、その要因は何かについてお尋ねします。東洋経済オンラインでは7月15日付けで「住みよさランキング2022」九州沖縄・中国・四国編が発表され、出水市は3年連続で鹿児島県で1位となりました。昨年度は、出水市のことを「畜産が盛んで、全国有数の農業産出額を誇る。『安心度』の評価が高く、その指標のうち『20~39歳女性人口当たり0~4歳児数』(全国55位)と『子ども医療費助成』(全国3位)のスコアが高い。」と評価してありましたが、2022年度版はサイトを見る限りでは特にそのような説明はありませんでした。つきましては、この出水市が住みやすくなるためにどのような政策をしたのか、そしてその成果や市民の評判はどうなのか分かる範囲でお答え願います。
次に、小項目の2番ですが、小・中学生の登下校の荷物を減らす工夫はできないのかについてお尋ねします。子供たちの荷物が重そうだなと感じるときがあります。学力を上げるためには仕方のないことかもしれませんが、教科書以外にも時には辞書やいろんな教材があると思います。水筒も持っています。たしか小学生は原則徒歩、中学生も2キロメートル以内は徒歩となっていると思うんですが、重い荷物を背負って長い距離を歩くのは大変だろうなと思います。そのあたり検討の余地がないのかお尋ねします。
次に、小項目の3番ですが、プール授業の目的は何か、時期は適正か、まだ寒い時期に始まって、まだ暖かいうちに終わってないかについてお尋ねします。これは、ある子供を持つお母さんから相談を受けまして、お尋ねするものです。プール授業を楽しみにしている子供たちも多く、水難事故から守るという目的もあるようですが、実態はどうなのかお尋ねします。
次に、小項目の4番ですが、戦争遺跡の保存をどのように考えているのか。ウクライナではなかなか戦争が終わらない。このような悲劇を繰り返さないためにも戦争遺跡の保存は重要であると思います。また、民間が保有している施設も多いが、どのように考えるかについてお尋ねします。出水市の場合、戦争遺跡の多くが民間の所有になっているようです。私はできるだけ多く残すべきと思っていますが、実際に戦争遺跡を保有している民間の方は壊すこともできずに困っている人も多いようです。難しいとは思いますが、残すべき遺産はどれなのか、どうやって保存していくのか考えをお尋ねします。
次に、小項目の5番目ですが、戦争遺跡もかなり老朽化していて、人が立ち入るには危険な施設もあるのではないか、耐震調査などは実施しているのか、必要に応じて補強工事等を行う考えはないかについてお尋ねします。戦争が終わって、80年近くになります。例えば、広島の原爆ドームなどは補強工事がされています。すぐに解決できる問題ではないかもしれませんが、もうそろそろ検討する時期に来ているのではないかと思います。
次に、小項目の6番ですが、魅力ある観光地づくり事業で整備した戦争遺跡について、昔は掩体壕の下に実物大の戦闘機の模型を置いてあったこともあったそうです。そのようなことで観光に配慮した整備をするつもりはないかについてお尋ねします。例えば、平和町の掩体壕については、この事業により駐車場が整備されましたが、肝心の掩体壕はかなり傷んでおり、周りも雑草が生い茂っているような気がします。せっかく県の事業で整備していただいたのに、肝心の掩体壕があれではちょっと申し訳ないなと思います。知覧に行った方が出水に寄ることもあると思います。そのような方々に感動を与えるような整備をする必要があるのではないかと思います。
次に、小項目の7番ですが、外国人の在住者について国籍、性別ごとに何人いるのかをお尋ねします。出水市も昔と比べて外国人の姿をよく見かけるようになりました。特に自転車に乗っている人は中高生を除けば圧倒的に外国人が多いと思うのですが、どこから来た人がどれくらいいるのか知りたい人も多いと思います。ただし、全部は大変ですので、人数の少ない国についてはまとめて教えてください。
次に、小項目の8番ですが、外国人の在住者向けのごみ出しのパンフレットを作るつもりはないかについてお尋ねします。日本に来た外国人は、その国民性の違いもあり、地域のごみ出しのルールが難しいのではないかと思います。すぐには難しいかもしれませんが、検討するつもりはないかお尋ねします。
次に、大項目2番、ふるさと納税についてどのように分析しているかの小項目1番、出水市のふるさと納税の額は、県内の自治体では何番目になるのか、平均より多いか少ないかについてお尋ねします。何事も分析し検証することは大事だと思います。
次に、小項目2番の出水市のふるさと納税の出品に際して、アンケートを実施してはどうか、また、出品者だけではなく、出品をしなかった方々にも実施したらどうかについてお尋ねします。
次に、小項目3番の使い道を選べるふるさと納税はできないかについてですが、これは、例えば、この出品物は、その納税額の一部を戦争遺跡の維持費用に充てます、あるいは、まちテラスの費用に充てますとか、各地域の夏祭りの費用に充てますなどにすると、その関係者もふるさと納税に協力してもらえるんじゃないかと思います。どれくらいの割合に充てるのか、そのあたりはお任せします。
次に、大項目3番の本年秋に行われる「和牛オリンピック」について本市の取組を伺うの小項目1番の鹿児島県代表牛24頭のうち1頭が出水市から選ばれたのは大変すばらしいことである。東京オリンピックの時のように懸垂幕などで応援することはできないかについてお尋ねします。8月30日の南日本新聞に載っているのを見ました。この件については、先の6月議会でも質問させていただいたこともあり、感慨深いものがありました。そして、先の東京オリンピックでも一山選手たちの懸垂幕が飾ってあったのを思い出しまして、今回は牛ですが、ぜひ同じように飾っていただきたいと、そして応援したらどうかと思います。
以上をもちまして、壇上での1回目の質問を終わります。
○椎木伸一市長 おはようございます。宇都修一議員の御質問にお答えいたします。
まず、東洋経済新報社が発表します「住みよさランキング」におきまして、3年連続、鹿児島県で第1位に選ばれたことは大変うれしく思っております。
掲載されたサイトの中で見る限り、本市は、ランキングの算出指標となっております安心度、利便度、快適度、富裕度のうち、対象の812市区で、安心度で47位、利便度で95位、快適度で87位と3指標においてトップ100に入っているようであります。
中でも、「安心度」の算出指標に含まれる子育て評価偏差値では全国で31位に評価されておりまして、就任以来、一貫して取り組んでおります「こどもの安心」「いのちの安心」「くらしの安心」を柱にした取組が着実に実を結びつつあるのではないかと大変ありがたく思っております。
また、令和2年8月に行いました出水麓地区の用途地域の変更等による規制緩和やリノベーションのまちづくりの取組も実を結びつつありまして、麓地区には今年の6月にオープンしたRITA出水麓宮路邸に続きまして、観光庁の補助事業を活用して、武家屋敷をリノベーションしたホテルやレストラン、土産物店を出店する民間事業者が3件、出水駅から麓地区につながる商店街の空き店舗等をリノベーションして、カフェや飲食店、アートギャラリー等を出店する民間事業者が3件のほか、これまで休止していた施設の再稼働に取り組む店舗もございます。今ある資源を生かし、見てもらい方を変え、稼げる観光地をつくる取組も進みつつあると考えております。
今後におきましても、現在の順位に甘んじることなく、持続可能な、ワクワクするまちづくりにチャレンジしてまいります。
次に、戦争遺跡の保存についてお答えいたします。
現在、市が把握しております市内に残る戦争遺跡は31か所あります。このうち市が所有しているものは、特効碑公園にある戦闘指揮所地下壕跡や平和町の掩体壕をはじめ、8か所ございます。残る23か所の戦争遺跡は、民間の敷地内や畑、山林等に残されています。
これらの戦争遺跡につきましては、詳しい現状やその価値を調べる学術調査はほとんど行われておりません。まずは、戦争遺跡それぞれについて現状調査を行い、その結果によって残すべき価値があるものなのか判断し、それに応じた保存方法をそれぞれごとに検討することが必要と考えております。
次に、戦争遺跡の老朽化についてお答えいたします。
市が所有する戦争遺跡のうち、現状調査等を行ったものについては安全を確保しながら公開していますが、民間の戦争遺跡につきましては、今後、現状を調査する中で保存が必要と判断される場合は、それぞれの戦争遺跡に対してどのような対策が必要か検討したいと考えます。
次に、戦争遺跡の観光に配慮した整備についてお答えします。
現在、本市には3基の掩体壕がございますが、平和町にある2基の掩体壕につきましては、県の魅力ある観光地づくり事業を活用し整備を行っているところです。整備内容としましては、市街地側にある1号基につきましては、平成30年度にトイレ及び駐車場が整備され、本年5月には遊歩道等の一部が完成しています。なお、今年度中に掩体壕の内部工事及び看板設置などの入り口付近の整備が実施され、完成予定となっています。2号基につきましては、令和5年度以降の周辺の整備工事を実施すると県からは伺っています。
この2基の掩体壕につきましては、ひび割れ等の劣化が確認されたことから、平成27年度に補強工事を行いました。また、掩体壕周辺の草刈り等につきましては、市職員や出水市平和学習ガイドの会が不定期で行っているところですが、周辺景観を損なうことのないよう、引き続き適正な環境整備に努めてまいります。
なお、過去に掩体壕の下に実物大の戦闘機の模型が設置してあったとのことでありますが、市では確認はできておりません。
掩体壕を含む出水航空基地戦争遺跡については、平和学習のような教育的活用のほか、希少性の高い遺跡を見学できる観光的活用ができますが、魅力ある観光地づくり事業による掩体壕の整備完了後は、観光資源の一つとして期待していることから、本市の主な観光資源であるラムサール条約登録湿地や出水麓武家屋敷群とも組み合わせた新たな観光ルートとして、観光客の誘致を図ってまいりたいと考えております。
次に、外国人の在住者の国籍、性別ごとの人数についてお答えいたします。
本年7月31日現在、本市に在住している外国人の人数は、26か国で、男性が299人、女性が539人、合わせて838人となっております。国ごとの詳細につきましては、後ほど市民部長のほうから答弁をいたします。
次に、外国人向けのごみ出しパンフレットについてお答えいたします。
外国人の市内居住者につきましては、外国人技能実習制度等を活用した就労者が多いことから、転入時に「リサイクル品」と「家庭ごみ」の分け方・出し方のパンフレットを配布し、雇用主である事業者からごみ出しの指導を行っていただいているところであります。本パンフレットは、日本語版に加え、中国語版もあり、必要に応じて活用しています。また、市のホームページにおいては、ごみの収集日やリサイクルに関することを英語や韓国語、中国語、ベトナム語でも閲覧できるようにしています。そのほか、ベトナム語や英語にも対応しましたごみの収集日のお知らせ機能などがあるごみ分別アプリ、「さんあ~る」を導入して、適正なごみの出し方の周知にも取り組んでいます。
本市においては、現在26か国の外国人の方が居住されており、言語が多岐にわたることから、全ての言語に対応したパンフレットの作成は難しいところではありますが、まずは外国人を雇用されている事業所等にも御意見を伺い、ごみ出しパンフレットの必要性やごみ出しのルールを守っていただくための手法を研究していきたいと考えます。
次に、ふるさと納税の御質問でありますが、令和3年度の本市のふるさと納税額は、4億2,658万6,500円で、県内19市中15位、県内43市町村中では19位となっております。
県内19市の平均は約16億833万6,000円、県内43市町村の平均は9億2,503万2,000円となっており、いずれも平均額に達していませんが、多額の寄附を受け入れている上位少数の自治体により平均額が押し上げられている状況となっています。
次に、アンケートの実施についてでありますが、現在、観光特産品協会と市が分担して事業者に直接出向き、出品事業者の開拓や返礼品の開発を進めております。また、協会では既に出品している事業者に対してのフォローも行っております。
アンケートの実施につきましては、現時点では実施の予定はございませんが、協会と連携して取り組む中で必要に応じて検討したいと思います。
次に、使い道を選べるふるさと納税についてでありますが、使い道につきましては、寄附される際に条例で定めた自然環境を守り育む事業、未来を担う人づくりの事業、地域資源の保全と活用を図る事業、その他地域活性化など目的達成のために必要な事業から選択していただいているところです。
なお、特定の事業を指定するふるさと納税の手法としてガバメントクラウドファンディングがありますが、必要性と効果を慎重に検討して取り組む必要があると考えております。
次に、「和牛オリンピック」に対する本市の取組についてですが、10月に本県で開催される全国和牛能力共進会に、本市から合同会社林ファームの1頭が鹿児島県代表として肉牛の部に出品することが決定しました。
このことを受けまして、本市では応援のための懸垂幕を市役所本庁に既に掲示したところであります。また、大会の周知と併せてホームページにも掲載し、広報いずみ10月号への掲載も予定しております。
なお、平成29年度に宮城県で開催されました前回大会では、本市から肉牛の部に出品した1頭が入賞し、鹿児島県の総合日本一の受賞に寄与されたことから、今大会においても好成績を収められることを期待しているところであります。
○大久保哲志教育長 おはようございます。宇都修一議員の御質問にお答えします。
まず、小・中学生の登下校時の携行品についてですが、教科書やその他教材、体育用品等が過重になることで身体の健やかな発達に影響が生じかねないことなどから、平成30年9月に文部科学省から「児童生徒の携行品に係る配慮について」の事務連絡がありました。
本市では、各学校に保護者等とも連携し、児童・生徒の携行品の重さや量について改めて検討の上、必要に応じ適切な配慮を講じるよう指導し、家庭学習で使用する予定のない教材を机の中などに置いて帰ることや、学校で栽培した植物等を持ち帰る場合、児童の状況等を踏まえ、保護者が学校に取りに来ることとしました。
今後も、教科書やその他教材等のうち、何を児童・生徒に持ち帰らせるのか、また何を学校に置くこととするかについて、保護者と連携し、児童・生徒の発達段階や学習上の必要性、通学上の負担等を踏まえた配慮を講じていきたいと考えています。
次に、プール授業の目的等についてですが、プールでの水泳指導は、水泳で求められる身体能力を身につけること、また水中での安全に関する知的な発達を促すこと、さらに水の事故を未然に防ぐ論理的な思考力を育むことを狙いとしています。
市内各小・中学校の水泳授業の実施時期についてですが、今年度の場合、最も早い学校では5月30日から開始し、全ての学校が1学期末で終了しています。
水泳を実施する際、各学校では必ず水温と気温、水質等の確認を行っており、5月30日から6月3日の週に水泳を開始した学校では、授業直前の水温と気温の合計が、おおよそ50度を超えていることを確認しています。
プールの適正な水温については、全国で統一した基準はありませんが、文部科学省が作成した「水泳指導の手引」の中で、水温は23度以上であることが望ましく、上級者や高学年であっても22度以上の水温が適当と言えるが、実際は、対象者の学年、能力、水温、気温、学習内容などを考慮して判断することが大切とされていることから、市内の各小・中学校では、おおむね水温と気温の合計が50度を下回る場合は実施しないなど、寒さへの対応をしながら水泳授業を実施しています。
先ほども申し上げたとおり、最も早い5月30日以降の時期において、実施時の水温と気温の合計がおおよそ50度に達していることから、実施時期については適正であると考えております。
○宮﨑毅市民部長 本市の外国人の在住者の国籍、性別ごとの人数でございます。先ほど市長も申しましたとおり、本年7月31日現在で本市に在住している外国人の方でございます。
まず、10人以上在住している国でございます。人数の多いほうから申し上げます。ベトナムが、男性161人、女性262人、合わせて423人。それから、中国が、男性45人、女性111人、合わせて156人。フィリピンが、男性11人、女性78人、合わせて89人。それから、ブラジルが、男性36人、女性29人、合わせて65人。インドネシアでございます。男性13人、女性19人、合わせて32人。カンボジアです。男性5人、女性9人、合わせて14人。韓国です。男性6人、女性7人、合わせて13人となっております。
それから、10人未満の国につきましては、アメリカ、ネパールのほか17か国ございまして、男性22人、女性24人、合わせて46人となっているところでございます。
○議長(田上真由美議員) 宇都修一議員より書画カメラの使用について申入れがありましたので、許可しております。
○5番(宇都修一議員) まず初めに、順番を入れ替えて、大項目3番、本年秋に行われる「和牛オリンピック」について本市の取組を伺うを先にします。
早速立派な懸垂幕をされたみたいで、動きが速いなと思いました。50年ぶりの地元開催ですから、出水の牛が出品されるというのは大変すばらしいことだと思います。出品者の林さんですけど、以前、市で持っていた野田の堆肥センターも引き継いでもらっていて、あそこも大変苦労したんですけど、大変いい人に引き継いでもらったなと思っています。健闘を祈ります。
これで、大項目の3番の質問は終わります。
次に、大項目1番、3年連続、鹿児島県の住みやすいまちナンバーワンに選ばれたが、その要因は何かですが、市長が今言われたように、安心度とか子育て支援とか、そういうのを頑張っていらっしゃるということをお聞きしました。なるほどなと思ったんですけど。
そこで、市長の答弁の中で観光庁の補助事業という話がありましたけど、よかったらそこのところをもうちょっと詳しく教えていただけますでしょうか。
○松岡秀和商工観光部長 観光庁の補助事業、地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業という事業でございまして、観光地の顔となる宿泊施設を中心としました地域一体となった面的な観光地の財政高付加価値化のために施設改修事業等を国が支援するものでございます。補助率が原則2分の1となっておりまして、今回採択されました事業は、民間事業者が連携をして、直接補助申請をされたものでございまして、観光庁のホームページでの公開内容も限られておりますので、個別事業の詳細というところまではちょっと申し上げにくいところでございますが、市長が答弁をしましたとおり、出水麓の武家屋敷のリノベーションが3件、出水駅から本町商店街の空き店舗のリノベーションが3件、既存施設の改修1件が市内の6つの事業者により予定をされておりまして、事業総額は約2億円と伺っております。この事業者の中に若手の事業者の方も参画をされているようです。これまで取り組んでまいりました麓の用途地域の見直しとか、リノベーションまちづくりが目に見える形で成果が現れ始めたかなというところでございます。なお、リノベーションまちづくりに関しましては、この補助事業とは別に本町商店街に今月末までにさらに2件の店舗が開業予定でありますほか、年内開業を目指している事例も1件あるところです。
○5番(宇都修一議員) よく分かりました。今後もさらに住みやすくなるまちを願いまして、小項目1番の質問を終わります。
次に、小項目の2番ですが、小・中学生の登下校の荷物を減らす工夫はできないのかについてですが、既に平成30年のそういう通知に基づいて実施をしているということをお伺いしました。ちょっと安心したんですが、せっかくですので、質問を続けさせてもらいます。
長い距離を歩く子供たちにとっては大変だろうと思います。例えば、平和団地から西出水小学校まで3キロ、ほかにももっと遠くから歩いてくる子供たちがいると思います。書画カメラ1番をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)これは、最近話題になった「さんぽセル」という商品です。これを宣伝するつもりじゃなくて、この中にこう書いてあるんです。小学生が数キロのランドセルを背負うことによる慢性的な腰痛や背骨への負担、ストレスなどが懸念されている。一般社団法人教科書協会の「教科書発行の現状と課題」によると、小学校1年生から6年生が使う教科書のページ数は、全教科の合計が2005年の4,857ページから、2020年度は8,520ページと倍近くに増加とあります。小学生の平均体重は、小学校1年生男子で21.4キロ、6年生男子で38.7キロだそうです。一方、ランドセルのほうは、水筒と合わせると6キロぐらいあるんじゃないかと書いてありました。実は、私、最近痩せて、80キロぐらいなんですけど、私の体重に換算すると、20キロの子供が5キロの荷物を持つということは、私、80キロですので、20キロの荷物を持つということになるそうです。私、ここにスーパーで売っている米を持ってきたんですけど、ちょっと重いんですけど、これ5キロです。私だったらこれを4つ担いで歩かないといけないということで、大変だなと思ったところです。教育長からお聞きしましたけれども、平成30年の通知により既に実施されているということですので、ぜひ父兄の方々と相談をしながら、学力も大事ですので、その辺兼ね合いはあると思いますけど、進めていっていただきたいと思います。この話ですね、実は、このことについて子供たちにも何人か聞いてみたんです。「荷物は重い」と言う子供も多かったんですけど、ある子供は、「重いけど、自分には夢がある」と、「夢があるから頑張るんだ」ということを言うので、「その夢って、何」って聞いたら、「私は、大人になって、ニュースキャスターになって、お天気お姉さんになりたい」と、「そのためにはいっぱい勉強したいから、重たいけど、頑張る」と言ってました。出水にもいい子供たちがいっぱい育っているなと思いました。先生たちのほうが詳しいかもしれませんけど、成長過程で骨の成長とか筋肉の成長が追いつかなかったりするらしくて、個人差もあると思うんですけど、腰を痛めたりとか、ひどい場合は背骨が曲がったりとかすることもあるらしいので、対応をよろしくお願いします。
以上で、小項目2番の質問を終わります。
次に、小項目の3番ですが、プール授業の目的は何か、時期は適正か、まだ寒い時期に始まって、まだ暖かいうちに終わってないかについてですが、今お話をお聞きしましたが、水温、気温も適正だということでした。
私のところに相談に来られた保護者の方々が言われるには、9月に運動会があるので、夏休みが終わると、プールをやめて、運動会の練習に切り替えないといけないから、プールはないんじゃないかということを言われるんです。ここで書画カメラ2をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)これはインターネットで調べたら出てくるんですけど、出水市の気温なんですけど、ちょっと見にくいですけど、6月中旬から9月の後半にかけて暖かい時期が続くんです。ただ、6月、7月にかけて、真ん中の赤いところが暖かい時期なんです。その上に降水量があります。6月は雨が多いんですね。保護者の方々は、唇が紫色になっているんじゃないかとか心配されるわけなんですけど。ちまたでは、10月、11月は稲刈りや米取り等でみんな忙しいから、運動会が9月になるんだと、その関係でプールは早く終わるんじゃないかという人がいらっしゃるようなんですけど。だったら、運動会をずらせばいいじゃないかという方もいらっしゃるんですけど、運動会のせいでプールが早く終わるということなのかなと思って、そのあたり、教育長、どうですか。
○大久保哲志教育長 水泳授業の時期が1学期中にあるということについてですけども、今、保護者の方の認識で、9月は体育大会とか運動会等があるので、1学期に済ませているんじゃないかというお話がありました。そういったこともあながち間違っていることではないんですけども、まず一番は、先ほどの話をした中でも、水の事故を未然に防ぐ論理的な思考力であったり、水中での安全に関する知的な発達を促すという話をしましたとおり、まず安全指導面で夏季休業の前にどうしても水泳指導をやるという必要があるということ、これがまず一番最初にあります。
それから、先ほどお話しされました2学期はという話ですが、これは運動会に限らず、2学期は、学校は運動会とか体育大会以外にも修学旅行とか陸上記録会とか文化祭、様々な行事が計画されていたりして、体育の授業も計画的に運用する必要がございまして、そういったことも理由の一つにございます。
それからまた、先ほど安全指導面のことをお話ししましたけども、今よく話題になる熱中症の対策でございますが、熱中症についてもプールの水温が33度を超えると水中でも熱中症の心配というのが出てくるということもございまして、時期からしますと9月の水温というのはかなり高くなってくることもありますので、こういったことも含めると1学期のうちにやっておくことが望ましいという、こういったことがあると。またそれから、これは維持管理の面でもあるわけですけども、1学期にスタートする水泳を、夏季休業を含めて2学期までする場合は、今度はプールの水の衛生管理等、こういったもので維持管理等にも負担がかかると、こういったことの理由が考えられます。
○5番(宇都修一議員) 分かりました。そういうちゃんとした理由があるんなら、疑問に思っていた方々も納得されると思います。小項目の3番の質問を終わります。
次に、小項目の4番ですが、戦争遺跡の保存をどのように考えているのか。ウクライナではなかなか戦争が終わらない。このような悲劇を繰り返さないためにも戦争遺跡の保存は重要であると思う。また、民間が保有している施設も多いが、どう考えるかですが、先ほど市長からも答弁いただきましたけれども、それに向けて検討を進めているということでしたので、早期の解決を期待しまして、小項目4番の質問を終わります。
次に、小項目の5番目ですけど、戦争遺跡もかなり老朽化していて、人が立ち入るには危険な施設もあるのではないか、耐震調査などは実施しているのか、必要に応じて補強工事等を行う考えはないかですけれども、そちらのほうも、先ほど答弁をいただきまして、進めているということでしたので、こちらのほうも早めの解決に期待して、小項目の5番を終わります。
次に、小項目の6番目、魅力ある観光地づくり事業で整備した戦争遺跡について、昔は掩体壕の下に実物大の戦闘機の模型を置いてあったこともあったそうだが、そのようにより観光に配慮した整備をするつもりはないかですけれども、私もそう言われて調べたんですけど、ちょっと分からなかったんですけど、一つには過去にあったということだけじゃなくて、そういうことをすると観光客も喜ぶんじゃないかという気持ちもあったんじゃないかなと思います。その辺もぜひ検討していただきながら、関係している方々と十分な協議も必要だと思いますけれども、魅力ある観光資源になることを期待して、小項目6番の質問を終わります。
7番の外国人の在住者について国籍、性別ごとに何人いるかお尋ねしますに入ります。
ここで書画カメラ3をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)ちょっと見にくいかもしれませんけど、左側が鹿児島県、右側が全国です。左側、青いところ、ベトナム人の方なんですけど、圧倒的にベトナム人が多いということで、これは出水市でもベトナム人が多いということで、鹿児島県全体的にベトナムの方が多いということのようです。ところが、右側は全国なんですけど、右側で全国的に見ると、やっぱり中国の方が多いらしいんです。この辺の微妙に違う理由というのを今後研究していく必要があるんじゃないかなと思うところです。ここで書画カメラ4をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)これは、鹿児島県における外国人の数です。県が発表している、鹿児島の国際交流だったかな、その冊子に載ってたんですけど、ちょっと見にくいですけど、平成26年で6,773人だったのが、令和元年では1万2,215人と5年間で倍に増えています。今コロナで止まっていますけど、コロナがもし終わったら、またさらにドンと増えるんじゃないかなと思うところです。
今後ますます外国人は増えていくと思うんですけど、私、先週土曜日に市役所でありました「地域の観光人材のインバウンド対応能力強化研修」に参加させていただきました。その中で、講師の先生も「外国人の観光客が今後増えていくだろう」と言われました。外国人の方についていろいろな相談をワンストップで対応できる窓口が必要になってくるんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりはまた次の機会に質問させていただきたいと思います。
小項目の7番の質問を終わり、8番の外国人の在住者向けのごみ出しのパンフレットを作るつもりはないかに入ります。
答弁のほうで既にパンフレットはできているということを聞いたんですけど、それはアプリですか、それとも紙ですか。
○堂之上健二生活環境課長 紙で制作しております。
○5番(宇都修一議員) その紙は、何部ぐらい作って、どの程度配布してあるのか、もし今ここで分かったら教えてください。
○堂之上健二生活環境課長 枚数等につきましては、正確には把握してないところです。
○宮﨑毅市民部長 すみません、先ほどのパンフレットの話なんですけれども、紙でのパンフレットは日本語版に加えて中国語版もあるというところ、それから市のホームページではいろんなごみに関するお知らせ、収集日であったりとか、そういうのも出ておりますので、それについては、ホームページは全体的に掲載されている部分を、日本語版はもちろんですけど、英語であったりとか、中国語であったりとか、それで置き換えてというか、閲覧ができるようになっているというところです。あと、市長が申しました、ごみの分別アプリ「さんあ~る」については、ベトナム語とか英語にも対応しているという状況でございます。
○5番(宇都修一議員) ホームページとか「さんあ~る」、「さんあ~る」は私も携帯に入れていて、これは便利なんですけど。ただ、ベトナムの方がここにいて、その人にホームページのどこに載ってますよと案内できる人がいるのか、あるいは、「さんあ~る」というアプリをベトナム人が持っているとしても、これをどうやって入れるのかと説明できる人、ちょっと難しいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりそういうふうな紙があったほうが、ポスターとか、例えば、後でも話しますけど、そういう地域で外国人の方の問題が出たときでも気軽に配れるので、紙であったほうがいいんじゃないかなと思うところです。ここで書画カメラの5番をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)先日、うちの自治会のごみステーションにたくさんのごみが出されてまして、これはせっかくここまで持ってきてあるんですけど、惜しいことに分別がいまいちなので、このままじゃ収集してもらえないんですよね。中身を調べてみると、ベトナムの方だったようです。これですね、ある程度ちゃんと分別されて、ごみステーションに持ってくるところを見ると、ちゃんと教えればできるんじゃないかなと思うんですよね。ここで書画カメラ6をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)これはあるサイトのコピーなんですけど、左側にお姉さんがこんな顔して、何かあきれ顔で載ってるんですけど、読みますね。「うちの近所にある外国人が多く住むアパートが大変なことになっています。ごみが散乱しているのです。生ごみを指定のボックスに入れないため、猫やカラスが散らかして、さらに通りすがりの車が踏みつぶして周囲の道路にまで広がっています。おまけに洗濯物を所構わず干すので、風で飛んだり、下着が道沿いに陳列されたりしています。あまりにも衛生面や景観面に問題があるので、周囲の自治会の方が眉をひそめていました。」こんな感じで女の人が写っていますけど、これ何にあきれているのかなと思ったんですけど。ここで書画カメラの7をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)ごみ問題が1日で解決したそうです。その方法とはということで、そこに書いてあるんですけど、「ある日突然ぱったりなくなりました。集積所まわりはきれいにされているし、分別もしっかりしてあります。指定日以外の粗大ゴミも見当たりません。事情を知っている人に話を聞くと、どんな対策をしたのか尋ねてみました。とった対策は、たった2つ。ごみ出しなど生活ルールの英語表記を貼り出した、管理会社が入居者向けの説明会を開いた」、そういうことらしいです。これですね、サイトの情報から見ると、多分都会の例だと思うんですけど、出水でもそのまま当てはまるかどうかは分かりませんけど、外国人を雇っている人、何人か聞いたら、ぜひ作ってくれということでした。ということで、やっぱり紙のパンフレットも作っていただきたいなと思います。英語版は職員でTOEFL高得点を取った人もいますし、中国語、韓国語も観光交流課で対応できるんじゃないかなと思います。ベトナム語も、平和町に人材派遣の会社があって、協力してくれると思いますので、ぜひ検討してください。
あと、外国人を雇っている事業者の方々を集めての説明会も実施したほうがいいんじゃないかなと思います。県にも国際交流課があるので、協力してくれると思いますので、このあたりはまた次の機会で質問したいと思います。
うちの自治会でもいろいろ話をするんですけど、せっかく日本に来て、出水に住んだからには日本はいいところだったなと、出水に来てよかったなと思って帰ってもらいたいと思います。私たちも自分たちの周りにどこの国の人たちがどれだけ住んでいるのか分からない。それを解決するにはどうしたらいいか。で、考えたんですけど、地域で外国人と地元との交流会をする、外国人に対してアンケートを取るなどしたらどうかなと思っているところです。それも今回通告してませんので、次の機会に質問したいと思います。
今、労働者として出水に来られている人たちも、将来、家族を連れて、また出水に観光に来たいなと、そんなふうに思っていただけるようなおもてなしができたらいいなと思います。
以上で、大項目1番の住みやすいまち鹿児島県ナンバーワンの出水市がさらに住みやすいまちになるためにを、日本人だけではなく、外国人にとっても住みやすいまちになるように期待を込めて終わります。
次に、大項目2番のふるさと納税についてどのように分析しているかの小項目1番、出水市のふるさと納税の額は、県内の自治体では何番目になるか、平均より多いか少ないかに入ります。反問権、ウエルカムですので、どんどん言ってくださいね。書画カメラ9番をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)これですね、総務省のポータルサイトに出てくるんですけど、額でいうと、出水市は15番目、これは市でだったかな、私が注目したいのは12番目の薩摩川内市と13番目の鹿児島市です。書画カメラ10番をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)出水市と鹿児島市と薩摩川内市のところをちょっと拡大してもらっていいですか。これは、人口1人当たりの額です。出水市は4億2,658万7,000円で、人口は5万2,471人ですから、8,130円ということになっているようで、県内では同じく15番なんですけど、薩摩川内市は17位、鹿児島市は19位です。書画カメラ11番をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)これは、役所の職員1人当たりの額です。こちらも出水市は15位なんですけど、薩摩川内市は17位、鹿児島市は19位です。ちなみに、鹿児島市は、職員1人当たりは10万円なんです。これは、1位の志布志市は1,665万円ですから、鹿児島市の166倍あると思います。
私なりに分析したときに、鹿児島市、薩摩川内市、出水市に共通しているのは何かというと、新幹線の駅があるという話なんですよね。この納税額を頑張っている南薩とか大隅とか、このままでは町が寂れていくという危機感が相当あると思うんですよね。ちなみに、私、佐多町に住んでいた叔母が一昨年亡くなったんですけど、佐多岬のすぐそばの町で、広さ的には東辺田と西辺田を合わせたぐらいだと思うんですけど、昨年初盆に行って、びっくりしたんですけど、ちょっと前まで49戸あったそうです。それが、今は2人しかいないと。2戸じゃなくて、2人なんです。まだちゃんと住めそうな家もいっぱいあるんですよ。でも、誰もいないと。2人とも70代で、「もう限界集落を通り越して、消滅寸前だ」と言ってました。
このように、地域によっては危機感が半端ないということで、地元の人たちとか都会で働いている出身者が一生懸命協力してくれると思うんです、ふるさと納税ですからね。こういうところは、この議場にいる皆さんも、例えばこの中で、じゃあ、俺は都会にいる親戚や友人にふるさと納税してくぃやんと頼んだことがあるとか、そういう人は少ないと思うんですけど、これからはそういうことをみんなでやっていったほうがいいんじゃないかなと、するべきじゃないかなと思うんです。これですね、担当者にやいのやいの言ってもしょうもないので、みんなで頑張るほうがいいなと思います。薩摩川内市や鹿児島市も担当がさぼっているわけじゃないと思います。恐らく優秀な担当者が担当していて、何でかなと首をひねっていると思うんですけど。そして、総務省がなぜこのような統計を取るのかということは、私には総務省が何事も市民、職員みんなで頑張りなさいと言っているように思います。
先の議会で目標額について質問がありました。議員は市民の代表であり代弁者でもありますから、そういう質問もありだと思うんですけど、例えば、売上げが昨年8,000万円、今年は9,000万円ぐらいだとなると、来年目標は1億円ですと言えると思うんですけど、このふるさと納税、ちょっと難しいんじゃないかなって。下手に言うと、その根拠は何かと。また、目標にいかんかったら、努力が足らんとじゃないかと言われる可能性もあるので、簡単に幾らと言えないんじゃないかなと思ったりもするんですけど。
ここでお尋ねしますけど、ふるさと納税の目標額について、市として具体的に金額を提示できるような材料がそろっていないというのが実情じゃないかと思うんですけど、そのあたりはいかがでしょうか。
○冨田忍政策経営部長 材料がそろわないのが実情ではないかというお尋ねでございます。目標として私どもが外に出しているのは6億7,000万円、それは返礼品の換算にしますと、まずは2億円の地場産品の売上げが上がるようにと、地場産品、地域の経済振興のために、まずは地元から売れる商品額が2億円、そこを目指そうということで取り組んでいるところでございます。
○5番(宇都修一議員) 分かりました。それから、ふるさと納税に興味を持ってもらうのは大変いいことなんですけど、いろいろ調べていくと、ふるさと納税をやりたくなるんですけど。でも、ちょっとそこは考えてもらって、ほかの町にふるさと納税をしちゃうと、出水に税金が入ってこなくなるので、できたら出水にお住いの方はちょっと考えてもらいたいなと思うところです。
それでは、次に小項目の2番、出水市のふるさと納税の出品に際して、アンケートを実施したらどうかに入りたいと思います。また、出品者だけではなく、出品をしなかった方々にも実施したらどうかですが、書画カメラ12番をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)上から順に出水市、紋別市、都城市の順に並んでいます。「寄附者と継続的な関係を構築するための取組を行っていますか」とあります。これは、つまり総務省は納税額を増やすためにはこれをしたほうがいいぞと教えてくれているわけなんですけど、紋別市はインスタグラムを使っている、都城市はオンラインイベントや調理体験をしたと書いてあります。出水市は楽天を通じてメールマガジンを配信しているということをこの前お聞きしたんですけど。あのですね、楽天を通じて買い物すると、した方は分かると思いますけど、楽天から山のようにメールが来るんです。その中から出水市の分を選ぶというのはなかなか難しい。あまり見てないんじゃないかなと思うんです。市長からメールが来れば見るとは思うんですけどね。あと、右上のほうにCRMとあります。「CRMの取り組み」。これは、私が書き足したんですけど、Customer Relationship Managementという略なんですけど、分かりやすく言うと、顧客の名簿管理です。議員の皆さんは得意分野だと思うんですけど。
ふるさと納税において、行政と寄附者のコミュニケーションを継続して、行政と出品者の信頼関係をつなぐためにも、担当者の熱意も必要ですけど、CRMも必要だと思います。
ここでお尋ねしたいんですけど、分かりやすいようにアンケートと書きましたけど、このCRMをやっていくつもりはないですか、どうでしょう。
○冨田忍政策経営部長 今御提案のCRM、楽天のメールマガジンを使って連携を図るということで、先の一般質問でもお答えをしております。今の御提案に対しては、改めて担当職員とも相談をしながら検討していきたいと思います。
○5番(宇都修一議員) ちょっと思ったより時間がかかっていて、全部いけないんじゃないかと。小項目の2番を終わりまして、3番の使い道を選べるふるさと納税はできないかですけど、書画カメラ13番をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)これちょっと見にくいかもしれませんけど、阿久根市は「寺島宗則旧家保存活用プロジェクト」というのをやっているようです。昨日行ってきましたけど、古城江観の絵が飾ってありました。書画カメラ14番をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)もう一つ、クラウドファンディング型というのがあります。データでいうと5番ですね、「プロジェクトの概要」のところを拡大してください。上から2つ目、岩手県一関市です。出水の野間の関みたいに関所があったところなんですけど、こちらは市民の憩いの場としてNSPファンの聖地「NSPメモリアルスポット」を設置しているということで、若い人たちは知らないと思うんですけど、New Sadistic Pinkというフォークソングのグループがあって、156万円を集めています。三田市では、猫のTNR費用100万円を集めていますね。その下、兵庫県加西市では、第二次世界大戦時の戦争遺跡を活用し、云々ということで、1億円の目標に対して1億8,000万円集めています。目標額1億円で、達成したのは1億8,000万円です。これは1年だとなかなかなので、何年も続けてしたほうがいいんじゃないかなと思います。
ここで、ちょっと時間もあれですけど、提案が幾つかあります。
まず、はがき作戦、無料で送れるはがきを作って、これは市長のはがきがあって、そのところに欄を2つ作って、例えば、欄の右側には私なら私の名前を書いて、あとこれを知り合いに持っていくと。100人に持っていけば、知り合いのところに5枚ずつ配ってきて、これはぜひ都会の子供たちとか親戚とか友だちに送ってくぃやんということはどうかなと思います。
それから、2つ目はSNS作戦、ふるさと納税のサイトに飛ぶような画像を作ってもらって、これをメールとかラインとか、そういうので都会に住む友だちに送ると。こういうふうにですね、はがき作戦、SNS作戦、若い人たちだともっといい案も出ると思うんですけど、こういうことをみんなでやっていくと、検討していくというのはどうでしょうか、お伺いします。
○青﨑譲二企画政策課長 いろいろ御提案いただきました。その効果というところも見ながら検討してまいりたいと思います。
○5番(宇都修一議員) 3つ目は、返礼品の工夫なんですけど、今年は和牛オリンピックが鹿児島で開催されます。出水市も和牛に特化した取組をしたらどうかなと思います。例えば、JAの牛肉じゃなくて、牛肉って生産履歴がついてるので、ただのJAの牛肉じゃなくて、例えば、高尾野の誰誰さんちの牛肉だとか、上場の誰誰さんちの牛肉だとか、そういうふうにすると喜ばれるんじゃないかなと思います。それから、江内には自分のブランド牛を立ち上げている方もいらっしゃいます。こういう人たちに協力してもらって、いろんな人に協力してもらうために、ぜひ市長のトップセールスで口説いてほしいと思うんですけど、市長、その辺いかがでしょうか。
○椎木伸一市長 るる御提案を賜りまして、誠にありがとうございます。
ふるさと納税については、いろいろ各自治体の非常に過熱している競争の中でございます。職員も一生懸命アイデアを出しながら頑張っているんですけれども、今いただいたような御提案も検討の中に入れながら、できるだけのふるさと納税を獲得できるように取り組んでいきたいと思います。
○5番(宇都修一議員) 実は、出水市にはほかの町のふるさと納税のアドバイザーを長年されている方もいらっしゃるんです。こういう方にも、ぜひアドバイスをもらうようにしていったらいかがかなと思っているところです。
それから、出品している人たちで協議会をつくったりとか、そういうふうにして、どうやったらもっと寄附が増えるのか、みんなで話し合う場を設けたらどうかなと思います。
6つ目ですけど、ちょっと私もふるさと納税の出品物を増やそうと思って、いろいろしたことあるんですけど、ちょっと条件が厳しいんじゃないかなと感じるところもあって、その辺をもう少し検討していただけないかなと思うんですけど。みんなでやるために、みんなで協議して、知恵を出し合えば、みんなで視察に行ったりとか、勉強できる場をぜひつくってもらいたいと思うんですけどね。
最後の質問ですけど、私、気持ち的には4億円あったので、来年は8億円、そしてその次の年は倍の16億円、その翌年には32億円ぐらい、個人的にはいってほしいなと思うんですけど。もし30億円にいった暁にはいろいろ要望もある。屋根付きのテニスコートとか、あるいは野球場の横にもサブグラウンドが必要なので、あそこにヘリポートも兼ねたサブグランドを造るとか、そういうのを検討していただきたいんですけど、市長、その辺どうですか。
○椎木伸一市長 市の行政についてはいろんな条件の中で整っていくものだと思っておりますので、いろいろ一つ一つ課題を解決しながら取り組んでいきたいと考えます。
○5番(宇都修一議員) 担当の方も議会でいろいろ質問があると大変でしょうけど、みんなが注目しているやりがいのある仕事だと思って、頑張っていただきたいと思います。
以上で、私の質問を終わります。
○議長(田上真由美議員) ここで、暫時休憩いたします。再開は午前11時20分とします。
午前11時03分 休 憩
午前11時20分 再 開
○議長(田上真由美議員) 再開いたします。休憩前に引き続き会議を続行し、髙崎正風議員の質問を許します。
○20番(髙崎正風議員) それでは、通告順に従い、道路行政とふるさと納税について、一般質問をいたします。
いつになったら収まるのか新型コロナウイルス感染とロシアのウクライナへの軍事侵攻はどうなるのか、それに起因する世界中が政治経済ともに不安定な状況に追い込まれ、軍事面や物価高を招き、国民生活に大きな影響を及ぼしていることは否めない事実であります。一日も早い通常の社会生活が築かれることを望むものでもあります。
それでは、道路行政についてですが、交通機関は人・物・情報を運び、私どもの生活基盤に重要な役割を果たしております。新幹線はもとより、南九州西回り自動車道、北薩横断道路も着々と整備が進み、近い将来には全線供用開始のめどが立ち、本市がどのようにさま変わりしていくのか期待をしているところであります。また、本市においても将来を見据えた骨格道路網が設定され、整備プログラムが策定され、その中で整備優先順位が示されております。
本市は、平成18年3月に1市2町が合併し、現在に至っております。合併当時は均衡ある発展と言葉が当たり前に使われてきました。合併してから16年6か月が経過すると、その言葉が薄れ、忘れられた今日であります。その中、市長、市議の改選もあり、市長も議員も変わり、旧出水市を中心に物事が進められているような気がいたしております。本年4月から旧野田町が過疎地域の指定を受け、過疎地域持続的発展計画が策定され、議会に提案されたことは、均衡の発展が崩れたことになります。時代の流れとはいえ、合併による急速な人口減少を招いてしまったことは反省し、一部過疎で旧市町の活気を失うことのないように均衡ある発展を基礎にした政策をとるべきであります。
これらのことを踏まえ、出水市道路総合計画の整備優先順位の見直しを考えるべきです。そのことは、必然的に旧出水市の方向に人・物の流れが動いていることは、交通量が多くなり、いろいろな場所で渋滞を招き、そういうところから優先して整備が進められ、そうなると旧高尾野町、野田町は優先度が落ちてきます。いつまでたっても整備が進みません。そのことで、優先順位を旧市町ごとに決め、整備していくことが均衡ある発展につながると思います。そこで、出水市道路総合計画の優先順位の考え方を旧市町ごとに考えられないかお伺いをいたします。
次に、高尾野川の矢房橋上流下流付近は、鹿児島県が親水公園として整備されると同時に、ジョギングロードが整備されました。その周辺には、ふれあい公園、温泉センターもみじ、きらめきドームがあります。ジョギングロードは、散策だけでなく、利用者も多く、スポーツ行事などに活用されております。
旧高尾野町時代は、草木の刈り取りが行き届き、非常に良い環境が保たれ、景観もよく、憩いの場として利用されてきました。合併後は、草木などの管理が悪くなってきました。旧出水市方式というのか、予算がないからといって、なかなか整備がなされなく、管理が行き届かなくなりました。二級河川だから、県が管理するからといったような思いなのか、整備がなされないようです。市道高尾野川左岸ジョギングロード1号、右岸2号は、県が管理するのか、市の管理になるのかというところです。そこで、市道高尾野川左岸ジョギングロード1号、右岸2号の県との管理協定はあるのかをお伺いいたします。
次に、ふるさと納税についてですが、私で3人目の質問となります。令和4年第2回定例会で一般質問しましたが、納得できないところがありましたので、再度質問をいたします。
将来の目標値をお尋ねしましたら、本年度の目標値も将来の目標値も6億7,000万円と同じ金額の答弁がありました。それに、合わせて反問権も行使されました。私の50億円目標の公約について説明が求められ、少しでも私は参考になるように例えて説明したら、全然具体性がないとか、事業計画は立てられたのかとお聞きしたいとの反問権でありました。反発するような反問権であって、執行部は何を考えているのか、本当に事業に取り組まれていくのか、唖然といたしました。私は、本県で40億円から50億円の実績がある市町村があります。私は、この50億円は何もないところの話じゃありません、先進地を学び、どうしたら、どのようにしたらその目標が達成できるか研究を重ねることでその手法があると思います。その目標が達成できるよう努力してほしいですが、執行部は対抗するような反問権を行使し、恥ずかしいと思いませんか。それだけの能力しか、考えがないかと思うと残念でなりません。そこで、将来目標は6億7,000万円ということだが、その根拠を示してほしいです。御答弁をお願いいたします。
次に、私は、ふるさと納税課を設置する考えはないか、また協議会を立ち上げる考えはないかと質問いたしてまいりました。ふるさと納税は、国の施策の地方創生の一環であり、地方が活性する大きなチャンスだと捉えています。自主財源確保と地場産業の創出、活性化は、本市の将来の位置づけとなる起爆剤になると私は確信をしております。
何回も何回も質問しておりますが、御存じのとおり、行政は運営でなく、経営であることは御存じのとおりだと思っております。このふるさと納税で経営能力が問われます。また、出水市の将来も変わります。旧態依然とした考え方を変えて負け組にならないよう、何はともあれ集中的に取り組むべきであります。私が提案してまいりましたのは採用されませんでしたが、代わりにと申しますか、出水市観光特産品協会に業務委託をされているが、その成果はどのようになっているかお伺いをいたします。
1回目の質問を終わります。
○椎木伸一市長 髙崎正風議員の御質問にお答えいたします。
まず、出水市道路総合整備計画における優先順位の考え方でございます。計画における長期・短期整備路線を選定するため、指標の一つとして定めているもので、経済性、そして機能性、安全性、緊急性を評価項目としまして、点数づけを行い、評価点の合計が上位となる路線から優先順位を定めているところです。
出水市道路総合整備計画のうち、幹線道路を整備する場合は、短期整備路線の中から交通事情の変化や市内渋滞路線の解消、また現在実施している道路整備の進捗を考慮しながら総合的に判断しているところです。
次に、高尾野川ジョギングロードの県との管理協定についてでありますが、河川堤防とジョギングロードとして使用する道路を兼ねる部分の維持管理に関し、平成9年11月4日に堤防と道路の兼用工作物の維持管理に関する協定としまして、道路管理者である当時の高尾野町長と河川管理者である鹿児島県知事の間で締結しております。
次に、ふるさと納税についてでありますが、私が就任した時点で4,000万円弱でございましたが、現在10倍以上の目標額に達してはいるところでございます。次年度以降の目標につきましては、前回定例会の答弁の繰り返しになりますけれども、まずは今掲げてございます6億7,000万円の寄附を早期に達成することを目指しまして、それ以降も制度の趣旨に沿って自主財源の確保と産業振興のために積極的に取り組みたいと考えております。
次に、出水市観光特産品協会への業務委託による成果でありますが、本年4月から8月末までの期間で、返礼品の増加数45個、事業所への訪問数20か所となっています。
なお、返礼品の開発と事業所への訪問は、市と観光特産品協会が連携して進めておりまして、分担しながら行っているところです。
引き続き、寄附者にとって魅力的な返礼品の開発に努めてまいりたいと考えているところです。
○20番(髙崎正風議員) 御答弁いただきました。道路整備の総合計画の順位のことでありますけれども、このことは、市長がおっしゃるように、その点数の付け方はちゃんと示されております。ところが、私が今申し上げているのは、そのことで旧野田町、高尾野町を別に取り上げて、順位を変えてもらうという、全部1番からずっとつけられているんですけど、いつまでたっても、こっちのほうが交通渋滞で頻繁になってくると、こっち整備しろ、こっち整備しろとなってくる。いつまでたっても順位が上がってこない。そこを申し上げているわけですから、例えば旧出水市が3路線やったとすれば、1路線を今度は旧高尾野にくると、2路線くるとか、そしてまた旧野田町に1路線すると、そういう順番を変えられないかと言っていることですが、いかがでしょうか。
○小原一郎建設部長 道路総合整備計画におきましては、全部で35路線指定しているところです。その中で早くすべき短期路線、そして、それ以降の長期路線としての位置づけをしているところでございます。それで、その中で市長のほうが言いましたように、いろいろな経済性、機能性、安全性、緊急性などを考慮して、実際に整備をするときにはそういうのを考慮して、その短期路線の中から整備をしていくと。その順番がどうのこうのではなくて、短期路線の整備の中から、渋滞であったりとか、整備の状況、それとか場合によっては、事業の採択になる要件などを考慮しまして、短期路線の中から整備を検討していくという形になると思います。
○20番(髙崎正風議員) 確か緊急的に整備しなければならないところが出てきたり、この順位どおりでないんだというふうに御答弁だったんですけど、いつまでたってもというのは、やっぱり若干過疎になるほど整備が遅れてくるということになりますので、ある程度道路というのは、冒頭申し上げましたように、結局、人・物・情報を運ぶ大切なものです。道路がよくなれば、その環境の中に人も住みついてくるという、いろんなことのメリットといいますか、そういうのが昔から言われているんですけれども、どうしてもこの道路だけはというのがあると思います。ですから、何回も言いますけど、旧野田、高尾野の路線を交互にですね、出水市全体を見るとどうしても後ろに全部すだってしまうんですよ。そうじゃなくて、さっき言ったように、出水市が2路線やったら、高尾野が1路線やるとかというふうに順位を変えて整備していただきたいと。そうじゃないと、危険度とかいろいろ、そういうのが出てこない限りは、ずっと後ろに下がってしまうことになるんです、優先度がですね。そうじゃなくて、そういう考え方はどうかということの質問ですから、その中身についてはよく示されているので、よく分かっているんです。そのことを言ってるんです。
○椎木伸一市長 議員のおっしゃる趣旨はよく理解できます。私もこの出水市全体のいろんな状況を踏まえて、先ほど部長からまた説明がありましたような指標等も考慮しながら、総合的に勘案しながら優先順位を決めているということでございます。
出水市道路総合整備計画につきましても、何年か置きにつくり変えるわけでございますけれども、二、三年前に全協で説明し、議会でも御議論いただきましたけれども、現在はそれに基づいて実施しながら、またその途中いろんな経済の変化、例えば道の駅の計画があったりとか、そういったもの等も勘案しながら、緊急性と経済性、そして機能性とか安全性も含めて検討しながら決めているわけでございます。
野田が過疎地域に指定されたということとか、そういったものは、私どもはバランス的には全く全体を見ながらやっているわけでございまして、高尾野がとか、野田がとか、そういったことは特段この道路の中では順位を個別に決めてというふうには考えておりません。通常の事業についても、私自身、地域バランスを考えて実施しているつもりであります。高尾野にもいろんな空き施設を利用したり、そういった活性化策というのも考えておりますし、野田についても、今お願いをしているところで、まだ提案がないところでございますけれども、野田地域についても何か市民のよりどころとなるものが必要であればそういったものにも対応していこうとは考えております。よって、道路につきましても同じような考え方でございますので、どうかその辺を御理解いただければと思います。
○20番(髙崎正風議員) 状況を見ながら整備を進めていくと、急にサービスエリアのところができたから、そのほうに今度は先行していくということになりますけど、その辺は分からんでもないですけれども、やはり取り残されてくるんじゃないかという考えがあるんですよね。例えば、矢房線の延伸の問題、これは一回質問しておりますけれども、順位としては7位に上がってきていると。なかなか7位から上がってない状況。見直しがなされてないからですけれども。それから、野田のほうで3位の順位をつけられているのが圃場幹線1号線ですね。これは3位なんですね。ところが、これだと全く両方とも3位になっても、ほかのところが、出水市のほうはどんどん追いかけてくるんですよ、旧出水市がですね。ですから、全く手つかずに、順位は上がっていても、そのときは進められないと。ですから、私が今日申し上げたいのは、矢房線の延伸ですね、松ヶ野野平線の広域農道までの延伸。ということは、ここはなぜ延伸をしなくちゃいけないかというと、ある程度工業団地内は2車線でちゃんとした立派な道路ができております。その上のほうが農道になっているものですから、市道なんですけれども、狭くて、離合の問題、農繁期等については非常にみんなが迷惑するというところが多いわけです。ですから、あれを広域農道まで延伸して。というのは、やはり北薩横断道路、これとの関係があって、大型車がどんどん頻繁に多く通るようになってきてるんですよね。ですから、そのことを整備してやることに、そこら辺の環境もよくなるし、物の流通なんかもよくなる。それを結んで、結局工業団地から西回り自動車道に行けるという1つの線が引かれるわけですから。ですから、早めにこれを、順位を待っていると、いつまでたっても、何年たっても、これはできないと思いますので、さっき申し上げました、くどいようですけれども、順位を変えて、整備する考えはないかということです。
○小原一郎建設部長 言われる松ヶ野野平線につきまして、その整備の必要性というのは感じているところなんですけれども、今現在、整備を進めております六月田上村線とか、いろいろ路線等もございますので、それらの整備の状況等も見ながら、一気にというのはなかなか難しい状況もございますので、そのような整備の状況であったり、国の採択要件とか、そこら辺を加味しながら、事業にどれに採択になるのかとかいうのを加味しながら、整備について判断していければと考えているところです。
○20番(髙崎正風議員) 矢房線の延伸は、高尾野町時代にも私は質問しているんですよね。そのときに、前に進めようということで段取りされたんですけれども、結局合併によって、16年6か月ですか、何にも手をつけられていないと。16年も経過している。その話が出てからですね。ですから、いつまでたっても前に進まないということですので、やはりそこら辺を順位の見直し、考え方の見直しをして、やっぱり整備をしていくということじゃないかと思います。
それと、また一つ、なぜこういう整備が遅れているのかというのは、何の関係で全体整備が遅れるのか、その辺についてお伺いしたいと思います。
○小原一郎建設部長 これらの整備につきましては、国の補助等をもらいながら、現在進めているところでございます。今、整備に当たりましては、橋梁の長寿命化でもあったり、そういうのも国の補助をいただきながらしているという現状で、出水市だけというわけにもいきませんし、県内のやはり全体的なものを見ながら配分していただいているという状況もございますので、御理解いただきたいと思います。
○20番(髙崎正風議員) 国や県の補助を使いながら進めてまいるということですが、本当にそうなのか、それとも自主財源がないのか、どちらでしょうか。
○椎木伸一市長 自主財源も含めて、できる限りの自主財源というか、市単独が持ち出しがないような工夫をしながら取り組んでいるわけでございますので、自主財源にかかわらず総合的にやっぱり勘案しているという表現しかできないわけですけれども。
それと、先ほどおっしゃったように、例えば野田の圃場幹線1号線についても、県とはずっと協議しております。これは、議員が一生懸命頑張ってこられた国道504号、これの空港道路のほうの整備状況も、今、阿久根、高尾野道路が鋭意進捗しておりますけれども、あの整備状況の中で交通量がどのように変わるか、それを踏まえて圃場幹線1号線をバイパス的な機能にするのかどうかというところを県や国とまた協議しながら取り組んでいきたいと思っておりますし、またおっしゃるように、矢房線についても、やはり国道504号からの流れがどういうふうに流れてくるのかというのも見極めながら対応していきたいということでございますので、冒頭説明しましたように、経済性とか、そういった緊急性等も十分勘案しながら取り組んでまいります。おっしゃったような状況も踏まえながら、今後いろんな路線の整備の順位等は決めていきたいと思っております。決してその時点では固定しますけれども、日々といいますか、状況に応じて対応していきたいと考えているところです。
○20番(髙崎正風議員) 交通量を言ったりとか、費用対効果を言うと、またそれも低くなるんですよね。ですから、そうでなくて、ある程度の考え方を変えて、ここは発展させていくんだという考え方を頭に持たないと、交通量とか費用対効果と言ったら、田舎の道路は一つもできないんですよ。ですから、そこら辺はどうやって開発、出水市を変えていくかという原点に立って、ものを考えていかないと、そっちのほうから優先度を決めてくると前に進まないということになりますので、その辺はやはり市長もよく考えていただきたいと思っております。
次に、市道高尾野川ジョギングロード左岸1号、それから右岸2号のことについてなんですけれども、この管理がうまくいってないんですね。というのは、うまくいってないというか、今までは高尾野町時代にはちゃんと重機の草刈り機があったんですよ。そうすると、丁寧にずっときれいに機械でされて、管理が行き届いてたんです。合併後に、結局はその機械をどこに譲るかというと、シルバー人材センターのほうに回して整備されたけれども、その頃のお話を聞くと、結局機械ですると、あんまりさばくっで、人力が、雇用対策も、その頃はちょうど雇用対策、合併後はそれが出てきました。なるだけ草刈り機とか、そういう機械を、重機類を使わないでということであって、ほとんど人力でやるということで、今になってみれば、人力じゃとても追いつかないんですよね。ですから、結局一回、シルバー人材センターで無償で貸付けできないかということを質問したこともあります。12番議員と14番議員が草刈りについてどうしても予算を増やせとか、何とかやれとかということで質問もありました。ですから、このことはどうしても人力では最近間に合わない、高齢化してしまって。そして、今、高齢化になったけど、今の若い人たちというのはなかなかそういう重労働に慣れていないといいますか、対応できない人が多くなる、年を取ってきて。そうなると、結局シルバー人材センターで、年金者でもありますけれども、もうそういう草払いなんか行かなくていいという感じで、なかなか人を集めることができないということになります。ですから、この管理をきちんとやってもらえないかということですが、そのことの考え方はどうでしょうか。
○椎木伸一市長 除草関係については、先にも回答したとおり、機械化とか、そういったものでの効率化とか、リースも含めて検討しなければならない時期に既に来ていると思っております。
私個人的なあれで恐縮ですけど、江内川の土地改良区の河川の除草作業についても、以前は集落から出合ってやっておりましたが、高齢化ということで、それぞれ非常に重労働でできないということで、それぞれ土地改良区に委託して機械を使ってやってもらっているというのが現状でございます。
高尾野川のジョギングロード等の維持管理についても、そういった機械化等も考慮しながら検討していかなければならないと思っておりますので、また協議をさせていただきたいと考えますので、どうかよろしくお願いいたします。
○20番(髙崎正風議員) 市長になられてから、みんなで守るふるさと市道管理事業と、それから農道の管理事業ということで予算化されて、非常に防草対策がうまくいってるなと思っております。全部のり面をコンクリート張りして、それを管理していくということでありますが、そういうところ、できるところはそうしていくとして、できないところもあるわけですから、どうしてもといったら、12番議員、14番議員がおっしゃったように、これをするにしては重機が私は必要だと思うんですよね。人力ではとてもじゃないけど、追いつかないと。ですから、これを旧高尾野時代に重機でやっていたのに、今、機械もよくなっておりますから、性能もよくなっているので、その考え方をまた考えていただくというふうに考えているんですけれども。このことについてですけれども、とにかく管理をきちんとやっていくということの意見を述べているわけですので、市民の一番の高尾野にとっては高尾野川ら辺がメインになっておりますので、やはり景観づくりですね。今、寄州除去でずっと取って、県のほうにしていただいて、それから草木も、洪水時期も全部重機を入れてやってもらう。河川の中は寄州を取ってもらうと。非常に整備がどんどん進んでおりますので、景観もよくなっております。ですから、このまま放っておくと、また非常に景観を悪くしてしまいますので、今後はこの取組についてということで意見を申し上げておきますので、お願いをしたいと思っております。
次に、ふるさと納税についてですが、これは、最初、南鶴議員ですね、7番と、今日、宇都議員が質問をされました。今日の宇都議員の質問で御答弁と質問内容が大体同じような考え方でありましたので、そうたくさんは質問しませんけれども。まず、将来の目標値というのが、先ほど答弁がありましたけれども、これがはっきりとまだしてないんですね。ぼかされて、まずは6億7,000万円やってみようということの答弁であって、その将来像が全く見えてこないんですよ。やはりこの将来像が見えてこないといけないということを私は考えているんですけれども、いかがでしょうか。
○椎木伸一市長 ふるさと納税については、それぞれの議員さんから、ありがたい提案とか激励をいただいて、非常にありがたく思っております。この6億7,000万円というのは、冨田部長のほうからも答弁がありましたように、地元に返礼品の3割ということですので、それが2億円地元に落ちるのをまずは目標にしての6億7,000万円という設定でございます。将来は、本当、議員がおっしゃるように、50億円とか、そういった価格に設定ができればそれが一番いいわけですけれども、現実問題として、先ほど私が答弁しましたように、非常にこのふるさと納税については各自治体、激化といいますか、大変な熾烈な状況でございます。どこかが一つのことで伸ばせば、それをみんなが見習って追随するということで、もともと伸びていたところも止まってしまう、あるいは減少してしまう、そういった現象の中でございます。よっぽど秀でたアイデアでないとなかなか伸びづらいというのが現状ではないかなと思っておりますけれども、それはそれで状況を踏まえながら、いろんな人の知恵を借りながらやっていきたいというのが本当の正直なところでございますけれども、答弁で申しましたように、まずは地元に2億円を落とす6億7,000万円ということがクリアできるところまでいけば、また次の目標を持っていきたいと思っているところでございまして、なかなか将来的な額というのが示せないのが現状でございます。高く掲げればいいと思いますけれども、なかなかその目標の額すら読みにくい今の状況だということであります。
○20番(髙崎正風議員) やっぱり目標値がないと、どっちかというと頑張るというか、将来のことを考えることがないわけですから、目標値というのはやっぱり頑張るために立てるべきであるんじゃないかと考えております。
何か言うと反問権の話が出てきますけれども、この前の反問権を聞いていると、おかしくてしょうがないんですよね。自分たちでなぜ考えないのか。言われたら、こうやりたいということを一つも考えないで、ただ単に反問権を使って、懲らしめてやろうとか、反発しようとか、そういうふうに私は聞こえたんですよ。本当に素直に真面目に謙虚で真摯に受け止めているのかと、私たち議員が言っていることを。そう非常に感じましたよ。それを傍聴されている方、全国配信されているんですけれども、その方からいっぱい言われましたよ。何で出水市はあのくらいことを答弁できないのか、反問権を使ってということがありました。ですから、やっぱり反問権を使うときは軽々に使うべきじゃないですよ。ここははっきりと私は申し上げておきます。
ですから、これだけやらなければいけないと。何でかというと、やはり出水市の将来を決めるんですよ、ふるさと納税。ということは、自主財源確保も大事だけれども、産業の活性化、何を出水市で一番のものをつくり出していくかと。ここも大事なんです。ただ、もったいない。例えば20億円の自主財源ができたとすれば、非常に使い道が多いわけです。さっき道路財源のことを聞きましたけれども、自主財源はないのか、それとも補助金がつかないのかという話をしましたけれども、自主財源があったらどんどん前に元気を出して進めるんですよ。補助金よりもですね。ですから、このふるさと納税をあまりにも真剣に捉えていらっしゃらないんじゃないかと。それは、19市、前の宇都議員がおっしゃいましたように、順位を平均値が鹿児島県で幾らなのか、10億円とか12億円ですね、言われた。人口割とか職員割を言われました。私は、人口割でいくと、鹿児島県の平均値からいくと、結局1人当たり4万4,955円なんですよね。ところが、出水市にこの換算を変えてみると、5万2,470人に換算すると23億5,800万円のふるさと納税を努力していかなきゃならないとなるんですよ。23億円ですよ。鹿児島県の平均でいくと、人口割でいくと。それは、ちゃんと資料があるので、そちらのほうで試算すれば分かります。資料をお持ちだから。
こういうことになっているのに、ただ単に小手先だけで、口先だけでやっていらっしゃると。非常にやっぱりもうちょっと力を入れるべきだと。そうしないと、出水市の将来がこれによって変わると思うんですよ。産業の活性化というのは一番大事ですから。そのことを申し上げているんですけれども、市長、このことについてどうか。ただ単に目標値をすれば、また議員から言われるので、ぼかしておこうと。返事はしない。何も計画がないんじゃないですか、計画性というのが。ちゃんと我々はこうやって、これまでいったら、これまでやるんだと。計画性を持って、本来であれば、これだけ言って、爆発的に10億円だと、来年は20億円ぐらいになるくらいのやっぱり元気がないと、ただ単に手前でこそこそこそこそやっているわけですから、その辺についてはどうなんですかね。
○議長(田上真由美議員) ここで、昼食のため暫時休憩いたします。再開は午後1時からとします。
午前11時59分 休 憩
午後1時00分 再 開
○議長(田上真由美議員) 再開いたします。休憩前に引き続き会議を続行し、髙崎正風議員の質問に対する当局の答弁を求めます。
○椎木伸一市長 目標を定めるべきというような趣旨の御質問でございました。議員御指摘のとおり、目標は高く、市も高く掲げるということが望ましいとは思っております。先ほど私が答弁いたしました繰り返しになるんですけれども、自治体間の競争であるとか、大変激化しておりまして、なかなか一つのものを多くのふるさと納税を一つのことで取得するというのは大変難しい状況になっておりますので、よって、目標を絞り込んで立てるということ、あるいはその根拠を見いだすということも非常に難しい状況の中でございます。
先の議会で職員のほうから反問権ということで50億円の根拠を尋ねたわけでございますが、それについては私どもの目標とする数値と非常にかけ離れていた数値でございましたので、そこらあたりの根拠をお伺いして、我々の目標がどうなのか、その辺の検証もしたい、あるいは目標をどのようにすべきかということも検討したい、そういった趣旨での目標設定数値の根拠についての確認の反問権だったと私は理解をしております。
目標数値は、根拠があってのものが望ましいとも思いますし、また私どもには説明責任ということも伴いますので、目標を立てるからにはある程度の数値的な根拠というものが必要かと思っておりますので、今のところ、まずは先ほど申しました6億7,000万円をクリアすることを目標として、その目標の勢いを見ながら次の設定を考えていきたいと思っているわけでございます。
○20番(髙崎正風議員) 目標値については、それぞれの意見がありました。答弁がありました。やはり出水市をどげんかせないかんと、一生懸命やらないかんということになると、真剣に考えていくべきじゃないかと、こういうふうに考えております。やはり市民の声に応えていくということでないと、魅力あるまちづくりというのができてこないんですよ。それは稼げる観光とか、いや、それはラムサールとか、いろいろ言われますけれども、それ以前にこのことが一番大事じゃないかと認識していただければありがたいなとは思っております。
ところで、昨日の新聞をお読みになられたと思うんですが、南日本新聞のやつですが、ふるさと納税と書いて、自慢のユニークな返礼品、我が町に寄附を、工夫を凝らすということですので、ある程度特集で紹介されておりますけれども、世間はふるさと返礼商品というのは非常にやっぱり関心を持っていらっしゃると思うんですよ。こういうことでございますので、私が言っているんじゃなくて、2名の質問者もいましたけれども。
昨日の新聞の記事、これは都城市のことであるんですけれども、PR度の秘訣は、PR戦略と官民一体というのが表に書いてあるんですが、ちょっと読ませていただくと、下のほうですが、市は14年、産出額全国1位の牛豚、牛と豚ですね、鶏や焼酎売上げ全国1位の霧島酒造に着目し、返礼品を肉と焼酎に限定したと。高寄附者への焼酎1年分、それから2頭分の牛肉などの話題を呼び、肉と焼酎のまちづくりのイメージを定着させたとなっております。
結局やるところは一生懸命になってやっているわけです。ところが、私は、協議会とか、かれこれ言ってきましたけれども、ここも市ふるさと納税振興協議会を立ち上げております。このことは137業者、あとは読んでもらえば分かりますけれども、その人たちが参加して、行政側も民間側も一緒になってやりましょうと、この体制づくりをやっていかないと、内部だけで一生懸命頑張ってもなかなか伸びないんじゃないかと、こういうふうに感じております。
ですから、次の質問にありましたように、出水市観光特産品協会に業務委託をされているが、その成果はどうなっているかという質問をしておりますけど、これは日置市にある伊集院のLR株式会社に出水市は五千何百万円投資して、今やっていらっしゃいますけれども、なかなかそこには外から見るとLRに丸投げしているんじゃないかという感じがしてならないところがあります。そういうことでございますので、取りあえず質問にあります業務を委託されている成果はどうなっているかお答えいただければと思います。
○冨田忍政策経営部長 観光特産品協会への業務委託の成果についてということかと思います。先ほど1問目の答弁におきまして、市長のほうから御答弁申し上げたところではございます。4月から8月まで5か月間、返礼品が15個新規商品の開発出店がかなっております。その間、事業所としては20か所訪問をし、商品の新規出品、あるいはその中身が利用者のニーズがだんだん変化をしてきております。大容量のものから小分けの組合せ、同じ10キロであっても、10キロ袋というよりは2キロの5袋とか、そういうことがございますので、それに対して出品者の皆さん方がその生産工程とか、加工委託されている事業所の対応であるとか、そういうところが可能であればそういうニーズを捉えた商品の組合せの変更作業であるとか、そういったところについて私どもと観光特産品協会と手分けをしながら、あるいは一緒に事業所訪問をして変更等にも対応できるようにお願いをして、一緒になって取り組んでいるところでございます。
○20番(髙崎正風議員) この業務委託契約書の中身を見てみますと、令和4年度ふるさと納税運営業務委託仕様書ということを書いて委託されているわけですけれども、この中で、ひと月当たり5社以上訪問しなさいとか、それから令和4年12月から令和5年2月まではその限りでないということは、もうちょっとたくさん回りなさいということを意味しているんだと思う。この時期が一番返礼商品の多い時期ですから、それを言われて、こういうふうに回ってくれということであるんじゃないかと思います。ですから、職員が、先ほど南鶴議員の答弁で3人常駐しているということなんですが、それはそれとして、それで十分なのかというのも疑問に思うところがあります。ですから、今の市と観光特産品協会の委託業務についても、金額は360万円ということで非常に3人の職員の1人年間120万円で、簡単に計算すれば、ところが、本来ならその諸経費は周りにいっぱいいると思うんですよ。人件費だけ、それだけしかないんじゃないかなと思っていますので、十分に活動できるのかということなんですが、それで十分なんでしょうか。
○冨田忍政策経営部長 観光特産品協会とはいろんな面で今連携をしながら、観光面、特産品の関係、協力しながら取り組んでいるところでございます。協会と私どもとの協議の中でお願いする業務量、それに対しての対価、金額等について一緒になってということで調整がついた金額でございます。
○20番(髙崎正風議員) LR株式会社と観光特産品協会の違いはどこにあるのかお答えできればと思いますが。
○青﨑譲二企画政策課長 LRは、寄附者から申込みがあった分の受注管理であったり、あとホームページの作成等をしていただいております。観光特産品協会には、先ほど来ありますとおり、新商品の開発であったり、新たな事業者の掘り起こしであったりをしていただいております。
○20番(髙崎正風議員) LRさんとの関係ですけれども、結局ここがこの業務の中で私たちが作っている、これは市長のほうには回してあります。皆さんには間に合わなかったんですけれども、こういうやつを作っております。それで、ずっと作っているんですが、結局この写真も全部自分で自作ですよ、これは。それで、印刷会社がこっちの印刷会社でやっていただいて、LRさんよりも上をいくぐらいの印刷会社が出水にはこういうのをレイアウトするところがあります。これを作るのは、やっぱり物語を作るのは大変ですけれども、柿なんかもこうやって作って、これは自分たちで作って、写真はほとんど私が撮っております、全部というよりもですね。それで、こういうのを作りながら、ふるさと納税に載せていきたいということは、いい商品を作って、いい値段で売れるというのが一つの狙いです。農家さんたちに安くして売るんじゃなくて、やはり1円でも高く農家所得が増えるように、農家であれば、そういう感覚でふるさと納税に臨んでいると私は思っております。ですから、自分たちのところでできる範囲はできるようにしていただきたいということです。
それと、今度、ちょっと向こうでどうしても写真を撮りたいと言ってきたから、LRさんのほうでですね。だから、写真を撮らせた。ところが、私は、今度はパンフに使おうと思って、これに「その写真をください」と言ったら、「いや、肖像権があるから駄目です」、こう断られた。これもがっかりしました。一体となってない、自分たちと。それは、いろいろ出どころが違うから、そうなってくるんだろうと思います。共通点がないわけなんですね。ただ、一方的に押してくる。やるだけです。自分たちの意見というのも、こういうのも、お互い交換しながらやれるかということなんですけど、そこが、肖像権があるから、この写真はやれないと。本当がっかりしました。全部また自分で撮り直しをして作ったんですけれども、そういうことの共通する点についてはできないのか、その辺について伺ってみたいと思います。
○青﨑譲二企画政策課長 LR株式会社様との契約の中でそのような取決めになっているところでございます。
○20番(髙崎正風議員) LRさんとのやっぱり意見交換もして、丸投げにならないようにいつもチェックをしていくべきでないかと、こういうふうに思っておりますので、その辺についてもしっかりとやっていただきたいと思っております。
今、何回も質問してまいりましたけど、出水市は電車に乗り遅れていると、まだおれんじ鉄道で走っているという感じがしたので、ちゃんと八代ら辺に着いたじゃろかいなという感じもするので、あとはまた在来線に乗るか、新幹線に乗るかということです。ですから、どうしても追いつかないので、ここからは新幹線で行かないかんという今の現状じゃないかと思います。それより遅れてくると飛行機で行かにゃならないということでございますので、いつまでもおれんじ鉄道に乗ってないで、ちゃんと新幹線に乗れるようなことで業務を進めていくべきじゃないかと考えております。
とにかく何回もくどく申し上げましたけれども、ふるさと納税についてやっぱり市民の魅力づくりの中の一つだと思っておりますから、自主財源確保と、結局は産業の活性化、これをよく考えていただきたいと思います。このことによって、出水市の発展は決まってしまいますので、そこは真剣に考えて取り組んでいくべきでないかという意見を述べて、これで質問を終わります。
○議長(田上真由美議員) 次に、北御門伸彦議員の質問を許します。
○11番(北御門伸彦議員) お疲れさまです。大変眠くなる時間かと思いますけれども、しばらくお付き合いをよろしくお願いいたします。
コロナの脅威がなかなか収まらないようですが、以前申し上げたように、2025年くらいまで影響があるだろうと予測されたのが正解になるのではないだろうかと思うところです。さらに、次の第8波に備えないとならないと思っております。現在、約10人に1人ぐらい感染していると言える段階かと思いますが、災害に備えるのと同様に各家庭でも特に自宅療養も念頭に様々な想定をしっかりしておかねばならないと考えております。また、自宅療養を多くの方が経験されたかと思いますが、大変だったかと思います。また、これまで先の見えない中、医療現場や介護現場などで奮闘されていることに改めて敬意を表するところです。さらに、夜の街も半分の店が閉まっているような日もあります。迫田議員から街の飲食店などの窮状が報告されましたが、私も8月に2回ほど街に出て、店を回りました。厳しい状況を聞いております。このままだと店じまいなど増えていくのではないかと心配しております。地域経済が縮小し続けると大変なことになりはしないかと案じております。市の職員の方々もどうかよろしくお願いいたします。
今期は、高齢者問題について多くの質問を行っていくつもりだと申し上げました。いきいき長寿課及び多くの関係課の方々にはお手数をおかけしますが、未来に対して多くの議論ができることを願っております。
さて、前回は介護について取り上げました。自分でもテーマが重いと感じましたが、今回はさらに大きなテーマを選んでしまいました。「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」について議論したいと思います。ここに持っておりますオレンジの表紙で約80ページに及ぶ手作りの計画です。現在、第8期計画の令和3年から5年までの3年計画のちょうど中間に当たります。議論するには少しタイミングが早かったとも考えますが、チャレンジして、共に考えていく議論が少しでもできればと思います。
まず、第9期計画の検討段階で、そのスケジュールや予想される新たな課題等があれば示してください。
続く質問項目は、この計画の章立てに少し強引に合わせたところもありますが、御容赦願います。御承知のように、施策の体系は4つに分けてあります。
まず、1つ目が「多様な生活支援の充実」となっており、中身が3項目で、1つは「地域包括ケアシステムの深化」です。深化とは、進む進化ではなく、深い方向へ変化する意味の深化です。私の質問も深化したいのですが、まだ勉強不足で御容赦いただきたいと思います。ほかに「地域ケアの推進」「高齢者を支える地域づくりの推進」の項目があります。この中で「高齢者を支える地域づくりの推進」を取り上げ、2点、質問いたします。まず、1点目、私は令和4年第1回定例会で地区コミュニティ協議会について質問いたしました。関連しますが、この計画では、この高齢者福祉計画ですが、コミュニティ協議会が果たす役割が大きいかと思います。その役割をどのように考えているかお尋ねいたします。2点目として、関連で孤立・孤独対策について、取り組まれていることについて具体的にお尋ねいたします。また、取組の成果があったら、併せてお知らせください。
次に、2つ目の施策に「高齢者が活躍できるまちづくりの推進」の項目があり、1つ目として「高齢者の社会参画の推進」「安全で快適な環境の確保」があります。また、「社会参画の推進」の中に「生涯学習の推進・環境の充実」の項目があります。高齢者学級は、時代の流れや行政の施策を理解していただいたり、コミュニケーションを図るなど、大変貴重な機会と考えます。最近は、以前より参加者が少なくなっているようです。原因をどう考えておられますか。また、参加者を増やす方策をどう考えておられるかお尋ねいたします。
次に、「老人クラブ活動の支援」の項目があります。例えば、施策の1つ目に出ている高齢者の見守りネットワークにも老人クラブは登場しております。そのほか計画に大きく関与するかと考えておりますが、現在、市は老人クラブに対し、どのようにサポートし、またどんな役割を期待しているのかをお尋ねいたします。また、加入率が算定できれば、併せてお知らせください。
次に、先ほど述べました孤立・孤独対策と同様に、市長がよく言われている「いのちの安心」に影響を与える「熱中症対策」に関し、質問をいたします。暑い夏がまだ続いております。暑さが少し和らいできましたが、予報では9月末まで暑さが続くと言われております。つい先日、市内のお年寄りが、エアコンを切っておられ、夜中に熱中症のような状況に陥り、朝に救急搬送されたというお話を聞きました。これから地球温暖化の影響も考えなければなりません。お年寄りは、昔ながらの考えでエアコンを積極的に使わない頑固な方もおられます。なかなか実態把握は難しいと考えますが、命に関わることですので、一人暮らしのお年寄りや認知症のお年寄りの環境の実態把握が必要と思います。また、対策を講じなければならない分野だと思います。お考えをお聞かせください。
次に、施策の3つ目の「安心と安らぎのある体制づくりの推進」では「介護(予防)・高齢者福祉サービスの充実」「認知症施策の推進」「権利擁護体制の整備」と3つの項目に分かれております。少し強引な結びつきとは思いますが、人生100年時代にあって、できるだけ長く健康であり続け、医療・介護などに頼るのを後回しにして、社会貢献を続けていただくことが超高齢化社会の中で求められることであると考えます。健康寿命を延ばすことは大きな命題だと考えます。健康増進課で実施されている事業も多くあるかと思います。健康寿命の延伸のためにどのような施策体系で事務事業を進めていかれるのかお尋ねいたします。
また、体の健康だけではなく、こころの健康が大きく人生に影響を与えます。生きがいを持って生活している人は長生きするとも言われており、社会的にも大きな好影響を与えます。後で触れますが、出水郡医師会立第二病院の顧問をされている田辺先生が高尾野の鶴亀大学で講演をしていただき、出水地区在宅医療・介護連携推進協議会で出しているノートを紹介いたしました。ここにあります。17ページにまとめられた人生の終活の一つにも当たると思うノートです。特に高齢者本人が意思表示できない場合、延命治療などの判断に家族や医療機関が苦慮することも多いと思います。延命治療の程度、余命告知、臓器提供・献体、介護に関して高齢者本人の希望を記録し、家族の負担を軽減することにつながる指針になるものだと私は考えます。私は、以前「エンディングノート」という言葉で質問をさせていただきました。自治体で取り組んでいるところがあるからです。今回、マイライフノートを取り上げておりますが、共通点は多いと思います。ノートをまとめることが心の区切りをつけ、人生の目標を持って、再スタートを切ることにつながり、生きがいにもつながると考えます。生きがいづくりも幅の広い分野かと思いますが、関係する施策、併せてマイライフノートの活用方法についてもお尋ねいたします。
壇上での最後の質問として、話は全然違う分野でありますが、通告いたしましたように、陸上競技場へのタイム計測器の設置について質問させていただきます。
6月議会ではボクシング競技の練習場設置に関するサポートができないかと競技指導者の声をお届けいたしました。質問後、担当課が直接、指導者に面会され、詳細を把握いただいたようで、まずもって感謝申し上げます。
今回は、陸上競技指導者からお話を聞き、質問といたしました。陸上競技場については、全天候型への整備も終わりました。出水は、これまで短距離や長距離で多くの全国区の選手を輩出してきたことは郷土の誇りでもあります。その背景には、それまで多くの指導者が粘り強くボランティアで指導してきていただいたことがあると思います。長年の御苦労に敬意を表したいと思います。
さて、国体で使用する野球場には立派な電光掲示板が設置されております。立派に改修された陸上競技場にもタイム計測器を設置できないかと指導者の方が要望されております。公認記録になるためには必要な設備でもあります。最低でも2,000万円はかかると聞いておりますが、もっと奮発していただいてもよいのではないかとも考えます。当局のお考えをお尋ねします。
以上、壇上からの質問を終わります。
○椎木伸一市長 北御門伸彦議員の御質問にお答えいたします。
まず、第9期高齢者福祉計画についてでありますけれども、高齢者福祉計画は、老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による供給体制の確保に関する計画で、平成18年施行の改正介護保険法により介護保険事業計画と一体として作成することとなっております。
現在、次期計画策定に向け、国において準備が進められているところであります。策定スケジュールといたしましては、令和4年8月に公表されました国からの資料によりますと、令和5年2月頃に国の基本的な考え方が提示される予定でありますが、本年度の事業としては、地域の抱える課題を探るための実態調査を実施することといたしております。
また、予想される新たな課題についてでありますが、2040年に向けて生産年齢人口が急減し、85歳以上人口が急速に増加していくことが見込まれております。現在、国の社会保障審議会介護保険部会において、地域包括ケアシステムをさらに深化・推進するとともに、介護ニーズの増大と介護人材確保への対応を両立させ、制度の持続可能性を確保するという観点で議論がなされており、本市の課題については実態調査を踏まえ、分析・評価した上で対応していきたいと考えております。
次に、地区コミュニティ協議会の役割についてお答えいたします。
地区コミュニティ協議会は、自治会等地域コミュニティの充実・強化を図り、住民と行政の共生・協働のまちづくりの実現に資するため、住民の自主性及び主体性に基づき、地域の身近な課題解決に向けた取組を行うものであります。
現在、本市には米ノ津東地区コミュニティ協議会、大川内地区コミュニティ協議会、野田地区コミュニティ協議会の3協議会が設立されております。具体的な活動といたしまして、米ノ津東地区コミュニティ協議会では、令和3年度から地域の高齢者の方を中心に健康体操を取り入れた通所型サービスBを実施されております。また、大川内地区コミュニティ協議会では、毎月、地域の農産物等を持ち寄り、販売する茶いっぺ市場や健康体操を実施されており、野田地区コミュニティ協議会においては、青木地区のかかし祭り、ちょうど今実施されておりますけれども、など、野田地区の様々な行事のサポートを実施されています。
第8期高齢者福祉計画では、地域住民が主体となった生活支援・介護予防サービスの充実に向けて生活支援体制整備事業を推進しており、多様な主体による多様なサービスの提供につなげていきたいと考えておりますことから、地区コミュニティ協議会は地域包括ケアシステムの重要な担い手の一つであると考えているところです。
次に、孤独・孤立対策についてお答えいたします。
新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化する中、孤独・孤立の問題がより深刻な社会問題となっていることを受け、国におきましては孤独・孤立対策の重点計画を作成し取り組んでいます。
高齢者への対策としては、「見守り」や「居場所づくり」が重要な取組とされ、本市においても、見守り活動では、自助・互助の取組を推進する地域見守りネットワークづくり支援として、民生委員や隣近所による声かけ、出水市高齢者見守り活動協定を締結した事業所による見守り、高齢者給食サービス事業及び高齢者訪問員設置事業を活用した取組を推進しているところです。また、居場所づくりについては、住民主体の通いの場である「出水こけん塾」やサロンなど、誰もが集える環境づくりを推進しています。
なお、鹿児島県警が令和3年に行った調査では、県内65歳以上の孤独死の件数は668件で、過去最多となっています。本市の65歳以上の孤独死の件数は、令和元年度及び令和2年度は各2件で、令和3年度は4件となっています。
孤独・孤立が気になる方の情報提供者は、自治会長や民生委員が多く、地域での見守りが異常の早期発見や対応につながっていることから、今後も様々な見守り・居場所づくりを推進し、人と人とのつながりを実感できる地域づくりを推進してまいります。
次に、老人クラブについてお答えいたします。
老人クラブは、老人福祉法において老人の福祉を増進するための事業に位置づけられており、おおむね60歳以上の方を入会の対象としております。
老人クラブ数と会員数については、全国的にも減少傾向にあり、本市においても同様の状況にございます。平成30年度は56クラブで3,199人でしたが、令和3年度は51クラブ、2,809人となっております。なお、組織率は、出水市全体で約34%となっております。
老人クラブ数と会員数減少の理由としましては、高齢者のニーズ等の変化や60歳代が現役で就労していること、役員の成り手がいないことなどが大きな要因とされています。
現在、市では老人クラブへの活動運営助成のほか、「不老いずみ」などの広報誌の配布を通じ、老人クラブの活動や魅力を情報発信しています。また、社会福祉協議会では書類作成などのサポートも行っているところであります。
老人クラブは、仲間づくりを通して、生きがいと健康づくりを行う場であるとともに、地域のサロン活動や見守り活動等の多様な生活支援活動の担い手としての役割を持つ組織であると認識していることから、今後も引き続き支援を行ってまいります。
次に、熱中症対策についてお答えいたします。
今年は、例年に比べ全国的な猛暑が続き、令和4年8月末現在で鹿児島県には熱中症警戒アラートが44回発表されました。
本市では、熱中症警戒アラートが発表されるたびに行政防災無線や市公式LINEを通じて市民の皆様に注意喚起を行っております。本市における熱中症による救急搬送は47件、そのうち65歳以上の高齢者の搬送は29件と全体の約62%を占めております。
エアコンの設置状況についての調査については特段行っておりませんが、いきいき長寿課では、例年、高齢者訪問員が、暑さが厳しくなる前頃から高齢者宅を訪問し、適切なエアコンの使用と小まめな水分補給を呼びかけるとともに、不在の場合は熱中症予防に関するチラシを配布し、注意喚起を行っているところであります。
地球温暖化が叫ばれる中、異常とも言えるような猛暑が例年続いていることから、今後も適切な熱中症予防に関する注意喚起を行っていきたいと考えております。
次に、健康寿命を延ばす方策についてお答えいたします。
市では、いきいき長寿課や健康増進課を中心に連携を取りながら施策を実施しております。
いきいき長寿課では、第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、介護予防普及啓発事業と出水こけん塾事業などを推進しております。介護予防普及啓発事業では講演会や介護予防教室を開催し、また出水こけん塾事業では、ころばん体操を取り入れ、身近な場所でなじみのある人たちと介護予防に取り組む仕組みづくりを進めています。現在、こけん塾は53団体で実施しており、今後も立ち上げ支援を継続してまいります。
健康増進課では、第3次健康いずみ21を策定し、健康寿命の延伸、生活の質の向上を基本目標に、本市の課題であります脳心血管病の発症・重症化予防を重点施策として取り組んでおり、特定健診の結果を基に訪問指導や健康相談を実施し、重症化予防に努めているところであります。
目標に対する現在の実績ですが、脳心血管病発症の大きな要因となる収縮期血圧について、男性は127ミリメートルエイチジーの目標値に対しまして、現状値は128ミリメートルエイチジーとなっております。女性は124ミリメートルエイチジーの目標値に対しまして、現状値は127ミリメートルエイチジーとなっているところです。
また、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割合は、特定健診受診者の25%以下を目標値としておりますが、現状値は33.9%となっているため、最終評価年度の令和6年度に向けて健康づくりを積極的に進めていくほか、がんの発症・重症化予防、こころの健康づくりの充実についても引き続き取り組み、健康寿命の延伸、生活の質の向上を図ってまいりたいと考えております。
次に、生きがいづくりについてお答えいたします。
いきいき長寿課では、高齢者自らが役割を持って活動したり、人とつながりを実感できる取組を推進しております。具体的には、地域介護予防活動支援事業での通いの場支援、とび出せ・広がれ笑顔塾事業でのこけん塾リーダー養成や認知症サポーター等養成講座事業による人材育成を行っております。地域の通いの場等で活動し、社会的な活動に積極的に参加していただくことで生きがいづくりにつなげてまいります。
また、マイライフノートについては、出水地区在宅医療・介護連携推進協議会が平成30年度に作成したもので、将来の万が一に備え、家族や周りの人に伝えたいことなどを記入するためのものであります。出水郡医師会在宅医療介護支援センターが実施する出前講座や研修会において参加者に配付されるほか、昨年10月に本市で開催いたしました映画上映会においても来場者に配付しているところであります。家族での話合いの参考にしていただきたいと考えております。
次に、陸上競技場のタイム計測器の設置についてお答えいたします。
陸上競技場については、昨年、全天候型への改修を行ったことで、より快適に競技ができる環境が整いました。今後、さらに多くの大会が開催されるとともに、合宿などの誘致も進むものと期待しているところであります。
陸上競技場の備品については、陸上競技協会と協議の上、費用対効果も考慮しながら、4種ライトの公認を得られるよう、令和3年度に購入いたしたところであります。
タイム計測器につきましては、競技記録のより正確な判定に資するものであり、大会の規模、レベルによっては必須のものと考えております。本市の陸上競技場にも常備したいところでありますが、高価な機器でありますことから、陸上競技協会と協議を行い、使用頻度なども考慮し、機器のリース等で対応することとしているところであります。
○大久保哲志教育長 北御門伸彦議員の高齢者大学の参加者を増やす対策についての御質問にお答えします。
市では、高齢者が健康と教養を高めながら生きがいを発見し、特技や人生経験を社会に役立てる活動を推進するため、市内3地域において出水市高齢者大学を開設しています。
学習内容は、必修科目の全体学習会と選択科目の趣味クラブ等があり、各種講師や社会教育指導員の指導の下、毎月実施しております。
対象者は、市内在住の65歳以上の方で、毎年4月に募集し、現在、出水キャンパス134人、高尾野キャンパス63人、野田キャンパス78人の計275人で活動しています。
参加者を増やす対策としましては、今後も関係団体等と連携しながら多様なニーズに対応した学習機会等を積極的に提供するとともに、高齢者への周知広報に努めてまいります。
○議長(田上真由美議員) 北御門伸彦議員より書画カメラの使用について申入れがありましたので、許可しております。
○11番(北御門伸彦議員) では、2問目は、大項目の2の陸上競技場へのタイム計測器の設置についてから入りたいと思います。
私が陸上競技の指導者からお話を聞いたときは、電気時計という言い方をされました。様々な機能や名前があろうかと思いますが、全天候型への改修の折、スターティングブロックのところに配線がされているとも聞いております。ゴールはレーザーで計測するとも聞いております。
現在、4種公認の競技場ですが、3種公認に至るとするならば必要な機器になるのではないかと思います。陸上競技協会の意見が統一されるまでには至っている段階ではございませんが、行政も情報を集め、判断する時期だと考えます。先ほどの答弁でリースという対応もお話にありましたが、せっかくですから設置できるように検討していただきたいと思いますし、要望書が出てからでなく、情報収集を検討していただけないかお尋ねいたします。
○松岡秀和商工観光部長 まず、電源の関係ですが、全天候型の競技場の備品を協議する中で将来的に、あるいはリースで借りたときに電源があったほうがいいということで、電源は準備をしております。今現在、その計測器がないことで非常に不便があるとか、そのあたりもないようです。
今後必要な大会等が出てきて、必要になるという場合は、また改めて検討していいのではないかと考えているところです。
○11番(北御門伸彦議員) ぜひ早めの取組をお願いしたいと思うんですが、2、3年後の令和7年には県民体育大会の陸上競技が出水で開催されるやにも聞いています。まだ検討の段階だろうと思うんですけれども、欲を言うと、大変お金もかかるかもしれませんけれども、電光掲示板に記録が表示できるようになれば、なお幸いなんですが、あの競技場は何も陸上だけでなく、野外コンサートなんかも考えられますし、ほかのイベントにも使えると思うのですが、ぜひ前向きに早期に御検討いただくようにお願いします。
次に、高齢者福祉計画・介護保険事業計画関連の質問をさせていただきます。
この計画は3年間という短いスパンですが、令和6年から9期目を迎えようとしております。次期計画の令和7年には団塊世代が75歳以上の後期高齢者に到達する2025年問題が待っております。今年度はアンケートに着手すると聞いておりますが、アンケートは前回委託していたようです。様々な計画は大体外部に委託されるものが多いと感じておりますが、計画本体は手作りのものと聞いておりまして、部局で練り上げるこの計画はより実態に即したものとして評価できると考えます。
前回の議会で老老介護について質問いたしました。質問では実態の掘り下げまで十分できておりませんが、私なりの課題を提示できたものと考えております。出水の実態を把握する必要があると判断される様々な観点について、計画策定に伴うアンケートに盛り込んでいただけるかを確認したいと思います。
○柿木彰保健福祉部長 前回の議会の中で北御門議員から老老介護についての御質問がございました。本年度調査を予定しておりますので、調査項目についても検討したいと御答弁したように記憶しております。
○11番(北御門伸彦議員) 今回の高齢者福祉計画についてもこれから質問させていただきますが、必要があると思われた場合はそのアンケートに追加していただくように希望いたします。
この高齢者福祉計画は、先ほども答弁がありましたけれども、国・県から指針が示される部分があるようですが、より地域の実態に沿った要素を取り入れた手作り感満載の計画になることを希望しております。
なお、令和4年版高齢社会白書では、昨年、高齢化率28.9%になったと書いてあります、全国でですね。超高齢化社会を迎えている理由は、御承知のように、寿命が延びていることと少子化と言われて続けておりますけれども、そのことによる影響の一番大きな課題は次世代への社会保障給付費の負担が増していることには間違いないと認識しております。いかに持続可能な社会システムに変えていくかがこれからの鍵となっていると認識しております。
2005年に施行された高齢社会対策基本法では、基本的施策として、就業及び所得、健康及び福祉、学習及び社会参加、生活環境、そして調査研究等の推進の分野ごとに取組が定められているようです。多くの分野にわたりますので、市でもいきいき長寿課、健康増進課、生涯学習課、くらし安心課、くらし安心課は交通防災なんかも関係してくるかと思うんですが、各課の連携を密にしなければならないと思っております。計画策定だけでなく、どう連携を取っていくか大きな課題になるかと思いますが、市長のお考えをお尋ねいたします。
○柿木彰保健福祉部長 計画策定はもちろんのことなんですが、施策の実施に当たっても、いわゆる高齢者の地域福祉計画を推進するに当たっては、いわゆる高齢者が住み慣れた地域でするための推進体制の構築、地域ケア包括システムと言われておりますけど、これをどれだけ充実したものにしていくかというのが大きな課題でございます。北御門議員ありましたとおり、いきいき長寿課で完結する問題ではございませんので、教育委員会を含めて他部局と連携を取って推進していきたいと考えております。
○11番(北御門伸彦議員) ぜひ国や県からの施策をそのまま実施していただくだけでなく、市独自のものを取り入れて、関係課の連携を取って取り組んでいただくことに期待をいたします。また、その数値目標を入れるとか、地域ごとの目標設定も大事かと思いますので、配慮いただきたいと思います。
先ほど答弁にありましたように、出水市では3つのコミュニティ協議会が立ち上がっておりますけれども、行政がこれから先、地域に依存することは福祉だけではないと考えております。その中でも福祉は特に支え合いが重要な要素でありますし、この協議会がうまく立ち上がっていかないことにより、同じ行政サービスを提供できなくなる懸念があります。行政サービスのやり方が地域でばらばらになってしまうのを危惧しておりますが、この点、当局はどういうふうにお考えでしょうか、お尋ねいたします。
○柿木彰保健福祉部長 生活圏域ごとに市内を5つの地区に分けてございますが、その中でコミ協が設置をされているのが3地区ということで、行政としましても、残りの未設置の地区についても、先ほどありましたとおり、介護だけではなくて、ほかの生涯、あるいは地域づくりにも大きな役割を果たすコミ協ですので、粘り強く設置に向けて、当然主体性を重んじて、設置に向けて取り組んでいきたいと考えております。
○11番(北御門伸彦議員) 大変前から気にしていることが一つあります。これはソフトというよりハードの問題なんですけれども、出水は中央公民館が設置されておりますけれども、地区公民館が不十分だと思うんです。そういう協議会を立ち上げる中でも、例えば米ノ津は協議会の事務所が事務所跡、大川内は店舗跡、野田は民間の跡になっていますね。地域全体で集まって会議をするとき、恐らく別の場所でされていらっしゃいます。非常にそういう地域の拠点が十分整備されているとは思えないんですが、既存の施設を十分利用して、それに充てることは可能だと思います。
若干外れるんですが、出水地区においても議会でいろいろ意見もいただいていますが、公共施設の出水公会堂の活用も検討できるのではないかと今回一般質問を聞きながら思ったところです。地域のコミュニティの場、それから田中議員からも提案ありましたけれども、若者のコミュニケーションの場、あるいは、例えば出水公会堂ですと、附属する石蔵が何か活用されるというお話も聞いておりますが、まちの活性化の拠点にもなり得ると思っています。ですから、その複合的な利用というのを地区公民館に持たせるということは可能だと思うんです。また、出水の場合、市民交流センターも近くにありますので、相乗効果も大きいと思います。以前、私も提案したことがあるんですが、昭和の、例えば生活用品を置いた認知症予防にもなる回想法センターですね、それを古い建物、出水公会堂にも当てはめられるんじゃないかと思っています。最近の流れでいいますと、本町商店街、先ほどほかの議員の答弁にもありましたように、地域おこし協力隊の方が店を立ち上げて、リノベーションによるまちづくりも進んでおりますし、麓でもイベントで驚いたんですけど、割と若い方が歩いているのを見かけるようになっています。ですから、高齢者と若者が集うコミュニケーションの場として出水公会堂など可能だと思いますし、ほかの地域も十分使われてない施設、そういうものを使えば、出不精の高齢者の重い腰を押してくれる一つのきっかけになるんじゃないかなと期待しているところです。非常にてんこ盛りの提案ですが、感想を市長ありましたらお話しください。
○椎木伸一市長 合併後、公共施設等総合管理計画の中で遊休施設等の活用というテーマも大きな問題でございます。公会堂につきましては、田中議員からも質問がありまして、あそこは地元のシンボル的な建物となっておりますし、また飲食等も可能ということで、若干古くなっておりますけれども、その辺も加味して、今後検討することとなっております。
今御提案のあったような、いろんなコミュニティ協議会にしろ、いろんな機能を持たせるところで遊休施設等もこれまでもいろいろ活用してきました。子育て支援室にしたり相撲道場にしたり、いろいろ活用しておりますけれども、これからもまだまだ遊休施設等ございますので、そういったことも踏まえて、どのように使っていくかということを検討してまいりたいと考えます。
○11番(北御門伸彦議員) ぜひ検討していただきたいと思いますし、後で話すことでもあるんですけれども、若者が出水公会堂に集まれば飲食店にも結構出ていかれると思いますので、まちの活性化にもつながります。もちろん高齢者もそうなんですけれども、そこのところの御検討をよろしくお願いしたいと思います。
高齢者が家から出ずにコミュケーションが取れない理由は非常に様々だと思うんですが、また、それに対する対策も非常に難しいと認識しますが、時折ニュースで出水でもあったかと思うんですけれども、孤独死が報道されるのは非常に痛ましいことでありますし、これを防止するためにも様々な実態を把握しなければならないと思いますし、対応はケース・バイ・ケースだと思います。一番いいのは御近所、自治会のコミュニティが一番かと思うんですが、自治会の未加入者も増える状況にあって、自治会も非常に難しいところ出ておりますし、民生委員さんの負担も大きいだろうと思っています。
先進事例として御紹介させていただきますが、埼玉県の日高市社会福祉協議会では、このコロナ禍において活動休止を余儀なくされたサロンやボランティア組織に対し、つながり続けるための選択肢の一つとして、オンラインの活用を促す取組をしております。高齢者も多く参加しているとのことで、新たな切り口かなと思います。せっかく大川内、江内地区にブロードバンドが整備されましたので、子供たちの利用だけじゃなく、お年寄りも活用するようにつながっていただく一つの施策になるのではないかと思います。
以前の病院事業管理者の今村先生は、離れたところにいらっしゃるお母様の安否を心配して、ウェブカメラを御自宅に付けて、時たま携帯で見ていらっしゃったんですけれども、私もそれに倣って、今、認知症の母の見守りのために携帯で状況を見れるように、ウェブカメラも安いものです、そんな数千円なんですけども、それを設置して、時たま見ることにしております。
そのようにオンラインを利用してやることは、いろいろできるのかなと思います。そういう検討の余地があるかどうかをお尋ねしたいと思います。
○柿木彰保健福祉部長 オンライン等を使った見守りということでございますが、確かに警備会社等もそういった機器のパンフレット等を作って、宣伝をしている企業もございます。今後、本来は人と人とのつながりの中で見守りをしていくのが本来の姿でありましょうけど、場合によってはそういったケースも必要なこともあり得ると思いますので、他市の状況等を見ながら検討させていただければと思っております。
○議長(田上真由美議員) ここで、暫時休憩いたします。再開は午後2時15分とします。
午後2時00分 休 憩
午後2時15分 再 開
○議長(田上真由美議員) 再開いたします。休憩前に引き続き会議を続行し、北御門伸彦議員の質問を許します。
○11番(北御門伸彦議員) 先ほどの答弁の中でウェブカメラに対するイメージだろうと思うんですけれども、監視するだけで済ませるものじゃなくて、会話もできますし、カメラも向きを変えたりできるような非常に便利なものがございますので、それも選択肢の一つになろうかと思いますし、実は、今朝ちょっと聞いたばっかりなんですけれども、そういうウェブカメラを各部屋4か所に付けて、その方は認知症だそうですけれども、他県にお住いの御子息がそれで安否を確認していて、結果的にそれがあったおかげで夜中に倒れているのを分かり、朝、救急搬送されたという事例もあるようですので、いろんな機器の組合せだろうと思うんですよ。埼玉の日高市の場合は、ズームを使って双方向で話ができる、そういったやり方をしているようですし、様々な方法の組合せで、ぜひ対応していただきますようにお願いしたいと思います。
次にまいります。こころの健康づくりにつながると考えますが、高齢者大学の話に入りたいと思います。私も2年目の参加となっております。高尾野の鶴亀大学でお話しくださった、先ほどの郡の医師会の田辺先生のお話は、高齢者の生きざまについて様々な示唆を与えてくださる部分がありました。老後の生活設計は大変大事です。また、もしものときのためのマイライフノートも紹介いただいたわけですが、歩く運動など健康にいいと、あるいは健康寿命を延ばして、寝たきり老人のことを「ネンネンコロリ」と言うそうですけども、「ピンピンコロリ」、よく使われる言葉ですが、それがベストだと講義されました。
高齢者大学以外に、高齢者の生活設計に関するサポートができる体制が現状でありましたらお知らせください。
○柿木彰保健福祉部長 すみません、もう少し具体的に質問していただければありがたいのですが。
○11番(北御門伸彦議員) 先ほど言いましたように、高齢者の余生という言い方はよくないと思うんですけれども、そこに関して生活設計をするということは非常に大事だろうと思うんですよ。その一つの指針がこのマイライフノート、病気になったときはどうする、介護はどこまでしてもらうとか、そして細かいことを言いますと、その費用はどこから捻出してほしいし、どういうことを希望する、延命治療は必要ないとか、いろいろある中の生活設計、先のことが見えたとき、初めてまた新たな人生の再スタートが切れると思うんですけれども、そういう生活設計をする一つの参考になったのが先日の高齢者大学の中の講義であったと私は認識しているんですよ。
その高齢者大学の何かちょっとしゃべりますと、例えば、お年寄りの交通安全の話もありますし、消費生活問題もありますし、そういうことで生活していく上に非常に指針になることが高齢者大学の中では講義が多いんです。その意識されているかどうかは別ですけれども、そういった生活設計、生きていく上にいろいろ安心サポートセンターなんかに行けば相談ができるのかもしれないんですが、その生活設計をする上に市がサポートできる体制が教育分野以外にあるんでしたらお知らせくださいという意味なんですが、すみません。
○柿木彰保健福祉部長 全体的には講演会とか、あるいは市からも出前講座等、要請があれば、自治会単位でも、あるいは老人クラブ単位でもお出かけをして、お話をさせていただく準備はできております。また、うちのほうも、高齢者訪問員とか、あるいは要支援者の方に対しましてもケアプラン等を作成する中で実際直接会ってお話をするわけですので、何気ない生活相談等も真摯に受け止めて、話をしているところでございます。
○11番(北御門伸彦議員) ケアが必要な方が今のイメージだと割と中心になってくるかと思うんですけれども、その出前講座とか、そういう準備があるなら、ぜひ積極的に出ていただきたい。お年寄りが来るのを待っていても、なかなか始まらないという気がするんですよ。ですから、高齢者大学にももっと人を呼び込めるようにと申し上げたのも、いろいろ準備をして来ていただいて、それで出不精を少しは解消していただいた上に、生活をしていくために、ためになる知識を持っていただく機会をたくさん提供するというのは、それがうまくいけば、行政の負担も少し緩和されるんじゃないかな、自分たちで頑張って考えていけますので、そういうふうに思うところです。
私の地元の老人クラブ山崎長寿会では、麓の景観を構成している威徳天神という神社があるんですけれども、その前の花壇にマリーゴールドを植えておりました。先日、奉仕作業で花を抜いて、冬場に自分たちで種から育てたハボタンを植える準備をしております。先ほど会長から電話もいただいたんですけれども、去年からですかね、生け垣がある、植える場所があるところは、ずっと御家庭の生け垣のところにも約500メートルぐらいになるのかなと思うんですが、ハボタンを植えて、景観をもっと盛り上げようということをしております。良好な景観形成につながると思っているんですが、私も今年4月から老人クラブに入りました。最初から役員の役割をいただいているんですが、7人で構成されておりまして、紅一点じゃないんですが、私が男1人です。非常ににぎやかな評議員会が開催されまして、そこで感じることなんですが、雑談はもちろん多いわけです。自治会内の人の動向がそこでよく分かります。こういったことはその地域のコミュニティを支えるベースになるものじゃないかなと再認識したんですが、お年寄りだけじゃないんです。地域に住む子供たちも見守ろうと、子ども会にも交流を申し入れて、夏休みは始まらなかったんですが、冬場に子供たちと交流する場も持てそうです。非常に老人クラブというのは、私は大事な組織じゃないかなと思っています。
ここで少し時間もですが、脱線したらちょっとやばいですね。老人クラブだけ1点申し上げますが、市長と語ろ会で、今、補助が会員が30人以上のクラブについて出ているという話なんですが、20人から30人未満に該当するところにも支援策はないかということが出たと聞いているんですが、このことも含めて老人クラブの組織率がものすごく落ちてきている、そこをサポートできる体制が取れないかお尋ねしたいと思います。
○田畑幸二いきいき長寿課長 20人から30人の会員さんのいらっしゃる老人クラブへの補助ということですが、一応私ども国の要綱等に基づいた形で事業を実施しておりまして、その要綱につきましては30人以上となっております。ですので、今現在としては30人未満の老人クラブさんということでは特に助成はしておりません。また、これにつきまして必要があるという状況になってくれば、県内の動向等を注視していきまして、必要性を勘案して、また検討していきたいと考えます。
○11番(北御門伸彦議員) 次にまいります。熱中症対策については、孤立・孤独対策同様、まず実態把握が必要かなと思いますし、先ほど見守りと同じだと思うんですが、多くの方法の組合せが必要かと思っています。高齢者のデータを集めた上で優先順位を決めて、できることから対応していただきたいと考えますが、例えばですが、部屋に物理的にエアコンを設置するのが一番かもしれないんですが、お金もかかりますし、例えばエアコンなら適用できるんですけれども、これに関しても設置工事費がかかります。あとは電気料の心配も出てくるわけで、場合によっては、さっきちょっとお話で何か言われたと思うんですが、昼間は涼しい公共施設に集まっていただいたりして、コミュケーションを取る方法もあろうかと思いますし、屋根付き市民ふれあい広場、夏、暑いとき利用するためにはミストも必要じゃないかなと思っているんです。対策もこれからだと思います。
熱中症対策について答弁は求めませんが、ここで書画カメラ1をお願いいたします。(議場内ディスプレーへの資料表示)ちょっと曲がってますけど、「70歳が老化の分かれ道」という本です。大小のタイトルに「健康長寿のカギは『70代』にある」と記されております。ターニングポイントが70代ということなんですね。私も準備をしっかりしなければと思っています。近づいておりますので、市長もですね。健康寿命を延伸するために、市長はどのように力を入れていこうと考えていらっしゃいますでしょうか。御自分の御持論で構いませんので、お聞かせいただきたいと思います。
○椎木伸一市長 70歳が分かれ目というような本を御紹介いただきまして、ありがとうございます。
もともと健康寿命を延ばすということは、やはり体は適当な運動を続けるということが一番ではないかな。それと、いろんな人と会える機会を持続して持っていくということが認知症防止等にも役立つのではないかなと思っておりますし、そしてまた何よりも生きがいといいますか、自分の社会に関わることとか、あるいは家庭でも家族でもいいんですけれども、集落でもいいんですが、そういった社会に関わるところをいつも持ち続けることが必要ではないかなと思いますし、趣味でもいいですし、そういったことでやっぱり閉じこもることなく、外向けに生きていくことが、そしてまた適当な運動をしていくことが必要だろうと思いますし、市政の中でもそういった機会が提供できるような施策を展開していければと考えております。
○11番(北御門伸彦議員) 大変模範解答をいただきました。おっしゃったその分野でなかなか生きがいづくりなど難しい施策だと思うんですけれども、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。
話は大変変わりますけれども、先月の28日に、日曜日でしたが、コロナの感染が収まらない中、マルマエ音楽ホールでアマチュア・ミュージック・フェスティバルが開催されました。私も聞きに行って、久々なんですけど、若い方を中心とした多くの市民の方が集まって、音楽を楽しんでおられました。
大変うれしく思ったところですが、聴衆者にも増して喜んでいらっしゃったのは、恐らく演奏者の皆さんだっただろうと思います。コロナ禍の中、音楽活動もままならなかったことは想像しても余りあるところだろうと思うんですけれども、様々な音楽活動をされている個人、グループの方々が登場しましたが、驚いたのは60歳を過ぎてからバンド活動を始めた方々が中心のバンドがありました。私たちの世代のなじみのある曲を中心に数曲演奏されたんですが、六十の手習いと昔からよく言われますが、驚きました。田上議長も1曲リードボーカルをされて、そのバンドで、これも大変驚いたんですが。
さて、何が言いたいかと申しますと、様々な文化活動やボランティア活動、そして私たちのこの議員活動もこういった範疇に入ってくるかなと、生きがいづくりの。健康長寿にも貢献すると言われているわけですけれども、以前より病は気からという言葉もあり、楽しいことがあるとか、生きがいがあるとか、心は元気になる、日々の生活も活動的になる、その結果、具体的な面でも健康の維持につながるとも言われているようです。
生きがいづくりには様々なサポートが必要かと思うんですけれども、多くの高齢者が生きがいを持って活動されることで、例えばグラウンドゴルフもだと思うんですが、そういったものを全てするのは大変難しいところかと思うんですが、分類した上に市がサポートできる多くの場面を考えていただくことが、ひいては地域の活性化につながるんじゃないかなと思いますし、健康長寿のまちになるんじゃないかなと思うところです。また、長寿ランキングで上位の県は、結構高齢者がお年を取っても働き続けているという統計もあるようですので、ここも一つのキーになってくるんじゃないかなと思います。
前回の議会で井伊議員が初めてフレイルを取り上げて質問されましたけども、フレイルというのは加齢により心身が老化し衰えた状態を言うそうですけども、フレイルにならないように活動的な生きがいを持ったお年寄りをたくさん増やしていくということが、ひいては市の元気につながると思うところです。市長、先ほど、運動、コミュニケーション、生きがいづくりとおっしゃっていただきましたが、今回触れてない部分でもありますが、働き続けるということも非常に大事かと思います。ここで、書画カメラ2をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)これが先ほど壇上でもお見せしましたマイライフノート、17ページですね。前回質問したときに使った「もしものときの安心メモリー帖」、これが書店で売っているエンディングノートの部類です。こっちは63ページあります。マイライフノートで私は十分じゃないかなと思うんですが、もっとこれを普及させていけば、割と人生の整理ができそうな気がしています。一番次世代に迷惑をかけるようなことはしたくないわけで、そのためにもこういったものは大事かなと思っています。ここが、書くことによって、新たなスタートが切れるんじゃないかと思いますが、市長、こういったものの普及、生きがいづくりに絡めて、お考えがありましたらお知らせください。
○椎木伸一市長 ありがとうございます。答弁でも申し上げましたとおり、いろんな場面で配布をさせていただいているところもありますし、私も経験がありますけど、やはり皆さんいずれ介護をする場面にどんな若い人も当たるわけで、そのときにいろんな問題が生じてくるわけですよね。そういったものをこのノートで整理しておきますと、自分の生きざまも変わってきますし、またその後に看てくれる子供とか、そういった人の心の本人の意思確認にも使えます。自分も非常に介護をしておったんですが、今もしておりますけれども、その中でやはり戸惑いがあるわけですよね。どうしたらいいんだろうかという、そういった方向性をお互いに確認できる一つの手段に非常に有効なものではないかなと思いますので、普及の方向で検討していきたいと思っております。
○11番(北御門伸彦議員) お考えをお聞かせいただきまして、大変よかったです。最後に、書画カメラ3をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)「LIFE SPAN 老いなき世界」ということで、あまり詳しく語れませんが、人生は120年、人類は生きれるよというお話です。専門家が書いている、こんな厚い本ですから、100年時代どころじゃないんです。これからは加速する時代で、ちょっと予想がつかない時代が来るということを頭に置いて、超高齢化社会に立ち向かっていただきたいと思いますし、私も頑張りたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
○議長(田上真由美議員) 次に、池田幸弘議員の質問を許します。
○3番(池田幸弘議員) 本日最後の質問者となります。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、9月5日から6日にかけて九州西岸を北上した台風11号ですが、本市では、9月5日月曜日午後1時に災害警戒本部体制に入り、午後3時に警戒レベル3高齢者等避難を発令され、午後5時には災害対策本部の設置と避難所6か所を開設、翌6日午前の解除まで大きな災害がなく、安心しましたが、担当課では答弁打合せとも重なり、大変な負担になったのではないかと推察するところです。お疲れさまでした。
さて、遡る9月1日は、防災の日でした。9月1日は、関東大震災が発生した日です。そこで、通告に従い、安心安全のまちづくりについて伺います。
初めに、地震と防災対策について伺います。
まず、令和4年8月26日午前8時48分に天草灘を震源地とする深さ10キロメートル、マグニチュード4.6の地震が発生しました。長島町で震度4、阿久根市、薩摩川内市、さつま町で震度3、出水市では震度2と発表されていましたが、震度の小さい今回のような地震についてはどのような対応となったのか伺います。
次に、マグニチュード7.0程度の地震が発生した場合についてですが、平成9年(1997年)3月に震度6強を観測した鹿児島県北西部地震においては3月26日17時31分にマグニチュード6.6の地震、震源の深さは12キロでございました、を観測した後、5月13日14時38分にはマグニチュード6.4の地震、震源の深さは9キロメートルです、を観測しています。震央は紫尾山近傍で、両者とも発震機構は、北東から南西圧縮の左横ずれ型でした。これは、鹿児島大学の資料から引用しております。出水市では震度5弱と表示されております。余震分布域は、高尾野町中屋敷から紫尾山、鶴田町紫尾、鶴田町鶴田を結ぶ西北西から東南東のラインに集中していました。
平成9年3月26日の本震による不通箇所が出水市近傍において、国道504号、高尾野町砂原から中屋敷の間で崖崩れ、4月3日の余震による不通箇所では、国道504号、堀切峠付近の崖崩れ、市道においても出水市武本での落石による通行止め箇所がありました。そのことを踏まえ、まず、山間地にある自治会等の住民が避難する方法について伺います。また、同地域におけるライフラインの確保方法等について伺います。
次に、自助・公助・共助の仕組みについてですが、市内の自主防災組織率は100%になったかと思いますが、自主防災組織の活動についてはどのような具体的取組があるのかお伺いします。平時からいざというときに対応できるようにしておくのが大事であるかと思いますが、私の住む自治会においては、水害が起きる地域ではないので、地震・台風の備えくらいであって、各自で防災対策はやりましょうとの感覚しかない状況です。そういった中ではありますが、隣近所の助け合い、日頃の声かけ、台風対策の雨戸閉めや自主的な隣家避難等はやっております。自助と隣近所の共助はある程度理解しておりますが、自治会版の共助の方法について理解が進んでいない現状があるところです。そこで、まず、自主防災組織の取組と市の支援について伺います。
次に、災害の起きにくい地域の自主防災組織が災害の起きた地域・自治会に応援に行くなどの自主防災組織同士の災害時応援の仕組みづくりができないかについて伺います。
次に、行政課題の解決に向けて、市民の利便性を向上させるデジタルトランスフォーメーション(DX)推進における組織体制、デジタル人材の確保・育成状況及び各分野での取組について、少ない人数でも業務を効率的に回し、生産性を向上させる仕組みを構築することで、住民に対する行政サービスの維持・向上を図ろうとする取組であるデジタルトランスフォーメーションの推進をどのように図っていかれようとしているか。デジタル庁の発足からちょうど1年を経過した現在において、国は自治体における主要な20の業務について、原則2025年を目標に国が策定する標準仕様に準拠したシステムへ移行することを義務づけました。各自治体で共通の情報システムを利用することで、職員にとっては業務負担の軽減、住民にとっては手続の簡素化・迅速化・地域間によるサービス格差の是正などの効果が期待できるとしていますが、自治体情報システムの標準化・共通化についてはどのような状況でしょうか。
次に、マイナンバーカードの普及促進状況はどうでしょうか。国民のほとんどがマイナンバーカードを保有することを目標に出張申請受付や臨時窓口の設置など、マイナンバーの申請促進及び交付体制の充実を図る取組が各自治体で行われています。これは、オンライン手続の際にマイナンバーを本人確認の手段として用いることを想定しており、後で述べる自治体行政手続のオンライン化を円滑に進める上でも重要な施策であると言えます。
次に、行政手続のオンライン化の状況はいかがでしょうか。住民がマイナンバーカードを用いて申請を行うことが想定される手続において、子育て関係で児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求等15手続、介護関係で要介護・要支援認定の申請等11手続、被災者支援で罹災証明書の発行申請の1手続、自動車保有関係で自動車税環境性能割の申告納付等4手続について、地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続とされています。行政手続のオンライン化が進むことにより、これまで仕事や育児等の事情により、役所まで行くことが難しかった住民の利便性の向上が期待できますが、具体的な施策としてはマイナポータルが挙げられます。マイナポータルとは、行政手続のオンライン窓口であり、マイナンバーを使用して、本人確認を行うものです。行政に関する手続のオンライン申請のほか、自身の情報の確認、行政機関からのお知らせ通知などのサービスを受けることができます。
次に、AI(人工知能)、RPA(Robotic Process Automation)、その利用推進の状況についてはどのようになっていますか。AI、RPAのいずれかを導入している地方公共団体は、令和3年6月末時点で535団体ありますが、情報システムの標準化や行政手続のオンライン化による業務の見直しを契機に、AI、RPAの利用を促進しようとする動きが出てきているようです。
次に、テレワークの推進状況についてはいかがでしょうか。職員それぞれのライフスタイルに合わせた多様な働き方の実現はもちろんのこと、新型コロナウイルスの感染拡大などの非常事態において、行政の機能を維持するBCP(事業継続計画)の観点からも自治体のテレワーク普及は重要であると言えます。実際にテレワークを経験してみて、どうだったのか。結果は、どうだったでしょうか。
次に、セキュリティ対策の徹底についてどのような状況かお伺いします。行政手続のオンライン化やテレワーク推進に伴い、個人情報の流失などセキュリティ面でのリスクの高まりが懸念されることから、セキュリティポリシーガイドラインの改定や、総務省が認定するセキュリティレベルの高いクラウドシステムへの移行支援等の取組が出水市でも行われていると思いますが、どうでしょう。
次に、新たな官民連携手法である成果連動型民間委託契約方式(Pay For Success:PFS)の活用についてお尋ねします。ここでPFS(Pay For Success)って何のことと思われるでしょう。簡単に言えば、委託のことですが、委託の仕方が従来のものと少し異なります。通常の委託契約では仕様が決まっています。業者には仕様どおりに事業を実施するとお金が支払われます。業者は、仕様書に書かれていること以外のことをしませんし、することも難しいのです。民間のノウハウを十分に生かすことができていない委託契約も中にはあると考えられます。内閣府の共通的ガイドラインでは、成果連動型民間委託方式は、行政課題の解決に対応した成果指標を設定し、成果指標の改善状況に連動して委託費等を支払うことにより、より高い成果の創出に向けたインセンティブ、インセンティブというのは目標を達成するための刺激とか誘因、報奨金のことですが、インセンティブを民間事業者に強く働かせることが可能となる新たな官民連携の手法です。民間の創意工夫を最大限引き出すことにより、従来型委託方式に比べて、行政課題が効果的に解決され、国民の満足度の向上が図られるほか、効果に応じた支払いを行うため、ワイズペンディング(賢い予算支出)、これを実践する上でも有用な手法であるとしています。
令和3年度には全国で4件の事業が採択されましたが、そのうち鹿児島県で鹿屋市と霧島市の2つの事業が採択されました。鹿屋市が要介護・要支援者自立支援・重度化防止事業で、霧島市では霧島市介護度維持改善率向上PFS事業という事業名で採択されています。
事業の実施に当たっては、地方公共団体が抱える行政課題及び達成したい成果を明確化し、対象テーマを設定することから始まります。抽出したテーマがPFSの導入が可能か調査し、続いてPFS導入の意義の整理、ロジックモデルの整理、成果指標の設定、財務モデルの検討、ヒアリング等を行い、可能性調査でPFSやSIB(Social Impact Bond)事業の実施可能性が見込めた場合、予算化を行います。その可能性調査の結果を踏まえて、募集要項、要求水準、契約書案、選定基準等の公募資料を作成します。事業者の選定は、公募型プロポーザルにて優先交渉権者を選定し、契約協議を経て、契約を締結します。そして、事業者による事業実施となるわけですが、事業の実施状況と成果指標の進捗を確認した上で、成果指標があらかじめ定めた値を上回った場合に事業者に委託費を支払うというものです。
本年4月から5月にかけて内閣府成果連動型事業推進室から全ての地方公共団体に対し、PFS事業の実施・検討状況アンケート調査が行われましたが、それによると、国内におけるPFSの実施状況として、PFSの実施件数は令和3年度末で100件、うち医療・健康分野で41件、介護分野で23件、再犯防止分野で1件、まちづくり分野で14件、就労支援分野で9件あるようです。
そのアンケート結果では、PFS事業の検討状況項目において、実施に向けた検討は行っていないと回答した自治体が1,615あります。本市においても同じ状況であると思いますが、全国アンケートにおいて自治体内や議会関係者の理解が不足しているとの項目もあり、市当局を含め、議会側もある程度の理解が必要であろうとの観点から今回質問をするものです。
担当課においてもPFS事業の内容も把握されたところだと思いますので、まず、成果連動型民間委託契約方式のメリット・デリメットについて伺います。次に、本市の様々な課題解決に向けてPFSの活用事例を調査し、導入を検討していく考えはないか伺います。
以上、お伺いしまして、壇上からの質問を終わります。
○椎木伸一市長 池田幸弘議員の御質問にお答えします。
まず、安全安心のまちづくりのうち、地震と防災対策についてであります。8月26日午前8時48分、天草灘を震源とするマグニチュード4.6の地震が発生いたしました。本市で観測した震度は、高尾野、野田及び桂島で震度2、出水で震度1でありました。
今回の地震に対する配備体制としましては、地域防災計画の震度に応じた基準に基づきまして対応しており、市内の震度は震度2以下であり、被害報告もなかったことから、その後の余震に備え、情報収集に努めていたところであります。
次に、本市でマグニチュード7.0程度の地震が発生した場合、山間地の自治会等の避難方法及びライフラインの確保についてお答えいたします。
地震で自宅が倒壊するなど命の危険性が高まっている場合を除き、自宅が土砂災害警戒区域外であれば、自宅待機をしながら情報収集と避難準備をすることになります。自宅が土砂災害警戒区域内であれば、すぐに避難準備を行い、一時避難所へ避難することになります。地震が継続するなど、さらなる被害が予想される場合は、開設する指定避難所へ避難することとなります。
避難ルートにつきましては、山間部では通行路線も限られることから、平時から自主防災組織等で把握している避難路及び通行できない場合の迂回路を利用しての避難が考えられます。
本市としましては、被害状況を早期に把握し、崖崩れ等で道路が通行できない場合は、災害時応援協定を締結しております建設業などの関係団体へ復旧の要請を行い、避難ルートの早期確保に努め、併せて復旧までの間の迂回路の確保に努めてまいります。
丸塚地区を例に申しますと、市道江川野丸塚線が通行できない場合の迂回路としては、平岩地区を抜けて、国道504号へ至るルートや、林道椿原線から林道金床線を通って、湯川内方面へ向かうルートを想定しているところであります。
その他の地区につきましても、自主防災組織と連携して、避難路及び迂回路の把握に努めてまいりたいと考えます。
ライフラインの確保につきましては、必要に応じて給水車による生活水の確保や備蓄物資の搬送による食料の確保、発電機の設置などによる電力の確保など必要な支援を実施するほか、電気事業者などの関係団体へ復旧の要請も併せて行います。万一、その地域が孤立し、陸上からの支援が難しい場合は、県の消防・防災ヘリコプターや災害派遣の自衛隊による支援物資の空輸が考えられます。
次に、自助・共助・公助の仕組みについてお答えいたします。
本市では、毎年、浸水・土砂災害想定地区を対象とした避難訓練や市民の自助・共助能力向上を目的とした地区防災訓練の実施のほか、防災意識高揚のための防災講演会、自主防災組織の機能向上を図る自主防災組織研修会を開催しております。
また、防災に関する出前講座や自主防災組織が主催する防災訓練時には、要望に合わせて職員を派遣するなどの支援をしてまいります。
次に、自主防災組織同士の災害時応援体制の仕組みづくりについてお答えいたします。
災害が発生した場合に、被害を受けていない地域の自主防災組織から被災地域への支援や被災地からの避難者受入れなどの地域間における助け合いは重要かつ有効な手段と考えます。
現在、自主防災組織の機能向上のため、自主防災避難所制度の創設に向け、自治会の皆様と協議を進めているところであります。
この制度に併せて、自主防災組織の活動を活発化するための協議の場を新たに設け、自主防災組織間の共同避難訓練や自主防災避難所での受入訓練など、相互の支援体制づくりに取り組むこととしております。
次に、行政課題の解決についてお答えいたします。
本市のDXの組織体制は、国で検討している住民情報システムの標準化の内容やスマートフォン等を活用した新たな行政サービスなどを踏まえまして、横断的な推進体制を検討しているところでございます。
デジタル人材につきましては、DX推進アドバイザー及びホームページアドバイザーを委嘱し、DXや情報発信などに関するアドバイスをいただいており、市民に分かりやすい情報発信や便利なデジタル社会の実現に向けて努めています。また、今後のデジタル社会に向けた人材育成の一環として、地方公共団体情報システム機構、J-LISですけれども、J-LISに職員を派遣し、最新のDXの情報収集を含め、情報連携に努めています。
次に、各分野での取組状況について申し上げます。
自治体情報システムの標準化は、令和7年度までに国が設置するガバメントクラウドに住民基本台帳や個人住民税などの20業務を移行することが決定しています。今年の夏頃をめどに関連する内容が国から示されるため、内容を精査し、構築に向けて取り組んでまいります。
次に、マイナンバーカードの普及についてでありますが、本市のマイナンバーカード取得率は8月31日現在、42.08%です。なお、現在申請をいただいている方の件数を含めますと、45.11%となっております。普及への取組として、第2回定例会で可決されました補正予算により、カード取得者に対し商品券を配付する普及促進事業を現在実施しています。7月末には総務省と共同で商業施設での出張申請窓口を開設し、この2日間で合計212件の申請をいただいたところであります。今後も大産業祭や文化祭などのイベント時の出張申請受付を行い、平日の窓口延長や休日窓口の開設などと併せて普及促進に取り組んでまいります。
次に、行政手続のオンライン化については、マイナンバーカードを使ったオンライン手続で、国の電子申請サイト「ぴったりサービス」を利用した転出手続サービスを令和5年2月からの開始に向けて準備しております。これによりまして、転出手続がスマートフォンとマイナンバーカードを使ってどこからでも行えるようになり、時間や場所に制限されることなく行政手続が可能となります。また、転出以外の手続もオンラインで行えるように検討してまいります。
次に、簡易的な定型入力作業などを行うAI-OCR・RPAは、こども課や市民生活課などで既に導入しておりまして、業務の効率化などで期待された効果を上げています。
今後も効果が期待できる業務への導入については積極的に取り組んでまいります。
次に、テレワークは、直近の実績といたしまして、本年7月は、31人、延べ48回、8月は、36人、延べ79回実施しています。自宅勤務が可能なテレワークは、働き方改革の一環として、特に新型コロナウイルスの影響で出勤できない職員が自宅等で業務を実施できるため、ここ2、3年の間で効果的な勤務形態として取り組んでいるところであります。
次に、セキュリティ対策は、毎年、情報セキュリティ対策委員会や特定個人情報等に関する監査を実施し、本市が保有する情報資産の保全に努めています。なお、コンピュータウイルスなどの脅威に対するセキュリティ認識を高めるため、毎年、職員全員にセキュリティ研修を受講させており、個人情報保護や情報システムのセキュリティ認識の向上の観点からも効果を上げております。
次に、成果連動型民間委託契約方式の活用のメリット・デメリットについてでありますが、まずメリットは目標を定量化して発注し、成果に応じた支払いをする仕組みですので、受注者にとってはインセンティブになり、発注者にとってはよりよい成果が得られること、デメリットは、成果指標の設定内容によっては指標を上げることのみに特化した取組になり、本来の目的が達成されない場合があると考えております。
次に、成果連動型民間委託契約方式の導入検討についてでありますが、今年度から出水市観光特産品協会に委託しておりますふるさと納税運営業務において、設定した金額以上の寄附を集めた場合は成果に連動して委託料を加算する契約を導入しているところであります。
○議長(田上真由美議員) 池田幸弘議員より書画カメラの使用について申入れがありましたので、許可しております。
○3番(池田幸弘議員) それでは、ここで書画カメラ1をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)これは、気象庁の震源・震度情報第2報の震度図でございます。野田支所及び高尾野支所では、先ほど市長からも示されましたが、震度2と表示されています。市役所では震度1でした。これは、国立研究開発法人防災科学技術研究所が設置している場所、准看護学校跡地にありますけれども、その地盤が固いためであるのですが、設置場所が軟弱地盤であれば、震度は当然大きくなります。地盤が違うと震度も変わるということを理解しておいたほうがよいというところであります。
8月26日以降は天草灘での地震情報は聞きませんけれども、東京大学地震研究所の古村孝志教授によると「マグニチュードはあまり大きくないが、狭い範囲で揺れが強くなった。この地域は地震活動が続くケースが多く、雨が降るなどして地盤が緩んでいるところでは土砂災害などのおそれもあるため注意が必要だ。また、今回の地震の震源周辺には活断層が多く存在していて、地震活動が活発なところで、しばらくの間は地震活動に注意してほしい」と話されているようです。
出水市だけではないんですけれども、様々な場所で、この震度というのは震度計の場所で変わるのだということを考慮しておいて、震度の強さにおいてはどのような判断が必要なのかというのを私たちも分かっておくべきと思いまして、示したところでした。
次に、本市の対応でございますが、地震は一般的に震度5強から大きな被害が出始めると言われておりますけれども、数字にとらわれず、震度3や4であっても生命財産に影響が及ぶ場合は、先ほどの説明の中にもありましたけれども、すぐ動かれるということでいいのか確認したいと思います。
○冨田忍政策経営部長 議員おっしゃるとおり、震度3、4、その震度にもよりますし、震源に近い場合等もございます。揺れ方も、直下型の場合、海洋型の場合、いろいろあろうかと思います。その時点、その時点で震度だけではなく、被災の状況等も踏まえて、迅速に初動対応するように心がけてまいります。
○3番(池田幸弘議員) 迅速な対応が必要であろうかと思います。
そこで、その迅速な対応手段とともに、情報伝達というところも併せて一緒に考えていただければと思います。現在のところ、情報伝達手段としては、防災無線、それからLINE、電子メール等での情報は私ども確認ができておりますけれども、高齢者でありますとか、携帯電話を利用されている方のほとんどはショートメールサービス、短い文章で送ってくる情報ですね、SMSと言いますけれども、その方法について使っていけば情報が届けやすくなると考えるところでございますが、様々な利用方法もほかにもあるかと思います。その利用について検討をしていただけないかお伺いいたします。
○冨田忍政策経営部長 SMSの災害時の情報伝達手段への活用ということでお尋ねかと思います。まずもって、今現在は、議員からも御紹介いただきましたけれども、防災メールに関する登録者が2,356人おられます。公式LINEの登録をいただいた方が9,514人いらっしゃいます。そのほかの手段として、県のLアラートの仕組みの中にいろいろ災害情報を登録しますと、テレビ各局を通じてデータ放送等で流していただけると、そのほかMBCアプリ等につきましては、個別の情報提供ということもできます。
今現在そういう取組をしておりますけれども、SMSにつきましては、基本的に登録をされる方の電話番号をこちらのほうで把握をしていく必要があります。届出をしていただいて、そういう登録がございますので、それに代えまして、防災メールの場合は、現在QRコードの読み込み方式でそのEメールアドレスを登録していただける仕組みをつくっておりますので、現在のところは、先ほど申し上げたような仕組みと防災メール、あるいはLINEの登録をできるだけ簡便に登録ができるような仕組みをつくり、いろんな機会でお願いをしていきたいと考えています。
○3番(池田幸弘議員) ショートメールサービスは、先ほど言ったように、便利な方法なんですけれども、その電話番号を把握する方法というのがなかなか難しいということになるかと思います。今後の検討課題になってくるのかなと思います。
次に、平成9年当時、高尾野町には紫尾山に一番近い平八重集落という自治会がありましたが、鹿児島県北西部地震での国道504号、高尾野町砂原から中屋敷間での数か所の崖崩れによりまして、平八重の住民の方々は、平岩・丸塚ルートで市街地に降りて行かれました。その後の余震で、またそのルートも一時使えなくなりまして、日常の買い出しにも不自由されたことがありました。堀切峠付近でも通行止めがあった関係で宮之城方面にも行けなかったという状況でありました。余震も頻発して、市街地への交通ルートでの不安もあって、山間地で生活していくことに気力を失い、平八重集落全ての世帯がやがて市街地に居住地を求めていかれ、集落コミュニティの消滅につながったことがありました。
現在の出水市内、小木場自治会は自治会の取扱いは廃止されたようでございますけれども、平岩・丸塚とか、上場、大川内等の山間地においても、住み慣れた地域で暮らし続けることのできる防災対策が必要であると考えております。
先ほどいろいろと説明がありまして、迂回路の確保に努めていくんだとか、ルートの建設業の方々の応援もあるといったところ、それから様々な発電機の貸与であったり給水車であったりという話もございました。丸塚については、平岩から国道504号を通っていくのが一つのルートと、そのほか林道の利用もできるんだと、林道の金床線と言われました。
その方法が、とにかくルートを何本でも確保するということは非常に大事になってくるところです。そういったところもありまして、大雨等が発生した場合に、今度は、平岩、丸塚ルートは、やっぱりこれも落石の危険等もあるかと思います。そこで、林道自体も大雨で土砂崩れが一緒に重なった場合には非常に通行に支障があるというとき、そういったときにはヘリコプターで、さて応援に行けるんだろうかといった懸念も若干出てきます。すぐさまの復旧を図っていきたくても、地震があった後、大雨が降れば山に入って上がっていけないという懸念もあるところです。そういったところについては、どのように迂回路の確保とともに、ライフラインを確保していかれるのか、もう少しその内容について教えていただければと思います。お願いします。
○冨田忍政策経営部長 災害時、あるいは復旧時期における迂回路、避難ルートの関係でございます。先ほど市長が申し上げましたとおり、発災後の災害復旧はもとよりでございますけれども、まず迅速にやるということでございますけど、災害発生前に、今現在、自主防災組織の方々との協議事項の重要事項の一つが避難ルートの確立、選定、そこはそれぞれの自主防災組織ごとにどういうルートがいいのか、2系統、3系統選定をしていただいて、それを近隣の自主防災組織等も併せて検討していく、そういうまずはルートの確認、その道路の状況の確認、安全性の確保、そういったものを取り組んでいき、必要があれば、建設部あるいは農林水産部と連携をして、その避難ルート、迂回路、そういったものの確保に努めていきたいと考えております。まずは、把握をきちんとしておくことが、我々もそうですけど、自主防災組織の皆様も、いざという場合の避難ルートの確立、そういったものが大事かと考えております。
○3番(池田幸弘議員) 今おっしゃいましたように、例えば平岩・丸塚ルートですと林道金床線、あそこが生命線になってまいります。大雨等があった場合は、すぐさま復旧できる体制、応急体制づくりというものをよろしくお願いしたいと思います。
次に、デジタルトランスフォーメーションについてお伺いをいたします。
2021年9月にデジタル庁が発足しまして、コロナ禍以降、ニューノーマルへの対応など、近年様々な業種・業態でデジタル化が求められております中、出水市におきましても国の地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に1名を派遣されていらっしゃいます。2021年5月12日に成立したデジタル社会形成整備法の中で、このJ-LISですが、国と地方公共団体が共同で管理する法人となったところでございます。そこで、1名の派遣をされているということですが、人材育成は1年でしたっけ、2年でしたっけ。
○冨田忍政策経営部長 今現在、派遣、2年の予定で進めております。
○議長(田上真由美議員) ここで、暫時休憩いたします。再開を午後3時30分とします。
午後3時14分 休 憩
午後3時30分 再 開
○議長(田上真由美議員) 再開いたします。休憩前に引き続き会議を続行し、池田幸弘議員の質問を許します。
○3番(池田幸弘議員) 先ほどJ-LISに派遣されている1名の方、2年間の派遣ということで、その方もデジタル人材となって帰ってきてくれることを願っております。デジタル推進アドバイザーにつきましては1人確保されたということの回答でございました。頑張っていただきたいと思います。
続きまして、地域社会のデジタル化のため、市民全員がデジタル社会の利便性を享受できるようになるための取組は進んでいますか、その状況についてお伺いします。
○冨田忍政策経営部長 市民の方のより多くがデジタル社会の利便性を享受できるような環境、そういう取組をということでございます。先ほど市長のほうから答弁がございましたように、提供するサービスとしてはオンライン上での転出手続サービス等がございます。そのほか登録していただいた方でございますけど、そういう方々には、災害情報であったり、市の催し物であったり、ワクチン接種等の情報提供であったり、LINEを使って、お知らせをしております。そのほかコンビニでの証明書の発行、あるいはLINEを使った行政サービスの予約システムを、先ほど議員も申されましたアドバイザーの御協力をいただいて、行政サービスの予約システムを、今現在準備をして取り組んでいるところでございます。
○3番(池田幸弘議員) デジタル活用支援におきましては、高齢者等への取扱い説明や様々な取組に国の補助事業があるところです。マイナポータルでありますとか、e-Taxの使い方、オンラインによる診療や予約等の仕方等がありますが、こういった取組というのはしていらっしゃいますでしょうか。
○冨田忍政策経営部長 活用の支援という形で申し上げますと、いろいろマイナポータル、e-Tax、あるいはオンライン診療等に活用をされつつあります。ただし、まだ今現在、市内高齢者の方々にとっては、いわゆるスマートフォンを使った情報の取得、自分の予約の入力等、なかなか難しい、慣れない面があるということでございますので、携帯電話の大手キャリアと連携をして、高齢者の方々のスマートフォン教室というものを開いております。4月に2日間、7月に2日間、それぞれ58名、67名の参加をいただいております。そういうところで出水市独自のLINEサービスであったり、防災メールのサービスであったり、そういう基本的な操作方法、登録方法をそのスマートフォン教室の中で取り入れていただいて、キャリアの方と一緒に共催に近い形で我々も参加をして、慣れていただく、使っていただく取組をしているところでございます。
そのほか、オンラインの転出手続のサービスが国のほうで始まります。それに向けては、令和5年2月から開始ということで、そこに標準を合わせて担当課のほうで取り組んでいます。
○3番(池田幸弘議員) そういった高齢者の方々にもスマホの扱い方が分かる人をなるべく増やしていくことで、先ほどありました災害情報が素早く伝わる、分かっていくということが市民みんなに広がっていけばいいかなと思います。
私、今年の2月にマイナンバーカードを使って市内の医療機関を受診しようと思って、電話をかけましたところ、マイナンバーカードはまだ使えないよということで、ああ、残念だなと思ったのが、ちょうど保険証がまだ来る時期じゃなかったものですから、保険証を待って、病院にも行かずに、どうしようかなと思っているときに、マイナンバーカードを使おうと思ったら、マイナポータル登録をして、せっかく使えるようにしたのに、使えないと分かってから、後でがっくりきたという経験がございます。
現在、市内ではマイナンバーカードを保険証として使えるところがどの程度あるのか分かれば教えてください。
○冨田忍政策経営部長 8月21日現在の数字がございますので、それを申し上げます。医療機関、医科でございます、13か所。歯科医院、歯科でございます、6か所。あと、薬局で13か所となっております。
○3番(池田幸弘議員) あっという間にというか、5か月ぐらいの間にすごく医療機関が増えたんだなと思いました。そういったところ、デジタル社会の利便性というものを享受できるようになりたいなと思って、いろいろ手続したところに、まだ使えないという状況があったんですけれども、医療機関が増えていけばマイナンバーを保険証として使うことも可能になっていくのかなと思うところです。
続きまして、先の6月議会におきまして、市長の施政方針等がいろいろとデジタル化につきましてもお話がありました。ブロードバンド化を整備しましたよ、小・中学校では商業高校でのタブレット端末、併せまして配置もできましたよ、デジタル化に対応していきますよということでございました。各部長からも、政策経営部長からは、デジタル庁の設置など急速に進展するデジタル化にも的確に対応していく、複数の部署が連携して推進していくことが必要不可欠であると、時期を逸することがないよう確実に浸透させていくため、行政運営体制の全庁的な改善強化にも取り組んでまいりたいと。教育部長からは、ICTを活用したさらなる学びの進化を図る。農林水産部長からは、市内で消費される農林水産物の約5割は市外から輸入(持ち込まれている)ことから、地域内調達率の向上、さらには市外への販路拡大など、近年のデジタルトランスフォーメーションを活用した施策を展開できるよう努めたいとの言葉もありました。相当困難な取組になるかと思いますが、頑張っていただきたいと思います。
続きまして、新たな官民連携手法である成果連動型民間委託契約方式(PFS)の活用についてですが、先ほど壇上で述べた内容をもう少し分かりやすくしますと、ここで書画カメラ2をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)「成果連動型民間委託契約方式(Pay For Success:PFS)を活用してみませんか」という題名で出ております。成果連動型民間委託契約方式についての内閣府の資料になります。PFSの定義とスキームについて記載されています。従来型の委託事業は、委託者である地方公共団体が、これは右側のほうのラインですね、ここの中に書いてあるのが、①では委託をする、②で受託者が事業活動を実施します、③で事業が終わると委託者が検査をします。この検査というのは、委託者が定めた仕様書にのっとり業務を実施したか、成果物が仕様を満たしているかを検査するものです。④にあらかじめ定めた額を支払うということになります。
一方、PFS事業は、委託者である地方公共団体が、①で委託をします。②で受託者、中間支援組織とも言いますけれども、受託者が事業活動を実施します。③で委託者が民間事業者の事業活動による成果を評価します。この前に選考委員会や大学等の第三者機関に評価を依頼することが多いです。④で成果に応じて、連動して費用を支払うというものです。書画カメラ3をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)次は、PFSで目指すもの、メリットです。住民にとっては、成果目標が達成されることで行政課題が効果的に解決され、満足度が向上します。民間委託業者にとっては、成果が達成されるほど報酬が増えることで、事業提案に創意工夫がみられることになり、事業取組の意欲が増すことになります。行政にとっては、成果目標の達成度合いに応じた支払いをすることで費用対効果に見合うことになり、従来の委託方式に比べ、賢い予算の支出ができることになります。
もう一つ、スキーム図があります。書画カメラ4をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)PFS事業及びSIB事業並びに従来型の委託事業のスキーム図です。SIB、真ん中のラインになります。このSIB事業は、民間資金を活用して解決を目指すというところがPFSとの違いになります。左側はPFS事業、真ん中のところはSIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)事業というところです。この事業は、PFSと合わせまして、今後、委託契約の主体となってくるものと考えられます。私たち議員も市当局も理解を深めておくべき契約方法であると考えます。
そういったところもありまして、今回質問したところでございますけれども、今のところメリットのほうがコスト面では大きいというところ、コストの面で非常に有利なんじゃないかなというところがあるんですけれども、このようなところで、今のところでは出水市のほうではPFSの実施に向けた検討というのは、先ほどお話を聞きますと、観光特産品協会に委託している契約というのは成果連動なんだよということの話を聞きましたけれども、完全に成果連動型というふうに捉えてよろしいんでしょうか。
○冨田忍政策経営部長 議員の御披露のあった純粋のPFS事業とは異なります。成果に応じた柔軟な委託料の支払いという意味では、そういう成果に応じた金額の増減というものを取り入れた委託契約をしているということでございます。
○3番(池田幸弘議員) 今の観光特産品協会に委託している事業というのも、結局はこのPFSに将来的に近いような取組になるのではないかなというふうに私は若干そのことが、事業実施した成果というのがどういうふうになるかというところで、そのサンプル的なものになるような気がいたします。
私が考えていましたのが、ちょうどそのような感じの取組に近いものでございまして、近年の業務委託契約を見ると、契約金額も大きく、成果がほしい業務の委託契約が多くなってきているようです。本市におきましても、例えば農産物販路拡大可能性調査事業というのがございますが、この中の支援業務委託料では940万5,000円の予算が計上されているところです。これは、委託者である市が定めた仕様書によって、受託者から成果品が出てくるものであります。その成果書にこれからはこんな取組をしていくべきであると、もし記載されていたとします。その取組が新しい取組で、これまで市の職員ではやったことがなく、仕様書を作成することも実施していくこともなかなか困難であることが想定される場合に、この成果連動型委託契約により民間のノウハウを生かし、成果が上がることを期待できることになります。成果が出て、その出た分の報酬を委託料として支払うことになりますが、成果がなかなか現れなかった行政課題の解決方法としては脚光を浴びてきた手法の一つでありますので、今後検討が必要かなと思っております。成果が上がった場合には、市の行政及び市民、そして受託業者にとってもウィン・ウィンとなります。各種事業の成果書を絵に描いた餅で終わらせないためにも、本市の様々な課題解決に向けてPFSの活用事例を調査し、導入を検討すべきと思いますが、市長、いかがでしょうか。
○椎木伸一市長 市民の皆様の福祉の増進という観点で、最小の経費で最大の効果を発揮するという予算の趣旨ですけれども、こういった民間の力も利用できますし、先ほど言われたようなウィン・ウィンの関係になれば非常にすばらしい制度だと思いますので、活用できる部門については大いに研究して、検討してまいりたいと思います。
○3番(池田幸弘議員) 今、市長が言われましたように、ウィン・ウィンの関係というのが築けていく分野は必ずあると思います。そこで、ぜひ導入の検討を進めていっていただきたいと思います。
以上で、私の質問を終わります。
○議長(田上真由美議員) 以上で、本日の一般質問を終結いたします。
-------------------------------------------------------
△ 延 会
○議長(田上真由美議員) お諮りします。本日の会議はこれで延会したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(田上真由美議員) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会いたします。
第5日の会議は、明日13日に開きます。御苦労さまでした。
午後3時47分 延 会
-------------------------------------------------------
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
出水市議会議長
出水市議会議員
出水市議会議員
出水市議会議員
- 180 -