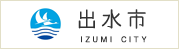令和3年出水市議会第4回定例会会議録第2号
-------------------------------------------------------
令和3年12月9日
-------------------------------------------------------
会議の場所 出水市議会議場
-------------------------------------------------------
出席議員 20名
1番 南 鶴 洋 志 議員
2番 橋 口 住 眞 議員
3番 上須田 清 議員
4番 日 髙 信 一 議員
5番 北御門 伸 彦 議員
6番 枦 山 卓 二 議員
7番 吉 元 勇 議員
8番 土 屋 工 吉 議員
9番 鶴 田 均 議員
10番 田 上 真由美 議員
11番 杉 本 尚 喜 議員
12番 出 水 睦 雄 議員
13番 鶴 田 悌次郎 議員
14番 中 嶋 敏 子 議員
15番 宮 田 幸 一 議員
16番 道 上 正 己 議員
17番 榎 園 隆 議員
18番 垣 内 雄 一 議員
19番 築 地 孝 一 議員
20番 髙 崎 正 風 議員
-------------------------------------------------------
地方自治法第121条の規定による出席者
椎 木 伸 一 市長
吉 田 定 男 副市長
冨 田 忍 政策経営部長
山 元 周 作 総務課長
中 原 貴 浩 総務課職員係長
戸 﨑 基 夫 くらし安心課長
駒 壽 ひとみ くらし安心課課長補佐兼コミュニティ推進係長
宮 﨑 毅 財政課長
大 田 直 子 財政課課長補佐兼財政係長
松 岡 秀 和 企画政策課長
青 﨑 譲 二 企画政策課秘書監(課長補佐・企画政策課秘書広報係長兼補)
冨 永 栄 二 保健福祉部長
双 津 真 安心サポート専門監(参与)
阿 多 広 隆 安心サポートセンター長
本 内 由 紀 安心サポートセンター次長(係長)
谷 川 弘 之 健康増進課長(健康増進課新型コロナウイルスワクチン接種対策室長(課長級)兼補)
萩 山 真奈美 健康増進課保健予防係長
高 口 悟 こども課長
中 里 豊 こども課こども福祉係長
松ケ角 哲 哉 こども課こども施設係長
揚 松 智 幸 市民部長
春 田 和 彦 商工観光部長
宗 像 完 治 観光交流課長
松 下 誠 観光交流課観光振興係長
田 中 誠 観光交流課交流推進係長
岡 本 賢 一 文化財課長
岩 﨑 新 輔 文化財課文化財係長
池 田 幸 弘 農林水産部長
中 原 克 章 農政課長
大 迫 健 次 農政課課長補佐兼農政畜産係長
橋 元 勝 志 農政課農業振興係長
中 村 孝 文 農林水産整備課長
志 水 靖 博 農林水産整備課課長補佐兼林務水産係長
小 原 一 郎 建設部長(水道部長併任)
小 村 郁 則 住宅課長
西 野 竜 一 住宅課主幹兼住宅対策係長
東 畠 賢 一 高尾野支所長
吉ケ島 英 章 野田支所長
鮫 島 幸 二 病院事業管理者
福 濱 敏 郎 出水総合医療センター事務部長
﨑 迫 真 也 出水総合医療センター総務課長
今 川 武 出水総合医療センター総務課課長補佐兼財政係長
大 平 伸 章 消防長
大久保 哲 志 教育長
溝 口 雄 二 教育部長
田 口 保 教育総務課長
西 鶴 浩 二 教育総務課教育総務係長
床 並 伸 治 学校教育課長
吉 元 利 裕 学校教育課指導監
西 村 かおり 学校教育課参事兼指導主事
諏訪園 直 子 学校教育課学校教育係長
阿久根 崇 学校教育課指導主事
甲 斐 優 子 学校教育課課付主任主査
小 田 大 吉 生涯学習課長(生涯学習課読書推進室長兼補)
岩 本 秀 一 生涯学習課生涯学習係長
酒 本 めぐみ 生涯学習課読書推進室次長(主幹)
-------------------------------------------------------
議会事務局
髙 橋 正 一 局長
華 野 順 一 次長(課長補佐級)
中 村 勇 士 主任主査
野 﨑 育 美 主査
北 紘 至 主査
-------------------------------------------------------
付議した事件
議案第79号 令和3年度出水市一般会計補正予算(第14号)
陳情第6号 生活保護の「扶養に関する届出書」等の見直しを求める陳情書
一般質問
午前10時00分 開 議
△ 開 議
○議長(杉本尚喜議員) おはようございます。ただいまの出席議員は20名であり、定足数に達しております。これより令和3年出水市議会第4回定例会第2日の会議を開きます。
ここで申し上げます。本日の会議に南日本新聞社及びMBC南日本放送局並びにKTS鹿児島テレビのほうから撮影したい旨の申出が出ております。よって、これを許可してございます。
-------------------------------------------------------
△ 発言の訂正の申出
○議長(杉本尚喜議員) ここで池田農林水産部長から、11月29日の議案第65号令和3年度出水市一般会計補正予算(第13号)の総括質疑において、中嶋議員の質疑に対する答弁について、発言の訂正の申出がありましたので、これを許可してあります。
○池田幸弘農林水産部長 11月29日、月曜日に開会がされました議案第65号令和3年度出水市一般会計補正予算(第13号)の総括質疑におきまして、中嶋議員から質疑のありました有害鳥獣防除事業費のうち、イノシシ・シカ等捕獲補助金の交付先について、「出水市有害鳥獣捕獲対策協議会に交付する」との発言をいたしましたが、正しくは「出水市猟友会の捕獲隊に対し交付する補助金」でございましたので、おわびして訂正いたします。
-------------------------------------------------------
△ 議会運営委員長の報告
○議長(杉本尚喜議員) ここで、議会運営委員長の報告を求めます。
○議会運営委員長(田上真由美議員) おはようございます。議会運営委員会が協議しました結果につきまして御報告申し上げます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりでございますが、12月6日に追加送付のありました議案第79号令和3年度出水市一般会計補正予算(第14号)を日程第1として上程、提案理由説明ののち、委員会付託を省略し、即決の取扱いといたします。
また、新たに提出されました陳情1件を日程第2として上程し、請願等の委員会付託区分表のとおり、文教厚生委員会に付託いたします。
皆様方の御協力をお願い申し上げ、議会運営委員会の委員長報告といたします。
-------------------------------------------------------
△ 議事日程の報告
○議長(杉本尚喜議員) 本日の議事日程は、お手元に配付しているとおり定めました。
令和3年出水市議会第4回定例会
議 事 日 程 第 2 号
令和3年12月9日 午前10時 開 議
第1 議案第79号 令和3年度出水市一般会計補正予算(第14号)
第2 陳情第6号 生活保護の「扶養に関する届出書」等の見直しを求める陳情書
第3 一般質問
-------------------------------------------------------
△ 議 事
○議長(杉本尚喜議員) これより議事日程により、議事を進めます。
-------------------------------------------------------
△ 日程第1議案第79号 上程
○議長(杉本尚喜議員) 日程第1、議案第79号令和3年度出水市一般会計補正予算(第14号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
○椎木伸一市長 おはようございます。よろしくお願いいたします。
令和3年度出水市一般会計補正予算(第14号)について、提案理由を説明します。
今回の補正はコロナ禍の長期化などに対応するための国の新たな経済対策に伴う子育て世帯への臨時特別給付金のほか、鳥インフルエンザ対策経費について計上するものです。いずれの経費につきましても、早急な対応が必要となりますことから、それぞれ予算措置するものです。
このほか、一般会計補正予算(第13号)の調整後に、寄附の受入れがありましたので、指定寄附金を計上するものであり、会期途中での補正予算の提案となったものでございまして、諸般の事情を御賢察の上、御理解を賜りたいと存じます。
補正予算第1条の歳出では、予算書13ページ、第3款民生費、児童福祉費の職員給与費では、子育て世帯への臨時特別給付金の給付事務にあたる職員の時間外手当に係る財源変更をし、また子育て世帯等臨時特別支援事業費では、子育て世帯への臨時特別給付金及び給付事務に係る経費をそれぞれ新規計上しました。
本給付金は、国のコロナ克服新時代開拓のための経済対策の一環として実施されるもので、ゼロ歳から18歳までの子供たちに一人当たり10万円相当の給付を行うこととなっており、現金による給付が5万円、クーポンを基本とした給付が5万円となっております。今回の補正予算につきましては、そのうち、現金5万円の給付に係る予算でございまして、現金給付分を迅速に支給することとし、中学生以下については児童手当の仕組みを活用して、今月27日の支給を予定しております。
なお、国の予算措置は中学生以下の現金給付分は予備費で、高校生の現金給付分は補正予算での対応となっており、高校生への給付につきましても給付金の趣旨に鑑み、国の補正予算成立後、速やかに支給準備に取りかかれますよう、本補正予算に計上をしております。
またクーポンを基本とした5万円の給付につきましては、詳細が分かり次第、予算措置させていただきますので、御理解を賜りたいと存じます。
続きまして、第6款農林水産業費、農業費の鳥インフルエンザ対策事業費ですが、11月11日には荒崎のツルのねぐらの水から、同13日には家禽からの高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたことを受け、市においては散水車による遊休地周辺の道路消毒の実施や有人の消毒ポイントを設置いたしました。また、県においても制限区域の設定や消毒ポイントを設置しておりましたが、12月2日には半径10キロメートル以内の搬出制限区域が解除され、昨日8日には半径3キロメートル以内の移動制限区域の解除とともに、県が設置しておりました消毒ポイントも撤去されたところであります。
しかしながら、ナベヅルやツルのねぐらの水からウイルスが続けて検出され、また他県の養鶏場等においても連続的にウイルスが確認されるなど、引き続きツル保護、家禽への感染防止に万全の体制を整えるべき緊急事態にありますことは、皆様と認識を同じくするところであります。
なお、環境省では全国での監視体制を既に「対応レベル3」としまして、監視を強化するとともに感染確認個体の回収場所を中心とした半径10キロメートル圏内を野鳥監視重点区域に指定しております。この区域指定は、最後の感染確認個体の回収日以降、28日を経過した時点で、野鳥監視重点区域が解除されることになりますが、新たな感染個体が確認されますと、その期間が延長されます。それらを踏まえ、防疫体制に係る経費につきましては、これまで規定予算及び予備費の充用で対応してまいりましたが、現段階では今後の動向が予測できませんので、1月末までの消毒薬等の購入費や消毒作業に係る業務委託料等の防疫対策経費を追加計上するものです。
また、鳥インフルエンザ対策への指定寄附がございましたので、所要経費の財源として歳入予算に計上しております。
続きまして、第10款教育費の中学校教材費では、高尾野中学校への指定寄附がございましたので、寄附の趣旨に添いまして図書購入費を計上しました。これに対します歳入としましては、国・県支出金及び寄附金を追加計上し、地方交付税を調整いたしました。
以上が本補正予算の内容でありますが、今回の補正額は4億9,258万円の追加で、これにより予算規模は300億4,105万2,000円となるものです。
よろしく御審議の上、御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○議長(杉本尚喜議員) 議案第79号令和3年度出水市一般会計補正予算(第14号)に対する質疑を許します。
○7番(吉元勇議員) 21、子育て世帯等臨時特別支援事業費の中の今回の5万円の給付ですが、これは先の衆議院選挙における自民党、公明党の公約の10万円給付の一環であります。政治色の強いお金でありますけれども、これは国民あるいは議員が認めるところでありますが、タイムスケジュールによりますと、この5万円については今月12月27日に給付金支給と、給付を受ける側の世帯に現金が入る仕組みになっております。本日、この出水市議会は常識のある議会だと認識していますので、恐らく可決するのであろうと思いますが、可決した後、日程を考えますと約17日しかありませんけれども、この17日の日程で27日の支給が本当に可能なのかどうか。少しタイムスケジュールのことが説明できれば、説明いただきたいと思いますが。
○冨永栄二保健福祉部長 今月の27日に振り込みをするということで、今作業を進めております。本日、御承認いただければ、12月14日に今回振り込みをする支給対象者の方には支給通知等を送付するという形で予定しています。その後、給付金について支給しなくてもいいという方がいらっしゃれば、その受付をした段階で、受付期間を12月21日までをもって、その後会計処理等をして、会計とも連携を取りながら27日には間違いなく振り込みできるような形で作業を進めていきたいという形で考えておりますので、間違いなく振り込むということで鋭意努力していきたいと考えております。
○7番(吉元勇議員) 今、タイムスケジュールの説明がありました。市長の意向もあって、なるべく今年中に給付を世帯に届けたいという意向で、今のような少し無理があるかもしれませんけれども、職員が頑張ってやるという説明がありました。
残りの5万円については、クーポン支給なのか現金支給なのか、今開かれている臨時国会での議論にもよりますが、たまたまこの臨時国会の会期が12月21日でございます。それで、本出水市定例会が23日までとなると、国会で決まってから2日はありますが、市長の中では、あるいはシステム的に本定例会の最終日であります12月23日に残りの5万円のクーポン支給あるいは現金支給のことの提案が、「やりたい」あるいは「できるだろう」あるいは「少し難しいかな」、その辺のちょっと説明、考えがあれば答弁いただきたいと思います。
○冨田忍政策経営部長 23日に予定される最終本会議の日に提案ができないのかというお尋ねかと思います。
臨時国会の会期の関係もございます。いつ可決をされるかの関係もございます。ただ、最終的には国から実施要項なるものが、確定的なものを含めて届かなければ判断のしようがないところでございますので、できるだけ国からの通知等が早く届くことを願っております。その段階で23日に提出ができれば、そのタイミングではいきたいとは思いますけれども、今のところ、なかなか難しいんじゃないかと考えております。
○7番(吉元勇議員) 畜産業費の鳥インフルエンザ対策事業費2,070万円の予算ですが、今回も鳥インフルエンザの発生によります作業については、職員の皆様に改めて敬意を表したいと思います。
そこで、この鳥インフルエンザの対策というのは、結果的には出水市の場合はマルイという会社、それからそれに加盟する組合員さん、恐らく出水市の養鶏それから卵については9割以上がこのマルイに関する組合員さんだと認識しますが、逆にいえば、こういうマルイさんの企業、あるいはその組合員さんを守るための施策だと認識しますが、となると鳥インフルエンザが発生したことによるこの企業からのなんらかのお示しがあってもいいんじゃないかと思いますが、今回、寄附金が20万円あります。この20万円というのは、そういった関係者からの寄附金だと認識していいのか、全く別物なのか、ちょっとその辺、答弁できる点があればお願いします。
○椎木伸一市長 出水市は農業の総産出額、三百数十億円ありますけれども、そのうちの8割が畜産に頼っております。その畜産のうちのさらに5割以上、55%程度が鶏産業に頼っております。そういった意味では、大変重要な市内の産業であります。ですから、一生懸命この鳥インフルエンザ対策を出水市はこれまでも取り組んできているわけでありますけれども、関係の団体様からもいずみみらい基金等へこれまで多額の寄附を頂き、いろんな助成等もいただいております。
今回の20万円につきましては、その関係団体ではございませんけれども、防疫を一緒にしてくださっている獣医師会のほうからの御寄附でございまして、この防疫対策に使ってほしいという旨でございましたので、今回使わせていただくというようなことでございます。
○18番(垣内雄一議員) 13ページの鳥インフルエンザ対策でありますけれども、12月8日に移動制限が解除されて、そして3キロ圏内の25農場は前回の検査におきましても全て陰性であったという、大変良好な結果が出ているわけですが、これ以後、解除したけれども市がまだ消毒作業を実施していくというふうに、市長からの全協の中でのお話があったところでございますが、この消毒作業に携わる方々、これまでは、以前発生したときも全て健友会の皆様方にお世話になって、多大なご苦労をおかけしたという経緯があるんですけれども、この後の消毒ポイントのそういった作業についてはどのようにお考えなのか、お答えいただきたいと思います。
○椎木伸一市長 消毒の従事の関係でございますけれども、建設業関係の皆様にはこれまでも鳥インフルエンザが発生した消毒ポイントの従事、あるいは、いわゆる防疫措置、鶏の処分ですね、に関しても重機等のオペレーターも含め、いろいろ御協力をいただいておりまして、そしてまた昨年までは我々の独自の遊休地等での消毒ポイント等については、一部お願いをしておりました。
昨今の災害等で、非常に災害復旧工事等も増えまして、非常に人員の確保が難しいという状況もありました。そういった中で、道路消毒については散水車を使っていただいておりますので、健友会さんのほうにお願いしていると思います。
そこで、私どもが有人の消毒ポイント、6ポイントを設けておりますけれども、こちらについては現在シルバー人材センターへの委託でお願いをしているところでございます。
○14番(中嶋敏子議員) ちょっと1点、確認もあってですけれども、今、吉元議員の質疑の中にも関係するかと思うんですが、今回の補正については中学生以下については国が予備費で、高校生については12月の今の国会に計上されている補正で対応するということの説明だったと思うんですね。クーポン券については、国の3月の補正で審議されると、計上されるというふうなことではなかったかなと。
そうであれば、全国で5万円現金給付にするかどうかは自治体の事情で現金給付にしてもよろしいということもあって、大阪の市長でしたか、何かもう10万円を12月中に現金で給付すると言ったら、政府から「それは待った」がかかったような話もあったわけですけれども、そういう予算措置の流れであれば、12月23日の出水市の最終本会議に間に合わせてどうするのかという議論は、ちょっと早計なのかなという気がして聞いたんですけれども、そこら確認も含めて回答をお願いします。
○冨田忍政策経営部長 そこらあたりの予算議案の関係については、全員協議会の中で田上議員のお尋ねに対して答える形で申し上げたと思うんですけれども、まずクーポン券を基本とする5万円に対する国の予算がまだ成立をしていないこと、実際問題、そのクーポンで配るか現金で配るかということについて、国の明確な方針が取扱実施要領等で通知も届いていないこと、それらを踏まえて、今現在いつの段階で予算化をできるかというのは難しいということでお答えをしたかと思います。
吉元議員に対する答弁もそういう形でお答えをいたしました。「23日にできれば」と申し上げたのは、できるだけ準備作業も含めましてクーポンとなりますと、いろんな形で事務手間がかかるわけです。それを3月までに新学期を迎える子供さん方に配ると、そういうような形で検討をしますと、3月議会ということにはならないかと今のところ考えております。そういう趣旨で、市長のほうも全員協議会で「早急な予算措置を講じなければならないこともあります」ということで、御理解をお願いしたいということで挨拶の中で申し上げたかと思います。そういうスケジュール感で進めておりますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(杉本尚喜議員) ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(杉本尚喜議員) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。本案は、委員会付託を省略することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(杉本尚喜議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。討論を許します。
○14番(中嶋敏子議員) ただいま提案をされております令和3年度出水市一般会計補正予算(第14号)について、予算に反対するものではありませんけれども、意見を述べさせて賛成したいと思います。
今、問題になっております補正予算の子育て世帯等臨時特別支援事業費、4億7,183万円ですか、計上されておりますけれども、これは18歳以下の子供に現金5万円とクーポン5万円を支給する原則だが、クーポンにすることで全額現金給付と比べて事務費が約3倍の967億円に膨らむことが問題になって、地方自治体の実情に応じて現金での対応も可能とする運用を一定程度容認するという考えを、昨日、岸田首相が国会の中でも答弁をされております。
しかし、それを認める具体的な基準は示されていないため、全国の自治体の対応に混乱がというか、いろんな問題が生じているように思います。
そもそも、この10万円給付というのは、所得制限を設けた上で11月に閣議決定した経済対策に盛り込まれたものでした。年内に5万円を現金給付し、残り5万円は春の入学新学期シーズンに向け、子育て関連商品などに使えるクーポンで支給すると。こうしたのは貯蓄に回るのを避け、消費喚起につなげる狙いがあったとされております。つまり子供のためなのか、景気対策なのか、政策目的がはっきりしていないことに起因しているのではないかと思います。その後、またクーポンにしなくてもいいとかですね、継ぎはぎしていよいよ分からなくなっているのが今の実態ではないかと思えてなりません。
そして、所得は低くても子供のいない世帯は支給対象外になるなど、問題を残しているということもありますけれども、今回、提案をされている補正予算そのものには賛成したいと思います。
○議長(杉本尚喜議員) ほかに討論ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(杉本尚喜議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。
採決いたします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(杉本尚喜議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
-------------------------------------------------------
△ 日程第2陳情第6号 上程
○議長(杉本尚喜議員) 日程第2、陳情第6号生活保護の「扶養に関する届出書」等の見直しを求める陳情書を議題といたします。
陳情第6号については、請願等の委員会付託区分表のとおり、文教厚生委員会に付託いたします。なお、付託された議案について、文教厚生委員会委員以外の委員で質疑事項があれば、あらかじめ当該委員長にその旨、お伝え置き願いたいと存じます。
-------------------------------------------------------
△ 日程第3一般質問 上程
○議長(杉本尚喜議員) 日程第3、一般質問を議題といたします。
本定例会の質問通告者は15名であります。
これより一般質問に入りますが、質問者の発言並びに当局の答弁は、できる限り重複を避け簡明・的確に、また通告外の質問や品位の保持等については遵守されるよう願います。なお、再質問から一問一答方式とし、各議員の質問時間は40分以内といたします。
質問順に従い、宮田幸一議員の質問を許します。
○15番(宮田幸一議員) おはようございます。
コロナウイルス感染症が日本全体で小康状態が続き、少しばかりの光が差し込む中、足元の出水市では、ラムサール条約湿地登録を喜ぶ間もなく、秋田県に次いで2例目・3例目の養鶏場で鳥インフルエンザが確認され、数日後にはナベヅル一羽が鳥インフルエンザで死んでいるのが発見されて、国の研究機関で分析した結果、毒性の強い高病原性の「H5N8型」のウイルスが検出されました。
視線を外に向けると、11月14日にはイギリスのグラスゴーで開催された国連気候変動枠組条約第26回締約国会議・通称COP26は、シャルマ議長の声を詰まらせる場面もありましたが、「世界の平均気温の上昇を1.5度に抑える努力を追求する」とした成果文書を採択して閉幕しました。二酸化炭素排出量世界第5位の日本は、2050年までにカーボンニュートラルを達成すると表明しましたが、課題を多く残すことでしょう。
11月26日、南アフリカでWHOが懸念される変異株に指定した新たな変異ウイルス「オミクロン株」検出の確認されたその日の夕方、岸田総理のパッケージ「新型コロナ感染拡大防止」・「社会経済活動の再開と次の危機への備え」・「新しい資本主義の起動」・「防災・減災など安心・安全の確保」の4つの柱からなる経済対策に必要な追加の歳出に、地方交付税交付金などを加えた一般会計の総額35兆9,895億円の補正予算としては、過去最大となる新たな経済対策の裏づけとなる今年度の補正予算案を閣議決定しました。
この政策の財源の中に国債を追加で22兆580億円発行することが含まれています。この結果、今年度の新規の国債発行額は65兆円を超える見通しで、財政が悪化の一途をたどる中、財政健全化への道筋が政府にとっての課題となります。
課題があるのは日本政府だけにとどまらず、出水市にも課題が山積していると私は思いますので、その幾つかを尋ねてまいります。
まず、市長の政治姿勢について、看護師募集方法等調整調停事件について伺います。
申立人は公益社団法人出水郡医師会で、相手方は出水市であります。私なりに調停事件に至るまでの経緯を推測し簡単に申し述べますと、令和元年末より令和2年9月28日まで、出水市病院事業が高額な給与・支度金を提示したチラシやポスターの貼付、朝夕の防災行政無線による勧誘により、出水医療圏の実務経験のある看護師に対し、募集を行った。これを憂慮した出水郡医師会は令和2年の1月から3月にかけて3度にわたり、当時の管理者、医院長、事務部長に対し、「このような募集は近い将来の地域医療の崩壊につながるので、自粛してほしい」と特使を派遣し、忠告を重ねたが、「看護師募集に関しては市が行っている」との回答が得られたのみであった。結局、医師会の進言を無視する形で、看護師募集はやむことなく、出水郡医師会の関係会員の事業所より約20名の看護師が出水市病院事業に転職した。
この結果、出水郡医師会広域医療センターにおいては、看護師10人が出水病院事業に転職したことに伴い、一般急性期病床が14床、非稼働に陥った。すなわち、本来なら患者さんを手厚く治療するための14のベッドが、出水市病院事業による「看護師引き抜き行為」により、患者さんの受入れができない状態になっている。つまり、医師会の予見した、地域医療崩壊を招いたわけである。以上のことから、市長に対し、「地域医療の崩壊を招いた、愚かな看護師引き抜きの責任は、己にある。」との旨を、市民に対して説明し、その事実に対する謝意を医師会に示すように、「要望書」「要請書」を提出したが、市長は「看護師募集については、自分は全く関与していない」と詭弁を繰り返すのみであった。
よって、医師会にとって、全く納得のいかない市長の対応。法的な処置やむなしで、調停に及んだ。というような経緯内容と私は認識します。
そこで、出水市民の「命の安全」を守る立場の市長として、出水郡医師会との連携・協力が必要不可欠であるということは十分承知のことと存じます。いかなる誠実な対応でもって、信頼関係を構築されていかれるのか。また、申立人代理人弁護士の神川洋一氏の意見書の「出水市防災行政無線管理運用細則の第2条に“同報無線局による放送を行うことができる範囲は次のとおりとする”とあり、4号には“その他、市長が特に必要と認める事項”とありますことから、「道義的・社会的責任を負うことは当然だ。」との文言について、市長の見解を問います。また、管理者と地方公共団体の長との関係を定めた地方公営企業法第16条適用に関する文言についても、市長の見識を伺います。
次に、出水総合医療センターの運営についてお聞きいたします。
防災行政無線等により勧誘した看護師さんは、20名いると以前の議会答弁で述べられました。他の病院に勤務されていた実務経験のある看護師の方々に、地方公務員としての高額な給与と支度金まで提示して募集されたのだから、その費用対効果の成果をまずお聞きします。私は、地域包括医療連携という部分で考えると、出水市内の市民の命の安心と地方公共団体の市民の福祉のパイの大きさは、出水総合医療センターの看護師不足の状態のときの他の出水市内の病院事業者の看護師さんの数など、出水郡医師会の当時の状況と同じだと考えます。しかし、現在は、看護師引き抜きの件でパイは小さくなったと思います。なぜなら、同じ地域内から看護師を引き抜かれた病院事業者は対策に追われ、心労が重なり、その分、体力が低下したからです。そこまでして看護師を勧誘されたのは、本業である医業収益を上げて、医業利益の赤字を削減しようとのことだろうと推察しますので、その費用対効果について明快な答弁を求めます。併せて、20名の看護師さんは、全員現在も出水総合医療センターに勤務されているのでしょうか。
漏れ聞くところによりますと、辞められた方もいると聞き及んでいますので、20名中何人辞められ、辞められた理由をもお聞きいたします。
続いて、学校給食について、各調理場は汚染作業区域と非汚染作業区域の区分は適切になされているのかについて、お尋ねいたします。
学校給食法は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的に定められた法であることや、平成29年6月16日付で厚生労働省医薬・生活衛生局、生活衛生・食品安全部長から、各都道府県知事と域内の市区町村の教育委員会に通知された学校給食衛生管理基準の取扱いについては、県教委に長年勤務されていた大久保教育長は熟知されていることと存じます。釈迦に説法みたいな質問になったら御容赦ください。
そこで、ノロウイルスを含む食中毒菌等からなる食中毒を予防するため、厚生労働省食品安全部長の大量調理施設衛生管理基準マニュアルや、学校給食衛生管理基準で定められた「学校給食施設は、汚染作業区域・非汚染作業区域に部屋単位で区分されること」が明記されている学校給食施設の区分のとおり、適切に区分されているのかを尋ねます。
次に、出水市学校施設等長寿命化計画の幼稚園の整備方針について問います。
スーパーコンピューターを駆使して作成し、内閣府が所管しているビッグデータによると、鹿児島県96市町村が平成の大合併で43市町村となったが、この43市町村の中で地方自治体として生き残れる数は8自治体で、出水市は第7位にランクされています。そこで、何としても生き残るため、少子高齢化対策は喫緊の課題であることは、皆様周知のとおりであります。
出水市学校施設等長寿命化計画に目を通しますと、「園児数の変化について、働き方の多様化による保育需要の増加や少子化による幼児数の減少等により、幼稚園需要は減少傾向にあると考えられることから、市立幼稚園の集約化・認定こども園への移行・民間活力の推進の3本柱を軸に、令和2年度から検討を始め、令和4年度までの、できるだけ早い時期に具体的な方針を決定し、整備を進めます。」と明記してありますので問うものです。
○椎木伸一市長 宮田幸一議員の御質問にお答えします。
まず、私の政治姿勢における看護師募集方法等調整調停事件についてであります。まず、宮田議員は今回の質問において私どもの職員からのヒアリングの中で、ある医師から入手した資料を基に質問するとのことであります。そもそも、現在、医師会と市との関係でありますが、現在新型コロナウイルス感染症対策、中でもワクチン接種対策などにつきましては、市民の安全・安心を守るために、医師会の先生方もワクチン接種を優先していただくなど、必死になって市民の命を守るために、そしてまた3回目の接種に向けても日夜取り組んでいただいているところでありまして、心から感謝を申し上げております。そしてまた、私ども出水市におきましても、医師会の先生方と同じ方向を見ながら、市民の命を守るため、医師会の先生方そして医療従事者の皆様の御協力をいただきながら取り組んできているところであります。また、出水市では医療センターの改革にも必死になって、これまで取り組んできているところでございます。
そのような中で、これまで私は宮田議員に対しまして、目に余る不当要求行為に対して3年前に警告を発しました。そしてまた、出水市議会におかれましても同様に、この間、2回にわたる辞職勧告がなされております。そのような宮田議員に対しまして、今回の調停に関係のある医師から、裁判所も関係する極めて機密性の高い調停の書類でありますけれども、その書類が渡され、このような質問がなされるということは、極めて残念でありまして、日頃から私どもと一緒に市民の命を守っていただいている医師会の多くの先生方もそのように思われていることと思います。
まずは、そのことを申し上げたいと思います。
今回、この調停に対しまして、私は首尾一貫して事実に基づき、同じ考えで臨んでまいりました。
この調停事件は、出水総合医療センターの看護師募集方法等に関し、出水郡医師会から調停の申立てを受けるもので、市としては申立ての趣旨の全てに応じることができませんでしたが、出水保健医療圏における医療従事者の確保等に係る様々な重要な問題を協議し、改善すべきところを改善していく機会を作りたいと考えております。
また、出水市民をはじめ、出水保健医療圏にお住まいの方々により良い医療を提供するための環境整備が最優先事項であると考えていますので、出水市も阿久根市及び長島町と連携しながら、最大限の協力をさせていただきたいと切に願い、調停の場において出水郡医師会と意見を出し合う協議会の設置などを提案し、真摯に対応してきたところであります。
○鮫島幸二病院事業管理者 宮田幸一議員の御質問にお答えします。
出水総合医療センターの運営に関する防災行政無線等により公募した看護師についてですが、防災行政無線により応募されたかどうかは定かではありませんが、令和元年12月から令和2年9月までに出水保健医療圏の医療機関等から採用した看護師20人については、そのほとんどが現在も当医療センターに在職しています。そのうち4人の方は、既に退職しております。
次に、この看護師採用における費用対効果についてですが、多くの看護師を採用するに至った主な理由が、地域医療構想に基づく、地域包括ケア病棟開設のためでしたので、令和2年7月に当病棟を開設したことにより、急性期の患者と回復期の患者のすみ分けがスムーズに行われるようになりました。また、同年9月から患者数・収益ともに増加傾向となったことから大いに期待しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きく状況が変わってしまいました。
全国的に感染が拡大する中、鹿児島県から感染症病床の増床について依頼を受けていたところ、本市においても同感染者が急増し始め、瞬く間に感染症病棟の4床では対応できない状況となってきましたので、同年12月から当地域包括ケア病棟を感染病棟に変更し運営することとしたところです。これにより病院全体の患者数・収益ともに減少しましたが、当病棟の開設に向け、多くの看護師を採用していたことが、その後の新型コロナウイルス感染症の対応を可能にした要因となり、数字では表すことのできない大きな効果があったものと考えています。
なお、退職された4人の方が当院を辞められた理由については、一身上の都合とのことであります。
○大久保哲志教育長 宮田幸一議員の御質問にお答えします。
まず、各学校の調理場の汚染作業区域と非汚染作業区域の区分についてですが、本市の各単独調理場では、「汚染作業区域」と「非汚染作業区域」を区分し、調理室等の非汚染作業区域に外部からの汚染を持ち込むことがないように衛生管理に努めています。
具体的には、施設・設備の面では、それぞれの作業区域が部屋単位で分けられており、非汚染作業区域と汚染作業区域が区分されています。検収室は設置がないものの、検収場所を汚染作業区域内に設け、泥や細菌からの汚染を防ぐための置台を設置したり、業者にあらかじめ泥を落として納入していただいたりしており、汚染作業区域内であっても、可能な限り汚染を低減するよう努めています。
運用面での工夫としては、調理従事員が作業途中に汚染作業区域と非汚染作業区域を往来することがないように、動線図や工程表を作成し、前日のミーティングで共通理解を図った上で調理にあたっています。また、作業区域ごとに専用の履物やエプロンを使用するとともに、器具や清掃用具についても作業区域別に使い分けています。さらに、非汚染作業区域に入る場合、2度の手洗い及び手指消毒を徹底しています。
汚染作業区域と非汚染作業区域の区分については、学校薬剤師の協力を得て行う定期検査や、大量調理施設に対して保健所が実施する検査においても課題は見られておらず、適正に行われているものと考えています。
今後も、薬剤師等に助言をいただきながら衛生管理の徹底を図り、安心・安全な給食を提供していきたいと考えております。
次に、幼稚園の整備方針についてでございますが、これまでに、幼稚園長、幼稚園教諭代表、こども課、教育委員会担当等で、幼稚園の在り方について意見交換をしてきました。
具体的な方針はまだ明確になっていませんが、今後、さらに企画政策課、財政課等から幅広い意見を聴取して、令和4年度末までに、方針を決定していきたいと考えています。
○福濱敏郎出水総合医療センター事務部長 ちょっと、確認をさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
○議長(杉本尚喜議員) それは反問権ですか。
○福濱敏郎出水総合医療センター事務部長 はい。
○議長(杉本尚喜議員) では、反問権を行使します。時間を止めてください。
○福濱敏郎出水総合医療センター事務部長 宮田議員のヒアリングの中で、「ある私の知人の医師からもらった資料」というふうに言われて、それは何なのか具体的に分からず、議員の話によりますと、「弁護士が裁判所に出している、あれ」「僕の持っているものを読んだと思うが」ということで、具体的にどういう資料をお持ちなのか、そのとき特定できませんでした。その資料は自宅に置いてきたということでしたので、具体的に何をお持ちなのかは教えていただきたいと思います。
○15番(宮田幸一議員) 私が持っているのは、出水郡医師会の医師なら全員の方が持っていらっしゃるものだと思います。ヒアリングのときには私、自宅に置いてきましたので。ヒアリングを受けた出水総合医療センターの、名前を言っていいのかどうかが、聞きにいらっしゃった2人とも「それは読んでいる」とおっしゃいました。私がここに持っているのは多分これ弁護士が。ここ読みましょうか、じゃあ。令和3年の第3号看護師募集方法等調整調停事件申立人 公益財団法人出水郡医師会、相手方 出水市。令和3年10月13日、出水簡易裁判所御中。申立人代理人弁護士 神川洋一、ということで、数ページにわたる意見書を出されていまして、同じものを当然、これは市長にも、相手方ですから、その出水市の代表者にも出されているんだと思います。それで、私へのヒアリングのときには、この中身も私にヒアリングをした出水総合医療センターの方は名前は申しませんが、2人お聞きでしたが、これ読んでいるとおっしゃいましたので、それでそのときに私、ヒアリングのときに持っていませんでしたけれども、そのとおりここの記述を読んで覚えていたことを尋ねたものであります。
○福濱敏郎出水総合医療センター事務部長 ということは、申立書をお持ちということになるんでしょうかね。
それは、結局コピーになるということで、ある医師からもらわれたということですけれども、それは申立人からもらわれたということで理解してよろしいんでしょうか。
○15番(宮田幸一議員) これ、公益財団法人出水郡医師会と申立人はなっていますので、その会員のメンバーの方だと思います。この出水郡医師会に入っている会員のメンバーは、みんなこれ同じものを持っていますということでしたから、多分私にくださったのも自分の持っているコピーを私にまたコピーしてくださったんじゃないかなと、私は思っていますけれども。
○福濱敏郎出水総合医療センター事務部長 では、理事の方からもらわれたということで、ありがとうございました。
○議長(杉本尚喜議員) 反問権、よろしいでしょうか。
○冨田忍政策経営部長 反問権で今の質疑の確認をしたいので。
○議長(杉本尚喜議員) それでは、反問権を行使します。引き続き、時間を止めてください。
○冨田忍政策経営部長 ただいま医師会の先生方は、皆さん、その資料を持っていらっしゃるということで宮田議員はおっしゃいました。宮田議員に渡された方もそういうふうにおっしゃったということは間違いないわけですね。全員がお持ちであるということは間違いない事実ですか。
○15番(宮田幸一議員) 私はいちいち確認をしていませんので、全員が持っているかどうかは分かりませんが、私にこれをくださった方は「出水郡医師会の会員であれば、全員がこれを持っていることですから」ということで、渡していただきました。
○冨田忍政策経営部長 その方は医師の方ですか。医師会員としての医師の方でしょうか。
○15番(宮田幸一議員) 医師の方です。
○議長(杉本尚喜議員) よろしいでしょうか。
○冨田忍政策経営部長 答弁するに当たりましては、そのお持ちの資料が正確に裁判所が関与するような機微な取扱いに非常に慎重を要するような資料でございます。そういったものを、宮田議員にお渡しになった方。どなたから受け取られたのか、教えてもらえませんでしょうか。
○15番(宮田幸一議員) それは申し上げられません。
○冨田忍政策経営部長 そういうことであれば、今お持ちの資料がどういったものなのか、本当に調停事件に関与した必用な正本であるのか、そういったものが確認ができないんですけれども、そういう答弁にならざるを得ません。医師会の皆さんがお持ちの資料ということで、そのうちどなたかの医師会の方から宮田議員に対して提供があったということでよろしいですね。
○議長(杉本尚喜議員) ここで反問権を解きます。引き続き、宮田議員の質問を許します。
○15番(宮田幸一議員) まず、市長にお尋ねいたしますが、出水総合医療センターは市長の附属機関、補助機関との見解を市長自身はお持ちでしょうか。
○椎木伸一市長 地方公営企業法を全部適用している企業体でありまして、私が設置者ということであります。
○15番(宮田幸一議員) 出水郡医師会は令和2年3月28日特使を派遣し、出水総合医療センター内において、当時の出水市病院事業今村純一管理者と面談した際、今村前管理者は「先生の御苦労、お察しいたしますが、看護師募集に関しては市が行っていますので、私ではお力添えできません」と回答されているのに対し、令和3年1月末の市長の出水郡医師会との会見では、「私は、地方公営企業法に基づく出水総合医療センターの設置者であり、経営形態の方針等の指示などの一部を除いて権限が制限されており、看護師採用等には関与できない規定になっている。すなわち市長の私ではない」との回答がされています。この二者の回答は明らかに矛盾していますが、どちらが本当なのでしょうか。
○福濱敏郎出水総合医療センター事務部長 今おっしゃった、元事業管理者の今村事業管理者につきまして、私も確認いたしました。しかし、そのようなことは言っていないということで、看護師募集は病院自体が行ったことであると。出水市は関係ないという証言を得ております。
○15番(宮田幸一議員) 市長は出水郡医師会に対して、誠実に対応されたのでしょうか。以前、私の質問に対し、今日もおっしゃいましたけれども、「出水郡医師会との関係は良好で、コロナワクチン接種にも協力していただいています」と答弁されていました。のに、なぜ裁判所へ出水郡医師会が調停を申し立てられたのか分かりませんので、お伺いいたします。
○椎木伸一市長 議員は資料を全部入手されていらっしゃるということですので、それを読んでいただければ、その中に詳細に書いてあると思います。
私は一つ一つに対して、先ほども申し上げましたけれども、事実に基づいて丁寧に対応しているところであります。
○15番(宮田幸一議員) 私が漏れ聞いたところによりますと、無投票で当選された椎木市長の後援会長は出水郡医師会会長さんだったと聞いております。政治を目指す人にとって、後援会長とは最も信頼関係が構築できる、いわば相思相愛の関係が通常なのですが、裁判所に調停を申立てされるまでの間に解決できなかったのは何が原因なのか、市長の見解を伺います。
○椎木伸一市長 おっしゃるとおり、私が第1回目に立候補した際の後援会長にお願いをいたしました。その後、私のほうで、ちょうど2年前になります。ちょうど2年前の12月でございましたけれども、出水医療センターへの答申の中に、いろいろ医師会への指定管理をすべしというような、するのが望ましいというような内容が出ておりましたので、いわゆる医師会長さんは阿久根広域医療センターの責任者でもあられますので、そういったことで、今後利害関係が発生するでしょうということで、そういった理由を説明いたしまして了解をいただき、2年前に後援会長は解消させていただいているところでございます。
○15番(宮田幸一議員) じゃあ、そういうことであれば、最初は一緒に行動されて、私の友人の阿久根市のある方とも後援会長さんと椎木市長で選挙運動して回ったというのは漏れ聞こえてきているのですが、それはそれとして。
じゃあ、今後、そういう関係だったら出水郡医師会との関係がこのままだと、出水市民の命の安心と地域医療の活性化が阻害されて、出水市民の健康を支える状態が半減することが私としては危惧されますが、市長のお考えはいかがでしょうか。
○椎木伸一市長 私は先ほど申しましたように、郡の医師会の先生方と出水市は良好な関係で、市民のほうをお互いに向き合って、同じ方向を向いてしてくださっているものと認識しております。
御質問の中で、非常に誤解を生じやすい、私が不本意と思うような部分がありますので、あえて発言をさせていただきたいと思いますけれども、今回のこの調停の案件につきましては、いわゆる私どもの出水医療センターの運営上の事案、これは私には権限がないわけですけれども、それを不合理に捉えられまして、全てを私の責任として出水総合医療センターの今後の在り方等の権限を持つ設置者である私に責められているというように感じているところであります。
もとより、私は就任前にこの答申がなされまして、議会へも一貫して自分の考えを述べ、そしていろんな機会に市民の皆様にも説明してきましたけれども、答申で出された7億円のラインというのは、経営の努力によりまして7億8,000万円のキャッシュフローができましたので、クリアいたしました。答申の中には、それをクリアできない場合はいろいろな方法があるけれども、中でも郡の医師会に指定管理を出すのが望ましいというような表現がございましたけれども、クリアした暁には、経営改善に取り組むというふうになっておりましたので、経営改善にそのまま取り組んでいるのが現状でございます。
これから人口が以前は10万人あったこの地域の出水医療圏の人口も8万人を切ろうとしております。そういった中で私が副市長の時代から郡の医師会の先生方とも話しながら申し上げてきましたけれども、私の考えというのは、医療センターはまずは経営改善をして、市民に負担をかけない形で経営をしていかなければならない。その上で、将来的にはこの8万人を切ろうとしているこの地域に200床以上の病院が阿久根広域医療センター、出水医療センター、この2つが存続していくのは、非常に難しいだろう。そう思いまして、その中でお互いに市民から求められる医療分野をお互いに共存できるような形で持ち合いながら、将来的にはずっと話合いを重ねながら、どういった形が将来に負担を残さず住民の皆さんによいことなのか、そういったことを話し合って対応していくべきであろうという思いがございました。答申の中には、非常に出水医療センターの実態を踏まえない部分もありましたので、諮問委員会、答申を出してくださった委員の先生方にも説明をし、お許しをいただいて今まで改革をしてきたところであります。
今回の一連のこの調停、あるいは新型コロナウイルスの対応のお礼等に行く際に、郡の医師会長さんにもそろそろそういった話合いを始めませんかという提案もしました。広域医療センターの院長先生にも、同じようなお話を実際にしております。これは私は録音も録っておりますので事実であります。
そういった中で、まずは答申にありますように経営改善をし、市民の皆さんに負担を残さないようにしているというのが現状でありまして、議会の皆様も御存じのとおり、80億円近くあった累積欠損金、会計処理で皆さまの同意をいただいて減少したわけであります。これも十数億まで減少することができました。そういったことで、未来に負担をかけない形で、今一生懸命、職員の給与も削減しながら、私も2割削減しておりますけれども、そういった中で必死の改善に努めているところであります。
どう考えても、先ほどの話に戻りますけれども、私に一連のことで責めがあるというのは、経営権の問題ではないかなというふうに思わざるを得ないわけであります。我々は一緒になろうと思って協議を始めたいと思っているのは事実であります。そのことを申し上げ、今後、さらに改革を進めながら、時期をみて医師会とも将来に向けての協議を進めながら取り組んでいきたいというのが、私もそうでありますし、病院のほうもそのように考えていると認識しているところであります。
○議長(杉本尚喜議員) ここで暫時休憩いたします。再開を11時20分といたします。
午前11時03分 休 憩
午前11時20分 再 開
○議長(杉本尚喜議員) 再開いたします。休憩前に引き続き会議を続行し、宮田幸一議員の質問を許します。
○15番(宮田幸一議員) 前の議会の私に対する答弁でも「良好だ、良好だ」と言われている。そのとき僕もちゃんと言っているんですけど、医師の職務、責務というのは病人を治すことですから、だからコロナウイルスのワクチンを協力されているのは医師の職責としてされているんであって、別に市長と信頼関係があるからでは私はないというふうに思うのですが、そこで申立人代理人弁護士の神川弁護士の意見書の中の、「出水市防災行政無線管理運用細則第2条4号の“そのほか、市長が特に必要と認める事項”として、今回の看護師募集が行われたことは、相手方出水市も認めるところである」との記述があるのですが、これに対して市長の反論があれば、どうぞお願いします。
○冨田忍政策経営部長 その相手方弁護士の方がどういうふうに言われているのか、ちょっと私は承知をしておりませんけれども、市長が特に認めるとかそういうことではなく、過去の議会においても答弁をしていると思いますけれども、過去からずっと市の行政に関わるもの、そこについては放送してきております。防災行政無線の無線管理運用細則というのがあります。これは市の防災行政無線の管理運用規定に基づき、細かいところを定めているものでございまして、放送の範囲というのが2条で規定をされております。災害情報であるとか、人命財産に重大な影響を与える場合とか、そのほか3号としまして時報、昔は時を知らせる時報もございました。それも範疇です。それと、市の行政事務に関する事項というのがあります。この市の行政事務に関する事項、これは広報も含めまして、市民の皆さんに周知が必要なものについて、この項目に基づいて放送をしているわけでございまして、出水市は従来、病院事業であろうとどんな職種の事業であろうと市の職員の採用に当たっては、防災行政無線を通じて広く市民の皆さんに知っていただく必要がある行政事務ということで、従来からこのような取扱いをして放送しているわけでございまして、決して特に市長が認めたから放送したというわけではございません。
私がこの答弁をしますのは、電波法に基づきまして無線局については総括管理者を置かなければならないと電波法上決まっております。その総括責任者が私でございまして、通常いろんな部署から、それは企業会計であろうと教育委員会であろうと任命権者が異なる組織からでも、出水市の行政事務として放送要請があれば、私のほうで単独で判断をしております。そういうことは、前回もいつかの議会で答弁をしていると思いますので、細則等を確認を取られて、どの条項に基づいて私がこういう話をしているかは、しっかり御理解をいただきたいと思います。
○福濱敏郎出水総合医療センター事務部長 今ありましたように、看護師募集につきましては議員がおっしゃるように地方公営企業法にのっとりますと、事業管理者が行うものでございます。ですから、看護師募集を決めたのは病院です。それの依頼をして、市のほうにしてもらったということで、あくまでも看護師募集をしているのは医療センターのほうということを御理解いただきたいと思います。
それと一つ、反問もよろしいですか。
○議長(杉本尚喜議員) 反問権ですか。
○福濱敏郎出水総合医療センター事務部長 はい。
○議長(杉本尚喜議員) 反問権を行使します。時間を止めてください。
○福濱敏郎出水総合医療センター事務部長 先ほど資料の確認をさせていただきました。そのとき「申立書」と議員はおっしゃったのですが、それは申立書ではなくて意見書じゃないですか。意見書は番号があると思うのですが、何番をお持ちでお話されているのか、そこを特定させていただきたいと思います。
○15番(宮田幸一議員) 今、そういうふうに聞かれたということは、当局としては相手方から、これでいけば相手方は出水市になっていますけれども、相手方はじゃあ、まだいっぱい私が持っている資料以外に何か言われているということになりますね。
(発言する者あり)
○15番(宮田幸一議員) いやいや、そうでないと「何番をお持ちですか」とか、多分私のこれを疑ってのことだろうと思うんだけど。
(発言する者あり)
○15番(宮田幸一議員) 私のこれでいくと、申立人がこうこうこうであって、それの申立人が出された意見書であります。それでさっきもちょっと言ったと思うんですが、令和3年、これ「ノ」と読むのかな。括弧書きしていて、(第3号)ということで、私が持っている資料は全てそれのかがみで分かる、それが表になって意見書がずっと述べられているものであるということです。
○福濱敏郎出水総合医療センター事務部長 先ほど資料の特定というので、意見書と言われなかったものですから、申立書とおっしゃったので、申立書の中に今議員がおっしゃるのがあまりなかったものですから。で、持っていらっしゃる資料が意見書ということで番号が振ってあったものですから、それはどれかなというところでお聞きしました。
また、この意見書、つまり今議員がおっしゃったこの資料は、出水郡医師会の会員の方は皆さん持っていらっしゃるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
○15番(宮田幸一議員) 人の答弁はしっかり聞いてもらいたい。同じことを向こうが言って、政策経営部長がそのときちゃんと言っているじゃないですか。人の質問を聞いていないということ。
○福濱敏郎出水総合医療センター事務部長 ですから、先ほど推測とおっしゃって、「だろう」ということをおっしゃったと思います。そのときは、申立書、薄いんですね。意見書となると、かなり分厚い資料になるものですから、それでそれを果たして会員様が皆さん持っていらっしゃるのかをもう一度聞きたかっただけです。別に聞いていないということではなくて、聞いておりまして、資料が多いものですから確認したかっただけです。
○15番(宮田幸一議員) 私にこれを渡された方は、だから「出水郡医師会の医師は、みんな同じものを持っているから」ということで。だからさっきも言ったように、私は出水郡医師会の皆さんに「持っていますか、持っていますか」といちいち確認したわけではありませんので、それは私は分かりません。ただ、私にくださった方は、出水郡医師会の会員であれば皆同じものを持っているということで、私にくだされたものです。
○福濱敏郎出水総合医療センター事務部長 意見書の何番というのだけ、教えていただけますか。
○15番(宮田幸一議員) 1、2、3です。
○福濱敏郎出水総合医療センター事務部長 ありがとうございました。
○議長(杉本尚喜議員) ここで反問を解きます。
○15番(宮田幸一議員) それでは、私も先ほど言われましたけれども、ちゃんと出水市防災行政無線の管理運用規則も、あれもちゃんと読んでいます。ただ、時間がありませんので言いませんが、弁護士は今の冨田部長の言われたことに対して意見書の中で反論されていますけれども、まあそれはそれでして。
次に、管理者と地方公共団体の長との関係について記述のある地方公営企業法第16条に対する市長の見識を伺います。
○椎木伸一市長 これまでも何回も答弁しておりますけれども、病院事業は地方公営企業法全適した病院事業体であります。そういった中に事業管理者を置いておりますので、運営権等は事業管理者が持っておりまして、私は設置者として、その経営の在り方、大きな基本路線だけを指示できるというふうになっていると考えております。
○15番(宮田幸一議員) 私が地方公営企業法第16条を読む限り、看護師引き抜きは「当該地方公共団体の住民の福祉に重大な影響がある地方公営企業の業務の執行に関し、その福祉を確保するため必要があるときは地方公共団体の長は当該管理者に対し、当該地方公営企業の業務の執行について必要な指示をすることができる」とありますので、主権者である出水市民も会員となっておられる出水郡医師会への職責を考えれば、出水郡医師会からの看護師募集については、中止の指示をすべきだったと私は読み解きますが、私の読み解き方は誤っているのでしょうか。
○椎木伸一市長 「引き抜き」という言葉を使われますけれども、ハローワークを通して正式に公募をしたというようなことで、私は報告を受けております。
先ほど、ちょっと質問がありました、いわゆる特使を送られて改善を求められたということでございましたけれども、後で私も報告を受けて、そのように改善され、相手の先生からもお礼があったというような話もありました。ですから、私に報告があったのが、確か令和2年の夏場、要請を県の医師会あるいは郡の医師会の連盟でいただく直前でございました。そういった要請が届きますのでという際に、そういったやり取りの報告を受けたところでありまして、私が受けた際には、もう改善をされ、それも阿久根広域医療センターのほうも了解されたというふうに認識しているところであります。
○15番(宮田幸一議員) 今の市長の言い方は令和2年のときにそういうことがあったのだけど、調停事件がされているのは令和3年10月13日なので、時系列的にちょっと私は理解に苦しむのですが、それはそれとして。
では、看護師募集方法等調停事件は裁判所の呼出しに対し、市長は初めの頃は「公務が忙しい」との理由で応じず、後からは「知らない」と放置されたため、不調に終わったと聞き及んでいます。それが事実だとするならば、私は市長と出水郡医師会との信頼関係の再構築は大変厳しいと考えますが、今の出水郡医師会との関係は市長としてはどうされるおつもりなんでしょうか。
○椎木伸一市長 冒頭に答弁いたしましたとおり、丁寧に対応をいたしたと私は思っております。事実に基づいて対応したと思っております。
その調停のいきさつについては詳細はあまり申し上げられませんけれども、病院の事務部長のほうから答弁をさせますが、郡医師会との関係につきましては、先ほど答弁いたしましたように、私はいろんな市民の皆様の安心・安全を確保するための対応等についてはこれまでも、そして過去もこれからも医師会の皆様と連携しながら取り組んでいけるものと思っておりまして、良好な関係であるというふうには思っております。
○福濱敏郎出水総合医療センター事務部長 調停につきましては、双方の意見がやはり隔たりがあるわけです。それでなかなか成立しなかったということでございます。
○15番(宮田幸一議員) それでは、令和3年1月末の出水郡医師会との会見の市長の言葉、「出水医療圏内の地域医療を守る重要な役割を担っておられる医師会の皆様には、出水市民の命の安心のため多大な御貢献をいただいており、深甚なる敬意を表しますとともに、心から感謝いたします。出水市として、出水郡医師会の皆様との連携・協力により、信頼関係を継続して構築していくことは、同時に市民の福祉の向上につながるものであると確信をしており、今後とも良好な関係を継続してまいりたいという考えに、いささかの偽りもありません」の言葉はどこへいったんでしょうかね。
○椎木伸一市長 そのとおり、私は答弁したつもりであります。
○15番(宮田幸一議員) ですから、それなのに調停が市長は1回も裁判所に出て行かれなかったということで、不調で終わったと。
先ほどから、非常に大事な書類が私に来たのはおかしいと言われるけど、もう御存じだと思いますが、裁判は結審したり不調になった場合は、この資料はどなたにも渡すことはできるんです。検察庁の検事さんに聞いてください。ですから、私が言うのはこの言葉とすれば、今の状況は違うので、この時の言葉はどこにいったんでしょうかと聞いています。
○椎木伸一市長 ですから、私は事実に基づいて丁寧に対応をしたと申し上げております。
調停の中で、私どもも法的な代理人を立てて、しっかりやってまいりましたし、事前に報告も受け、また事後にも報告を受け、そういった手続の中で私の意向も確実に反映されながら行われたものと思っておりまして、私が申し上げましたように、繰り返しになりますが、事実に基づいて丁寧に一つ一つ対応してきたところであります。
○15番(宮田幸一議員) 次は時間の関係で、出水総合医療センターの運営についてをお尋ねいたします。
防災無線等により出水総合医療センターに勧誘され、勤務されていて途中で辞められた看護師さんに直接お会いをし、話を伺いました。給与は地方公務員の適用でよかったが、仕事は厳しく、夜中2時頃に帰宅することも多く、家族との会話の時間もなくなり、家族が体調不良に陥り、家族を守るため支度金を返還して出水総合医療センターを辞めたが、元の職場には戻れず、全く違う職場で看護師の仕事をしているとのことでありました。
そこで、引き抜きにより出水総合医療センターに勤務され、途中で辞められた方が先ほどの答弁では4名いらっしゃるとおっしゃいました。なぜ辞められたかの理由は一身上の都合とおっしゃいましたかね、管理者は、そういうことでしたが、私はここで聞きたいのは、じゃあ、辞められた4人の方で元の職場に復帰された人はいらっしゃるのかどうか。分かる範囲内で結構ですので、教えてください、
○福濱敏郎出水総合医療センター事務部長 先ほど一身上の都合ということで、その後どこに行かれたかまでは、ちょっと調査はしておりませんので分かりません。
○15番(宮田幸一議員) 私に言わせれば、看護師を引き抜かれた病院事業所の経営者も引き抜かれないために、看護師さんの待遇のため賃金を上げざるを得ず、年間経営経費がかさみ、この方々も被害者。引き抜かれた看護師さんも感情的問題から元の職場に復帰できず、被害者であると私は思います。だから両方被害者。だとすれば、出水市全体で見れば、地域力は低下し、何も利は生まれなかったとしか、私は思えません。この辺を深く反省し、看護師募集に活用していただきたいし、現在も出水総合医療センターに勤務されている引き抜かれた看護師さんたちの職場環境を整えるべきだと考えますが、管理者の見解を求めます。
○鮫島幸二病院事業管理者 現在いるスタッフの職場環境を保全すること、それから働きやすい環境を作ること。その上で市民のための医療を提供すること。これは私たちの使命だと思っておりますので、おっしゃられたとおり、そのように努力していきたいと思います。
○福濱敏郎出水総合医療センター事務部長 今おっしゃったように、地域の医療を守るということで、調停の中でも市長の提案で看護師不足の解消とか、医療従事者の出水地区からの流出を防ぐとか、そういうために協議会を設置しましょうという提案もしております。それがつまり、出水地域内の医療を守っていくことにつながるということで、そういう御提案もこれまでもしてきたところでございます。しかし、協議会の設置は、今のところできていない状況でございます。
○15番(宮田幸一議員) 先ほど言った令和3年1月末の出水郡医師会との会見の中で、市長が申し訳なかったと謝られたところの文章も出てきます。今回の看護師採用に関わる事案は、地域医療への配慮が足りず、皆様に多大な迷惑をおかけすることになり、大変申し訳なく誠に残念であり、深く反省しております、と。
それで、今後は実務経験のある看護師を募集するにあたり、一番としてUターン、Iターン優先枠を設置するとか、2番目に二次試験の受験者には勤務中によるいかん、在職証明書(出水総合医療センターを受験するための証明書である旨を明記したもの)も提出してもらうとか、なお募集方法の見直しに関する市民への周知は募集要項を市役所本庁、各支所、出水総合医療センター各診所等に配布するほか、出水総合医療センターのホームページで周知するの3点ですと。こうやって改善しますから、ごめんなさいというか、すみませんでしたという文章があるのですが、これについては病院事業管理者としてはこのとおり今後はやっていかれるおつもりかどうかをお尋ねいたします。
○鮫島幸二病院事業管理者 おっしゃるとおりです。Uターン、Iターンの方々、ぜひ、当出水の医療センターのほうに帰ってきてほしいと願っております。そのために、どのような広報が必要なのか、学校、看護学校、あるいは薬剤師も不足しておりますので薬剤師、それから医師も不足しておりますので、各大学病院の教室等を毎年、挨拶して回っているところです。
私としましては、もしこの出水市で出水医療センターがどうしても必要だと、市民の命を守るために必要だと皆さんが認識してくれるのでありましたら、市民皆さまの声を上げていただいて、議会からもいろんな他の地域に行っている看護師さんで、「地元に帰ってきて働きたいんだけど」という相談がありましたら、ぜひうちの医療センターのほうに一報御相談いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○15番(宮田幸一議員) わざわざ通告書に、ここの部分では市長にも答えをもらうようになっていますので、うっかりして忘れるところでした。
市長にお尋ねします。私に入った情報によりますと、椎木市長は鹿児島大学の教授に産科医3名を、出水総合医療センターに常勤してくださるよう交渉されていたので、その準備として麻酔科医を探すと同時に看護師募集にも力を注入されていたということですが、この情報は間違っておりますか。
○椎木伸一市長 答えから申しますと、間違っております。
私が鹿児島大学病院の教授の先生方、そして熊本大学の教授の先生方、同じ回数だけ訪問するようにいたしておりました。必ず大体月に1回は県庁に行く際、あるいは熊本の関係地方事務所に行く際、そういった折り合いを見ながら、必ず出かけておりました。
しかしながら、具体的な話を教授とした覚えはございません。産科について申しますと、出水では2人の現役の先生が産科医を開業されて非常に頑張っていらっしゃるけれども、取り上げる件数がほかのところの1.5倍以上あるというようなことで、非常に心配しているという話は先生からもお伺いしました。くれぐれも今後もよろしくお願いしますと、そういった方々を医療センターも応援したいと思っていますので、安心して出産できる環境に持っていきたいという、私の気持ちはお伝えしましたが、先ほどおっしゃったような具体的な話をしたことは一度もございません。
○15番(宮田幸一議員) じゃあ、私に入った情報は。実は私、鹿大の教授の名前も存じ上げているのですが、間違っているとおっしゃるんですから教授の名前も申し上げません。
では、次に移ります。学校給食について、教育長は平成9年4月1日に制定された学校給食衛生管理の基準を旧基準といい、現在、施行されている学校給食衛生管理の基準は旧基準を踏まえ策定されたことだということは、御存じでしょうか。
○大久保哲志教育長 この学校給食衛生管理基準につきましては、平成9年に通知されましてから何度かの改正といいますか、学校給食の改正に基づいて基準のほうも新しく変わってきているというのは存じ上げております。
○15番(宮田幸一議員) 今、教育長がおっしゃるとおり、平成9年にできたのが俗に言うO-157の食中毒が出て、平成21年に変わり、それから今度はまた違う食中毒がはやって、そして平成28年に変わってきているということは御存じだということで、質問を続けてまいります。
では、厚生労働省食品安全部長の通知は、薬事食品衛生審議会、食品衛生分科会、食中毒部会において平成28年度の食中毒発生状況を報告し、ノロウイルス対策、腸管出血性大腸菌対策等について議論が行われ、食中毒調査結果により食中毒の発生原因の多くは一般衛生管理の実施の不備によるものとされております。それを受けて、学校給食衛生管理の基準はしっかりと順守すべきとの強いお考えは、大久保教育長にはおありでしょうか。
○大久保哲志教育長 学校給食につきまして、今ありましたように衛生基準に基づいて実施すべきというふうに考えております。
○15番(宮田幸一議員) それでは引き続き、厚生労働省食品安全部長の通知以前の平成21年4月1日、文部科学省スポーツ青少年局長の通知の学校給食衛生管理の基準は、旧基準からの主な変更点の中に学校給食施設管理に関わる衛生管理基準には、何と書いてあるでしょうか。
○大久保哲志教育長 手元に今資料を持ち合わせておりませんので、お答えできません。
○15番(宮田幸一議員) 先ほど、すごく衛生管理に徹底しているとおっしゃる割には、これを知られていないというのは、ちょっと私はあれなんですが。ここには、ちゃんと書いてあるんですね。要するに、旧基準から新しいものの主な変更点ということで真っ先に挙げてあるのが、今まさしく質問している学校給食施設の区分について、汚染作業区域、非汚染作業区域及びその他の区域の整理をし、その前に前室を加えることとした。これが変わっているんだよということで、留意点が書いてあります。
私が質問しているのは、汚染作業区域と非汚染作業区域の区別なんですが、そうなりますと当然、ここに書いてある、これを区別するということは、その他の区域も分けなさいと書いてある。その他の区域に、大久保教育長はトイレとかそんなのが入るのはお分かりですよね。
○大久保哲志教育長 その他の区域には、更衣室、休憩室、専用トイレそれから前室等があるのは、存じ上げております。
○15番(宮田幸一議員) それでは、大久保教育長に真摯にお尋ねいたします。
じゃあ、なぜ、国がここまで厳しくしているのか。もともと教育長は、この学校給食衛生管理基準というものができたのは、元々は厚生労働省でいろんな事例があって大量調理施設というんですが、まあ老人ホームでもそうですね、大量に作りますから。そこの中に学校給食が含まれているのですが、そこでいろいろと食中毒に関していろいろあったから、厚生労働省からの通達によって学校給食法の中に安全基準を取り入れたということは、お分かりでいらっしゃいますよね。
○大久保哲志教育長 今お話をされた大量調理施設衛生管理マニュアルの改正について、という文書の中に、今おっしゃったようなことが書かれていると認識しております。
○15番(宮田幸一議員) それなら質問しやすいです。
じゃあ、お尋ねしますが、なぜ汚染作業区域と非汚染作業区域及びその他の区域を部屋単位で区分することを、文部科学省の学校給食衛生管理の基準において、早急に整備を図ることが必要な事項の冒頭に明記されているのは、教育長もお分かりだと思うのですが。じゃあ、なぜ冒頭に書かれているかとういうと、二次汚染の防止と作業動線が明確になるようにということでありますよね。そこはお分かりだと思います。
そこで尋ねますが、汚染作業区域から非汚染作業区域に調理従事者が移動する場合の留意点を教えていただきたいと思います。
○大久保哲志教育長 今ありましたように、汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する際には、先ほど答弁の中でもお話をしましたように、外部からの汚染を持ち込むことがないように、例えば着ているもの、これを着替えたりとか、それから手洗い消毒、こういったものをするから、今答弁の中でも言いましたけれども、エプロンとか履物とかこういったものも変えるということで、汚染作業区域から非汚染作業区域へ外部からの汚染を持ち込むことがないようにしていると認識しております。
○15番(宮田幸一議員) もうじゃあ、私から言いましょうか。汚染作業区域から非汚染作業区域に行くときは、先ほど1回目の答弁でもおっしゃいましたけれども、エプロンとか履物を全部履き替えるということ以外に、手指の消毒までおっしゃった。だから聞くつもりはなかったんだけど漏れていたから、いいですか、使い捨ての手袋であっても、そこで全部それを捨てて、そして新しい手袋に変えて移動することというのが明記してあります。その点は御存じでしたか。
○大久保哲志教育長 そういうことも書いてあったように記憶しております。
○15番(宮田幸一議員) では、先ほどの答弁では、部屋単位でちゃんと区分されていると。単独調理場と全ておっしゃいましたけれども、では部屋単位で区分されていない学校給食施設の場合は、汚染作業区域と非汚染作業区域の境にはカウンター等を設けるなど、食品のみが移動するよう工夫することになっていますが、出水市内は本当に全学校の給食施設はちゃんとそのようになっているのでしょうか。
○大久保哲志教育長 カウンターの設置の確認はしておりませんけれども、今、汚染作業区域から非汚染作業区域に入るのが食材というか、人間がそこからそこに移動がすぐにはできないようになっていることは確認しております。
○15番(宮田幸一議員) 結局何と言えばいいですかね、私が知っている限り、部屋ごとに分けていないところもあるんですけれども。部屋の中で同じ作業をして、そっちでは壁を作って部屋ごとだと言われるかもしれんけど、なぜかと言ったら、調理する所は汚染作業区域になりますよね、ですよね大久保教育長。それを違うところに、違うというのは要するに配膳するとか、給食を運ぶほうに持って行くとか、非汚染作業区域になりますから、それを人間が汚染したままこう、部屋が間仕切りがなければ持っていかなければいけないというのは、駄目だよと。だからカウンターを持って。分かりますかね、境にカウンターを設けて汚染作業区域から調理したものを非汚染作業区域にいる人がそれを持って配膳するんだというのが、できていない学校、学校名を言うと傍聴席に保護者の方がいらっしゃるといけませんので言いませんけれども、それを私は全部できていないと思うんですけど、いかがですか。
○大久保哲志教育長 今議員がおっしゃった「調理したものを」ということがありましたけれども、先ほどの答弁の中で言いましたように、汚染作業区域と非汚染作業区域は明確に分けてありまして、例えば今おっしゃった下処理室というのがあるんですけれども、ここで検収室で食材が入ったものを下処理するわけですけれども、ここでしたものについては、ここはまだ汚染作業区域ですから、ここは食材が入ったものを洗ったりとか皮をむいたりというのはありますけれども、それが済んだものを今度は調理を行う調理室、これは非汚染作業区域になるわけで、ここに持ち込む際には人は同時に移動できなくて、きちんと処理がされたものが調理室に持ち込まれて調理がなされると。そういうことで汚染作業区域と非汚染作業区域は明確に区別されていて、ここは厳密にしてあることを私も確認しております。
○15番(宮田幸一議員) 聞き方が悪かったのか。
じゃあ言いますけれども、全部部屋ごとにちゃんと書いてあるんですよ、この法律に。部屋ごとに分けなさいと。区分しなさいと。部屋ごとになっていますか、全部。
○大久保哲志教育長 答弁の中で申しましたけれども、検収室というものは、これは食品の下処理室と特別に設けていないところはあります。これはなぜかと申しますと、先ほど厚労省から大量調理施設衛生管理マニュアルのところから衛生管理基準が平成9年から施行されたという話をしましたけれども、そもそも本市の調理場というのは一番新しいものでも平成元年度ということで、この検収室については当時は設置のことについては下処理室と区別することはなかったので、検収室については下処理室の前に、手前で受け取って、そして下処理室に入れるというところはありますけれども、それ以外の一番肝心な下処理をした後、調理をする際に持ち込むときにはきちんと分けて、ここについてはしっかり部屋も区別してあるということでございます。
○15番(宮田幸一議員) だんだん私の質問の最後にほうに近づく方向に答弁が進んでいるようでありがたいことです。
もうこれ、読んでみられて分かると思うんですが、安全基準にはちゃんと「部屋ごとに区分しなさい」と書いてあります。それはなぜか分かりますよね。二次汚染を防ぐためですから。そこまで分かっていらっしゃるんだったら、次にいきます。
じゃあ、調理場の外部に開放される部分にはエアカーテンとか網戸を設置し、ネズミや昆虫の侵入を防止することや調理室の入り口にはエアシャワーを備えることが望ましいと、安全基準にはあることは御存じだと思いますが、出水市内の学校の給食施設の状況を教えていただけませんか。
○大久保哲志教育長 今、幾つか例が出されましたけれども、検収室の件でお話したように、エアシャワーですか、そういった新しい施設について、まだ十分に整っていないところがあるのは認識しております。
○15番(宮田幸一議員) 以前の議会でも申し上げました衛生管理に関する指導体制の中で、「実態把握に努め、衛生管理上の問題点がある場合には速やかに改善措置を講じるようにすること」と書いてあります。そのことを9月議会で質問しましたら、教育長の答弁では「視察を行い、実態把握はしている」とのことでしたが、先ほども言われましたとおり、下処理は汚染作業区域で確実に行い、非汚染作業区域を汚染しないこととありますので、各学校施設において実態を把握していらっしゃるのであれば、本当に全学校給食施設はそうなっているのかどうかをお尋ねいたします。
○大久保哲志教育長 汚染作業区域と非汚染作業区域の区別については、最初に答弁しましたので省かせていただきますけれども、この学校給食衛生管理基準を踏まえて、各調理場で定期検査をしている結果については、前回、前々回の中でも答弁の中に盛り込んでおりましたけれども、ほとんどのところが運用ではありますけれども、クリアしているということで、96.4%の数値が衛生管理基準を満たしていると認識しております。
○15番(宮田幸一議員) 私が聞いているのは、それはそうだとしても、じゃあ安全基準で示されている点検表の一覧があるのは御存じでしょうか。その点検表の一覧の中に、調理等における点検表という中で、下処理調理中の取扱いというところの一番上に、「下処理は汚染作業区域で確実に行い、非汚染作業区域に汚染の二次感染をさせないこと」というのは、もう確実に。それを全部チェックされて、今の答弁いただいたその答えだと理解してよろしいでしょうか。
○大久保哲志教育長 今私が96.4%の達成度と申しましたのは、その衛生管理基準にある点検をクリアしている割合でございますが、今、議員がおっしゃった下処理室から、つまり汚染作業区域から非汚染作業区域へ持ち込む際の二次汚染がないようにということについては、これについてはそれぞれの調理従事員の方に、ここのところは厳格に行っていると。つまり、下処理するものは下処理室で、それが済んだものが部屋を隔てて調理室のほうに運ばれているというふうに理解しています。
○議長(杉本尚喜議員) ここで、暫時休憩いたします。再開を午後1時といたします。
午前11時59分 休 憩
午後1時00分 再 開
○議長(杉本尚喜議員) 再開いたします。休憩前に引き続き会議を続行し、宮田幸一議員の質問を許します。
○15番(宮田幸一議員) 学校給食における衛生管理については、平成8年度に発生した腸管出血性大腸菌O-157による食中毒の教訓を踏まえ、平成20年6月の学校給食法の改正において、学校給食衛生管理基準が法律上、明確に位置づけられたことは教育長も御存じのことと思います。だったら、児童生徒の食の安全を守るため、先ほどから教育長はそれぞれの各単独調理場の学校ができたのは、もう古くなって老朽化しているのもあると、だから一律にこうこうできないんだということは、答弁で何度もおっしゃいました。だんだん私の質問の最終方向に、私のレールの上を走ってくださって非常にありがたいんですが。
だとすれば、いつになったら出水市内の学校教育施設、要するに給食施設は学校給食衛生管理基準に定められたとおりになるのでしょうか。
○大久保哲志教育長 この給食室の改善・改築というあたりですけれども、今先ほど申しましたように、確かに給食調理場といいますか、給食調理場というのは、今の安全管理基準ができる前に造られていて老朽化しているのは事実でありますけれども、この安全管理基準というのは、その時代時代で何回も改正をされてきたと申しましたように、何か新しい事案が発生すれば、当然のことながら、こういった安全管理基準というのは、さらに厳しくなったりあるいは改善されたりするものと認識しております。
大事なことは、もちろんこの給食調理場の改修・改善、それからそういったものを含めたことが大事だということは十分認識しておりますけれども、まずはそこの調理場で働いていらっしゃる給食調理に従事している方々、こういった方々がいかに衛生管理基準にのっとって、その運用を図っていこうとする、そういった意識がどうあるかというのが大事であると。もちろん、それに頼っておいてはいけないわけですけれども、私も何か所かの給食調理場を視察させていただいた際に感じたことは、どの調理場においても給食調理従事員の方は非常に意識が高くて、先ほどから出ております非汚染作業区域、そして汚染作業区域、この区別でありましたり、あるいはその中での作業工程、そういったものを含めまして厳格に実施されていると。そういったところは大事にしていかなくてはならないというふうに認識しております。
○15番(宮田幸一議員) 私の質問の仕方が悪かったのか分かりませんが、もう御存じだと思います。学校給食衛生管理基準は、このとおり平成9年4月1日に制定されて、それから平成15年、平成17年、平成20年と改正を積み重ね、こちらに私が持っているのは厚生労働省からの指示書ですが、これが平成28年に食中毒がでての先ほど言いました大量調理施設についての管理で、これで強化されております。
これに書いてあることは、「早急に改善すること」の中に入っているから、私は聞いているんです。「早急」というのは、教育長の「早急」はいつなのか。私の早急というのは、少なくとも1年以内という感覚ですが、教育長の早急という期間はどれくらいの期間とお考えでしょうか。
○大久保哲志教育長 早急というのは感覚的なもので、何年というふうにお答えする立場にないので、私では今お答えできません。
○15番(宮田幸一議員) そうしたら、ここに書いてある出水市学校施設等長寿命化でも、ある程度年月を決めて学校給食に関しては書いてあるんですが、それには各学校が何年に建って、どれくらい老朽化しているというのを一覧表も載っています。
じゃあ、少なくともこれを目標にされていくべきではないかなと行政マンとしては思うのですが、だったらこれでいくとあと何年ぐらいに文部科学省が決めた学校給食施設の衛生管理基準に基づくようになっていくのかということをお答えください。
○大久保哲志教育長 私としてお答えできるのは、先ほど申したように安全衛生管理基準に基づく検査項目については、96.4%をその運用によって達成しているという状況はありますので、そのことを踏まえた上で、さらに先ほど私も述べたように老朽化が進んでいるのは事実ではございますので、今後、単独調理場の大規模改修や新設等を含めて検討していく必要はあるというふうに考えております。
○15番(宮田幸一議員) 人任せだから、いろんな食中毒が起こっていることが書いてあります。だから施設としてこうしなさいと、早急に改善するところは改善しなさいと書いてあるわけですから、その辺は早急にしていただきたいと思います。それで老朽化したから改善していかなきゃいけないと思っているということですので、では学校給食施設を改善する場合の教育長の留意点を教えてください。
○大久保哲志教育長 その留意点というのは、私のほうで今の衛生管理基準に基づいて、その必要な事項が定められておりますので、そういった事項を踏まえて改修・改善をしていくべきだというふうに考えております。
○15番(宮田幸一議員) 学校給食施設改善をする場合は、もう御存じだと思いますが、平成23年3月の独立行政法人日本スポーツ振興センター学校安全部のマニュアルが発行されていることは、教育委員会の後ろの方、お持ちですよね。それによりますと、学校給食施設等を整備する際には、いいですか、設計段階から栄養教諭等の意見を取り入れて、衛生面に配慮した作業しやすい調理場を作ることが大事とあります。つまり、二次汚染を防ぐ作業動線を明確にするということですので、参考までにここで申し述べますが、それに対して大久保教育長の御意見があればどうぞ。
○大久保哲志教育長 その平成23年度のマニュアルです。それはまた後ほど確認するとしまして、今おっしゃったように先ほどから出ていますように、調理に従事をされている方々というのは、皆さん非常に綿密に計画も立てていらっしゃいまして、一日一日給食調理が終わった後、片付けが終わった後は、作業動線図ということで次の日の作業の動線図、それから調理をする際の作業の工程表、こういうものを綿密に作っておられます。私も実際、これを見せていただきましたけれども、非常に綿密な計画が毎日毎日、全て記録も残っておりまして、こういったものがされておりますので、こういったものは今後も引き続き大事にしていきたいと考えております。
○15番(宮田幸一議員) 今、教育長がおっしゃったように記録に残すということは、これもまた衛生管理基準に書いてあるんですが、これ永久に保存しなさいと書いてありますので。その辺はちゃんと記録を取って、それを残していかなければならない。
それで、要するに動線をしっかりして、きちっとやっていくんだということは、私が申すまでもなく、とにかく食中毒をなくすんだと。要するに、言い換えれば汚染作業区域から非汚染作業区域への二次汚染を防いで、食中毒をなくすんだというのが大前提だということは、もう教育長お分かりだと思いますので、このことはやめます。
では、次にいきます。先ほど教育長の見解で、私聞いてびっくりしたんですが、出水市学校施設等長寿命化計画についてですが、幼稚園の問題です。教育長の見解では、すみません、先ほどの答弁を聞いていると、「まだ明確にはなっていないが令和4年度末までに方針を決める」と答弁されました。そこで、教育長の見解では、「令和4年度まで」という文言は、令和4年度を含んでいるとお考えでしょうか。
○大久保哲志教育長 先ほど答弁したとおり、令和4年度末までにというふうに理解しております。
○15番(宮田幸一議員) 私がこれを読む限りでは、「令和4年度まで」と書いてあるから。私の高校時代に全国一斉の能力検定試験というものを受けまして、主要5科目の中で、私、国語はとんでもない成績でラサールから訪問にいらっしゃったことあるぐらいだったんですが、私の読解力が間違っているのでしょうか。私に言わせれば令和4年度までと聞いたら、令和3年度がぎりぎりの期間だと私は思っている。違いますかね。
○大久保哲志教育長 今、長寿命化計画の中にあるように、「令和2年度から検討を始め、令和4年度までのできるだけ早い時期に、具体的な方針を決定し」というふうに書かれておりますが、私はこれは令和4年度末までと理解しております。
○15番(宮田幸一議員) 4年度までのという、「の」というのは、国語の文法で助詞になるんですが、私に言わせればこれを「に」と置き換えても、となると令和3年度と。じゃあ、私の頭脳が悪いのか、高校時代はそれだけ国語の検定はよかったのに、年を取ったから私の能力が落ちたということなのかなと。じゃあ、自己反省をいたします。
それで、さらにお尋ねいたしますが、この記述の中に特に市立幼稚園の園児数の著しい減少ですと、近い将来において半数以上の市立幼稚園が単独での運用ができなくなる恐れがあります、との文言を受けて、3本柱の一つ、市立幼稚園の集約化につながっていると私は考えております。
そこで出水市内7つの市立幼稚園を幾つかに統合されるのか。それとも全てを認定こども園に移行させられるお考えなのでしょうか、お尋ねいたします。
○大久保哲志教育長 先ほど答弁で申したように、まだその方針という、集約化それから認定こども園への移行についても、まだ方針が明確になっておりません。と答えたとおりでございます。
○15番(宮田幸一議員) じゃあ、もう期間がないわけですので、もう間もなくすると令和3年度が終わります。ですから、今後の対策として、方針が今決まっていないんだったら、この方針を決めるまでの手だて、手順という言葉で御理解いただけますかね。どうやって今から進めていかれるつもりか教えていただけませんか。
○大久保哲志教育長 この件については、先ほど答弁で申したとおりでございますが、今後はさらに企画政策課、財政課等から幅広い意見を聴取すると申したとおりでございます。
○15番(宮田幸一議員) 私に言わせれば、そういう問題ではなくて、幼稚園だから教育委員会の所管になるんですよね。これが保育園だったら所管が違ってくるんです。だから、私は教育委員会の教育長にお尋ねしているわけですので、その辺を。どこかと語るではなくて、まず保護者とかそういう方とも。それから幼稚園関係者、そことも協議は必要だと思うんですが、そういう手順は全く踏まれないで、行政一本やりでやっていかれるつもりですか。
○大久保哲志教育長 今、問うと申したように、どういったところから幅広い意見を聴取するかということも含めて検討することも対象に当たると考えておりますが、その前に一言申しておきますけれども、私はこの幼稚園の考え方というのは、学校教育の立場から考えますと、非常に大事だと考えております。
昨今、中1ギャップという言葉しばらくよく聞かれましたけれども、小学1年生においても、ギャップというか分かりませんけれども、学校になかなか適応できない児童が増えてきているという状況がございます。これは一つはいろいろなことが原因として考えられますけれども、やはり小学校1年生に上がるまでに、幼稚園の段階、つまり就学前の段階で今文部科学省のほうでは身につけさせたい10の姿ということで明確に述べてあるわけですけれども、そういったものがなかなか身につけられないままに入学してくると。そうすると、小学校1年生でなかなか適応できない状況が生まれると。ですから、そういったことを考えた上でも、幼稚園での教育というものは非常に大事だというふうには理解しています。
しかし、この幼稚園の10の姿を身につけさせるにも、ある一定程度は児童の確保ができないといけないという課題もありまして、したがって、この長寿命化計画で保育需要が高まって、特に市立幼稚園の園児数の著しい減少は非常に今後の運営に大きく関わるということが書かれているのだと理解しておりますので、そこのところは十分頭に入れて検討を進めていく必要があると考えております。
○15番(宮田幸一議員) 今回、私4問の質問をさせていただきました。どれに対しても適切な答弁を求めることができませんでした。私の勉強不足だと思います。次の議会のときには、しっかりと勉強して、ちゃんと明確な答弁をいただけるように頑張ってまいります。
以上で私の質問を終わります。
○椎木伸一市長 先ほどの医師会の絡みで、看護師の募集の調停に関するところで、私がまた誤解をいただきやすいところがありましたので、あえて答弁をさせていただきますが、最後に宮田議員のほうが示された、私は郡の医師会に出向いて謝罪をしたところの文言のところです。内容についてはおっしゃるとおり、あのように私も丁寧におわびを申し上げました。結果として、非常に申し訳ないことをしたということで、謝罪を申し上げました。
その際、私が理事会に行って謝罪をしますということを伝えたんですけれども、医師会のほうの都合で向こうから連絡がありまして、理事会に出れば多くの人がいるので、会長が一人で聞くということで、この時間に来てくださいということで1月12日の夜間に、指定された理事会のある前に会議室のほうに出向いて、私が整理した文面と合わせて、その文面に沿って謝罪を申し上げ、文面も差し上げ、録音もされました。
その後、理事会がある予定でしたので、私から皆さんによろしくお伝えくださいということを申し上げ、お願いをしたところでありまして、その御披瀝いただいた文章については、医師会長さんにお渡しをいたしました。その後、医師会長さんがコピーをされて渡されたか、録音も聞かされたか、その辺の結果は伺っていないところでありますけれども、私自身はその文書については医師会長さんに直接お渡ししたところでありますので、申し添えさせていただきます。
○議長(杉本尚喜議員) 次に橋口住眞議員の質問を許します。
○2番(橋口住眞議員) こんにちは。
本日、2人目の質問者となりました。よろしくお願いいたします。
鳥インフルエンザの被害に遭われました皆様に心からお見舞いを申し上げます。また、鳥インフルエンザ対応におきまして、関係職員の方々は2、3日、泊まり込みで対応され、関係団体の皆様もまた、昼夜たがわず消毒作業、鶏の処理作業に従事されてこられました。御尽力に心から感謝、申し上げます。
一般質問前の前語りが長くなりますが、寛大にお聞きいただければ幸いです。
私は、去る11月23日の不特定多数の方々が参加された集会において、お集まりの皆様に、「先に行われた衆議院議員選挙において市長は、一候補者の街宣車に乗ったり、応援演説をされました。その考えを問う一般質問をします。」と約束いたしました。しかし、そのことについて事務局・議長から「一般質問は市の一般事務に関することを質問するものでありなじまない」と指導があり、一般質問することがかないませんでした。ちなみに鹿児島県議会において、同様の質問が代表質問においてはなされているところであります。市長は3年半前、就任後、初めての定例会において「今回の市長選挙に臨み、私は、市民が納得できる透明性の高い、しがらみのない市政」を訴えてきた、と話され、また「私は、市政において最も大切なことは、市民の皆様の心をしっかりと受けとめ、その思いを酌み取ることである」と話されました。特定の候補者をあからさまに応援することが、全市民が納得できるしがらみのない市政といえるのか、また、全市民の心をしっかり受け止めることになるのか、市長の政治姿勢について答弁を頂きたいと思ったからであります。また、選挙後の国会議員への市の対応として、予定しておりました一般質問の主旨を踏まえ述べさせていただきます。
1点目は、国会議員は政治の根幹に位置する存在だということです。このことは憲法の前文において「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」と述べています。また、憲法43条第1項は賛成派も反対派も、すべての選挙区の人を含めた全国民を代表する議員であることを宣言しているものであります。このような根拠から、鳥インフルエンザなど災害等の一大事におきましては、代議士側から、アポ・連絡があるないにかかわらず、市当局の方から市民の暮らしを守るために積極的に情報を伝達していただきたいと思います。
2点目は、選挙は、代表者を確定する仕組みではありますが、むしろ、選挙が終わった後の、私たちと代表者との間の豊かなコミュニケーションが代表制民主主義の質を決めるということです。これは憲法12条にのっとった考えです。このような根拠から、市の最大イベントといっても過言ではない産業祭等については、代議士が来られる来られないにかかわらず、案内状を出していただきたいと考えます。これからは、当選されたお2人の代議士に対する全市民が納得する公平な関係づくりを切にお願いするものであります。このことは私、個人の意見ではなく、日本国憲法にのっとったものであり、憲法を尊重する行為であります。
以上、議員として約束が果たせなかったことの説明責任として、そして地域のよりよい発展を願って今回の一般質問の冒頭に話をさせていただきました。
それでは、通告に従い、一般質問をいたします。今回は、大項目3つ。
大項目1「新型コロナ感染症対策の検証と今後の取組」について、大項目2「困難を抱える児童・生徒への支援」について、大項目3「職員の働く環境について」伺います。
まず、大項目1、新型コロナ感染症対策の検証と今後の取組についてですが、新型コロナウイルスが中国の武漢で発生して2年ほどになります。感染拡大の5波が収まりかけた現在ではありますが、一方で、新たな変異株「オミクロン株」が出現しており6波が懸念されております。今こそ、この6波に備え、準備しておくことが大切であると思います。
1点目は今までの感染症対策について、どのように検証しておられるか伺います。
2点目は検証を踏まえ、再び感染拡大が起きないために、また感染拡大が起きた場合に備え今後どのように取組をしていかれるか伺います。
次に大項目2、困難を抱える児童・生徒への支援についてですが、11月27日に開催されました読書活動日本一のまちづくり推進大会に参加させていただきました。講師の絵本作家、くすのきしげのり先生の講話のなかで、「子供の環境は大人が作る」とおっしゃった言葉が印象的でした。「子供の環境は大人が作る」間違いなく未来を作るのは、今の子供たちです。その子供たちの環境を整えるのは大人の責任であります。安心サポートセンターについては以前質問させていただきました。今回は子供たちが一番生活する時間が長いと思われる学校を管轄する教育委員会に関わることについて質問させていただきます。
1点目は、子供の貧困と教育格差について教育長の見解を伺います。
2点目は、鹿児島県内の不登校児童・生徒が増加しております。2020年度、前年度に比べて286人増の2,989人で2年連続最多を更新しております。県教育委員会は「新型コロナウイルス感染症拡大の影響」と分析しました。出水市の現状についてどのように分析されているか伺います。
3点目は、困難を抱える児童・生徒の置かれている環境の現状把握は大切です。教育委員会と福祉課、健康増進課等との連携の必要性について、どのようにお考えか伺います。
4点目は、現在、教育委員会と福祉課、健康増進課等とは、細やかに連携ができているか伺います。
大項目3、職員の働く環境についてですが、市民の皆様への持続的な質の高い公共サービスのためには、職員の働きやすい職場環境は不可欠です。
1点目は、病気休暇・休職者等において、心の病気と心の病気以外の人数、それぞれの方の病気休暇日数について伺います。2019年度、2020年度、2021年10月末現在の数字を教えてください。
2点目は、病気休暇・休職中の職員へのフォローは、行われているか伺います。
私事ですが、私自身も病気休暇を取り、それでは足りず、休職を丸2年取りました。このように長期間、休暇は取ったのは市役所始まって以来、私が初めてとのことでありました。私の場合は身体の病気でありましたが、休んでいる身としては、職場に迷惑をかけて申し訳ない、という思いでいっぱいでした。退職した方がいいのではないか、と思い悩む毎日でした。そんな中、復帰できましたのは、職場の同僚の皆様、先輩の皆様の温かい励ましがあったからであります。胸の内を先輩に話しますと、「気にしなくていいのよ。ゆっくり静養しなさい。あなたが元気になった時、今度は、あなたが職場で困っている人を助けてあげればいいの。」と励げまされました。否定し続けてきた自分の存在を肯定的に捉えることができた瞬間でありました。しかしながら職場からの連絡は、30年以上前の話ではありますが「提出してもらう書類があります」とか事務的なものでありました。連絡を受けることは大変苦痛であり、提出物はすべて配偶者が行ってくれておりました。休んでいる間、市役所は私にとって、怖い、恐ろしい、寄り付きたくないところでありました。
資料請求し取り寄せた安全衛生委員会会議録(2021年7月26日)によりますと、「今後とも休職中の職員や復帰した職員と定期的に連絡を取りながら様子を見ていきたい。」と担当事務局は発言されておられます。取組状況について伺います。
3点目は、振替休日取得率と対応について伺います。2019年度、2020年度、2021年10月末現在の数字を教えてください。
職員(病院職員を除く)は、2006年度と2020年度を比較すると、115人少ない現状であります。平常時においても、時間外が減らない中、新型コロナ、鳥インフルエンザ等、特殊要因により業務も増え続けております。休むことなく働き続けることは心身の健康に大きな悪影響があります。資料請求し、取り寄せた2021年8月11日の時間外縮減対策委員会会議録によると、振替休日について「部課長の責任において、職員に必ず取得させること」とあります。お考えを伺います。
4点目はパワハラの現状と対応について伺います。
先の安全衛生委員会会議録において、「こころ機構が行った職員へのメンタルヘルスアンケートによるとパワーハラスメントについて4%の職員、22人が悩んでいる。全てがパワハラにあたるわけではなく、何がパワハラで何がそうでないのかを周知していこうと思っている」との記載がありました。お考えを伺います。
以上、壇上からの質問を終わります。
○椎木伸一市長 橋口住眞議員の御質問にお答えします。
新型コロナウイルス感染症対策の検証についてでありますが、市内では新規感染者が確認されない日が続いていますが、第6波も懸念され、国内では、いまだ収束していない状況にあります。
本市においては、4件のクラスターが発生しましたが、保健所に保健師を派遣するなどして県と連携し、感染拡大を防ぎました。
これまで、73回の新型インフルエンザ等対策本部会議を開催し、正確な情報の共有を図りながら、適宜適切な対応を協議してまいりました。
本市独自の主な対策といたしましては、高齢者施設等に在宅から新規に入所する方へのPCR検査の実施、2つ目が、公共施設の利用制限、そして3つ目に、出水駅構内での検温作業、4つ目に、福祉施設や学校等への感染予防用品やモニター付き体温計の配布、5点目が、自宅待機する濃厚接触者への食料品等を支給する生活支援、6番目が、感染防止対策に必要な店舗改装への補助など、様々な対策を実施してまいりました。
次に、再び感染拡大が起きないための取組についてでありますが、これまでと同様の対策をとりながら、市民の皆様には、引き続き基本的な感染予防対策をお願いするとともに、3回目のワクチン接種を遅滞なく進めていくことが重要であると考えております。
今後とも、市民の皆様には、同報無線、ホームページ、LINEなどを活用して、感染者の発生状況等を含め、正確な情報を提供してまいります。
次に、職員の働く環境についてお答えします。
病気休暇・休職者数については、後ほど政策経営部長に答弁をさせます。
次に、病気休暇・休職中の職員へのフォローについて申し上げます。当該職員がこころ機構の面談を希望する場合、直接連絡をこころ機構と取って秘密保持のうえ気兼ねなく面談できる体制を取っております。総務課においても、担当職員が当該職員の体調等を見ながら定期的に面談や必要な支援を行っております。
また、病気休職中の職員が復職する際は、出水市職員の復職支援制度の実施に関する要綱に基づき、まず職員の意向を聞き、職場や勤務時間を設定して行う試し出勤制度による支援を行い、復職後においても、当該職員に対して声かけや面談を行うなど、フォローを行っているところです。
次に、振替休日取得率とその対応についてでありますが、まず2019年度末の振替休日取得率は、40.61%であり、2020年度も同程度の取得率となっております。また、本年10月末現在の取得率は、63.86%であります。
振替休日の取得については、本年8月に開催した時間外縮減等対策委員会において、各所属長に対して振替状況一覧表を配布し、職員の健康保持の観点から現在取得できていない分について、必ず取得させるよう指示したところであります。
その後、豪雨災害や鳥インフルエンザなどの特殊要因や、時期的に繁忙期を迎えるなど取得が難しい職場もありますが、引き続き取得推進を図ってまいります。
次に、パワハラの現状と対応についてであります。こころ機構が実施したアンケートに対し、パワーハラスメントで悩んでいると回答した22名に対して、こころ機構が個別に面談等実施しています。その結果報告によりますと、全てがパワハラにあたるわけではなく、必要な指導や注意の範囲内であるケースもあり、パワハラの定義や明るい職場づくりについて、個別にアドバイスしたとのことです。全体的な対応としては、研修等を通じ、今後においてもハラスメントに対する理解を進めるとの報告を受けております。
また、市主催の研修においても、本年2月に管理・監督職を対象に、11月には一般職を対象に、外部講師によるハラスメント研修を実施し、その中でパワーハラスメントの定義や具体的事例等について紹介するなど、ハラスメントに対する正確な理解の定着に努めているところであります。
今後におきましても、これらの取組を継続し、パワーハラスメントの防止と明るい職場づくりに取り組んでまいります。
○大久保哲志教育長 橋口住眞議員の御質問にお答えします。
まず、子供の貧困と教育格差についてですが、教育格差とは、子供の生まれ育った国や地域、環境等によって受けられる教育に格差が生じることだと捉えており、我が国の教育制度は、教育の機会均等を実現しながら高い教育水準の維持・向上を目指して様々な制度を整備してきたと考えております。
私は、経済的・社会的な事情にかかわらず、誰に対しても能力に応じて等しく教育を受ける機会が確保され、すべての子供が前向きな気持ちで夢や希望の実現を目指すことのできる社会をつくっていくことが重要だと考えております。
しかしながら、近年、経済的理由や家庭の事情等で満足な教育を受けられないという問題がクローズアップされたことは認識しています。
このような状況を踏まえ、教育委員会としては、経済的に支援が必要な世帯に対しては、就学援助制度や鶴の恩返し奨学金の貸与などを実施しており、現在行っている制度がより有効に活用されるよう、さらに周知を図っていきたいと考えています。
次に、出水市内の不登校児童・生徒の現状についてですが、令和2年度に不登校を理由として30日以上欠席した児童生徒は、令和元年度と比較しますと、やや増加しています。また、本年度、現時点では、昨年度同時期と比較して同数程度です。
このうち、明確に新型コロナウイルス感染拡大の影響によるものと判断できる児童生徒はおりません。
不登校の理由は、個々の児童生徒により様々であり、学校生活、家庭環境等、本人に係る状況が複雑に絡み合ったものであると考えられることから、新型コロナウイルス感染拡大の影響も含め、幅広く事態を捉え、個々の状況に応じ、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門家や関係機関等とも連携しながら、個々の児童生徒が抱える困難に寄り添い、不登校解消に向けて取り組んでまいります。
次に、関係機関等との連携の必要性についてですが、児童生徒の抱える問題は、非常に多様化、複雑化しており、学校だけでは解決することが難しい状況になってきています。現在も専門家や警察、児童相談所などの関係機関、民生委員・児童委員等の地域の方々などと連携を図って解決に向けて取り組んでおり、今後とも、幅広く連携する必要性があると考えます。
次に、福祉課、健康増進課等との細やかな連携についてですが、これまでも、生活保護や障害を持つ児童生徒の状況等については福祉課と、子供の発達の状況や子育ての状況については健康増進課と、個々に情報共有・連携を図ってきました。
市安心サポートセンターが設立されたことにより、様々な困難を抱える幼児、児童生徒やその家庭の情報が一元化され、より多くの関係機関や関係者が情報を共有し、解決に向けて、チームとして継続的に取り組む体制が整いつつあると考えています。
さらには、個別の事案に対して、必要な関係者が集結し、具体的な解決策を検討・実行するためのケース検討会議も定期的に開催されるようになったことで、より細やかでスピーディーな対策が図られるようになっています。
今後も、困難を抱える幼児、児童生徒の課題解決に向け、多くの関係者と密に連携を図り、協力・協働した取組を推進してまいります。
○冨田忍政策経営部長 病気休暇・休職者数について延べ人数でお答えいたします。
2019年度は、心の病気による職員が8人、心の病気以外が15人です。
病気休暇日数について申し上げます。10日以上30日までは、心の病気による職員が1人、心の病気以外が9人、31日以上90日までについては、心の病気による職員が4人、心の病気以外が6人です。
91日以上になります病気休職者は、心の病気による職員3人のみです。
2020年度は、心の病気による職員が10人、心の病気以外が21人です。
病気休暇日数について申し上げますと、10日以上30日までは、心の病気による職員が1人、心の病気以外が13人、31日以上90日までは、心の病気による職員が6人、心の病気以外が8人です。
91日以上の病気休職者は、心の病気による職員3人のみです。
2021年10月末現在の延べ人数で申し上げますと、心の病気による職員が11人、心の病気以外が10人です。
病気休暇日数について、10日以上30日までは、心の病気による職員が1人、心の病気以外が5人です。
31日以上90日までは、心の病気による職員が3人、心の病気以外が2人です。
91日以上の病気休職者については、心の病気による職員が7人、心の病気以外が3人です。
なお、12月1日現在で申し上げます。心の病気による病気休暇者は1人、病気休職者が5人であり、心の病気以外の病気休暇者が2人、病気休職者が2人となっております。
○2番(橋口住眞議員) 大変、御丁寧な回答をいただきました。
それでは、大項目の順番を入れ替えまして、大項目3、職員の働く環境についてを先に一問一答させていただきまして、次に大項目1、大項目2とさせていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
大項目1、職員の働く環境についてですが、大変お忙しい中、2度3度、担当課には資料請求をいたしましたが、対応いただきましたことに心から感謝を申し上げます。ありがとうございます。
今回は心の病気について、質問をさせていただきます。12月1日の数字をいただきました。それまで令和元年8人、令和2年10人、令和3年11人、ここにおいては減らない、むしろ増えてきている状況だということで理解してよろしいのでしょうか。確認をさせてください。
○冨田忍政策経営部長 人数については、先ほど申し上げた数字が正確なところでございまして、直近の今現在の数字も申し上げたところです。1日現在では、心の病気による休暇者が1人、休職者が5人という状況になっております。年度内においても、いろんな総務課のほうのフォローアップ等の支援もございますので、若干、直近では減っているかと思っております。
○2番(橋口住眞議員) では、この中で、再度復帰をされたけれども、再び休職をとられたという方が、令和元年から令和3年までに何人おられたのか教えてください。
○山元周作総務課長 お答えします。令和元年に病気休暇になった職員で、再度令和2年、令和3年で再発した職員については3名(93ページ、発言訂正あり)です。
○2番(橋口住眞議員) 心の病気の方々が減らない、こういう8、10、11そしてまた12月1日現在については今のところはゼロ、休職中が何人かいらっしゃるということでしたが、なかなかなくならない状況だということで危惧しております。
優秀な職員が誠実に一生懸命時間外をこなし、市民のために一途に働いているうちに心の病気になってしまわれる。人は宝、職員は財産であります。市民にとりましても、大変な損失であります。市長は心の病気の原因をどのようにお考えか、お伺いをいたします。
○冨田忍政策経営部長 所管の者としては、人それぞれ、いろいろあろうかと思います。現在のところ、家庭的な事情であったり人間関係に悩んでいるというようなものが多い傾向かなとは思っております。
○2番(橋口住眞議員) 厚生労働省が平成27年11月30日に発行した労働者の心の健康の保持増進の指針において、「メンタルヘルスケアの基本的な考え方として、労働者の健康は職場配置・人事異動・職場の組織等の人事労務管理と密接に関係する要因によって、大きな影響を受ける」と書いてございます。この労働者の心の健康保持増進のための指針、これは、総務課の皆さんも指針にされながら仕事をされていることだと思いますけれども、安全衛生法第69条事業者は労働者に対する健康教育及び健康相談、その他、労働者の健康の保持増進を図るための必要な措置、継続的かつ計画的に講ずるための指針ということになっております。法に基づく指針ですので、非常に大きな方向性を示すものの一つだと思っております。その中に記載されてあるこの「大きな影響」、影響と原因は違うと思いますけれども、しかしながら大きな影響を与えるのが、先ほど申し上げた項目でございます。つまり、労働者自身の力だけで取り除くことができないものであるからこそ、職場環境の改善が必要だとうたっているものです。
心の病気がゼロにならない、こういったことにおいては、このような改善の取組がさらに必要なことを示しているのではないかと考えますが、市長、お考えはいかがでしょうか。
○冨田忍政策経営部長 そのようなことだと思います。そのようなことでございますので、所管課においても、そういう取組をしてきているところでございます。
○2番(橋口住眞議員) その取組の具体的な内容について、お伺いをさせていただきますけれども、この指針の中で、心の健康については客観的な測定方法が十分確定しておらず、その評価については労働者本人から心身の状況に関する情報を取得する必要があると記載されております。
例えば、今まで心の病気で休暇をとられた方に対し、実際、先ほど教育長が「困難に寄り添う」という言葉をおっしゃいましたけれども、今まで心の病気休暇を取得された方々に対して、困難に寄り添う情報取得等を行ってこられたのか、お伺いをいたします。
○冨田忍政策経営部長 先ほど市長も申し上げましたとおり、直接、こころ機構のほうと面談をできる仕組みをつくり、秘密を保持した上で、いろいろな相談事に乗ってもらったり、復職に向けたアドバイスをいただいたりと、そういう制度的なものもつくっておりますし、総務課の中には担当職員もおりまして、復職に向けていろんな職員さんの希望を聞いたり、今度は人事配置、先ほど試し出勤の話を市長がしましたけれども、それも総務課だけでできるわけではなくて、受入れをしてくれる新しい職場の管理職であったり、同僚であったり、いわゆる市役所の職員が受け入れるに当たって、より過ごしやすい場をできるだけ作ってあげようと、そういった取組もやっておりまして、総務課の担当職員は連絡を受ければ、時間外であっても、直接昼間の業務のときに人が多い時ではない時間帯も含めて、懇切に対応していると私は思っております。そういうことが、少しずつ心の病気を減らしていければいいかなと思って、そういう思いで我々職員は取り組んでいるところでございます。
○2番(橋口住眞議員) 十分に行ってきたという答弁でございます。頭をひねっておられますけれども、そういう理解でよろしいですか。
○冨田忍政策経営部長 十分やってきたと誇って言えるためには、ゼロであるべきだろうと私自身は考えておりますので、ただ、一生懸命できる部分については努めてきたと申し上げております。
○2番(橋口住眞議員) そのこころ機構の方が実際に病休に入っていらっしゃる方とやり取りをされた。やり取りをしてこられたということなんですけれども、では職場の方々とは、例えばどういう状況なのかということについては、全くその辺はプライバシーということで職場の人は御存じないという理解でよろしいんでしょうか。
○冨田忍政策経営部長 先ほど申し上げましたとおり、所管課として総務課のほうで把握した情報につきましては、それぞれの所管課、あるいは試し出勤をする場合の職場の者等に伝えて、どうやったら支援をしていけるかというようなことをプライバシーに触らない範囲で情報共有をして、受入れのための体制を取っておりまして、こういうことは制度的なものができる前からのことではないかなと私は思っております。
先ほど議員も、救われたという場面があったというお話でしたが、そのときも多分私の考えでは、同じようなことで職場の皆さんがいろいろ話をされて、手助けをしようということで取り組まれたのではないかなと思っております。
○2番(橋口住眞議員) 本当に私が思いますのは、このステップを踏んだから、この方に対してはアポが取れている。そういうことではなくて、本当に困難に寄り添う、そういった体制、そういった気持ちが必要なんじゃないかなということで、再度くどい形になりましたがお聞きしたところでした。
というのが、そういった中にこそ貴重な予防策、次への一歩が含まれていると私は考えるからです。今のお話では、病休の方々と連絡は取っている。いろいろな形でプライバシーに気をつけながら行っているということでしたが、その連絡を取っていらっしゃる方は専門性の高い方なのか、普通の事務の方なのか、その辺は配慮があった上で非常に専門性の高い分野でもあるかと思うんですが、連絡を取っていらっしゃって、情報共有の元となられる方は専門性の高い方が誰かいらっしゃるのか教えてください。
○議長(杉本尚喜議員) ここで暫時休憩いたします。再開を午後2時15分といたします。
午後2時00分 休 憩
午後2時15分 再 開
○議長(杉本尚喜議員) 再開いたします。休憩前に引き続き、会議を続行し橋口住眞議員の質問に対する当局の答弁を求めます。
○冨田忍政策経営部長 専門家はいるかというお尋ねだったと思います。これについては、臨床心理士とかそういう専門職は職員の中におりませんので、総務課のほうで委託契約でこころ機構という専門機関にお願いをしていることは、もう橋口議員も御存じのとおりでございます。そういう専門機関の専門資格を持った方と秘密を保持した上で、気兼ねなく相談できる体制をとっておりますと、冒頭でもお答えしたとおりでございます。
市には専門家がおりませんので、そういう体制をとっております。これもう数年以上前からのことでございます。
○2番(橋口住眞議員) 私には、どうしても見えてこないんです。どうしても、病気で休職されている方がこころ機構とやり取りをして、十分、自分の困難に対して前向きに取り組んでいっていらっしゃるというその状況が、私にはなかなか、いろいろな情報が入ってくる中において見えてこないんです。
しかし、当局はそのようにこころ機構を通じていろいろやっていらっしゃるということ、これは水掛け論になりますのでこの辺でやめようと思いますが、再度お尋ねいたしますが、この原因究明についてはこころ機構だけでなく、真摯に向き合っていただいて何が原因でこの方たちが休みに入らざるを得なかったのか、そこは原因究明、いろいろ複層的で重層的だというのは分かりますけれども、これだけ影響があるのが業務内容、いろいろ出ておりますので、その辺はお願いをしたいと思います。
それから、復帰にあたっては短期就労とかありますけれども、復帰にあたっての再度なんですが、就業上の配慮、具体的に先ほど短期、慣らしとかいろいろおっしゃいましたが、ほかにどういうことを配慮しておられるのかお伺いをいたします。
○冨田忍政策経営部長 誤解のないように申し上げておきますが、市長答弁にもありましたとおり、こころ機構のほうに丸投げをしているわけではございませんで、総務課の中にも担当職員がおります。担当職員が責任を持って、いろんな形で接触をもって状況をお聞きしたり、悩みごとの相談に乗ったりしています。
復職にあたっての制度について申し上げます。まず、総務課のほうで対象の職員の意向を聞いて、面談の時間やら復帰、試し出勤する場合にはどういう職場か、何時から何時まで短時間でいいのか、あるいは1日勤務ができるのか、そういったことをこと細かに相談を受け意向を確認した上で、その当時、休職するときにいた職場ではなく、違う職場であってもここならどうだろうかという提案をして、そこの受入先の管理職も含め、周りの職員にもフォローのお願いをするなど、復職の支援に向けて我々総務課としても、できる手だてはきちんと講じていると思っております。
ゼロにならないのは、まだ足りないということをおっしゃりたいのかもしれませんけど、我々としては懸命にやっているところで、そういう制度に基づいてそういう対応をしているところでございます。
○2番(橋口住眞議員) 一生懸命取り組んでいらっしゃるということ、取り組み方としてはそのように制度にのっとってやっていらっしゃる。こころ機構に丸投げしてというふうに、私も思ってはおりませんが、現状がなかなか今当局の答弁と違うということだけは認識をいただきたいと思います。
その上で、復帰支援についてですが、全ての労働者が心の問題を抱える可能性があるにもかかわらず、心の問題を抱える労働者に対して誤解や偏見等が生じないよう、研修を行っていただきたい。いかがでしょうか。
○山元周作総務課長 すみません。先ほど令和元年度病気休暇・休職者のうち、令和2年度、令和3年度に再び病気休暇・休職に入った職員は3人とお答えしましたけれども、申し訳ございません5人ということで訂正をしておわびいたします。
それから、研修について、そのような研修については毎年度こころ機構が行う研修と、我々が外部講師を招いて行う研修、それから職員を外に派遣をしまして受講させる研修、3種類を用意してそれぞれ研修をしているところです。
○2番(橋口住眞議員) さらなる深みのある研修、進んだ研修になることを希望いたします。
次に入れ替えまして、パワハラの現状と対応についてなんですけれども、パワハラの現状と対応、先ほど22人が全てパワハラにあたるわけではないということなんですが、じゃあ何人がパワハラにあたったのか、お答えいただけますでしょうか。
○冨田忍政策経営部長 ちょっと議員、聞き取れなかったのでお願いしていいですか。
○議長(杉本尚喜議員) 再度、お願いします。
○2番(橋口住眞議員) パワハラのメンタルヘルスのアンケートにおいて、4%の職員、22人が悩んでいる。全てがパワハラにあたるわけではないということなんですけれども、全てがパワハラにあたらないにしても、パワハラだという方が何人いらっしゃったのか。
○山元周作総務課長 まずパワハラの定義なんですけれども、パワハラに該当するというところでいくと、優越的な関係を背景とした言動やそういうものがあって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの。それから就業環境が害される。この3つ全てが満たされたときにパワハラとして該当しますが、この全てがあたらないという件数が結構あります。それが具体的に何件あって、パワハラが何件あって、パワハラでないのが何件あってというのを、具体的に数値としては報告を受けておりません。
○2番(橋口住眞議員) せっかく、パワハラの予兆として職員は一生懸命書いたと思うんですよ。悩んでいると。だけど、この3項目で当たらないからパワハラでない。じゃあ、この22名の方に対しての後の対応はどのようにされたのか。
さっき、面談を行って相談を受けられたということでしたけれども、その後、その方たちについてパワハラに対しての詳しい面接・その他が継続的に行われているのか教えてください。
○冨田忍政策経営部長 最初の答弁で市長がそこらあたりは申し上げたと思います。再度、私のほうからも申し上げます。
全てがパワハラにあたるわけではなくて、必要な部分もあったと。そこで、こころ機構としては相談アンケートを受けられた方に、パワハラや定義、あるいは明るい職場づくりについて個別にアドバイスをしたという報告を受けております。
それと、全体的な対応として、今後とも研修等を通じてハラスメントに対する理解を進める必要があるので、その旨、取り組みますという報告を受けております。
○2番(橋口住眞議員) では、お伺いをいたしますが、今現在、出水市役所において、パワハラ苦情委員会があると思うんですが、そこに申出があっている事例があるのか、ないのか教えてください。
○山元周作総務課長 パワーハラスメントの苦情処理委員会に申出のあった案件、今のところございません。
○2番(橋口住眞議員) こちらは、テレビ静岡11月19日の放送によるものですが、静岡県沼津市職員が複数の部下に大声で罵声を浴びせるなど、パワハラ行為を行い、減給6か月の懲戒処分となりました。処分を受けたのは、沼津市役所に勤務する50代の課長級職員です。沼津市役所によると、この職員は一昨年から約2年間、同じ部署の部下複数人に対して、無視をしたり、ミスに対する叱責の際、必要以上に部下の人格を否定するような暴言を吐くなど、パワハラ行為を繰り返していたというような事例が発生しておりますが、これと似たような事例を耳にするんですが、市長、御存じないでしょうか。
○冨田忍政策経営部長 先ほど総務課長が答えたとおりでございまして、その耳にする、耳にしない、ここで個別の案件をですね、こういう話があったとか、そういうことは私がここで答弁するものではないかと思います。
きちんと制度にのっとって、そういう申立てがあれば、きちんと対応していくということになっておりますので、そういう対応はいたしてまいります。
○2番(橋口住眞議員) パワーハラスメントは、心身共に疲れる前に職場環境の改善を図ることは大変重要なことであり、令和2年4月1日、人事院事務総長発の文書によりますと、パワーハラスメントが職場で行われていないか。またはその恐れがないか。職場環境に十分な注意を払うこととあります。要するに、職場においてパワハラの恐れを事前に把握し、その対応を図らなければならない。心身が疲れてしまう前に、原因となる背景を調べる必要があるということが書かれているんですが、今、全く総務課にも苦情、パワハラの事案が上ってきていないということであります。申立ても上がってきていない。
私は個別の事案で、ある意味犯人捜しをするわけではないです。それを通じて、より良い職場にするにはどうしたらいいのかということを、当局の皆さんにお考えいただくために、この事例を出させてもらって、突破口としてお話をさせてもらおうと思っているのですが、全く事案が生じていない。市長、大声で怒鳴る、そういった事案を市民から聞いていらっしゃるのではないですか。お聞かせください。
○冨田忍政策経営部長 いろんな形で職員の皆さんからは、総務課のほうにいろんな相談がございます。一つ一つを捉えてパワハラなのかどうなのかというところまで、御本人等の希望もございますので、そこについてはプライバシーに配慮した上で総務課のほうで対応をしております。
先ほど、橋口議員が「早めに芽を摘まなければいけない」というような趣旨のことを申し上げました。だからこそ、管理監督職の職員に研修をしたり、職場でのそういう異常がないかどうかを察知するためのパワハラに関する研修も、管理監督者、課長級管理職に対してもしておりますし、いち早くそういう事象をつかまえるために、パワハラとは何ぞや、ほかのハラスメントも含めてですけれども、そういうことを正確に理解するような研修も実施をしておりますということを、先ほども申し上げたとおりでございまして、何か事が起こってから動くんですよというようなことではございませんで、早く見つけて、対応していくというようなことでも、研修等を通じて職員に徹底を図っているところでございます。
○2番(橋口住眞議員) これは市長にお伺いしたいんです。市長にお伺いします。
市長は市民からこういった大声で長時間、職員を怒鳴る。そういうことが行われているよということを聞かれたことはないですか。
○椎木伸一市長 はい、全くございません。
○2番(橋口住眞議員) 市長は3年半前に議員をパワハラで訴えられ、厳正な動きをしてくださいました。その方向性は私も全く異存のないところでございます。
しかし、今度は職員の中で行われていることに対して、そういうふうな答弁をされるというのは、働きやすい職場、クリーンな職場にはなっていかない。実際の事例を挙げることは、私、非常にはばかられましたので、あえて市長にお伺いをしたところであります。実際に録音も聞きました。
○議長(杉本尚喜議員) 橋口議員、ちょっと発言中、申し訳ないのですが、ちょっと時間を止めてください。今、発言されている内容をお聞きすれば、そういう事実があったということを自分で確認した上での発言だろうと思うのですが、その辺の内容をもうちょっと具体的に言われないと、当局の答弁も難しいんじゃないかと思います。
○2番(橋口住眞議員) では、私は非常に個別の案件でありますし、プライバシーに関することでもありますし、さっき部長がおっしゃってくださった個人攻撃に終始することがよいことなのか、最終的に私の働きやすい職場には行きつかない気がしたので申し上げなかったんですけれども。
では、指示でありますので申し上げさせていただきます。野田支所において、支所職員全員の前で、しかも来庁者の市民のいる前で、大声で特定の職員を叱責する。期日前投票所初日は、期日前の会場にも漏れる大声で特定の職員を長時間叱責し、投票所の従事者も驚かれる。ある日は、職員全員の前で、複数の職員の名前を大声で呼び、呼び捨てで絶叫される。ある日は、職員の頭をたたいた。これは、私、事実確認はしておりませんが、当事者から聞いた話ですが、職員の頭をたたいたと聞いております。録音も取ってございます。こういった事実があるにも関わらず、これは申出が総務課には行っているはずなんです。行って、職員係も受理してあるはずなんです。なのに、全くそういう事実はない、パワハラはない、その辺の整合性について教えていただけますか。
○山元周作総務課長 相談としてはありますけれども、そのパワハラの申出書ということでは届いておりません。ただ、いろんな相談がある中でそういった案件もありまして、調査をいたしております。
○2番(橋口住眞議員) 暴力まで出た事件なんですよ。とても急ぐ事件です。周りの職員もストレスで仕事ができない状況にある中にあって、そういった申出を聞いたけれども、それは正式な申出でないとか、そういう悠長なことを言っている場合ではないと思います。すぐに調査をかける、これ以上、被害が広がらないために行っていただきたいと思いますが、早急な対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○山元周作総務課長 職員から申出があったその日に、既にそれぞれヒアリングを行っております。今、改善がなされているところであると私は考えております。
○2番(橋口住眞議員) 問いかけが悪かったんでしょうか。先ほどの答弁では、パワハラは行われていなかった、そういったものは上がってきていないというお答えであった。で、今お聞きすると、上ってきて職員に事情を聴いた。では事情を聴いた後の流れとしては、どういうふうになるのでしょうか。苦情処理委員会で取扱いをされる形になるんですかね。
○山元周作総務課長 苦情処理委員会に申出書として申出がありますと、我々はその申出者に対してヒアリングを行って、いろいろ経由して聞き取りを行わないといけませんので、その本人が直接申し出ていただければ、その日に解決ができますので、申出書という形ではなくて、すぐ相談を受けて、その日のうちに私は対応させていただきました。次の日に、別の職員からも、いろんな職員から聞き取りを行わないといけませんので、周りの職員からもヒアリングをさせていただきましたし、相手方からもヒアリングをさせていただいております。計4人の職員からヒアリングをさせていただきまして、必要な対応は取って、今改善がなされているところだと思っております。
○2番(橋口住眞議員) 改善がなされているという判断は誰がされた。私はパワハラ根絶のためには、継続的な組織的な取組は欠かせないと思います。せっかく、ハラスメント苦情処理委員会がありますので、そこで審議いただいて、そして懲戒処分等ですね。しっかり基準を作っていただいて、二度と再発が起きないような取組をしていただきたい。いかがでしょうか。
○冨田忍政策経営部長 先ほども私のほうから申し上げましたけれども、総務課長が申し上げているのは、苦情委員会に対する申出はないけれども、そういう予兆があったので、総務課のほうできちんと対応して、いろいろお話を聞いてきたということで、もし苦情委員会のほうに申出が出てまいりますれば、定められた手続に従って進めてまいります。
それと、予断を抱くようなことになるといけませんので、今、懲戒処分の話が出ましたけれども、それぞれからきちんとした事情聴取をした上で、双方の話をきちんと公的に聞いて、その後の判断になりますので、一方側の意見だけで懲戒だとか何だとかということにはなりませんので、そこは御理解をいただきたいと思います。
○2番(橋口住眞議員) もちろん、そのために組織的な取組をしてくださいと。聞き取りも、一方の聞き取り、一方の聞き取りですので、複数人を交えての事実確認をもって先に進めていただきたい。そして、ハラスメント苦情処理委員会の要綱を見ますと、はっきり基準がなかなか定められておりません。なので、早急なそういった定めを設けて、例えばこういった場合、暴力が出た場合にはこうだとか、というので、きちっと対応していっていただくという形が、私は非常に大切なことであり、職場の雰囲気を前に進めるのでは、明るい雰囲気になっていくのではないかなと思います。
それと、この件については本当に、今公務員のパワハラは非常に問題になります。組織の体質ということで、全国から問われる形になりますので、本当にそこのところですね、体質改善も含めて行っていただきたいと思います。
そして、市長はよく、職員挨拶は一番できる市役所づくりということで、私もそれは非常によいことだと思います。大きな声で挨拶する。本当に一日すがすがしい気持ちになる、その挨拶の取組はよいことだなと思うんですが、ちょっと気になるのが、役職付けの方において部下を呼び捨てにされる、名前を呼び捨てにされる方がいらっしゃる。そのこともささいなことですけれども、取りようによったらパワハラと取る人もいるかもしれない。さっき3つ項目を挙げられましたけれども、そういった明るい雰囲気づくり、挨拶推進をされるのであれば、やはりそういった身近なところから改めていただいて、ぜひ自分より下の者だから呼び捨てにしていいということでは決してないので、人権に関わる問題になります。12月4日から12月10日までは基本的人権週間でございます。私が取り上げさせていただいた病休の方、そしてまたパワハラ問題等々、人権に大きく関わる問題ですので、よろしく対処をいただきたいと思います。
それでは、教育委員会。教育長にお尋ねをいたします。連携が取れているということで、お答えをいただきました。就学援助の件数について推移等分かれば教えてください。
○溝口雄二教育部長 就学援助制度の直近3年間の対象者の人数でございます。平成30年度は小学校が656人、中学校が313人、令和元年度は小学校が687人、中学校は296人、令和2年度は小学校が661人、中学校が317人となっているところです。
○2番(橋口住眞議員) かなりいらっしゃるなということで、この就学援助、非常に助かっていらっしゃるのではないかなと思います。
その上で、ほかにも鶴の奨学金があったと思うんですが、その3年間の推移、件数を教えていただいてよろしいでしょうか。
○田口保教育総務課長 数字をちょっと手元に持っていないところですが、ここ2年ほど申込者も増えている状況にございまして、今年の申込者が22人あったところです。
○2番(橋口住眞議員) 御回答ありがとうございます。
この4月に先ほど来、コロナの件についてもですけれども、保護者にお金が渡る時期というのは、入学前に渡るのかどうなのか教えてください。
○溝口雄二教育部長 就学援助制度の入学準備金のことかと思います。準備金につきましては、入学前に支給されるものでございます。3月ごろの支給を予定しているところです。
○2番(橋口住眞議員) 教育委員会、いろいろ努力して進めておられる、連携を取っておられるということは答弁でよく理解したところなんですが、私が問題だと思っておりますのは、問題が起きていない、問題が出る前の、先ほどのパワハラもですけれども、小さな芽を摘むということが、ケース会議、問題が出てからその子たちを追っていくというのもですけれども、問題が出る前の小さな芽を摘むというためにも、先ほどの繰り返しになりますが、この点について福祉課との連携はどのような形で行っていらっしゃるのか。例えば、急に親御さんが病気になられて、子供さんが大変だとか、失業されて大変だとか、まだその子に問題は起こっていないんだけど、環境的に大きな変化が出たよとか、そういった問題が起こる前の何か教育委員会が察知される方法が。
というのは、学校の先生たちはなかなか難しいと思います。だから、教育委員会が福祉課、いろんなところと連携を取られやすいのではないかなと思うので、お答えができられたら。
○大久保哲志教育長 先ほど答弁の中で、安心サポートセンターの話をさせていただきましたけれども、通常子供たちの問題というのは、学校内の問題で非常に苦しんでいる場合と、それから今申されたように家庭の経済的状況であったり、あるいは家庭の状況で苦しんでいる児童生徒もいると思います。
学校の中での状況については、月ごとにアンケートを取ったりして、そのアンケートの中にささいな兆候が見えた場合には、すぐに教育相談を勧めたり、あるいは定期的な専門家が学校に来校したりという形で対応しているわけですけれども、今お話があったように、学校ではなかなか予兆さえもつかめないといいますか、そういったものがあるのはよく分かっておりますので、それについては先ほどちょっと言いました、安心サポートセンター等でそれぞれが持っている情報を共有することによって、例えば学校では知り得ない情報が、あるいはさっきおっしゃった福祉課とかあるいは健康増進課とか、そういったところから出たものを今度は学校で注意深く見守って支援ができないかとか、そういったことはやってきておりますので、今後もそれは続けていきたいと考えております。
○2番(橋口住眞議員) 大項目1について、コロナ対策についてなんですけれども、出水市におきましては、関係者の御尽力により感染力抑止に努められてこられましたことに感謝を申し上げます。
6波を起こさないためにワクチン接種も大変重要なんですが、再度、基本に立ち返り、感染対策がおろそかにならないように感染予防の基本的な対策の発信というのを、ワクチン接種状況の発信に加えて、こういった基本的な対策が大切ですよということを、2年もたつとなかなか皆さん気が緩みますので、その辺をホームページ、あとSNS、広報紙で行っていただきたいと思いますが、そういった取組はできないかお伺いをいたします。
○冨永栄二保健福祉部長 市長答弁にもありましたけれども、最後のほうに、市民の皆様には同報無線、ホームページ、LINEなどを活用して、感染状況も含めて正しい情報を正確にお伝えしていきたい。また、感染予防についても基本的な部分、いろいろ含めて広報をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○2番(橋口住眞議員) 本当にいろいろ行政当局の皆さん、頑張ってくださって、市民の生活を守ってくださっていることに感謝をいたします。本当に困っている人の立場に立って、さらなる聞き取り、寄り添いを切に切に切にお願いをして、今回の一般質問とさせていただきます。ありがとうございました。
○春田和彦商工観光部長 すみません、橋口議員が冒頭、前語りのところでお話された中に、産業祭に国会議員を2人とも招待してくださいという要望のようなお話がございました。あたかもお1人だけを呼んだかのような話に皆さんが誤解されると困るので申し上げたいと思いますけれども、これまで産業祭につきましては、国会議員の方、それから県議会議員の方も含めて、どちらも招待をしておりませんので、そこは御理解をいただきたいと思います。
○議長(杉本尚喜議員) 次に田上真由美議員の質問を許します。
○10番(田上真由美議員) 今回は大項目1、職員の職場環境について、2、ラムサール条約登録後の課題について、3、国道・県道の植栽帯について、4、「広報いずみ」について、5、「誰でも生きやすい社会」「生きにくさに目を背けない市政」について、通告に従い伺います。
まず、大項目1、職員の職場環境についてです。
コロナ禍において職員の皆様も通常業務に加え、多くの負担が生じていることと思います。このような状況下において、精神的に圧迫を受け休職に至るケースがあると伺いました。このことは、職場環境として望ましくないと考えます。そこで、伺います。
現在、91日以上、メンタル不調で休職中の職員は何名か伺います。
次に、信頼関係が構築され、安心感が得られた後でないと真の原因は把握されにくいとは思いますが、休職に至った真の原因を精査はされているのでしょうか。
次に、復職に関しては、休職中の当事者だけではなく、受け入れる側の職員も多くの配慮を求められるのではないかと考えます。その際に受け入れる側の職員の負担を軽減するために、どのような対策をとっておられるのか伺います。
次に、大項目2、ラムサール条約登録後の課題について伺います。
湿地の環境保全の観点から、ラムサール条約登録はすばらしいことだと考えます。しかし、今後、ラムサール条約登録したことでの弊害は生じないのか、確認をいたします。
(1)まず農業です。農家の皆様に御理解いただいてこそ、このラムサール条約登録が実現できたと思いますが、今後、農業を推奨するにあたり、農家の皆様が困ることは生じないのか伺います。
(2)次に観光です。市ではラムサール条約を機に、現在実施されている利用調整事業を通年化していきたい方針だと伺っています。利用調整事業は、ツルの新しい見せ方として、渡来地への出入りを一定程度規制されることと理解しています。
さらには、鳥インフルエンザは今後も警戒しなければならず、ツルに高病原性鳥インフルエンザが発生すれば、車両の消毒作業等のお願いもしていかなければなりません。
さらには、風評被害も心配されます。
これらの事柄を考慮した場合、今回の条約登録をきっかけとした観光への悪影響はないのか、伺います。
次に、大項目3、国道・県道の植栽帯について伺います。
出水市内の国道・県道の植栽帯は県の所管であり、この場で取り上げるには限界があることは承知しておりますが、このままでは鹿児島県の玄関口である出水市の景観が悲惨なことになりかねないので、今回議論すべきと判断いたしました。
これまで、市民の協力で県道・国道の植栽帯の美化が図られていたところもありますが、昨年に引き続き、今年も新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、毎年恒例となっている「市内一斉クリーン作戦」が中止となり、現在は景観を損ねているところも多々、見受けられます。
本来であれば、県が管理すべきではありますが、県の対応では追いつかないのが現実です。そもそも、県が行う剪定作業だけでは限界があり、表面を整える剪定作業ではカヤ等が根を張り、場所によってはカヤの丈が歩道を歩く子供の背丈を超すところもあります。そこで伺います。
(1)市内の県道・国道の植栽帯の現状の把握をする考えはないか伺います。
(2)地域の皆さんが県の道路で定期的に行う清掃・草刈・植栽帯の花植えなどの美化活動を、県が支援する「ふるさとの道サポート推進事業」があります。この事業の円滑な利用促進に向け、自治会や企業に積極的に出水市として周知等できないか伺います。
次に大項目4、「広報いずみ」について。
8月号から紙面が大きく変わり、とてもおしゃれな雰囲気で構成されています。
広報誌は、市民に事業等の周知を図る重要な媒体の一つです。そこで、(1)紙面のリニューアルの要因は何か、伺います。
(2)「広報いずみ」の発行に関して、行政はどこまで作成に関与するのか、伺います。
次に、大項目5、「誰でも生きやすい社会」「生きにくさに目を背けない市政」について。
社会生活を送るうえで、当事者として、もしくは家族や親しい人の中で、そのような「生きにくさ」を感じる場面に直面する可能性が、誰にでもあります。
例えば、①物の見方や考え方に特性がある発達障害、②何かしらの要因を抱える引きこもり、③鬱等の精神疾患など。
この「①発達障害」に関しては、特別支援学級の充実、またケアを行う担当教員の存在、それを効果的に生かすために、保育園・幼稚園などの子供の生活への目配り、当事者の親へのサポートと「親世代」の理解を高める努力、これらが、重要であると考えられます。
「②ひきこもり」に関しては、今、ありがたいことに、事業化されております。ただ。プライバシーを守れる形での相談窓口の設置が今後必要ではないかと考えます。
「③鬱等の精神疾患」に関しては、差別をすることなく、誰もがそのような状態になる可能性があることを理解できるような告知・周知の活動を広げていく。
このようなことが、課題として存在します。
そして、いずれにしても「特別な人」「おかしな人」という目で見ることがない社会、すなわち、自分事としても考えられ、個性の延長として捉えることのできる寛容な社会をつくりたい。
そのためには、多くの人にこれらの「生きにくさを感じる」事象についての認知を広げていく必要があります。
今回は、「誰でも生きやすい社会」を構築するために、物の見方や考え方に特性があることで支援を必要とする人に、行政がどのように、どこの時点で寄り添うことができるのか、議論を深めたいと考えます。
(1)未就学児が多く関わる保育園、こども園、幼稚園ですが、現状、療育を必要とする児童の増加に伴い、一人一人の特性と向き合おうとすればするほど、保育士や幼稚園教諭の負担が大きくなっています。そのことについてどのように捉えておられるのか、認識を問います。
(2)子育て応援券、産後ケア事業などの子育て環境の充実が図られていますが、そこから見えてくるのは、家族力の低下、シングル等母親の精神的なサポート等の課題が顕著になっています。私たちは誰でも精神的な基盤の弱さは有していますが、そのことが発症する引き金としては、「環境」が大きいと言われています。この環境を整えることは、心の基盤を整えることであり、小学校就学前に心の基盤を整えることで、その後の生きにくさの軽減が図れると考えます。
そこで重要な役割を果たすのが、保育園、こども園、幼稚園です。ここに、子供のサポート、親へのアドバイスを行う支援員の人的配置はできないか、伺います。
(3)令和4年度保育関係予算概算要求の概要の中に、「多様な保育の充実」があり、そこに「保育所等における要支援児童等対応推進事業」も掲載されています。これは、「保育所等において、保育士等が有する専門性を生かした保護者の状況に応じた相談支援などの業務を行う地域連携推進員の配置を促進し、保育所等における要支援児童等(要支援児童、要保護児童及びその保護者等)の対応や関係機関との連携の強化、運営の円滑化を図るものです。この「保育所等における要支援児童等対応推進事業」を活用する考えはないか、伺います。
(4)保育園・こども園・幼稚園では所管する省庁の違いがあり、システム上の相違がありますが、そこで伺います。文部科学省所管の教育委員会の附属幼稚園においては、スクールソーシャルワーカー等の活用はされているのか。活用されているならば、その効果を問います。また、活用されていなければ、その原因と、今後の見解について問います。
(5)支援員を出水市が雇用し、各園を巡回し個別計画等の作成がスムーズに行われることで、幼保との情報共有が図られれば、それを引き継ぐ小学校での学習はより実りのある、その子の特性を伸ばせるものになるのではないかと考えます。また、連携がスムーズになることで、教職員の負担軽減にもつながるのではないかと考えますが、見解を問います。
(6)何かしらの要因を抱え、ほっとハウスを選択する児童生徒がいます。そこでの支援を行うにあたって、ほっとハウスの職員の年齢構成と、どのような資格を有しておられるのかを問います。
(7)どの年代であっても、多くの困りごとが集約されるのが、安心サポートセンターです。正規職員は配置転換があることから、経験、知識が積み上がることが期待できるのは、専属の職員になってきます。安心サポートセンターの人材育成の計画はどのようになっているのか、また、窓口をプライバシーがもっと守れる場所へ移動する必要があるのではないかと思いますが、見解を問います。
以上で、壇上からの質問を終わります。
○椎木伸一市長 田上真由美議員の御質問にお答えします。
まず、心の病気を原因とした病気休職中の職員は、12月1日現在で5名おります。
次に、職員が病気休職に至った原因の精査については、病気休職職員に対してこころ機構に秘密保持のうえ、気兼ねなく相談できる環境を整備しており、総務課では、当該職員の体調等を見ながら定期的に面談を実施し、詳細な原因把握に努めております。
また、病気休職中の職員が復職する際は、出水市職員の復職支援制度の実施に関する要綱に基づき、試し出勤による復職支援を行っております。試し出勤を希望する職員と試し出勤する部署の所属長と、それぞれ当該職場の現状や受入れ体制などの聞き取りを十分行い、試し出勤先の職員にも理解を得て行うなどの対策をとっているところです。
また、令和4年1月には全職員を対象に、職員間のコミュニケーションや、ラインケア、休職中・職場復帰後のフォロー等を目的とした研修を実施予定としており、受入側の職員の負担軽減も含め、今後も各種対策を講じていき、心の病気の休職職員の早期復帰と再発防止に努めてまいります。
次に、観光への影響に関する御質問にお答えいたします。
本年11月18日出水ツルの越冬地がラムサール条約湿地に登録いただきました。
これは、地域の皆様が親子3代、60年にわたりツル保護活動に御尽力いただき、さらに登録地である湿地を大切に守り続けてこられた成果のたまものと改めて深く感謝を申し上げます。
ラムサール条約の登録は、水鳥の生息地として国際的に重要な湿地であることはもちろんのこと、私たち「ヒト」も含め、多様な生物が持続可能な形で生息できる湿地であることが必要であります。
この条約は、湿地の「保全・再生」と「賢明な利用」、これを促進する「交流・学習」の3つの柱で構成されていますが、本市では、独自に「越冬地利用調整」という4つ目の柱を設け、登録湿地の「保全・利活用計画」を策定中であります。
現在実施中の利用調整実証実験事業は、「ツルへの配慮」、「住民と来訪者の共生」、「鳥インフルエンザへの防疫体制の強化」の観点から、観光目的のお客様を中心に、入域制限と越冬地環境保全協力金をお願いしております。
また、ツルの朝の飛び立ちを御覧いただくためにツル観察センターの早朝開館、環境に優しい低速走行の電気自動車でエリア内を見学できるグリーンスローモビリティーレンタル事業、エコツーリズムガイドによるガイド付きバスツアー等も同時に実施し、新しいツルの見せ方についても提案しております。
これらは、ラムサール条約湿地登録を機に、ツル渡来期間中の通年開催を検討しており、本市のすばらしい環境の中で、ヒト、農業、養鶏業、ツルをはじめとする野鳥が共生できる社会を目指していきます。
私は、市長に就任以来、本市観光の2本柱である、「ツル観光」と「出水麓観光」について、観光地としての魅力をこれまで以上に引き出すには、新しい見せ方、新しい見てもらい方を提案することだと言い続けてまいりました。その結果として、「ツル観光」については先ほど述べたとおりですが、「出水麓観光」については、民間参入を促進することが不可欠であり、結果として地元住民の皆様の生活の利便性も向上するものと確信しております。
今後もこの観点で、関係者の皆様の御理解と御協力をいただきながら実施していきたいと考えています。
また、11月からの一連の鳥インフルエンザ発生による観光への風評被害については、今のところ大きな混乱は見受けられませんが、ツル観光の安全性はもちろん、出水産の鶏肉・鶏卵についてもその安全性に誤解が生じないよう、発生直後から、対策本部会議の場でも関係者にお願いしているほか、県や近隣自治体と連携した啓発広報等に努め、報道機関にも周知等を依頼しているところであります。
出水のすばらしい環境を守りながら、10年後も20年後も、観光業、農林水産業をはじめとする元気な産業が活躍するふるさとを、次世代の子供たちに引き継いでいくためにも、国連が提唱する「持続可能な開発目標」いわゆるSDGsの理念も踏まえながら、観光業に関わる各種事業へ積極果敢に挑戦していきたいと考えております。
ツル観光の現状については、後ほど商工観光部長に答弁をさせます。
次に、国道・県道の植栽帯についてお答えします。
市内の国道・県道の植栽帯から雑草が繁茂し、特にカヤ等は成長も早く、適正な管理が困難であることから、景観を損ねている状況となっています。
このことから、出水地区社会基盤整備推進協議会等の各種協議会を通じ、適正な維持管理に係る予算の確保や管理方法の検討等についての要望を毎年機会があるごとに行い、権限移譲についても協議を行っているところであります。
次に、「ふるさとの道サポート推進事業」は、県が管理している国道・県道で認定団体が定期的に行う清掃・草刈・植栽帯の花植えなどの美化活動を県が支援している事業で、年間上限3万円が支給されています。
現在、出水市内においては、19の認定団体が登録されているとのことですが、現状をみますと、まだまだ不足していると考えております。
このようなことから、認定団体が増えるよう市ではこれらのサポートを行いながら、広報いずみや市のホームページ等で周知を行ってまいります。
また、認定団体は、市の「出水市市道等の花いっぱいプロジェクト支援事業」の助成対象にもなることから、これと併せて事業推進を図っていきます。
今後も引き続き、道路の適正な維持管理を図り、地域環境の向上や共生協働による活力ある地域づくりに努めてまいります。
次に、広報いずみについてお答えします。
まず、紙面のリニューアルについてでありますが、8月号から表紙のレイアウトを変更しました。広報紙は記事の内容も含めて、常に見やすくなるよう改善を図っており、今回もその一環であります。今後も引き続き、市民の皆様に伝わる広報紙の作成に努めてまいります。
次に、広報いずみに対する市の関与についてですが、取材や記事の作成・レイアウト、印刷データ作成まで全て市の職員で行っており、印刷のみ外部発注をしております。
次に、「誰でも生きやすい社会」「生きにくさに目を背けない市政」についてお答えします。
まず、保育所等で療育を必要とする児童については、年々増加しておりまして、集団保育を行う中で保育士の負担は増えているものと認識しています。
また、子供のサポートや親へのアドバイスを行う支援員を配置することについては、保育所等からそのような意見は届いていないことから、まずは保育所等で抱えている問題・課題等を調査しまして、実状の把握に努めたいと考えます。
「保育所等における要支援児童等対応推進事業」の活用については、保育所等に対し、実施要望調査を行っていますが、現在のところ要望はなく、実施に至っていませんが、令和4年4月に安心サポートセンターに設置を予定している「子ども家庭総合支援拠点」の取組において、保育所等の関係機関との適切な情報共有、子供の発達段階や家庭状況等に応じた対応により、子供やその保護者に寄り添った支援を行っていきたいと考えております。
次に、安心サポートセンターの人材育成計画と設置場所について、お答えします。
まず、家庭相談員等の人材育成についてでありますが、子供や家庭の相談業務に携わる職員は、複雑多様化する相談に対応するため、専門的な基礎知識、アセスメント力に加え、コミュニケーション能力の習得が必要であり、日々の業務を通した更なるスキルアップも重要であると考えます。
そのようなことから、毎年、県主催の研修会を受講させ、専門的知識・技術の習得に努めるとともに、面接の場面では、先輩相談員が新任相談員に対して実践を通したOJT研修を実施するなど、計画的な人材育成に努めているところです。
なお、正規職員については、人事交流により児童相談所の勤務経験がある県職員をセンターに配置し、虐待対応の事務改善に努めるとともに、市職員も児童相談所に派遣するなど職員のスキルアップに取り組んでおります。
また、現在、福祉の専門職である社会福祉士を保健福祉部内に8人配置しており、これらの職員が各部署において経験を積み、配置転換していくことで、職員及び組織全体の専門性の向上、スキルの積み上げにつながるものと考えています。
次に、設置場所についてですが、同センターは、児童虐待、高齢者虐待、ひきこもり、生活困窮等の対応を一本化し、専門的・包括的な支援するとともに、保健福祉部の横断的な連携体制を構築・強化するために設置したものです。現在の相談対応については、電話相談をしていただき、他の職員と接することのないよう、必ず相談室で話を伺い、相談者のプライバシーに配慮した相談しやすい環境づくりに努めていることから、現在の場所でも支障がないものと考えております。今後も「来てよかった」と感じてもらえるよう、相談者の気持ちに寄り添った面接を心がけていきます。
私からは以上でございます。
大変失礼しました。答弁に漏れの部分がございました。
ラムサール条約登録後の課題についての御質問にお答えします。
まず、農業についてでありますが、ラムサール条約湿地登録に当たり、農業生産活動の制限はなく、これまでどおりの営農が継続できるところであります。
また、登録を機に農産物に付加価値を付けた販売を促進していくなどの新たな方策を検討しているところであり、地元農業者にも御理解をいただいているところであります。
大変失礼しました。
○大久保哲志教育長 田上真由美議員の御質問にお答えします。
まず、附属幼稚園における療育を必要とする園児の増加に伴う負担についてですが、療育を必要とする園児の割合は、ここ数年増加傾向にあるとともに、個々の程度も重くなってきていることから、職員の負担は増加していると認識しています。
次に、子供のサポート、親へのアドバイスを行う支援員の人的配置についてですが、附属幼稚園は、教育委員会が管轄しており、小学校の校長が園長も兼ねていることから、支援が必要な園児に対しては、小学校に所属している特別支援教育コーディネーターの教諭が状況を確認し、助言を行ったり、出水養護学校の教員に巡回相談を依頼したりするなどして対応しています。
さらには、心理面の課題が疑われる園児がいた場合には、教育委員会が委嘱している臨床心理士を活用して、心の安定を図ったり、医療機関につなげたりするなどして、解決に当たる体制が整っています。
また、子育てに課題のある保護者や育児に悩んでいる保護者に対しては、園長が直接、面談を行ったり、教育委員会が委嘱しているスクールソーシャルワーカーを活用して、悩みを和らげる継続的な面談の実施、場合によっては関係機関との橋渡しを行ったりしています。
また、スクールソーシャルワーカーは、小学校入学前の説明会等の場で、子育て講演会や相談会等も実施しており、保護者が相談しやすい体制づくりに努めています。
次に、個別計画等の作成によるスムーズな連携についてお答えします。
小学校及び中学校においては、支援が必要な児童生徒に対する個別の指導計画・支援計画の作成が義務付けられています。幼稚園については努力義務でありますが、本市の附属幼稚園においては100%作成することとしています。
このことによって、幼稚園と小学校の引継ぎが丁寧かつスムーズに行われているため、教職員の負担軽減にもつながっていると考えます。
さらには、小学校に入学する際に生じる不安や心配を軽減するために、小学校低学年と一緒に生活科の授業を体験したり、合同の行事を実施したりしていることから、園児と児童の交流及び幼稚園教諭と小学校教諭の連携が深まっていると考えます。
次に、ほっとハウスの職員の年齢構成と資格ですが、現在、ほっとハウスには、4人の会計年度任用職員を配置しております。年齢は60代から70代であり、全員、教員免許状を所持しています。そのうち3人は小・中学校の校長経験者です。
○春田和彦商工観光部長 ツル観光の現状について、お答えいたします。
今年度のツル越冬地利用調整実証実験事業の開催期間ですけれども、11月20日から12月19日までとなっております。これに加えまして現在、渡来地周辺に有人消毒ポイントを6か所設けて、鳥インフルエンザへの防疫体制の強化も図っているところです。
観光に来られたお客様等の風評被害による大きな混乱は現在のところ確認されておりません。
また、この利用調整事業の11月20日から12月5日までの16日間で、越冬地環境保全協力金への協力に対しまして、車両で107台(107ページ、発言訂正あり)、2,792人の方に協力いただいております。それからグリーンスローモビリティーレンタル事業利用台数は48台、ガイド付きバスツアー参加者は77人となっております。
また、この16日間のツル観察センターの入館者数は3,724人で、このうち早朝開館に限った展望台利用者数は、99人となっております。
なお、コロナ前の令和元年度の同時期が3,576人ですので、若干ではありますが増えているということでございます。
○議長(杉本尚喜議員) ここで暫時休憩いたします。再開を午後3時35分といたします。
午後3時18分 休 憩
午後3時35分 再 開
-------------------------------------------------------
△ 発言の訂正の申出
○議長(杉本尚喜議員) 再開いたします。休憩前に引き続き、会議を続行いたします。田上真由美議員の再質問の前に、2、3申出がございましたので、これを許可します。
まず1点目です。先ほど春田商工観光部長から答弁がございました。発言の訂正の申出がございましたので、これを許可してあります。
○春田和彦商工観光部長 申し訳ございません。先ほど利用調整事業の11月20日から12月5日の16日間で協力をいただいた車両台数を1,067台と申し上げないといけないところを、107台と申し上げたそうですので、訂正をしておわび申し上げます。
-------------------------------------------------------
△ 途中退席の申出
○議長(杉本尚喜議員) 次に、吉元勇議員から、本日の会議を途中退席する旨の届出がございました。
さらに、田上真由美議員から書画カメラの使用について申出がございましたので、これを許可してあります。
○10番(田上真由美議員) では、大項目1からまいります。
先ほど2番議員のほうからも同じような形でのこの職場環境につきましての質疑がありましたので、ちょっと重複する点もあろうかと思いますが、少し視点を変えて質問をさせていただきたいと思います。
職場の人間関係や健康問題や家庭のこと、介護や育児など、他人に気軽に相談できないことも私たちの中には多々ございます。しかし、せめて職場のこの人間関係だけは、早めに相談できる環境が必要ではないかと考えております。
まずは、精神的に追い込まれない人材育成ができる職場である必要があると考えますが、見解を問います。
○冨田忍政策経営部長 できるだけ予兆をつかまえて、早期対応をするという基本を我々も考えております。
総務課においても、担当職員がおりますので、心の相談だけではなく、総務課職員係のほうに、担当の職員のほうに時間外等に相談をしてくる職員もおりますので、まずはそこできちんと拾い上げて、それがきちんとその後のフォローアップ対応につながるような形で運営していきたいと考えております。
○10番(田上真由美議員) やはり、この心の不調に陥るということは、それまでの経緯の中でいろんなことがあろうかと想定がされます。その中で先ほど登壇しての質問もいたしましたが、その不調に陥るときの環境の職場の方々も大変気にされる点もあろうかと思います。何かしらの早めの事象が起こった場合には、それに適切に対応するというふうに言われましたが、その事象はやはりきちんと両方からの話を聞き取った上で、そしてその精査をしていただく必要があろうかと思いますが、その点につきましてはどのようにお考えかお聞きいたします。
○冨田忍政策経営部長 当然、そのように両方のほうから話を聞いて、解決の糸口をつかめればいいんですけれども、休職中に入っている職員に過度にそこの部分を一般の職員のように問いただすようなこともできないものですから、担当の職員のほうも苦慮しているようですけれども、その対人関係といいましても、職場でないものもあります。家庭内であったり、健康面に関するものであったり、地域の中での対人関係とかいろいろ種々ございますので、それらの要因に寄り添った対応ということで努めているところです。
○10番(田上真由美議員) おっしゃるとおり、踏み込めない部分というのも人それぞれ領域がありますので、そこに配慮しながらではありますが、せめてこの職場の人間関係は職場内で改善ができればなと思っております。
そして、業務過多です。これは人から優しさとかゆとりを奪ってしまいかねないということなんですね。私自身も子育てをしている中で、「忙しい、忙しい、忙しい、忙しい」と言いながら1日を過ごしておりましたが、娘から言われたのが「お母さん、忙しいという字はね、心亡くすって書くんだよ」と言われたときに、「あ、まずい、まずい」と思ったことがありました。この忙しさというのは、本当に人からゆとりを奪ってしまいかねないということがございます。業務過多がそのことにつながらなければいいなと考えるところでもございます。
公務員としてスキルを磨いていただき、能力アップに努めていただきたいですが、あまりにも負荷がかかりすぎていると、健全な人間関係を築き継続することができなくなるのではないかと考えます。精神的なゆとりのある環境を構築するために、今後、どのように取り組まれるのかお聞かせください。
○冨田忍政策経営部長 先の橋口議員の御質問でもお答えしておりますとおり、研修等をですね、そういう理解を進めるものももちろんそうなんですけれども、私が今の段階で、ここも要因かなと思うものは、職員に対する期待等もございまして、いろんな人事異動等を行います。そのことがかえってその職員の負担感を増していることがないのか、そういったところは人事異動、昇任昇格等においても十分配慮をした上でやっていければいいかなと思っております。
○10番(田上真由美議員) 人間誰でも認められるということが一番うれしい行為であります。お互いに年齢差を超えてでも、何かできたときには「ありがとう」という言葉を掛け合いながらですね。その中で、皆様が有効に仕事ができるように、活力を持って臨めるように、ぜひ今後も努めていただきたいと思っております。
それでは、次の大項目2、ラムサール条約登録後の課題について質問をいたします。
今後、農家に対する縛りは全くないと言えるのかを、ちょっとお伺いしたいと思うんです。やはり、先ほど市長もおっしゃいまいたが、いろんな形でこの環境に配慮するということ。SDGsに絡めてのことでもございますが、やはりラムサール条約となってくると、大きくこの湿地を守っていこう、自然を守っていこうというところに重きを置いてしまいます。そうしたときに、もし今後、そのような何かしらの縛りが農家に出てくる場合はないのかを、まずお聞かせください。
○池田幸弘農林水産部長 現在のところ、新たな縛りというものは特には聞いていないところでございます。
ただ、施設等を造る場合はこれまでも制限がかかっておりましたので、そういった施設につきましては、許可を得るのに相当時間等はかかると思います。
○10番(田上真由美議員) では、そのように皆さんの理解を得た上で、これはなっているものだと思いますので、丁寧に扱っていただけたらなと思っております。
広報「いずみ」におきましても12月号の中でこのラムサール条約登録ということで、大きく記事が特集で1面、2面を飾っておりました。その中で、この祝賀メッセージ一部抜粋で掲載してありましたが、あちらを読ませていただきましたときに、本当にこれはものすごい大切なものを、私たち出水市民は守り、そうやってずっと維持してきてくださったんだなということを、あのメッセージを見て改めて心新たにしたところでもございます。
ぜひ、その場所で生活をされる方が困ることのないように、今後もそこのところはしっかりと調整をお願いしたいと思います。
それでは続きまして、観光についてですが、今、観光客の方も少し足が伸びているということでございます。そこで、出水麓武家屋敷は、観光に重きを置くために規制緩和をいたしました。そのほうが、観光にとりまして得策になるというふうな考えでございますが、何かしらこの規制を緩和するほうが観光に有効になるようなことは、今後ないのか。このラムサール条約登録がですね、そういったことがないのか。このまま、条約を締結したことが観光にとってメリットしかないのかお聞かせください。
○椎木伸一市長 麓武家屋敷のほうは用途のほうを見直しまして、規制緩和をしながら、また出水市の地区指定である程度戻しております。
ラムサール条約のツル観光のほうと麓観光については、規制については全く別物でございます。麓のほうにつきましては、皆さん御存じのとおり縛りが強すぎて、売店もできなければ民泊をすることもできないというような地域でございましたので、生活もしやすく見てもらいやすいという環境を作ろうということで、ああいう対策をとっているところでありまして、ラムサール条約、ツルの観光につきましては、環境を守りながら、また賢い利用をしながら、産業振興にも役立てましょう、子供たちのふるさとへの醸成、市民の誇り醸成にも努めましょうというような趣旨でありまして、鳥インフルエンザとのすみ分けもちゃんと規制ができるように、防疫体制もしっかりできるようにしましょうというようなことでのラムサール条約での登録の実証実験をしておりますけれども、規制等も実施していきましょうという方向でありまして、いずれも出水市の観光振興にはこれまでも両方標榜しながら取り組んできたわけでありまして、両方が相乗効果で観光が伸びていくようにしたいという思いもありますし、またツル観光につきましても終年での野鳥が非常に多いと、ラムサール条約湿地の登録地だということを含めて、そのツルのシーズン以外も野鳥観察ツアー等をできれば終年の宿泊型の観光も成立していくのではないかというような思いで、登録したところでございまして、お互いに相乗効果を発揮したいという思いでやっております。
○10番(田上真由美議員) それでは、このラムサール条約登録後につきましては、また出水議員のほうも考えていらっしゃるようですので、私はここで終わりたいとは思いますが、このラムサール条約登録をしたことで、「観光との相乗効果」ともおっしゃいましたが、そこで生活する方とも相乗効果が出るように、ぜひ、これからも維持していただきたいと思っております。
それでは次に、大項目3、国道・県道の植栽帯について質問を繰り返します。
12月6日、伊藤県議も一般質問で取り上げてくださいました。「県も限られた予算内で効率的な維持管理手法を検討するとともに、予算の確保に努める」と答弁をされております。本来であれば、この手法で適切に管理されるべきですが、限界があるというのが今の実情ではないかと思っております。
今、市役所職員の皆様の手で、市役所前の植栽帯がとてもきれいになっております。このことを例にして、こんなふうに変われるんだよみたいな、これを広報「いずみ」がリニューアルいたしましたので、このふるさとの道サポート推進事業を県のほうでも周知を図っていくと言われておりますが、出水市のほうでも改めてそのように周知をしていただけたらなと思います。
この点につきまして、答弁をお願いいたします。
○椎木伸一市長 この国道・県道の植栽帯、我々の市道もそうですけれども、植樹帯の管理につきましては、県内全体の大きな課題となっております。
私も就任以来、そのことは非常に危惧しておりまして、この高齢化の中でどうやったら維持管理ができていくのかという思いの中で、単独でつくりましたのが、この「みんなで守る市道・農道管理事業」ということでありました。それらの中にもいわゆる「花いっぱいプロジェクト」ということで花壇の苗等を補助するというような試みもやっております。平米1,500円でしたか。それを、今度は県道・国道へも広げられるというような対策をとりました。これにつきましては、先ほど御紹介いただいた県の「ふるさとの道サポート推進事業」このサポート隊になってもらいたいという、その上でうちの事業も適用できるという仕組みをつくっております。
私が思いますのは、県のほうに権限移譲をお願いしておりますのは、今高木とか低木とかずっとあります。低木の中にはカヤ等が繁茂しまして、刈ってもすぐまた伸びてしまうという実情があります。そういった中で、メンテナンスフリーあるいは花壇整備、抜根の上のことなんですけれども、そういった地域の要望がある沿道については、そういったことをしながら少しずつでも市に移譲してもらって、市の事業も相乗りしてもらって、市民の皆様に守っていただく。そういったシステムが出来上がればいいのではないかという思いで、今やっておりまして、今後もそのことを周知広報しながら県と協働して取り組んでいきたいというふうに考えております。
○10番(田上真由美議員) 私も父の家の前のワンブロックですが、カヤがすごく、巻き付くような草がずっと生えていましたので、それを草取りをしてみました。そうすると90リットルに5袋草が取れたんですね。そのぐらいの量だと、燃えるごみの日の粗大ごみの日に出させていただくというようなことをするんですが、なかなか誰かが特定の個人でというのは、とても限界があるなと思いながら、市長のおっしゃるとおり企業なども県の事業であれば100メートル単位でその企業がやりますということであれば、看板も県が作ってくださいます。その企業の宣伝効果にもつながるよみたいな話を周知していただけたらなと思っておりますので、今後もこのことは一緒にやっていけたらと思っております。よろしくお願いいたします。
それで、広報「いずみ」についてですが、市民の反応はそれぞれでございますが、「ちょっと字がちっちゃくなっているところがあるんじゃないか」とか、「いや逆に、とてもお知らせなど見やすくなった」とか、いろんな声がありますが、まずとてもおしゃれになって、若い人が少し手に取ろうかなという気にはなったんじゃないのという声も聞こえております。意識して、この変革をしておられることをヒアリングでも伺いました。その発想はすごいというか、思い切ったことをされたなと思い、評価をさせていただきたいと思います。ただ、中の細かい気付いた点につきましては、ヒアリングでも指摘をさせていただきましたので、ここで御披瀝することは控えますが、広報紙は情報発信の重要な媒体でございます。今後も試行錯誤しながら、より良いものになるよう充実を求めます。
それでは大項目5です。「誰でも生きやすい社会」「生きにくさに目を背けない市政について」話をさせていただきたいと思います。
まずここで話をさせていただきたいのは、現在、こども課の職員の皆さんがどれほど市民の皆さんに真摯に向き合っていただいているか、私が本当に改めて頭の下がる思いでございます。ありがたいと思っております。
以前より、この保育事業者の皆様と連携を図るために、情報交換会を開いてはどうかということをこの議会におきましても提案をさせていただいておりましたが、なかなか日常の煩雑さ、たくさん事業を抱えていらっしゃる中で実現するものではなかったんですね。ただ、今年の10月27日、出水市保育所等情報交換会としまして開催をしていただきました。保育事業者の皆様は大変喜んでおられまして、こども課職員の皆様方にとても感謝をされておりました。あのような場所で皆さんの意見を集約して聞いてくださることが、今までなかったということでした。これからも年に1回程度できればいいなというふうにお話しくださったことも、とても喜んでおられます。このことを、まず私からも感謝をもってお伝えしたいと思います。ありがとうございます。
そして、先ほど来、市長も答弁いただきましたけれども、保育園、今支援を必要とする子供の増加で、それぞれの個を安全に預かることに大きな配慮を要しているところでもございます。教育委員会のほうからも答弁をいただきました幼稚園です。そして、保育園、こども課、どこもそのような現状があるという認識は、どちらもされております。
先ほど来、壇上でお話をさせていただきましたが、家族力の低下、こういったことが今見えてきております。子育て中、出産が済んだ後のお母様方と接するときに最近よく感じるのは、自分の親を頼れない、頼りたくないというママたちがとても増えているのが現状だなと思っております。ワンオペで1人で育児をしなきゃいけなかったり、そしてシングルで子供を育てていらっしゃる方など、そしてまた生活上の不安を抱える保護者も今多くなっております。それに伴い、保育園に求められるものというのが、とても大きくなっています。この現状をどのように把握されるのか。こども課の皆様方が痛いほど分かっていらっしゃると思いますので、市長がどのように認識をされているか伺いたいと思います。お願いします。
○椎木伸一市長 今、答弁で申しましたように、療育を必要とする子供とか様々な課題が多様化している時代だというふうに思っております。そういった中で、先ほどおっしゃった保育士の方の御苦労とかそういったものは担当課等からも聞いておりまして、そういったまず実態調査をしながら課題整理をして、今後も誰でも生きやすい社会、生きにくさに目を背けない市政というようなことを目標に、皆さんのお声を聞きながら対応していきたいと考えます。
○10番(田上真由美議員) 先ほど壇上でも申しましたが、保育所等における要支援児童等対応推進事業、この事業は「保育所等において保育士等が有する専門性を生かした保護者の状況に応じた相談支援などの業務を行う地域連携推進委員の配置を促進し」というふうになっています。
そしてまた、「要支援児童、要保護児童及びその保護者などの対応や関係機関との連携の強化、運営の円滑化を図る」というふうに明記をしてございます。国もその必要性を認めて事業化していると認識をしているところでもございます。
先ほど市長は、保育園、こども園からのそのような話が届いていないというふうにおっしゃいましたが、その声はすぐにでも届けられる自信が私にはあります。これを、私が今回一般質問をするに当たり、このことはリサーチをしっかりとかけておりますし、そのような会を設けさせていただければ、どういったことが望ましいのか、その声はすぐにでもお届けすることが可能でございます。
まずもって、国そのものが必要性を認めて事業化していると認識をしておりますが、市長の見解を伺います。
○冨永栄二保健福祉部長 議員の言われるとおり、最近は子供を取りまく環境が多様化しているということです。DVや児童虐待、いろいろと保育士だけではなかなか解決できない問題等が増えてきているところもあります。そういったところもあって、国の事業におきましても地域連携推進委員の配置ができる事業ということで、国のほうも事業化をしているところです。
これにつきましては、市長の答弁にもありましたけれども、その必要性についてそれぞれ市内の保育園等に調査をしながら、また実情把握をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○10番(田上真由美議員) ありがとうございます。ぜひ、調査をかけていただき、必要であれば私がすぐにまとめて、皆さんを招集をかけて、そして一緒にお話を聞いていただくことが可能ですので、ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。
そして、「支援学級が増えているけれども、それはなぜ」とよく聞かれます。皆さんもそうだと思いますが、見解は様々だと思いますが、一人一人の特性や多様性を受け入れ、その特性を伸ばすことの重要性が、今認められてきたことが大きいのではないかと考えます。
ここで書画カメラをお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)まず、ちょっと見にくいかもしれませんが、字体で皆さんのほうに見ていただこうと思います。
まず、妊娠・出産に関しましては、出水市としてできる支援、すばらしいんですよ。これは国も推進しておりますように、不妊治療助成、これは国が不妊治療を進めているということもあって、とても充実していると。そして、次に子育て応援券です。そして産後ケアなどです。もうこの子育て応援券と産後ケアにつきましては、この壇上にて何度も何度も繰り返し繰り返し質問をさせていただいた結果、予算を付けていただき、今子育て中の皆様方が使ってくださっております。
そうしたときに何が起こっているかというと、今、保健師と開業助産師との連携が徐々に図られてきております。なぜかというと、開業助産師のお一人が、この連携を取るための月1の会議というのが、予算がないんですね。だから出られたところで、会議費は出ないけれども、私たちは子育て応援券を事業として扱っているんだ、だから会議をしっかりと1か月に1回はやっていきましょうという、開業助産師からの声かけで、「なかなか予算が付かないからちょっとやりにくかったです」という保健師の皆様に、あえて開業助産師のほうから声をかけて月に1回の連携が図られております。
そして、育児不安やワンオペ等へのサポートが今、できているのが実情です。そして、早期支援が今、可能になっているのが実情なんですね。私の娘やめいっ子の友達が、インスタやいろんなSNSで「出水市、こんな事業があります。すごくラッキー」みたいなことを上げてくださるんです。そうしたら、「あ、いいね、出水市。羨ましい」という声があるよというのを聞きます。そうしたときに私が思うのは、何がいいと思っているかというと、この支援が充実していることを喜んでくださっているのですが、まずそこには、安心感があるんじゃないかと思うんです。自分がいざ困ったときには、こういうところがあって、助けてもらえるという安心感があって喜んでいただけるのではないかと思うんです。
それでは次に、2枚目をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)ヒアリングの際に聞いて、もうびっくりしました。すばらしいです。附属幼稚園です。子供のサポート、親へのアドバイス、個別計画作成、これを保育園、幼稚園、それぞれどうしているのかという担当課の方に2人、2人来ていただきまして話を聞きました。先ほどの答弁にもありましたように、この附属の幼稚園の子供であれば、小学校の支援学級の教諭のサポートが受けられる。そしてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーのサポートも受けられる。そして、教育委員会のバックアップも受けられる。いざとなれば、園長先生は校長先生ですからね、何かあったときには、そういうふうにして、すぐにその幼稚園教諭のサポートにも入れる。すばらしいなと思って見せていただいたところでございます。幼稚園に通う子供、すごく手厚いなと思って見せていただいたところでもございます。ヒアリングの際にも本当にすばらしい仕組みが、同じ所管の中でしっかりできているというのがすばらしいなと思って聞かせていただきました。
そして次に、小学校をお願いします。3枚目です。(議場内ディスプレーへの資料表示)小学校は、支援教室が増加しております。そして個別計画の的確な活用ができることで、この支援がより一層充実したものになっていきます。そして、幼稚園、保育園との情報共有をするために、先生方、保育園やこども園に行かれて情報収集をされることもあるように聞いております。そうしたときに、小学校では児童生徒の特性を伸ばす教育のより一層の充実が、今、図られつつあります。そして、教職員のいろんな負担の軽減につながるのではないかというのもあります。そして、これができてくると、子供たちの生きにくさというのが軽減が図られるというのが実情です。すばらしいなと思っております。
そこで保育園です。お願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)ないんです。幼稚園のようなサポートがないんです。そして、長い期間、通園する子供も多いことから、圧倒的に幼稚園ではなく保育園、こども園を利用される子供さんの数のほうが出水市内に絶対的に多いんです。そして、なぜ私がこの専門家の支援員を市が雇用することが必要だと言っているかというと、今、その親の要望にも答えなければならないというところが、先生方、保育士の方々の負担がものすごく大きいんですね。言われてしまうこともあるそうなんです。「子供も産んだことないくせに」とか、いろんなそんな言葉が保育士さんに投げかけられる。子供に対しての指導に関してはプロという意識で対応してくださっていますが、親に対して、そこのアプローチがうまくできなかったりすると、保育士さんたちのメンタルがやられてしまう。今、保育士不足も叫ばれている中、ここが改善をされなければ、保育士になりたいという、ずっと続けていきたいという人たちを、出水市の中で仕事をしていただくことができなくなるという危険性も今、はらんでいる。本当に瀬戸際だと思っております。
本来であれば、このような予算があるというのは当然、こども課の皆さんも御存じで、「こういうことがありますよ」と園に投げかける。でも、園はこれを活用して、自分のところで一つその専属の職員を雇用するというゆとりがない。だからこそ、市で雇用をして、全部の園を巡回してくださる。こういったことが必要ではないかと思っているんです。なので、この中で保育園への支援が欠落しているということは、御理解をいただけたのではないかと思いますが、市長の見解をお伺いします。
○冨永栄二保健福祉部長 先ほども申し上げましたけれども、保育士だけではなかなか対応できない相談等も増えてきております。
その中で、市長答弁にもありましたけれども、安心サポートセンターに来年の4月1日から、子ども家庭総合支援拠点を設置いたします。これが子供家庭支援全般にわたる業務とか、いわゆる実情の把握、情報の提供・相談等を対応します。
それと、要支援児童及び要保護児童等への支援業務、あと関係機関との連携調整、機能強化を図っていくということで設置をすることとしております。その中で、やはり関係する保育園とかそういった学校関係も含めて、幼稚園も含めて、そこあたりでそういう支援が必要な方については情報提供をいただきながら、支援をしていきたいと考えております。
あわせて、議員がおっしゃるいわゆる地域連携推進委員の配置のことだと思います。配置をして、それぞれ必要とする保育園に巡回をして、対応をしていくという形のシステムにもなっております。そういったところを今回、安心サポートセンターのほうにも、そういった拠点づくりもしますので、そこあたりとの連携もできないかというところも今後研究していきたいと考えております。
○10番(田上真由美議員) 今の答弁は、私が望んでいるものに近いものができるという認識をしていいのかどうか、確認をしたいと思います。新たにその拠点をつくられるということで、新たな人材の雇用を行うのか、それとも今いらっしゃる人材の中で行うのかで、大きく違ってくると思いますが、その辺をお聞かせください。
○冨永栄二保健福祉部長 今回、4月に開設します家庭総合支援拠点につきましては、今働いていらっしゃる家庭相談員で対応しようということで、今考えております。そういった中で、議員の言われる地域連携推進委員の配置となると、なかなかそこまでは対応できるかというのは、現段階ではちょっと見えていないところもございます。そこあたり、人的な配置が必要なのか、そこあたりも予算的な部分もございますし、そこあたりも含めて研究をさせていただければと考えております。
○10番(田上真由美議員) それでは少し視点を変えます。
生きにくさを抱えているのは、子供だけではないというのが、今の実情だと考えます。私たち親世代、このような手厚い支援はありませんでした。ですが、社会の中でそれなりにやっていけた。今は、その多様性を受け入れるとわざわざ言わなくてはいけないということは、なかなかその多様性を受け入れづらい社会になっているんだろうなというふうに思っております。
今、サポーターを必要とするのは親なのかもしれないということです。例えば、子供が園で困っているという事象があります。保育園が療育につながることで困っていることが解消できるのではないかと考えました。親に伝えます。しかし、そのことを親が受け入れられない、そういう事例が多くございます。そうしたら、子供は困ったままということです。そのことの原因として伝えるのが、心理士等の専門家ではないということ。支援を受けるということへの偏見、そして家族内の中でも母親の育て方が悪いという認識の相違、そして祖父母の無理解などの声を頂きました。
で、あれば支援員という専門家が伝えることで、円滑に子供の「困った」、これの「困った」の解消につながりやすくなると考えております。保護者への理解を深めるためにも、そして保育士の負担軽減にも有効と考えますが、このような役割を今、保健福祉部長がおっしゃったような今度サポートセンターの中にあるもので、ここまでの対応ができるのかどうか、お聞かせください。
○冨永栄二保健福祉部長 4月に子ども家庭総合支援拠点を安心サポートセンター内に設置をします。それは市内、いわゆる全般的な子供さんを対象とした支援拠点になりますので、いろいろな相談についても保育園等また幼稚園等、また各関係機関から相談があった場合には、十分そちらのほうで対応はしていきたいと考えております。
その中で、どうしても相談件数が増えたりとか、またいろいろな部分で人的な配置が必要になってくるようであれば、そこあたりはまた今後考えていきたいと考えております。
○10番(田上真由美議員) 少子化が進む中、地域の小学校・中学校・幼稚園・保育園・こども園が全て連携し、連動していくことは最重要課題だと考えております。今、出産後のサポートができること、そして小学校や中学校で適切な支援を受けられる環境であることは、大変有意義なことだと考えております。しかし、連携し連動するために、幼児期のサポートに予算を投入することで子供たちの未来が大きく変わるならば、すばらしいことだと考えます。しかも、次の世代につながることでもあります。確かに、時間がかかることで、すぐに結果は出ないでしょう。でも、今やらなければ、いつまでたってもできないのではないかと考えております。子育て応援券も産後ケア事業もひきこもり支援事業も、繰り返し質問し、市長をはじめ市行政職員の皆様方やそして議員の皆様の御理解をいただき、実現しております。予算化し、事業に取りかかる必要性を強くここで訴えたいと思います。
先ほど来おっしゃっておりますように、このことが本当にどれだけ必要なんだということは、これからも担当の職員の方々とそして保育園、本当にこども課の皆様には頭の下がる思いです。園に対する苦情も全部こども課で受けられる。そして子供のために一生懸命やろうと思う園の経営者の苦情も受けられる。そして、実際に公立も抱えているので、その中で療育を必要とする子供さん、その家庭のサポートにも入られる。とても大変な中で、今私がこれを言っていることは、余計に負荷をかけることなのかもしれませんが、ただ、今、この前も全体会、そのように情報交換会をやってくださった皆様なら、今ならできるのではないかと思っております。私の中でも申し訳ございませんが、大変評価が高くございます。ぜひ、お力を貸していただきたい。そして、市長にもここのところ、今粛々とやっていく事業というのは確かに必要です。そこに上乗せをして、これを構築していくことも忘れず、頭のどこかに入れながら、その情報収集しながらの中で、ぜひ予算化、事業化していただくことを熱望したいと思っております。
いずれにしても、特別な人、おかしな人という目で見られることがない社会、すなわち自分事として考えられて、個性の延長として捉えることのできる寛容な社会を作るためにも、多くの人にこれらの「生きにくさ」を感じる事象についての認知を広げていく必要があります。それぞれの事柄を身近な人があたるかもしれないから知っておこうよというスタンスの講習会、勉強会の開催はできないかお伺いいたします。
○高口悟こども課長 先ほどおっしゃったように、これまでも保育園と話をする機会とかそういうものは少なかったのかと思っております。そういったいろんな問題、課題、子育て支援につながるような、そういう課題解決に向けた話合い等はぜひ、多く機会を持って行っていきたいと考えております。
○10番(田上真由美議員) そして、講習会、勉強ですね、一般の市民に向けてのものです。なかなかひきこもりの時にもお話をしましたが、自分の家の中に子供がいるけどなという人は、「なかなか自分の家にいるから」といって、行きにくい。
だけれども、サポーターを養成するとか、身近な人がそういう困ったことがあるかもしれないよというような講演会などを開催していただければ、このコロナが落ち着いてからでもそのようにしていただけると、大変どなたでもアプローチできる、参加できるものができないかと思うのですが、その辺についてお答えください。
○冨永栄二保健福祉部長 以前も御質問いただいたときにも、そういったひきこもりサポーターが市民の方にもできないかという御質問もいただきました。そういったところも含めて、今後はそういったひきこもりに関する情報提供をしっかりと市民の方に伝えながら、また講演会等できればそこあたりも考えていければと思っております。
○10番(田上真由美議員) それではほっとハウスです。
児童生徒との、この職員の方の年齢差がものすごく大きいのではないかと考えますが、これだけ情報のあふれた社会におきまして、世代間のギャップがないのかどうかお聞かせください。
○大久保哲志教育長 議員がおっしゃいますように、ギャップがないのかと言われると、先ほども申しましたように年代が60代から70代ですから、そういった方々に主に10代ですね、そういった子供たちのギャップ、これを埋められるのかという部分は御指摘される意味はよく分かります。
ただ、一つは先ほど申しましたように小学校の教諭、校長、教頭、そういった経験をしている方々ですので、そういった意味では子供たちの気持ちというのはある程度分かっているので、そういう意味では十分にそこはできていると思うんですけれども、まず、そのほっとハウスへの通級に関してなんですけれども、そのままただ話を聞くのではなくて、最初にスクールソーシャルワーカーが面談をしまして、そして指導員との面談とか、それから体験の通所を経て、そして最終的にはその保護者、そして御本人が決定するという形でやっているわけですけれども、その中で個々の児童生徒の困り感とか不適応感とかそういったものを把握して、個に応じた対応を検討して学校復帰に向けたカムバックプログラムを作成していると、そのような形で進めているわけであります。
まず基本的には、今話したような形で進めておりますので、対応として不足している分はないのではないかと思うんですけれども、おっしゃる世代間のギャップについては、例えば子供たちに近い世代であったり、あるいは保護者の世代、こういったものが必要性というのは分かりますので、今後募集をする際は今でも年代は問わずに広く募集をしているのですけれども、なかなか若い年代の応募もないというような現状もあります。
そしてまた、先ほど特別支援学級のこともおっしゃいましたけれども、特別支援学級は非常に充実して増えている関係もありまして、今教員免許を持った方というのは、圧倒的に世の中から不足しておりまして、今出水市では必要な教員は全て配置ができていますけれども、本当にどこの地区でも配置ができない状況にあります。そうしたときに、その若い世代で教員免許を持っていたりとか、そういった方々というのは、そういった学校への配置を優先していましたので、そういう意味ではなかなかいないという現状もあります。そういったことも踏まえて、今後は対応を考えていかなくちゃいけないのかなというふうに思っております。
○10番(田上真由美議員) それでは、中学校卒業後、このほっとハウスに通っていた子供たちなんですが、高校進学などで社会とつながる生活ができることが理想だとは思ってはいるのですが、それがない場合ですね、いかに社会とつながっていくか、誰かが自分のことを気にかけてくれているんだという、この支えがとても重要ではないかとは思うのですが、その点についてどのように見解を持っていらっしゃるかお聞かせください。
○大久保哲志教育長 まさに、今先ほど私がお答えしたところにありましたように、このほっとハウスにおきましては、通級をする際に、最初の面談でスクールソーシャルワーカーの方が面談をするという話をしましたけれども、その際には、その時点の児童生徒の困り感とか不適応感の把握だけではなくて、その後の継続的な支援の必要性とかそういったことも把握して、ほっとハウスに通うだけではなくて、その後のほうについてもこのような支援が必要ということで伝えていって、そしてまた必要があれば話に来たら、それに対して支援をしていくと現在も例えば卒業した後にほっとハウスに現在の状況を話に来たりとか、それからそういった相談に来たりということもあるというふうに把握しております。
○10番(田上真由美議員) 安心サポートセンターは今後も重要な部署であります。ますます重責を担うことになるのではないかとは思っております。適正な人的配置とスキルアップが必要でありますが、人的配置について人材の育成ができる環境なのかどうか、これが課題だと思いますが、その点につきましての見解をお伺いいたします。
○冨永栄二保健福祉部長 市長答弁にもありましたように、県のほうからも専門監ということで人事交流で来てもらっています。その中でも、職員に対するいわゆる家庭相談員等を含めて、相談業務、またスキルアップも大分上がってきております。
それとまた、本市からも児童相談所に人事交流ということで行っております。昨年度1年行って、こちらのほうに帰ってきた職員が、今安心サポートセンターで相談員として、社会福祉士ですけれども頑張ってもらっています。やはり、1年行ったことで大分スキルアップといいますか、児童相談所で勉強してきたことについては、非常に役立っていると思っております。そういったことも含めて今後もそういった人事交流も含め、スキルアップに努めていければなということで考えております。
○10番(田上真由美議員) 本当に子供たちが小学校に行くと、自分たちで往復もします。親との接点がなくなる、親との接点が持てるこども園、保育園、幼稚園というのは、とても重要なところです。心の基盤を整える社会に出て行く第一歩につながる大切なところです。ぜひこれからも情報収集をしながら、出水市の子供たちが心豊かに生きられるように、ぜひ一緒に尽力させてください。
ありがとうございました。
-------------------------------------------------------
△ 会議時間の延長
○議長(杉本尚喜議員) ここで申し上げます。
しばらくしますと、本日の会議終了時刻となりますが、次に控えていらっしゃいます北御門伸彦議員の質問が終了するまで、会議時間を延長いたします。
次に北御門伸彦議員の質問を許します。
○5番(北御門伸彦議員) 5時が近づいてまいりまして、時間のプレッシャーに押されておりますけれども、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。
コロナ禍の中で2021年も終わろうとしておりますが、オミクロン株が猛威を振るわないで済むことを願っています。
今年印象に残ったことは、大リーグで圧倒的な活躍をした日本人、大谷翔平でした。目標を持って着々と実績を積み上げるやり方は多くのヒントを示してくれていると思います。また、コロナ禍にあって、平和の祭典と言われる東京オリンピックと合わせスポーツで夢や希望を与えてくれました。
また、ノーベル物理学賞を受賞した眞鍋淑郎さんは50年以上前から地球温暖化の警鐘を鳴らした方で気候変動の研究の先駆けをとされた方であり、日本人として誇れることだと思いました。
地球温暖化のせいかもしれませんが、私の感覚では日本の季節の春や秋と感じる期間が短くなった気がします。それでも私にとって先月11月はスポーツの秋、芸術の秋、読書の秋にふさわしい月になりました。
少しこじつけではありますが、ウォーキングクラブ主催の宮崎県高鍋町の九州オルレのコースを一部歩いてきました。また、初めて文化祭に高齢者学級の絵手紙教室の生徒として作品を出品しました。そういった体験なども一部生かしながら質問を行ってまいりたいと思います。
さて、私たち議員の任期もあと4か月ほどとなりました。議場で質問できる貴重な機会も今回とあと3月の2回しかありません。私は今期のマニフェストで9つの視点をあげて活動することを提起しておりました。それは「人材育成」「産業」「観光」「医療」「福祉」「防災」「子育て」「教育」「まちづくり」の9つの分野です。これまで行ってきた質間を振り返り、バランスよく質問に反映できたのか今年はじめの段階で確認を行い、意識して質問を行ってまいりました。今期の最初の頃は病院経営などについての質問が多くなりました。後半は風力発電計画の質問が増えました。市全体に関わる質問のほかには地元麓の問題について幾つかの観点で質問をしてまいりました。
今回の最初のテーマは生活基盤である「衣食住」としました。コロナ禍の中で新しい生活様式という言葉が使われだしましたが、コロナが終息しても恐らく、これまでの生活と違ったものが残っていくと思いますし、人工知能など進歩が加速している時代ですので、これからの未来は想像を超える部分があると思います。人々のこれからの暮らしに関し、現時点で私が課題として頭に浮かぶ幾つかの観点について質問をさせていただきます。
また、そのほかは時間が足りず、さらに深堀もできていないところですが、「読書活動」「文化活動」「文化財保護」「平和学習」そして「出水麓地区の課題」について欲張って質問していきたいと思います。なお、質問の動機は様々ですが、共通して情報の共有化や共感を得たい観点での質問が主となります。
さて、なぜ「衣食住」の順番なのかということについては諸説あるようですが、私にとっての解釈は、まず人が生まれた時に最初に必要なのは、自分では何もできない赤ちゃんにとって体温を維持するためのおくるみが命を守る最初のすべであったからだと思います。体温が保持できて母乳を飲むつまり「食」、そして寒さや雨風をしのぐための「住」という順番になったのではないかと考えます。
現代、衣類については後進国に古着を送ったりするほど日本は豊かになっています。私は医療の「医」をかわりに当てはめてみました。議会でも医療問題はよく取り上げられる観点で、地域医療構想なども気がかりですが、今回、この出水市内での医療体制の課題は何かと考えました。コロナ対応の観点も今後、検証される中で医療体制の変化が起きると考えます。質問のきっかけになったのは、市内のある小児科のクリニックが閉院したことが、子供の安心・安全に関してひとつの心配な要因であったからです。もちろん医療は市内ですべて完結するものではありませんが、現時点で当局が医療体制の課題と認識されている点を確認いたします。
次に「食」について、コロナ禍の中で思ったことがあります。グローバル化した社会の中で食料について外国に依存している割合が高いことに改めて気づかされました。食料の輸入が止まった時にどう食べていくのか、考えさせられます。国は食料の安全保障の観点もあり食料自給率を高めるという方針を出しています。国の方針も大事ではありますが、私は災害時などに物流が止まった時を考えると地域内でも食料調達の道筋を見つけておくことは大事なことだと思います。単純に出水市の食料自給率を算出するのは難しいと思いますが、物流などを把握しておくことは無駄にはならないと思います。地産地消にもつながりますので、現時点での取組や考え方などお伺いします。
次に出水市の住宅事情についてお尋ねします。市外の方から出水市は結構、家が建築されている印象だと聞きました。私は浪人時代、鹿児島市の吉野地区や始良市で仕事をした経験があります。どちらも目覚ましい発展が進行しており、それと比較した時、出水は変化が遅いイメージがありました。しかし確かに最近30坪未満の住宅があちこちで建築されているのを見かけます。資料請求をさせていただきましたが、持ち家比率が平成30年度住宅・土地統計調査では全国平均で61.18%、出水市は72.88%となっていて、全国より10%以上高いようですが、平行して空き家も増えている現状があります。当局が現時点で市内の住宅事情について把握されていることについてお尋ねいたします。
次に出水の大きな施策のひとつである「読書活動日本一」を標務して実践活動に取り組んでいることについて、お尋ねします。
先日11月27日にマルマエホール出水で開催された第15回目の推進大会に参加させていただきました。講師の児童文学作家のくすのきしげのり先生も展示されている実践活動の様子を講演前に見られたようで、講演の中で高い評価をしていただきました。現時点でこれまでの活動を振り返り、目標に対する実績や効果、実践が難しいと感じる点などお伺いします。
私は文武両道という言葉が気に入っています。ボケずに頭も体も健康で生き続けることに憧れております。私は今年、高尾野の鶴亀大学に通い、絵手紙を習い始めました。講演を聞いた後に絵手紙を教えていただいておりますが、コロナのせいでまだ2回しか習っていない時点で文化祭にも作品を出品することになりました。市長、副市長も文化祭に来てくださっておりましたが、文化活動について文化祭を切り口に質問をいたします。コロナ禍の中で初めての総合文化祭についての評価をお尋ねします。
次に平和学習について、学校現場での取組状況と戦争遺跡の活用についてお尋ねします。私の父は公務員生活の半分以上を図書館で勤務し、子供の読書活動が大事だと以前から考えていたようでした。また、酔った時は終戦当時に出水町役場の職員として戦死通知を届ける役目をしていたようで、近くの父と同年の子供を持つ母親に戦死通知を届けた時の様子を語り、なんとも言えない苦しかった心情を吐露して、二度と戦争を起こしてはならないと何度も語っておりました。私に平和に関する強い思いは受け継がれたと思います。
次に文化財の保護と活用について、今回、主に郷土芸能を取り上げ質問したいと思います。地域活動の低下とともに郷土芸能の保存活動について心配をしております。コロナ禍にあって、麓の県指定無形文化財の「種子島楽」も披露する機会が少なかったようです。やはり発表の機会がないと定期的な練習にもつながりにくく、伝承していくのがますます大変になって行きます。市全体の郷土芸能保存活動の現状と見通しについてお尋ねいたします。
最後に出水麓地区の課題としてまず9月議会でも質問させていただいた「キオビエダシャク」の被害対策について再度、質問をいたします。質問にあたり、資料を請求させていただきました。先月末では、2度散布されたところもあるようですが、延べ36団体、250万円の予算額に対し、確定している市の負担は52万8,000円で、執行率は21.12%になるようです。残念ながら皆様もよく見るようにキオビエダシャクは寒さに強くなったのか、11月でも飛んでおりました。最近幼虫が植木から下がっているのも見ました。イヌマキにとっては新型コロナのように最大の危機かと思います。被害状況、防除の状況、現状の対策の評価など御答弁ください。
小項目の2番目として民間主導で進みつつある「出水麓サムライプロジェクト」についての質問です。出水出身で以前より麓の資源を生かすことを考えておられた筑紫さんが、御自分の経営される会社で計画されたものです。出水麓街なみ保存会も協力することになっています。出水麓サムライプロジェクトのコンセプトは、①人的・経済的活性化、②歴史遺産の再生と認知度向上、③国内や海外来訪者への研修・修養の場と機会の提供、④歴史・武芸・文化・生活の紹介と理解促進、⑤サムライスピリッツを学ぶ場、⑥SDGsとESGの啓蒙・普及活動の拠点の6つです。このプロジェクトに対する市の対応についてお尋ねします。
最後の「地区内の児童の交通安全対策について」は、何人もの方から御意見をいただいたことによる項目です。最初に課題としては防犯灯やゴミ問題もお伝えしましたが、お伝えしたことで対応していただく点もあり、今回はこの1件だけお尋ねします。以前の質問で触れました事例で、出水小学校前から町の方へ下った野間口坂の途中で飛び出しによる子供の交通事故があり、その後交通安全対策をしていただいたことがありました。今回は、下校時に出水小学校校門の御仮屋門から道路に飛び出す事例で、ひやりとしたドライバーが何人かいらっしゃったことによるものです。交通安全施設で何か対応できないかと思ったところでの質問でしたが、まず学校の方での指導が効果的とのことでもあり、その答弁を求めることにしました。
以上、壇上からの質問を終わります。
○議長(杉本尚喜議員) ここで暫時休憩いたします。再開を午後4時50分といたします。
午後4時38分 休 憩
午後4時50分 再 開
○議長(杉本尚喜議員) 再開いたします。休憩前に引き続き、会議を続行し北御門伸彦議員の質問に対する当局の答弁を求めます。
○椎木伸一市長 北御門伸彦議員には文化祭にも御出品いただきまして、ありがとうございました。それでは御質問にお答えします。
本市の医療体制の課題について、全国的に少子高齢化が進む中で、医療保険制度を維持していくためには、病床の機能分化・連携を進め、効率的で質の高い医療提供体制の構築と在宅医療・介護の充実を図る必要があると考えております。
県においては、「鹿児島県保健医療計画」を策定し、医師の地域的偏在や特定診療科の医師不足解消等に取り組んでいます。
本市においても、医療従事者の勤務環境改善や医師不足の問題、併せて看護師不足が課題となっております。
診療科別では、産婦人科については、現在2医療機関で2市1町の診療や分娩等に対応していただいていますが、過度な負担がかかっている状況であり、このままこの状況が続きますと、市内での分娩に影響がでることが懸念されます。
また、小児科については、市内に4医療機関ありますが、1医療機関が診療を休止され、現在は3医療機関で診療等に対応していただいているところであります。産婦人科同様、小児科が減少していけば、1医療機関への負担が増加するとともに、小さなお子さんを持たれる市民に与える影響が大きいと考えます。
次に、「食」についての御質問にお答えします。
令和元年度のカロリーベースでの食料自給率は、国が38%、鹿児島県では78%となっていますが、市町村単位での食料自給率については、統計がありません。
本市では、学校給食において、できるだけ地元産を使用するよう取り組むなど、食料自給率の向上に向け、地産地消の取組を進めています。
次に、持ち家比率及び空き家対策についてですが、平成30年住宅・土地統計調査の全国のデータになりますが、一戸建ての延べ床面積は、126.63平方メートル、1室当たり人員は0.47人となっています。平成25年調査と比較し、延べ床面積で2.0平方メートル、1室当たり人員で0.01人それぞれ減少しており、わずかですが、小規模化しているようです。
次に持ち家比率でありますが、同じく平成30年住宅・土地統計調査では、全国が61.18%、鹿児島県が64.61%、出水市が72.88%となっています。
また、空き家率は、全国が13.6%、鹿児島県が19.0%、出水市が21.7%となっています。なお、この空き家には賃貸や売却のため空いている住宅も含まれます。
人口減少に伴い全国的にも空き家は増加傾向にあり、住宅解体補助と併せ、空き家バンク制度など空き家の有効活用を図る必要があると考えているところであります。
次に、文化財の保護と活用についてお答えいたします。
現在、出水市に残る郷土芸能の中で、保存会として活動を行い、文化財課が所管する郷土芸能連絡協議会に加盟されているのは22団体ございます。
各保存会には例年、その運営・活動の申請に対して予算の範囲内で補助金を交付しています。
コロナ禍の昨年度は、各保存会においては、通常の活動が実施できた郷土芸能がある一方で、活動の規模を縮小したり披露を控えざるを得なかったものもあったと聞いています。
コロナ禍以前からも少しずつ構成員の高齢化や後継者不足により活動を休止する保存会が出ていましたが、コロナ禍がこの活動の停滞に拍車をかけたようにも思われます。
このような中、昨年度に運営補助金の申請を出された保存会は8団体でした。
市では、郷土芸能の保存活動につきまして、これまでどおり助成を継続していく当該地域の、ひいては出水市に残し伝えていくべき郷土の貴重な文化財として各保存会に継続的な保存活動をお願いしてまいりたいと考えます。
また、その動機付けとなるよう、郷土芸能の発表の場を増やす取組を進めていきたいと考えております。
次に、キオビエダシャクの被害対策について、答えします。
イヌマキの害虫キオビエダシャクの被害状況の把握についてでありますが、これまで広報紙や市役所からのお知らせを通じて、市民の皆様に薬剤散布による防除をお願いしてきました。
これにより、発生箇所や防除の仕方などについて連絡を多くいただくようになりました。
連絡をいただいた際は、発生箇所や被害状況を聞き取り、現場を確認し、薬剤散布による防除をお願いしております。
また、本年度から薬剤散布の一斉防除を行う自治会に対して経費の3分の1を補助する制度を実施していますので、この制度を周知し、効果的な防除を行っていただくようお願いしているところであります。
本年度の補助制度の実施状況でありますが、31自治会に補助制度を利用していただいたところです。
なお、現在補助の上限を1日2万円の2回分で4万円としていますが、自治会の規模によっては散布に数日かかるところもありますので、上限について検討を進めてまいります。
薬剤を散布する際、イヌマキは麓地区をはじめ壁木や庭木などに多く植栽されており、中には高木への散布や近くに畑などがあって散布に注意しなければならない場所もありますので、その際は植木の専門業者に依頼するなどの対応が必要ではないかと考えます。
また、防除には広範囲による一斉防除が効果的でありますが、地域によっては散布時期にばらつきが生じてしまうことから、近隣自治会における共同防除の調整や植木業者への防除協力などを市で行いたいと考えます。
これまで市民の皆様の防除のおかげで点在的な被害発生にとどまっていますが、害虫の生息地域は市内全域に広がっていることから、今後も補助制度を活用していただき、被害拡大の防止を図りたいと考えています。
イヌマキは、市の木であり、麓地区において重要な景観及び財産でありますので、今後もその保護に努めていたいと思っております。
次に、出水麓サムライプロジェクトへの支援についてお答えします。
当該事業については、総務省のローカル10,000プロジェクトを活用して事業を実施したいとの相談を受けております。
ローカル10,000プロジェクトとは、地域で稼いだ所得を地域内で循環させる仕組みづくりを目的として、地域の人材・資源・資金を活用した新たな事業を立ち上げようとする民間事業者の初期投資費用を、国と地方公共団体が一体となって支援するものであります。
交付金と同額以上の地域金融機関等の融資を受け実施する民間事業が対象となり、原則として、交付金上限額は2,500万円、うち国と地方の交付割合は各2分の1となっております。
進捗状況ですが、10月から金融機関を交えて国への申請に必要な事業計画書作成に当たっての協議を始めており、現在は、2回目の協議を踏まえ、計画書の熟度を高める修正作業を事業者側で検討されているところでございます。
今後、国が求める地域経済循環の創出や事業実現性、持続性等の条件が整理できれば、市の支援について最終的に判断してまいります。
事業の課題については、民間事業でもありますので、計画書作成段階での回答は控えさせていただきたいと思います。
私からは以上であります。
○大久保哲志教育長 北御門伸彦議員の御質問にお答えします。
まず、読書活動のこれまでの実績と今後の展開についてですが、本市では、平成19年から「読書活動日本一のまちづくり」を掲げ、全ての市民が、あらゆる機会に、自主的に読書に親しむことができるように、市と市民が協働して、読書環境の整備を進め、今年で15年目になります。
これまで、読書に関する文部科学大臣賞を今年度受賞した出水中学校を含め、学校が6校、読み聞かせボランティア団体が2団体、及び図書館が1館受賞しています。
加えて、高橋松之助記念大賞を平成23年度に出水市が、令和元年度に出水商業高校が受賞しました。これは、毎年、全国で1団体、校種ごとに1校、文字・活字文化の振興や朝の読書活動に顕著な功績を収めた団体等に贈られる名誉ある賞です。本市の取組が全国で高く評価された結果だと捉えています。
そのほか、「読書活動日本一のまちづくり推進大会」を継続して開催したり、各学校での読書活動のパネルの展示や読書標語・短作文の募集、読み聞かせイベントを開催など、市民への周知を図ってきました。
現在、第三次出水市読書活動推進計画に基づく読書活動の推進に取り組んでおり、4つの年代別の目標を①乳幼児,小学生は、家族と一緒に20分、②中学生は、ジャンルを広げて20分、③高校生は、自分を見つめる20分、④大人は、読書を楽しむ20分と位置付けて家読20分間運動を推進しています。
活動の推進に当たり、課題となったのは、大人へのアプローチです。
そこで、大人が親として子育ての第一歩を踏み出す時期に、読書のよさや大切さを知る手立てとしてブックスタート事業やセカンドブック事業を行っています。
また、大人に本を身近に感じていただくために、自治会に出向いての出前読み聞かせ事業や、自治会文庫等の設置の支援を行いました。
これらの事業を通して、大人の読書に対する関心が高まりつつあることを感じています。
しかしながら、共働き家庭が増えてきていることから、そのような方々への読書支援も必要となっています。そこで、今後は、企業等と連携・協働して、企業内研修や企業内文庫の設置等、働く大人への読書活動のアプローチを推進していこうと計画しています。
子供の読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものです。そのためには、まず、大人が、常日頃から身近に本を置いて積極的に読書に親しむことが大切であることから、未来の「ひとづくり、ふるさとづくり」のために「読書活動日本一のまちづくり」の出水市が築きあげられるよう、幼稚園や保育園をはじめ、各学校、関係団体、関係機関及び図書館等と連携を図り、読書活動の推進に取り組んでまいります。
次に、文化活動への市の関与についてですが、これまで、コロナ禍にあり、一堂に会しての文化活動や芸術活動に取り組むことは、非常に困難な状況にありました。
しかしながら、芸術文化の火が消えないようにと、昨年度中止となった文化祭を関係者の御尽力もあり、今年度から3つの地域で行われていたものを統合する形で11月6日と7日の2日間に渡り、出水市総合文化祭として開催したところです。
芸能発表部門はマルマエホール出水、展示発表部門はマルマエスポーツセンター出水を会場に開催しました。基本的な感染症対策の徹底に加え、芸能は事前に撮影したものを大型スクリーンに上映することで出演者の舞台袖での密を回避したり、展示は場内に順路を設定し、会場内で人が流れるようにしたりして、工夫を凝らした結果、1,285人の来場がありました。
また、今年度は、「出水市伝統文化親子体験フェスタ」を同時開催し、華道、茶道、俳句、能の4部門で75組、延べ305人の親子が参加しました。親子の文化活動に対する関心が向上したり、伝統文化の魅力を身近に感じるなど大変好評を得たところです。
3つの地域を統合した初めての文化祭であり、また、コロナ禍での開催であったため、準備から当日までの運営や搬出時の混乱などもありましたが、問題点を検証して、次年度以降に生かしていきたいと考えます。
また、文化活動については、出水市文化協会が中心となり、日本舞踊、太鼓、書道、俳句、華道、茶道、絵画、水墨画、陶芸など多岐にわたる活動が展開されています。会員の皆様は、それぞれの部門で著名な賞を受賞されたり、高い評価を得たりするなど精力的に活動されています。
市の独自事業としては、今年で6回目を迎える鶴のまち俳句賞があります。毎年多くの応募の中から、特選5句、入選25句が選ばれ、特選句は出水市生涯学習・福祉・ボランティアフェスタで表彰しています。今年度は2,964句の応募がありました。
また、友好都市である釧路市との文化団体交流事業もあります。平成3年から隔年で、両市の文化交流を深めるために相互訪問しており、今年度は、来年1月に釧路市への訪問を予定しております。この事業により、お互いの活動への意識や技術の向上が図られ、市民レベルでの文化活動の振興に寄与しているところです。
今後も、文化協会等の関係機関・団体等と連携・協働しながら文化活動の充実・活性化を図ってまいります。
次に「平和学習」についてお答えします。
現在、本市では、平和を守り築くために世界的な視野で考え行動できる児童生徒を育てるために平和学習に取り組んでおります。
出水市立小中高等学校では全ての学校で平和学習を実施しており、その中で出水市内の戦争遺跡を活用している学校は19校あり、ボランティアガイドや高齢者の戦争体験の講話を行っている学校は12校あります。
具体的な取組としては、各小学校の3・4年生で社会科副読本「わたしたちの出水市」を活用して、特攻碑公園や掩体ごうなどの戦争遺跡について調べたり、小学校の小規模5校集合学習で特攻碑公園の見学や、ボランティアガイドの講話を通して平和について考えたりしています。
このように出水市内の各学校では、地域の人材や戦争遺跡を活用しながら、各教科の学習や総合的な学習において平和学習を進めております。
次に、児童の交通安全対策についてお答えします。
交通安全については、児童生徒が危険を予測して、自ら安全に行動できるようにすることを目指す「安全教育」と、児童生徒を取り巻く環境を安全に整えることを目指す「安全管理」の2つの側面から取組を行っています。
「安全教育」については、各担任による日常的な指導に加え、PTAと連携を図って登下校時の立哨指導をしたり、出水警察署の協力を得て交通安全教室を実施したりして充実を図っています。
また、「安全管理」については、各学校で定期に実施する通学路点検や、学校関係者・出水警察署・国や県の道路管理者・関係課による合同通学路点検を通して危険箇所の把握を行い、状況に応じて改善を図っています。
教育委員会としましては、管理職研修会において、映像や写真を用いて具体的に交通安全指導をすることや、校内で組織的に取り組む体制を整えることを各学校に指導するとともに、出水警察署・道路管理者・関係課等の関係機関との連携を図り、児童生徒にとって安全な通学路を確保できるように取り組んでいます。
今後も各関係機関と連携を図り、安全な環境を整えながら、児童生徒が「自分の命を自分で守る」力を養っていくことができるよう、交通安全教育を推進していきたいと考えています。
○議長(杉本尚喜議員) ここで申し上げます。
北御門伸彦議員より、書画カメラの使用について申出がございました。よってこれを許可してあります。
○5番(北御門伸彦議員) まずもって、人間の新型コロナ、鶏の鳥インフル、イヌマキのキオビエダシャクとそれぞれ大変でございますが、この困難に対応されている市長をはじめ、職員の皆さまに御慰労申し上げます。
さて、最初にお断りさせていただきます。今回のテーマについては深堀ができていません。思いを伝えることに始終した部分もあります。題材にも関係しますが、答えにくい質問になろうかと思いますので、御容赦いただきたいと思います。
また、2問目以降の質問については順番を入れ替え、大項目6から行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。大項目6については、当局に対応をお願いするしかありません。まとめて質問しますので、よろしくお願いいたします。
まず、キオビエダシャクによるイヌマキ被害対策についてですが、前回の質問の後、車で道路を走っておりまして、市役所付近など幹線道路でもキオビエダシャクの死骸を見ることがありました。キオビエダシャクのせいで国道328、西之口交差点に植樹されていたイヌマキが枯れ、切られております。麓の生け垣でも、木が枯れた事例が出ております。物言わぬイヌマキにとって、死活問題となるキオビエダシャク対策を手厚く行う必要を感じております。
いうまでもなく、市長も御紹介いただきましたが、市の木として選定され、街路樹にも多く植えられており、麓武家屋敷群の中にあって、市指定の文化財としての景観を構成しておりますイヌマキであります。木が枯れて、葉が茶色になれば、観光にも大きな影響があります。危機感を持っての対応を再度お願いいたします。イヌマキに成り代わって、訴えさせていただきます。
次に、麓を中心として引き継がれている侍スピリッツ、精神文化になりますが、それを体験していただこうという側面を持つ出水麓サムライプロジェクトですが、計画書の写しを拝見させていただきました。非常に多方面にわたり多くのサポートが必要だというふうに感じております。
それから、麓地区に関して、最後の項目の子供たちの安全に関わる問題なんですが、事故が起きてからでは何もなりません。ぜひ、学校だけでの問題ではなく、関係部署の連携した全市にわたる問題として御検討くださるようお願いいたします。
以上、3点に関し、答弁できればお願いいたします。
○椎木伸一市長 イヌマキに代わってお話がありましたキオビエダシャクの件でございます。
おっしゃるように麓地区は伝建地域でありまして、ほかの麓というか武家屋敷群と違うところは、非常に樹齢の長いというか大木が残されているという点に非常に特徴的なものがあると考えておりまして、そういった中でこのイヌマキを保存していくことは、我々の一つの仕事でもあるというふうに考えておりますので、今後、非常に高木ということで散布もしにくい状況等がありますので、その辺をどうやったらいいのか検討をしていきたい。
それから、先ほど申しましたように、上限につきまして2万円ということで2回までとなっておりますけれども、地域によっては非常に広範囲な集落もございます。しかも、イヌマキが多い集落もございます。そういったことも勘案しながら、上限についても検討していきたいと。上限回数ですか、検討していきたいと思っているところであります。
それから、サムライプロジェクトにつきましても、大変民間のほうで積極的に市の振興発展のために御尽力いただいている事業だと認識しております。できる限りのサポートをしながら、申請がうまくいくように、まずは取り組んで、その後市のほうでも助成をするようになっておりますので、その辺についても積極的に対応していきたいと考えております。
それから、子供の交通安全の関係で、出水小学校の門の所のお話でよろしいんですかね。あそこについては、階段からすぐ歩道になりますので、以前から非常に危ないと思っておりました。ですから、階段から歩道に出たときに、車道との間に何か景観にふさわしいような防護柵のようなものができないか、今後検討をしていきたいというふうに考えます。
○5番(北御門伸彦議員) ひとつよろしくお願いいたします。
書画カメラ1をお願いいたします。(議場内ディスプレーへの資料表示)これは、地元の郷土史家の故田島先生と私の父が携わった明治・大正・昭和の時代の写真を集めた写真集です。こちらに現物がありますが、カバーを映していまして、こういうもので、中はいろいろ分類されております。
書画カメラ2をお願いいたします。(議場内ディスプレーへの資料表示)市長、これ見られたことはあるでしょうか。大幟楽という大変珍しい郷土芸能です。この中にあるわけですが、私も定かではないんですけれども、1回見たような記憶があります。
書画カメラ3をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)これは、教育委員会が昭和61年に発行した出水の生活全書という本ですが、この第3章の芸能に、次のように大幟のことについて記載があります。種子島楽や小幟楽は出水特有の踊りではないが、大幟楽はほかに類例のない郷土芸能といえると。要するに、ほかにはないかもしれないということなんですが、こののぼり丈の長さは13メートル、太鼓が人より高いところにありますので、13メートル、本当は大きくて補助がないと踊れないんですが、もう一度見てみたいと思う郷土芸能なんです。まずは、保存活動が大変大事かと思うのですが、例えば過去の踊り手だった方からの聞き取りとか、映像の収集など検討できないか、まずお尋ねいたします。
○春田和彦商工観光部長 ただいま御紹介がありました大幟楽につきましてでございますけれども、この映像とか資料は、今市には残っていない状況でございます。
平成16年に発行されました出水郷土史によりますと、先ほど紹介があったかもしれませんが、大幟楽については宇都野々、折尾野、君名川、軸谷などの地区で踊られていたという記載がございます。今、このことについては、その資料によりますと昭和39年の市政施行10周年のときに踊られたのが最後ということで、記録として残っていないということでございます。
○5番(北御門伸彦議員) 保存活動を定例的に行わないとなくなってしまうのが郷土芸能だと思います。麓には種子島楽のほかに伝承されている昔の行事として、児請(ちごもうし)がありますけれども、これは麓祭の中で復活して伝承してまいりましたが、ここ5年ほど祭りもできていませんので、あるいはまた少子高齢化社会でありまして、マンパワー的にも金銭的にも非常に難しい状況になっています。
これは、聞いた話なんですけれども、伝承される方の意識を高める方法として、お金はさほどかからないんですが、認証というのか認定というのか分からないですが、「あなたはこの郷土芸能の伝承者として認定します」とお墨付き。例えば紙1枚でも発行して登録することによって、子供たちだったり、あるいは大人の方、モチベーションが向上するという方法も現にあるそうです。
市として、保存伝承をしていきたい文化財を、そのような方法でサポートできないのか、お尋ねいたします。
○椎木伸一市長 今、北御門議員が御披瀝されました制度等も、非常に有効ではないかなというふうに感じたところです。
現在、今回ラムサール条約に登録されて、祝賀会というか式典を1月の末のほうに延期しておりますけれども、蕨島小学校のほうで新地節、いわゆる干拓当時のそういった踊り等を披露してもらうようにしておりまして、保存会の皆さんが運動会に向けて指導してくださったものでございます。それとか、江内の山田楽もPTAの方々が中心になって、子供たちに伝承をずっとされているところでございます。
そういった子供たちにつないでいくということも非常に重要なことだと思っておりますし、いろんな仕組みづくりがあると思いますので、保存に向けてそういった取組を検討していきたいと思いますし、また平成23年ごろでしたか、いろんな郷土芸能を保存しなければならないということ、記録保存しなければならないということで、当時映像に残した記憶がございますので、そういったものの活用も含めて今後できるだけなくならないような努力をしていきたいと思っております。
○5番(北御門伸彦議員) 力強い答弁、ありがとうございました。
ひと工夫しながら、子供たちも巻き込んでモチベーションを上げて、保存活動が進んでいったらいいなと思います。
書画カメラ4をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)これまで、10冊発刊されたと思うのですが、戦争体験談集、これをまとめてこられたことは大変大事なことだと評価したいと思います。記憶を風化させてはならないと思います。また、この本がもっと活用されることを望んでいるわけですが、書画カメラ5をお願いいたします。(議場内ディスプレーへの資料表示)
最初、紹介した写真集の中ですが、恐らく戦後間もなくだったと思うんですが、航空隊跡の上から撮った航空写真だというふうに思います。今では、この飛行場があったとはなかなかイメージできないところなんですが、知るところでは、戦争遺跡はあちこちにまだ残されております。出水市平和学習ガイドの会では、先日、整備されていない掩体ごうの清掃活動をされたと聞いておりますが、その方々はまた文化祭の中でも資料などを展示されておりました。
会の方からの要望をお伝えいたします。書画カメラ6をお願いいたします(議場内ディスプレーへの資料表示)これは麓の堅馬場公園に設置されている観光ボランティアガイドの詰所です。修学旅行や市内の学校の平和学習で、例えば先ほど出たかと思うんですが、特攻碑公園あるいは掩体ごうでガイドの方が案内する場合、平和学習ガイドの皆さんには、その詰所がありません。資料や史料、遺物ですね、そういうものをたくさんもっていらっしゃるわけなんですが、それらを収納するばかりでなく、こんな寒いときなんかは退避場所にもなるほか、ガイドの会の活動拠点としても使えると思うんですが、市の対応をお尋ねいたします。
○春田和彦商工観光部長 平和学習ガイドの会の方から詰所の設置について、詰所というか資料の置き場ということも含めての要望があったということでございますけれども、我々としましても、今そのことをお聞きしましたので、また会の皆様にその現状等について直接話を聞いた上で、検討してまいりたいと考えております。
○5番(北御門伸彦議員) 先ほど来、出ていますように、ラムサール条約登録ということで、拠点はクレインパークを使ったり、ツル観察センターを使ったりして、環境学習はしっかりできる状況かと思いますし、歴史の学習をしようとすれば、麓日本遺産に認定されたということもあり、麓歴史館という拠点があります。平和学習をするとなると、今の時点では戦争遺跡をまわるということになるんですが、段階的にでもいいと思うんですけれども、詰所を、ちょっとしたスペースですが設置していただいて、理想なんですけれども、世界に訴えることができる平和学習の拠点も市長に考えていただきたいと思うところです。
鹿屋市の話もちょっと聞いたんですけれども、戦争遺跡を市の指定文化財にしたりですね、その広報紙も毎年1回は平和について特集を組むとか、そういったことをやっているようです。ぜひ、出水市でもこの平和学習ということに、学校だけではなくて力を入れていただきたいと思います。
次に、文化活動についての質問です。文化の定義というのは非常に広範囲にわたりますが、今回は主に行政が関与する部分について、話を進めたいと考えます。
このコロナ禍の中で、ドイツのグリュッタース文化相が言った言葉なんですが、「文化はよき時代においてのみ享受されるぜいたく品ではない、と認識している。」と発言された上に、フリーランス芸術家への無制限の支援に言及されたことに関して、本当に文化度が高い国、ドイツだなと心に残りました。文化度という表現については、例えばですがネットに、良い映画を見て感動すること、すばらしい本を読んで視野が広がること、それだけで文化度が上がるというようなことも記載がありましたが、コロナ禍の中で癒しにもなる文化活動について、教育長はどのような感想をお持ちか、またこの出水地方の地方文化というものに関して、ちょっと難しい聞き方かもしれませんが、どういう感想を持っていらっしゃるか御答弁いただければ幸いです。
○大久保哲志教育長 今申されたように、文化活動が心の癒しになるというあたりもありましたけれども、やはり心の豊かさが、・・・(声、不鮮明)・・・そういった感性とかを磨く意味では、こういった文化活動に触れる、あるいは体験するというのは、非常に大事なことだと捉えております。
先ほど、答弁の中でも申しましたように、伝統文化親子体験フェスタを開催して、その中で4つの部門で・・・(声、不鮮明)・・・しましたけれども、やはり子供たちだけで参加するのではなくて、こうやって親子で参加するといったのは、先ほど読書活動の中でもちょっとありましたけれども、大人も一緒になってそういった文化活動というのは、今後も計画していく必要があるのかなというふうに思っております。
そしてまた、地方の文化というのも、これも例えば踊りの話がちょっとありましたけれども、・・・(声、不鮮明)・・・伝えないとなくなっていくものも数多くありますので、体育祭などで今例えば踊りをやっているのもあったりと・・・(声、不鮮明)・・・。失礼しました。ボタンが押されていました。地方文化は、結局子供たちは知らずに町を出て行ってしまうと。私も高校3年まで、この出水市で育ったわけですけれども、地元の文化活動に触れる機会がさほどなかったからかもしれませんけれども、ここにきていろんな文化活動があることを知りました。やはり、そういう意味では様々な文化活動に子供たちが触れる機会というのも、今後作っていく必要があるのではないかと思っております。
○5番(北御門伸彦議員) 文化活動というのも、本当に範囲が広いんですけれども、例えばお隣の長島町は県内でも数か所しかないと思うんですが、劇団四季とつながりを持っています。それから、だいぶ以前なんですけれども、旧高尾野町では九州交響楽団とつながりを持っていたですね。交流会に、私もなぜか参加した記憶が10年以上前だと思うんですけれども、あります。出水の自主文化事業の中で、最近、交響楽団というのはほとんど呼ばれていない。学校にはもしかしたら行っているのかもしれないんですけれども、そういったひとつのつながり、地方独特のものを大事にしていただいて、さらに子供たちの情操教育に役立てていただければというふうに思うところです。
では、書画カメラ7をお願いいたします。(議場内ディスプレーへの資料表示)これは、先日ツル観察センターでたまたま偶然、市長にもお会いいたしましたが、観察センターの2階から撮った写真です。これに一つはツルが飛んでいるのが重なれば、本当は二重の虹で上のほうが消えてしまっているんですけれども、恐らくうまく撮れたら、市のポスターに使ってもらえたのかなと思うんですが、言いたいことは、現在開催中のクレインパークの企画展、湿地の写真コンテストというものを開催していただいておりますが、ツル及びその生息環境を取り扱った写真コンテストを毎年継続して実施していただけないか、考えているところです。
例えば、お隣阿久根市では、23回目となる阿久根洋画展が開催されて、その作品が出水市の文化祭にも出されておりました。また、これは副賞は20万円だそうですけれども、長島町ではもう御存じのように、2年に1回長島造形美術展というものが観光でも多くの方を集めてきております。出水市では、過去ですね、私も聞いた記憶があるんですけれども、例えばツルの造形展、そういうものが考えられないかという相談が市に上ったこともあったと思うんですけれども、定例的な写真展あるいは美術展が検討できないか、お尋ねいたします。
○椎木伸一市長 ラムサールの関係で湿地の写真コンテストを今年初めて、ラムサールを目指してと、登録を目指してということでやりまして、63点の応募がありました。非常にすばらしい写真ばかりで、来年度も継続して実施してまいる予定でございます。地元出身の有名な写真家で斎藤巧一郎さんという方がいらっしゃって、審査をお願いしましたけれども、意欲を示していらっしゃいましたので、一緒にやっていきましょうということで話をしております。
それから、私もかねてから屋根付き広場の活用についての一つの案として、この郷土芸能を披露する場としても活用したいと思っておりますし、また霧島のほうで毎年あります霧島国際音楽祭、こういった継続的に文化度の高いといいますか、つくり上げていくのが一番いいわけですけれども、何か定期的にできるようなものが、屋根付き市民広場を活用してできないものか。そして、そういったものを活用して、文化の水準を市民の皆様に味わってもらうというような思いがありますので、今後屋根付き広場ができました暁には、そういったことも含めて考えていきたいと思っております。
○5番(北御門伸彦議員) 力強い、いろいろ取組を提案いただきましたが、ぜひ市が文化に関与して、文化度の高いまちをつくっていっていただきたいと希望いたします。
次に、読書活動についての質問ですが、確かに15年やってきた中で、名誉ある表彰とかいろいろ受けているんですが、私自身がなかなか身近に感じにくいという、先ほど教育長が言われたように大人へのアプローチというのが非常に難しいのかなと思うんですが、読書活動について、なかなか教育分野の評価として難しいものだというのは認識しているんですけれども、でもできるだけ実績を把握して、ステップアップするためのヒントを探る必要があると思っています。
また、以前より言われていた図書情報館というものがあります。図書館の名前がちょっと変わった部分があるんでしょうけれども、私も正確には把握していないんですが、そういった名称が付いた図書館があります。恐らく、時代の流れを意識してできている、例えば映像がちゃんと見れるようなものとかですね。現在、読書の形自体も、教育長御存じのように電子ブックですね、普及してきております。そういったことで、図書館の在り方というのも変化しないといけないと思うわけです。もちろん、ニーズも変化していきますので、現時点で実際に読書活動の拠点の一つになる図書館について、運営を担当している指定管理者、全国で展開されていますので、いろんな提案もあろうかと思うんですが、そういったことを参考に、図書館の時代のこれからの流れ、それについてお考え方があれば御披露いただきたいと思います。
○大久保哲志教育長 図書館における時代の流れで変化する観点をどのように捉えているかということでございますけれども、時代の流れで変化する観点としましては現在のコロナ禍にありまして、この非来館型サービスへの期待というものが高まっているのではないかと。図書館のデジタル化が進んで、電子図書館でありましたり、デジタルアーカイブ、オンラインデータベース等の必要性の高まりというものがあるのではないかというふうに、そこは理解しております。
ただ、私はそこの部分はもちろん理解しておりますので、今後、そういったことも考えていく必要があるとは思っておりますけれども、ただ、やはり読書というものは紙媒体の書籍というものにはページをめくる楽しさでありましたり、好奇心への問いかけ、それから情報を理解しやすいといった、そういったよさも多くあります。
したがって今後は電子書籍の導入等も検討しつつも、紙媒体のよさに感じられるような図書館にして、実際に本を手に取る、親子で一緒に本に親しむ、そんな姿を変わらず大切にしていきたいと、そのように考えております。
○5番(北御門伸彦議員) 教育長が深く理解していただいているということが、ちょっとかいま見れまして非常に期待したいところであります。
中央図書館もだいぶ古くなってまいりました。市政旧出水市の20周年か30周年の建物だったかと思うんですけれども、そういったことも視野に読書活動日本一にふさわしいソフト、ハード、整えていっていただきたいと思います。
次に、最後の大項目になりますが、最低限の優先順位といわれる「衣食住」について、衣類の衣を医療に変えて質問しましたが、話を戻しますと、10年前の東日本大震災で被災し、津波に流されるも一命を取り留めた方々の話では、濡れた衣服を着替え、暖を取るのがまず第一だったと。そして、命を守る順番そのものが「衣食住」になっていたということらしいです。注目すべき指摘だろうと思います。人間が生きていく中で「衣食住」の順番で災害から身も守っていったということになるようです。
また、本来的な意味を見直すと、「衣」は「まとう」という段階、「食」とは維持成長の段階、「住」とは確立する段階であり、自己確立するための三段階と言われる方もいらっしゃいます。ちょっと引用としていいのか分からないんですけど、お隣の熊本県の歌手、水前寺清子の歌に「ぼろは着てても心は錦」というフレーズがありますが、私が思うには、心が美しく強い人は着ているものではなく、その人からにじみ出る雰囲気から人物が分かるんじゃないかというふうに、勝手に思っております。つまり、私のもう一つの自己解釈では、この「衣食住」の「衣」は着るものではなく、その人物が身につけている雰囲気。ま、心の着物じゃないかとか勝手に思うところです。
自分を律する精神文化、侍スピリッツですね、これは出水では御存じのように出水兵児修養掟として伝承されてきております。大事にしたい精神文化じゃないかと思います。自己主張を相手に強く押しつけるのではなく、平和を基調とした議論をしたいもので、世界平和につながっていく観点だと思います。
脱線いたしましたけれども、医療体制は大事な生活基盤で、話を戻しますと日本医師会がネット上に地域医療システムとしてデータなどを掲載しております。このことは事前にお伝えしましたが、当局としてそれを見て、どんなふうに感じられたかお伺いしたいと思います。
○冨永栄二保健福祉部長 議員のほうから日本医師会が作成しています地域医療情報システム、一応見させていただきました。中身的にはいろいろな国勢調査の人口とかいろいろな情報を基に作成をしているようでございます。中身的にもう少し詳しく見ないと、この情報といいますか、この数値が私どもといいますか県が持っている数値と見比べないと、動向というのが言えないと思います。今後、このシステムをまた勉強させていただければと思っているところでございます。
○5番(北御門伸彦議員) その中の診療科に関わる部分をちょっと見ていただいて感想がないかということで、今お尋ねしていたんですが、決してこれは私だけの判断ですので、全てがこういうことではないと思いますが、この出水医療圏で単純には比較できないと思うんですが、診療科の施設数だけの部分ですね、全国平均の5割に達していないのが一つありまして、これが皮膚科系ですね、皮膚科系の診療所がやっぱり足りない。ちょっと不思議だったんですけれども、その次が眼科系で全国平均の約55%、続いて精神科系、小児科系というふうに全国平均より低いものが出ています。もちろん、これだけでは単純に分析できないと思うんですが、もちろん地域独自の傾向もあると思いますので。そういったものを不足する診療科を総合医療センターだけが解決できるものじゃないと思うのですが、そういったものも分析の一つとしてお使いいただきたいと思います。
次に食について、お尋ねしたいと思うんですが、食料安全保障にもつながっていくと思うのですが、食料自給率に関し、少し話をしたいと思います。自給率については、難しい判断があると認識しております。その全体的な話、国の話でいっても国際的に採用しているのが非常に少ないカロリーベースで日本は出しております。先ほど御披露があったと思いますけれども、38%ですね。重量ベースでは65%、生産額ベースでは66%と、非常に難解なものです。ただ、先進国ではこの食料自給率というものに対しては、生産額ベースが主だと思うんですが、改善がなされてきているというのが実情で、日本は相対的に海外依存が高く、改善すべきところがたくさんあるかなと認識しております。また、農業全般の切り口というのは非常にたくさんあって、今いわれているスマート農業に限らず多くの変革が望まれる分野だと思います。
ここで、私にとって恒例になりつつある本の紹介をいたします。書画カメラ8をお願いいたします。(議場内ディスプレーへの資料表示)ちょっと下が変なふうになっていますが、これは著者は農業関係者でない弁護士をされている方で、非常に緻密に分析して、様々な切り口、例えば第一章が日本の国際的ランキングと食文化ということで、第二章はグローバル経済で見る日本の食と農業など、全十章にわたって未来を見据えて、テーマとして食と農業を取り巻く環境を知り、現在と将来をどうすべきか考える、できることをするとして、著述されております。例えば地産地消を進めるということは、地元への食料依存度が高くなるわけで、地元に金がおちるメリットがあるというふうに考えますが、あるいはまた食品ロスを抑える効果も出てくる。地元の市場に出せない野菜とか、そういったものを使えるわけですので。この著者の松田さんという方ですが、テーマとして「できることをするべき」と言われております。様々な情報とアイデアを示しておられて、そのほか文化・教育・観光・気候変動などの切り口も合わせて解説してあります。まだ熟読しておりませんが、出水の基幹の産業である農業については、大変多くの課題があろうと思います。今回、ほんの一部の課題、食料自給率だけを取ってお話をしましたが、何が言いたいのかというと、またどんな答弁を求めているかといいますと、当局も大変困惑するかと思うんですけれども、市長の食料自給率に対する考え方をちょっと御披露いただければと思います。
○椎木伸一市長 北御門議員がおっしゃるように、非常に難しい問題だと思っております。食料自給率はやはり国をなす以上は、できるだけ高いことが望ましいというふうに考えております。カロリーベース、重量ベースとかいろいろあるんでしょうけれども、基本的に自国で賄えるのが一番すばらしいことだというふうには思っておりますけれども、その中でも食の質ですね。食の質についても、安心・安全なものを求める傾向が最近高くなってきているのかなという思いはしておりまして、安心・安全な食料自給率というようなことが、今後求められていくのではないかというふうに考えております。
○5番(北御門伸彦議員) 読み間違えまして、あと1分しかありません。
住について、簡単に申し上げたいと思いますが、書画カメラをお願いいたします。(議場内ディスプレーへの資料表示)今回、資料請求をさせていただいて、初めてこういうのがあるのというふうに気がついて、勉強不足で申し訳ないのですが、平成25年作成で目標年次が2020年となっている出水市住生活基本計画、旧出水市の住宅マスタープランがベースになっているんですがこれが政策や議論のベースになっていくと思いますので、新しい計画の今後の対応をお願いしたいと思います。間もなく2022年へ突入しますが、オミクロン株に置き換わるという可能性もあって、乳幼児も感染する可能性があります。長いスパンでウイルスと戦っていかないといけないと思いますが、楽しみな戦いもあります。出水中央高校の男子駅伝部の全国大会出場です。本当に明るい話題で、テレビ観戦を楽しみにして、新年を迎えたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
○議長(杉本尚喜議員) 以上で、本日の一般質問を終結いたします。
-------------------------------------------------------
△ 延 会
○議長(杉本尚喜議員) お諮りいたします。本日の会議はこれで延会したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(杉本尚喜議員) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会いたします。
第3日の会議は、明日10日に開きます。御苦労様でした。
午後5時51分 延 会
-------------------------------------------------------
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
出水市議会議長
出水市議会議員
出水市議会議員
出水市議会議員
- 99 -