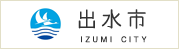令和3年出水市議会第1回定例会会議録第4号
-------------------------------------------------------
令和3年3月9日
-------------------------------------------------------
会議の場所 出水市議会議場
-------------------------------------------------------
出席議員 19名
2番 橋 口 住 眞 議員
3番 上須田 清 議員
4番 日 髙 信 一 議員
5番 北御門 伸 彦 議員
6番 枦 山 卓 二 議員
7番 吉 元 勇 議員
8番 土 屋 工 吉 議員
9番 鶴 田 均 議員
10番 田 上 真由美 議員
11番 杉 本 尚 喜 議員
12番 出 水 睦 雄 議員
13番 鶴 田 悌次郎 議員
14番 中 嶋 敏 子 議員
15番 宮 田 幸 一 議員
16番 道 上 正 己 議員
17番 榎 園 隆 議員
18番 垣 内 雄 一 議員
19番 築 地 孝 一 議員
20番 髙 崎 正 風 議員
-------------------------------------------------------
欠席議員 1名
1番 南 鶴 洋 志 議員
-------------------------------------------------------
地方自治法第121条の規定による出席者
椎 木 伸 一 市長
吉 田 定 男 副市長
冨 田 忍 政策経営部長
山 元 周 作 総務課長
中 原 貴 浩 総務課職員係長
駒 壽 ひとみ くらし安心課課長補佐兼コミュニティ推進係長(健康増進課新型コロナウイルスワクチン接種対策室室長補佐(課長補佐級))
宮 﨑 毅 財政課長
大 田 直 子 財政課課長補佐兼財政係長
松 岡 秀 和 企画政策課長
青 﨑 譲 二 企画政策課課長補佐兼総合政策係長
宗 像 完 治 企画政策課秘書監(課長補佐)
川 畑 正 樹 企画政策課課長補佐兼行政改革係長
冨 永 栄 二 保健福祉部長
佐 藤 義 明 健康増進課長(健康増進課新型コロナウイルスワクチン接種対策室長(課長級))
園 屋 治 健康増進課新型コロナウイルスワクチン接種対策室次長(係長級)
揚 松 智 幸 市民部長
谷 川 弘 之 生活環境課長
中 園 健 二 生活環境課生活環境係長
春 田 和 彦 産業振興部長
東 畠 賢 一 農林水産統括監(参与、農林水産整備課長事務取扱)
酒 本 祐 喜 農林水産整備課技術主幹兼基盤整備係長
小 原 一 郎 建設部長
江川野 誠 一 都市計画課長
澤 田 誠 一 都市計画課技監(参事、都市計画課建築係長事務取扱)
高 見 勇 吉 都市計画課課長補佐兼計画管理係長
山 村 祐一郎 道路河川課長
松 尾 善 博 道路河川課管理係長
永 山 勝 久 道路河川課課長補佐兼建設第一係長
松 木 健 治 道路河川課課長補佐兼建設第二係長
池 田 幸 弘 高尾野支所長
山 口 徹 野田支所長
鮫 島 幸 二 病院事業管理者
髙 橋 正 一 出水総合医療センター事務部長
﨑 迫 真 也 出水総合医療センター総務課長
大 平 伸 章 消防長
溝 口 省 三 教育長
溝 口 雄 二 教育部長
-------------------------------------------------------
議会事務局
畠 山 義 昭 局長
華 野 順 一 次長(課長補佐級)
浦 﨑 紀 光 主任主査
中 村 勇 士 主査
野 﨑 育 美 主査
-------------------------------------------------------
付議した事件
一般質問
午前10時00分 開 会
△ 開 議
○議長(杉本尚喜議員) おはようございます。ただいまの出席議員は19名であり、定足数に達しております。これより令和3年出水市議会第1回定例会第4日の会議を開きます。
-------------------------------------------------------
△ 議員の欠席の届出
○議長(杉本尚喜議員) 南鶴洋志議員から本日の会議に欠席する旨の届出が出ております。
-------------------------------------------------------
△ 議 事
○議長(杉本尚喜議員) これより議事日程により、議事を進めます。
-------------------------------------------------------
△ 日程第1一般質問 上程
○議長(杉本尚喜議員) 日程第1、一般質問を議題といたします。
これより、昨日に引き続き一般質問を続行いたします。
質問順に従い、道上正己議員の質問を許します。
○16番(道上正己議員) おはようございます。一般質問3日目の朝一番、道上正己でございます。
新型コロナウイルス感染症国内発生後、1年が経過しようとする中、国・県・出水市それぞれ売上減少のある企業、商工業、農林水産業に支援金などを支給されましたこと、誠にありがたく感謝申し上げたい次第でございます。が、しかし、実情は長引くコロナ禍の中で、日々経営が悪化しているとお聞きしているところでございます。それぞれの経営者の皆様、悲痛な思いを訴えていることもお聞きしている状況であります。
また、一方、企業努力、コロナ禍の中で新たな商法を取り入れ何とか生き延びようとしている企業もあります。また、経営者の方もおられます。そういった方々がそれぞれコロナ禍の中で生活をしながら経済活性化を望んでいられると思います。一日も早い生活環境が帰ってくることを願うばかりであります。
それでは、通告に従いまして、質問をさせていただきます。
屋根付き市民ふれあい広場整備事業についてであります。
令和2年3月定例会におきまして上程された議案が、今回、9か月目に本定例会に提案されることになっております。それぞれの機関におきまして、イベント事業再構築検討会を立ち上げられて5回ほどの会議を重ねられて、今回、ある程度、前回、議員の意見も出されたわけでありますので、その中で検討された結果、今定例会に上程されるということであります。でも、中身については、全員協議会でもある程度の御報告は受けましたけれども、それぞれ再度お尋ねしてみたいと思っております。
屋根付き市民ふれあい広場整備事業は、イベント事業再構築検討会で協議されたと思いますが、メンバーは何名で、どのような方々だったのか、お聞かせ願いたいと思います。
2番目に、建設場所等については、どのような御意見が出されたのか。出た御意見は漏れなく御報告、お知らせいただければと思っております。
3番目に、利用については、市民に幅広く利用してほしいとの市長のいつものお言葉であります。私は常々思っておりますけれども、市民向け内需型、外需、外向きの施設、それぞれ必要な整備であると思っております。両方を兼ね備えた施設整備、利用できる場所など検討をされたのか、お伺いしたいと思います。
4番目に、建設については、市民の希望、意向が強ければ「屋根付き市民ふれあい広場整備事業税」それぞれ税にはいろんな税があると思います。創設し、事業を実施することは考えられないかということについて、1回目の質問を終わります。
○椎木伸一市長 おはようございます。道上正己議員の御質問にお答えいたします。
まず、屋根付き市民ふれあい広場整備事業について、基本構想策定に係るイベント事業再構築検討会についてですが、関係団体やイベントの協賛者、専門家、イベント参加者、公募委員など、幅広い市民の方々20人に参加していただき、御披瀝のとおり、5回にわたって御意見をいただきました。団体名は、後ほど政策経営部長から答弁をさせます。
次に建設場所についてですが、検討会では、総合運動公園芝生広場が駐車場の確保等を考えれば適地であるとの意見をいただきました。また、施設に求める機能については、災害時に活用できる機能についての意見を多くいただきました。
次に、広場を利用した交流人口の拡大についてですが、天候の影響を受けないメリットを生かして、これまでなかった大規模なイベントやスポーツ合宿などにより、市外からの誘客が見込めると考えております。
次に、広場整備のための目的税の創設についてでありますが、制度上、法定外目的税を創設することは可能ですが、本事業については、国の補助金の内示もいただきましたので、財源については国の補助金や企業版ふるさと納税等を活用してまいりたいと考えております。
○冨田忍政策経営部長 私のほうから検討会の構成団体等についてお答えいたします。
出水商工会議所、鶴の町商工会、出水市観光協会、出水市特産品協会、出水市飲食業組合、鹿児島県ホテル旅館生活衛生同業組合、高尾野青年団、野田青年団、さつま出水青年会議所、イズミライプロジェクト、出水市自治会連合会、ただいまの11団体が関係団体としてお願いをした構成員でございます。そのほか、イベントの協賛者として、鶴翔祭協賛者、たかおの夏祭りの協賛者、野田郷夏祭りの協賛者、3名でございます。専門家として意見をお伺いしようとして任命をしておりますのが、税理士、社会保険労務士の方お二人、イベント参加者として、出水商業高校生、あと子育て支援室の利用者の方、そのほか公募委員としてお二人の合計20人の方でございます。
○16番(道上正己議員) ありがとうございました。それぞれいつもいろんな検討会といいますか、市の中における事業については、先ほど申し述べられた方々が常に入っているという状況であると思います。
そこで、出水市には、地域協力隊の方がいらっしゃいますけれども、これはもうよそから来て、出水市を何とか盛り上げようという位置づけかと思うんですが、その方々の御検討というのは全くなかったのか。そこら辺との関係についてはどのようなお考えをお持ちなのか、お聞かせ願いたいと思います。
○冨田忍政策経営部長 地域おこし協力隊のみなさんのことかと思います。地域おこし協力隊の皆さんには、今それぞれ特産品の開発でありますとか、観光振興の関係で御尽力をいただいております。今回の検討会の中にはですね、入っていただいておりません。検討したかということであればですね、そこの部分は検討していないところでございます。市民の方々にということでお願いをしてあります。
○16番(道上正己議員) せっかくですね、出水市を盛り上げようという形でそれぞれ希望を持って出水市で生涯過ごそうかという関係の方々と思うんですが、できることならですね、やっぱり外部の意見としては、直接、他県、よそから見えられた方々の感覚、感性、そういうものも生かすべきではなかったかなというふうに思っているところであります。それができなかったということであれば、今後それぞれですね、最後の最後まで直接関係者でなくても、何とか出水市を盛り上げようというお考えでこっちに、出水市にいらっしゃる方々の御意見というものもですね、大事に伺っていってほしいというふうに思います。
そこで、税理士さんと社会保険労務士さんも加わっていただいたということであります。税理士さん、専門家といいますか、地域経済それぞれ出水市がどういうふうな事業でどういう形で流れているかという、一般的に考えれば私はそういうふうに思うんですが、どういうお考えで税理士さん、社会保険労務士さんをこのメンバーの中に入れて検討会を開いたのか、お聞かせ願いたいと思います。
○松岡秀和企画政策課長 今、議員からもございましたとおり、その経済的な立場、それから、社会保険労務士の方については、イベントの再構築のほうでもちょっと関係をしてきますが、各種イベントにそれぞれ人が出られる中で、保険労務と言いますか、その観点からも御意見をいただければというふうに考えて、選任をさせていただきました。幅広い御意見をお持ちかと思いますので、いろいろな場面で有益な御意見がいただけると思ってお願いをしたところです。
○16番(道上正己議員) それぞれ御意見を出していただくためにそういう選抜といいますか、こっちからお願いして、前向きな検討とか、出水市活性化のためにはどういう方向づけがいいとか、御意見を出していただくことだと思うんですが、なかなか経験もありますが、出ていけば言いたいこともといいますかね、それぞれ発言できないというときもあります。でも、せっかく皆さん方が6月定例会で出された案件を再度検討する意味で5回も重ねられて、今回出されたわけですが、そうしてみればですね、せっかくイベント事業再構築等検討会ということで、私はこの屋根付き市民ふれあい広場整備事業等のですね、管理がちょっと小さすぎるんじゃないかと。あまり大きな検討会といいますか、屋根付き広場とのどうするかという、議論をする場において、イベント再構築という検討会の名前からして、ちょっと重みが足らないのじゃないかなという気はするんですが、これはもう出たあとの結果論なんですけれども、もうちょっと屋根付き広場に関した将来の出水市を考えた立場のどうすればいいかという検討会というか、協議会なりできなかったのか。そこのところをちょっとお伺いしたいと思います。
○松岡秀和企画政策課長 当初はそこも検討いたしましたが、かなりの関係者の方、かなりの部分が重なりがあると考えまして、会議をそれぞれするために、それぞれ委員をお願いするのも、関係者の方にも御負担があるのではないかというふうに考えて、同時にではございましたけれども、検討していただければというふうに考えてお願いをしたところでございます。
○16番(道上正己議員) 一番6月定例会で話になったのが、商工会議所主催の鶴翔祭ですね、花火の問題、屋根が大丈夫なのかとか、そんな中で議員の皆さん方もいろいろ御意見を出されてやられたわけです。その辺のところが、ちょっとこの検討会の中では会をする前に議員の方々からこういう御意見もあって再度検討委員会を開いて、屋根付き広場の建設に向けての会だという、お知らせがどっちだったのか分かりませんけれども、その流れの中でですね、造るということの前提であったのか。まあ検討の中ではどうしたほうがいいのかというところだったのか。一番市民の皆様方、今回、検討して重要なところだと思いますので、スタートのラインをお聞かせ願えばと思います。この検討委員会のですね。
○松岡秀和企画政策課長 まず、一番最初、検討をお願いする段階で、議会での流れも御説明をさせていただいて、基本構想の予算を提案をさせていただく段階で、市としてはぜひ造りたいと、造る方向で検討したいと思いますので御意見をいただけないでしょうかということで始めさせていただいております。おっしゃるとおり、そもそも造るべきなのかというような御意見が全くなかったわけではないですけども、最初のほう。ただ、協議をしていく中で、検討会としては、その造らないという方向には話としては行かずに、造るとすればよいものを造りたい。そのためには、こういう視点で考えてはどうかという御意見をいただいたと感じております。
○16番(道上正己議員) それぞれ検討会の委員の皆さんが5回ということで、それぞれ協議された結果だというふうに認識というか、思わないといけないと思います。過去2度ですね、建設場所等についてはどのような意見が出されたということなんですが、説明を受けた時に、これくらいの大きさで、その施設整備する場所が6か所ですかね、7か所ですかね、説明がありました。当てはまるのは、もう今のこうして挙がっている場所なんですよね。それが最適だと思うのか。もうちょっと縮小してどうなのか。もうちょっと大きくして別の場所を検討するのかというところもですね、議論の一部に上がるべきだと思うんですが、委員のメンバーから、検討のメンバーからですね。そういう意見はなかったのか。提案されたのをどうするという話で終わったのか、お聞かせ願いたいと思います。
○冨田忍政策経営部長 候補地の検討に当たってですね、まず、2回目の会議を開催をしたときにですね、委員の皆様からそれぞれ候補地としてどういったものがあるか御意見を伺いたいということで、お諮りをしたところ、具体的なものが示されずですね、まずは事務局のほうから検討材料になる候補地をあげて検討すべきではないかということでございました。その後、候補地をお示しをして、議論をしていただいたわけです。そこの細かい議論については、企画課長のほうに答弁をしてもらいます。
○松岡秀和企画政策課長 今、部長からございましたとおり、建設場所、まずは自由なところで御意見をいただこうと考えたところですが、その具体的にこの場所というのについては、検討会の中では提案がなく、事務局のほうで示してほしいということでしたので、そのあとコンサルのほうとも協議をしまして、利用者の交通アクセスとか、既存の公共施設等の連携を考慮しまして、あとイベントの開催状況、道路・鉄道等のインフラの整備状況、公共施設の分布状況等を勘案して、7か所を選定してそのさっきの検討会でお示しをいたしました。その検討会の中では、また、その先ほど議員が言われましたように、その面積を増やしたりだとか、それ以外の候補地についての御意見というか、御提案はなかったところです。芝生広場が適当ではないかということで選定をいただいたというところです。
○16番(道上正己議員) 出水市は人口5万4,000人と言われております。300平方キロメートルの中の5万、山林がほとんど占めているわけですけれども、紫尾山系の裾野に、こっちから行けば東出水、出水、西出水、高尾野、野田、この領域が出水市の範囲だと思います。人口密度からいけば、やっぱり出水、この辺りと言われております。でも、人口5万4,000、市長が言われる子育て、それぞれ雨天時でも高齢者それぞれスポーツ営める場所として設置したいということなんですが、私も商工会、青年部、それぞれ商工会関係をしながらイベント事業、関わりをもっていろんな施設整備、また、どういう方々を的を絞って来ていただくのか、集客するのか。もう幅広くやっていかないことには内需型だけではそれぞれ市民の利便性はあっても外需、経済的効果というものはそうは述べられないということも事実お聞きしたり、現地視察しても見ております。今、施設を造るところ、それぞれ指宿のほうでも今テレビ放送もして、それぞれマスコミ使って来てくださいということでやっております。隣の長島町も。出水市が今やろうとしている市営グラウンド、来年度は400メートルコース整備をやろうというふうにお聞きしております。その中で、ターゲットとしてどういう方々をとお聞きしますと、もうそろそろかかっているという、今まで来ていただいた方もいらっしゃるので、その方を通じて、その関係者を通して来ていただくための、今所管で努力している最中であるというふうにもお聞きしております。市内向け、子供・幼児向けということなんですけれども、また、ものすごい猛暑のときと、雨天時利用ということで、どうだろうかなと利用率についてですね。そしてまた、スポーツそれぞれできるということですが、それはさておきまして、スポーツと言えば、フットサルはできるというふうに説明を受けております。そのあと、グラウンドゴルフ、テニス、それぞれ各種スポーツはあるわけですが、その造るとする場合、野球のときのウォーミングアップ、キャッチボール、ちょっとしたことなど考えられるわけですけれども、本当にどういう施設なのか。造ったあとに、そういうことじゃなかったよねってということで、ただ市民憩いの場としての広場の位置づけなのか、明確な御答弁をお願いしたいと思います。
○椎木伸一市長 屋根付き広場の利用についてのお尋ねでありますけれども、私はですね、道上議員がおっしゃっていただいたように、幅広い年代の方に御利用いただきたいと思っておりまして、具体的には、子供たちの遊び場であったり、高齢者の健康増進のための場であったり、あるいは、市民全体の皆様の語らいの場であったり、高校生をはじめとする若者の交流の場、音楽を通しての交流の場であったり、あるいは、デイサービスや保育園の子供たちの遠足、花見等のですね、場であったりということ。それから、産業振興的に言えば、今テントを張ってやっております産業祭はじめ、いろんな大きなイベント、それから鶴翔祭、はじめ祭り、そして、今テイクアウトも一生懸命していただいておりますけども、カフェとかマルシェとかですね、そういった利用、いわゆるその市民の憩いの場というようなことでありますけれども、それプラス、先ほど御紹介いただきましたフットサルやグラウンドゴルフなどのスポーツ、そして、全協でも御説明しましたとおり、災害時の拠点ということでのボランティアセンターであったり、物資置場であったり、一時的な避難所であったりですね、そして、万が一の原発のときのいわゆるスクリーニングであったり、言い忘れましたけれども、今、修学旅行が中止をしている状況でありますけれども、再開しましたら、この場を使ってですね、この入村式をしたり、閉校式というんですかね、離村式をしたりというような場にも使えるというふうに思っておりまして、これまでにはないですね、地方創生のための総合的な拠点として、あるいは、万が一の災害時の対応拠点としてですね、市民の憩いの場、経済振興、交流促進、健康促進、災害時拠点というようなことで、多くの市民、あるいは市外の皆様に御利用いただける施設になるものというふうに思っております。
○16番(道上正己議員) スポーツができるっていいますか、それぞれ榎園議員も数年前といいますかね、毎回、高尾野にあるようなきらめきドームみたいな施設ができたらという話もあったんですが、ある程度それも兼ね備えられるのか、ちょっとそこあたりの答弁はなかったんですが、何かできるスポーツをお答え願いたいと思います。
○椎木伸一市長 ちょっと私も御紹介できなかったんですけれども、思いとしてはですね、合宿等のですね、今、先日まで西日本工業大学の硬式野球部も野球場に来ておりましたけれども、雨天時の練習場であるとかですね、そういったものにも使えますし、幅が70メートルほど、そして、縦が25メートルほどというようなことでございますので、その範囲内でですね、できるいろんなスポーツ、そして合宿の対応等もできればというふうには考えております。
○16番(道上正己議員) 今回、計画をされる事業というのは、類似施設といいますかね、いわば近くにクレインパーク、花公園、山手に行けば東光山、これまた景観整備しながら莫大な金を投資して、観光、地元の方、それぞれ来ていただきたいということなんですよね。どこまでどうしたときがどうなのかというのは、それは経済情勢とかそれぞれ鑑みながらやっていかないけないところもあると思うんですが、あまり施設、そういうものにですね、ちょっとかけすぎといいますか、既存のやつはやっぱり整備せないかん。プールとか陸上競技場ですね、野球場もまた新しくなったし、利用者もそうして増えてきているわけですけれども、本当で子育て、高齢者、スポーツ、あの場所と、場所を今度は言いますけれども、場所で、片や、今天気のいい穏やかな、春、秋、ときは、あの芝公園というところはものすごくお父さんたちは野球とか、テニスとかお母さんたちと来て応援したり、子供たちは走り回って遊んでいるという状況、そうであれば屋根付きであればなお最高じゃないかというお考えもあるでしょう。でもかぶりというのがあって、それぞれ施設。共同利用する施設というのは。だからそこのところをちょっと私は、今の会場、いろいろグラウンドゴルフすべてやっているような会場の中の芝生広場、あれは広大な場所として景観を整えた芝公園というので生かされたほうがいいんじゃないかなという気持ちがいっぱいです。そしてまた、あそこに野外のステージがあるということも、それは晴天のとき、使えるとき、夜間でも使う道、あそこに屋根をもっていかなくてもやれるというふうに思っています。どうしてもあの場所があるからあそこというふうに感じるところもあるし、そのほうがいいという方々もいらっしゃると思うんですが、そこのところは、市長としてもいろいろお考えだったろうと思うんですが、どういうお考えだったんでしょうか。やっぱりあれを生かしたほうが施設整備としてはいいというふうにお考えたんでしょうか。
○椎木伸一市長 屋外ステージについてはですね、以前、渋谷市長の時代に若者が気楽に交流できる場所を提供したいというような思いから、あそこに屋外ステージをですね、造られ、これまで夏祭り等々にですね、活用されてきた経緯がございます。場所はですね、先ほど松岡課長のほうから説明しましたとおり、いろんな御意見を求めながらやったわけでございまして、そこにあったからというわけではないというふうに認識しております。そもそも私があの場所にと思っていたわけでもございませんけれども、屋根付き広場をその思ったのはですね、芝生広場のほうがいいのではないかというような御意見ですけれども、もともと鹿児島市で生活している際に「かんまちあ」という施設が本港近くにできまして、ずっと見ておりますとですね、非常にこの幅広い年代層、夜までいろんな方々が活用して使っていらっしゃいます。そして、最近は災害にも対応されるというようなことも聞きました。そういう思いもあり、また、市長に就任してからも市民とのこの市長と語ろ会という対話集会でですね、子育て支援室にまいりましたときに、若いお母さまが、「出水はいいところだけれども、雨の日に子供を伸び伸びと遊ばせる場所がないというのが一番の悩みです」というようなお話も伺いました。そして、またその後にもいろんな方からそんな話を伺い、音楽の野外フェスをですね、民間の方に企画、実施していただきましたけれども、そのときにも、出演された関係者とか、企画・立案された方とか、お出での方とかですね、「雨天でも濡れないでできるような場所が出水もあればいいですね」というような話を聞きました。そうすると、新幹線駅でありますとか、あるいは、「今後、西回り自動車道もできますので、交流促進の場として大きく活用できますよね」という話を聞きましたので、私の独自の考えで御提案をさせていただいたところでございます。そういった中での場所の選定ということで、あそこにいろんな施設があったからとか、そういった既存のですね、概念というか、先入観はなく決めてもらったところでございます。
○16番(道上正己議員) ありがとうございます。今、市長のほうが新幹線東口、この間といいますか、東出水校区の皆さんからグラウンドゴルフを整備してほしいということで、あの一部、おれんじ鉄道の車庫のあそこの空き地を利用してやりたいというので、審査をいたしております。できることならその整備は難しいから緑の公園のところで使ってもいいですよというお話がありました。そのときに、道路挟んで隣り、民有地ですけれども、何とかしなくてはならないということで、あの土地を何とかするために、駐車貸付けをお断りするということで、その時、話が出て伺いました。いろいろ整備をする中で、私はやっぱり新幹線、やっぱりよそからこう受けるためには、いろんなイベント企画会社、世界にはいろんな企画会社があったり、地元にもイベント企画をされている方もいらっしゃいます。鹿児島、福岡、わざわざと言いますか、新幹線、車使って大阪、コンサートそれぞれ行っている若者もたくさんいます。休みのたびに行って、どこ行っとったのて言えば、いや、大阪、福岡、鹿児島という話を聞きます。であるならば、逆に一番私が言わせてもらえれば、やっぱり新幹線東口の活性化という位置づけでやってほしいなというふうに思っております。
そこでですね、私が最後に打ち出したのが、整備事業税、本当に出水市活性化、交流人口、ましては住んでみたい、利便性の高い出水市というところで定住促進、一体型と考えたときには、いいのじゃないかなと。だから、今回の場所というのは、それぞれ複合する施設もあって、競合するときには、駐車場整備についても質問もありましたけれども、何とか努力して片方は日程変更して使えるようなというふうな私受け止め方したんですが、果たしてそれでいいんだろうかと。できたおかげで、またそれぞれ利用する人たちに迷惑かけたりするんじゃないかということもあるんですが、これはもう民間の土地ですので、協議もかかったり、いろんなこともせないかんと思いますけれども、現在地の候補地あがってますけれども、改めてそういう御相談とかするお考えはないのか、お聞かせ願いたいと思います。
○椎木伸一市長 選定についてはですね、先般、全協で説明をさせていただいたとおりでございますけれども、新たに土地を求めての候補地というのは原則入れないということでの考えもございました。出水駅周辺、特に新幹線口のほうについては、民有地ということもありまして、いろんな経緯で我々も駐車場整備をしたり、あるいは、その御披瀝いただきましたグラウンドゴルフ場としての利用もですね、積極的に考えているところでございまして、何よりも今回の場所に選定したのは、その駐車場の関係でありますとか、ほかの公共施設との兼ね合い、新幹線駅との距離、そういったものを総合的に勘案して決められたというふうに考えております。
○16番(道上正己議員) 市長が言われたとおりですね、どっちにしてもその位置にあるというふうに思うんですよ。今のインターから、今度新しくできるインターですね。だからですね、この要件を満たすのはですね、本当民間の土地であるんですけど、最適なんですよね。何も弊害もない、問題も出ないというところで。これもし造ったときに、利用者の、まあやってみないと分からんことですので、これをやっぱり予見しながらやっぱり進めないことには、造った後に壊すわけもいかないし、造ったけれども利用する人が少ないじゃいけないわけですので、本当に市民が希望を持って、また要望されて造るという意思があればですね、今一つここを奮起して、やっぱり私は造るべきだと思います。だから造ったからいいということではなくて、投資ですけれども、これはもう長期的投資で5年なら5年、10年なら10年、土地代含め工事費、それぞれ住民税、固定資産税、どこから取るかはそれぞれですけれども、これはもう困っている人から税を取るわけにはいきませんので、できる限り、今までの市長が建設に向けての寄附とか申し上げました。そこにやっぱり賛同される方をどういう形で募るのか。そして、また造った後に、そういう方々が、賛同された方がどれだけ利用されてくれるのか。利用に当たっても情報をいただいたり、提携しながら活用、そして、また出水市に泊まっていただくとか、やっぱり一つのことが積み重ねていけばやっぱり10になり、20になり、100になりという、今の検討された場所ていうところは、可能性はあっても、そう飛躍するような私は形は望めないかというふうに思っております。それで、私も専門家じゃありませんけれども、専門家が人の流れ、物の流れ、だからそこら辺の関係需要を考えたときにどうなのというところをやっぱり行政職の皆さん方も含めてですね、出水市の繁栄のためであれば、市民もなんとはということは言わないと思いますけれども、改めてですね、そこら辺のところのお考えを示し、ちょっと時期的にはどうなるかわかりませんけれども、再度検討される余地はないのか、お伺いしたいと思います。
○椎木伸一市長 道上正己議員から新幹線口のほうのですね、民有地の活用等の御提案もいただいておりますけれども、私は、新たにこの土地まで求めてですね、というふうには考えておりませんし、また、先ほど説明したように、駐車場が既存のものがですね、野球場用でありますとか、多目的グラウンド用でありますとかですね、陸上競技場、文化会館等の駐車場がありますので、そことも連動して使えるわけですし、また、こないだ質問がありましたように、交通渋滞等が考えられますので、今回の整備の際にですね、それらも合わせてできれば対応していきたいというふうには考えております。
これまで、私は、ラムサール条約、それから麓地域の武家屋敷の活用、これらはですね、新たなものをつくるのではなくて、既存のもののいろいろなこのソフト面の対策をすることで、付加価値をつけて出水市のグレードをあげたい。あるいは、所得向上につなげたいというものがあります。
今回の屋根付きにつきましても、従来ある広場にいろんな人の方々の御意見からすると、あるいは、先般の災害対応で球磨村にあります「さくらドーム」というところが、非常にこの災害時に活用されておりましたけれども、それらを見るにつけですね、こういった付加価値を付けることでいろんなこの産業振興やいろんな地方創生のために役立つのではないかという思いがありまして、今のこの場所を選定していただいたところでありますので、改めて考え直すというところまでは考えておりませんで、この検討会で決めていただいたところに造りたいというふうに思っております。
○16番(道上正己議員) 市長が造りたいのも腹いっぱい、民間の土地まで求めてはできない。やっぱりここら辺のところがですね、政策的重い考え方、何でそうなったのっていうのもですね、民間まで求めてやらないということは、裏返せばといいますかね、言葉悪いんですけども、ややも人が集客しなかったり、もしそれに利用者が少なかったりという可能性が含まれるわけですよね。今現在の土地であれば、仕方なく市民のために造ったんだよと。だから、利用者が少なければ市民の皆さん行って、くつろいで、それぞれ市民の対話の場所としても利用してくださいと声はかけやすい。でも、別地を設けてやったということには相当な批判もあると思いますよ。うまくいかんかったら。でも、現在の地に造るということは、土地まで求めんだったら逆に言えば、土地まで求めて造ってないんだから、市民のために造った施設なんだから仕方ないだろうで、私は終わると思うんですよ。だから、事業というのは、どういう感覚でやるかも含めてですけれども、失敗は許されないですね。事業主は。ただやりたいから事業やったら大きな失敗につながる。こつこつこつこつ情報を収集しながら、それに重ねて重ねて人との出会いをしながら良い話を聞いて、少しずつ固めて、それを絶対間違いないという方向づけの中で事業着手するのが事業化の事業手法だと思うんですよ。それが劣っとるとは言いませんけれども、あまり打ち抜きでこの施設を造りたいということについて、もうちょっと考えてほしいというふうな思いがあります。
そこで、市長もそこまでは考えていないんだということですので、今後ですね、全ていろいろな事業をするに当たってですね、やっぱり新規事業というのは、本当幼い頃、欲しい物って言われましたよね。三日経てば忘するったっで、1週間経てば、1か月経てば忘るったっでて、年取ってくれば物忘れになったりして忘れますけれども、もう親はそう言いましたよね、それぞれ。ようようようと言っとけば忘るったがて、もう忘れますよね、本当、ようようようと言っとけば。せんじんおれば。すればしたで、今度はどうのこうのと言うか、まあ意見が出たりするわけですけれども、それはですね。やっぱり事業を整備するときには、私たちも市民から選ばれた議員20名です。市長も市民から選ばれた一人、出水市政を担うトップであります。だから、市長は一人の考え方でやるかも分かりませんけれども、議員は20人のそれぞれ生きざまがあったり、生活体験があったり、あるのはこれは事実です。やっぱりそれを理解した上で、いろんな事業とか、今回の事業につきましても事細かく話せる範囲内で順番を置いて進めていってほしいなというふうに思っております。
意見になりますけれども、今後それぞれコロナ禍、変わった生活様式の中でありますけれども、体に気をつけて、いろんな議論をしながら、どうなるか分かりませんけれども、頑張っていきましょう。終わります。
○椎木伸一市長 御支援でしたか、ありがとうございます。最後に一言、私も申させていただきたいと思います。
いろんな事業をするにあたりですね、私もいろんな提言を職員に申し上げ、また、議会にお諮りし、その中で御意見をいただいたのをば、また一つ一つ解決していくわけですけれども、今回もそのように対応したつもりでございます。そしてまた、市民からなる検討会でも揉んでいただいた結果でございます。そして、今、御提案のあった民有地につきましてもですね、今思いますと、候補地にはなり得たのかもしれませんけれども、ただ新しく駐車場を、あれだけの駐車場を設けるとなれば相当の費用がかかるだろうというふうに思うわけでございます。野外フェスタをしたときも2,000人以上の方が集まりましたし、商工会議所中心に実行委員会で花火大会、夏祭りをしたときも相当の方々がお集まりになった場所でございます。そういったことでですね、今のこの予定地については、集客についてはですね、私は問題ないものというふうに認識しております。できるだけこのいろんな人の意見を聞くように、今後も対応していきたいと思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
ありがとうございました。
○16番(道上正己議員) いやいや、今、市長が別地と言えば駐車場の話されましたけれども、おれんじ鉄道のこっちに駐車場というのが、まあ駐車場じゃないですけど、空き地があるということで、それを含めて私はそのできることなら民有地でという話をしたところであります。
申し訳ありません。終わります。
○議長(杉本尚喜議員) 次に、北御門伸彦議員の質問を許します。
○5番(北御門伸彦議員) コロナの終息が見えないところで、1年が経過いたしました。コロナ禍の中で、我が国が世界の中で先頭グループを走っていると思っていたことが、いくつもの分野で世界に遅れていたと見えてきました。特にワクチン開発もその分野でした。その原因はいくつもありますが、国民の命を守る観点でワクチン輸入量に一喜一憂するのではなく、かねてからの独自の準備が必要だと思うところでした。
また、一昨年の12月議会で質問しましたAIなどのIT分野でもアメリカのグーグルをはじめとする頭文字を取ったGAFAという巨大企業に加え、ネットフリックスやマイクロソフトなどを加えた大企業や電気自動車メーカーのテスラなどが業種の枠を超えた様々な展開を見せています。日本でもヤフーとLINEが経営統合するなど追撃の動きがありますが、その差は大きいところで、独自の革新的なサービス提供が鍵となるようです。
さらに、オリンピック大会組織委員会前会長の森元総理の女性蔑視発言を受け、日本の男女格差が153か国中121位であり、改めて世界の潮流に相当遅れていることがクローズアップされました。人権にかかわる認識が遅れているということも今後改めていかねばならないことだと再認識するところです。
ただ、私は世界で1番になることを国の目標にすることも大事かとは思いますが、日本では人口減少が避けて通れない超高齢化社会が到来するわけで、その中で次世代に残す成熟社会をどうつくっていくかを手探りで走りながら考えていかねばならないと思うところです。
そのためには、社会変動や気候変動に高いアンテナを張って、今、何がベストなのかを判断する力が求められているのではないかと思うところです。
さて、テレビニュースを見ていると、ワクチン供給のスケジュールが依然として読みにくいと感じますが、ワクチン接種について市民の関心が一番高いところです。当局も先読みを苦慮している中で、複数の議員が質問され、概要が少し見えてまいりました。できるだけ重複を避けた簡略した答弁をいただき、次の質問につなげたいと思います。
次に、関連して医療センターがワクチン接種の大きな役割を担うと思うのですが、どのような体制で臨もうと検討されているか、お尋ねします。
また、発熱外来を本館前の駐車場へ設置されましたが、設置に至る経緯及び運用実態などについて、お尋ねいたします。
アフターコロナとよく言われますが、気候変動が進み、北極や南極の氷が解けると未知のウイルスや過去のウイルスが出てくるとも言われています。これからもたくさんのウイルスと戦っていく覚悟が必要だと感じております。
昨年9月議会では、洪水対策について少し質問をさせていただきましたが、今回は地震対策で質問させていただきます。
きっかけは、言うまでもなく、明後日で10年になる東日本大震災です。政務調査で復興の現状を見て来てからと考えていましたが、コロナで願いもかなわず、内容の深い質問となりませんが、まず公共施設の耐震化の整備状況についてお尋ねします。
次に、指定避難所についても耐震化の整備状況をお尋ねします。
日本は地震大国と言われ、世界のマグニチュード6以上の地震の20%は日本周辺で起きていると言われています。地震が起きた時、自宅にいる確率は高いものと思います。特に寝ているときの被害は大きくなるため、市でも対応のため、今年の広報いずみ2月号に1ページを割いてPRされました耐震化補助に関して、これまでの実績数、今後の目標値、把握している家屋対象数などお知らせください。
次に、洪水が起きた場合、市は米之津川にかかる橋で右岸、左岸が分断される可能性が高いと前々回質問で申し上げたところですが、地震でも橋が落ちる場合があります。橋梁の耐震化についてお尋ねします。
さて、この課題については3回目となる質問です。
出水市は、平成18年に環境基本条例を制定し、その前段で「利便性の進行による生活様式の変化や経済活動の多様化に伴う資源やエネルギーの大量消費、個々の環境への配慮に欠けた行為などにより、出水市においても環境への負荷が増大している。」また、「健全で恵み豊かな環境が現在から将来にわたって維持されるよう、環境への負荷の少ないよりよい社会を築き、(中略)自然を生かしたよりよい環境を形成し、これを将来の市民に引き継ぐために、環境の保全に取り組むことを決意し、この条例を制定する。」とうたっています。この理念からしても大規模風力発電は、後世につけをまわすことになると思われます。この理念に照らして、風力発電施設の建設は問題ないか、最初の質問とさせていただきます。
次に、屋根付き市民ふれあい広場については、先日の全員協議会で11名の議員から質問がありました。私は一般質問でお伺いする予定でしたので、黙って伺っておりましたが、その中で、たくさんの論点が出てまいりました。整理して一部になりますが、質問させていただきます。
まず、最初に、昨年度の9月補正に計上され、大半の議員の反対で予算を削除した経緯がある事業です。その最初に出た懸念の1つが夏祭り花火大会との関係です。なぜ何回も質問があるかと言えば、昔は本町商店街の近くで打ち上げられていて、そこから4回の会場変更が余儀なくされ、新たに打ち上げ会場を設定するのは許可が大変難しくなっているからです。場合によっては、花火の殻が火がついたまま地上に落下することもあり、文化会館の屋根を傷めないように、田んぼの中にできるだけ落ちないようになど、様々考えると打ち上げ場所は限定されます。苦労して落ち着いた場所であり、花火の殻が落ちる場所に新たな屋根のある施設ができるなら、花火の殻がたまらない構造ばかりか、耐火構造まで付加する必要が生じることになります。全員協議会で何度も質問が出された観点でありますが、ヒアリングで質問項目としてお伝えしていましたので、改めて花火対策の詳細について、お尋ねします。
○議長(杉本尚喜議員) 北御門議員、この東光山のはよかったですか。
○5番(北御門伸彦議員) すみません、東光山の花見山公園については、ちょっと2問目に入れてしまいまして、申し訳ありません。東光山の花見山公園についてお尋ねしたいのは、その概要についてでございます。また2問目で詳しく質問させていただきますので、概要についての答弁をお願いいたします。失礼しました。
○議長(杉本尚喜議員) ここで暫時休憩いたします。再開を午前11時15分といたします。
午前10時57分 休 憩
午前11時15分 再 開
○議長(杉本尚喜議員) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を続行し、北御門伸彦議員の質問に対する当局の答弁を求めます。
○椎木伸一市長 北御門伸彦議員の御質問にお答えいたします。
まず、リスクマネジメントに関するコロナ対策のワクチン接種についてですが、先日の橋口住眞議員の質問でもお答えしたとおり、ワクチン接種については、市内の医療従事者向け接種が今月中旬から始まり、その後、来月には65歳以上の高齢者の方に接種券を郵送し、来月中旬以降に接種を開始できる予定です。
ワクチンの供給量に未確定の部分はありますが、郡医師会や総合医療センターに協力をいただきながら、接種を希望される市民の皆様が安全に安心して接種ができるよう準備を進めていきます。
次に、公共施設の耐震化についてお答えします。
不特定多数の利用がある公共施設135施設の耐震化率は、面積換算で93.8%であり、指定避難所39施設の耐震化率は、面積換算で94.3%です。
次に、一般住宅の耐震化についてお答えします。
耐震化を図るべき住宅としては、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準に基づいて建てられた全ての住宅が対象となります。
まず、住宅の耐震化の現状については、国から示された推計方法により算出すると、市の耐震化率は82%となり、住宅総数約2万戸に対して耐震性が不十分な住宅は3,560戸となります。
次に、木造住宅耐震診断・耐震改修工事補助事業の実績については、制度を設けた平成22年度から耐震診断を14件実施し、そのうち耐震性がありと判定された住宅が3件、なしと判定された住宅が11件です。また、耐震改修工事は3件実施しています。
今後については、国から示された新たな目標に即して策定した、出水市建築物耐震改修促進計画に基づき、令和7年度までに耐震化率を95%に、令和12年度までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目標とします。
住宅の耐震化を促進するためには、住宅所有者に地震への備えが大事であることを強く認識していただく必要があると考えますので、支援制度の継続と耐震化の効果や費用の目安など、耐震化の全体像が把握できる具体的な情報の提供を出前講座を通じて周知するなどして、住宅の耐震化の促進に努めます。
次に、橋梁の耐震化についてお答えします。
本市内の橋梁は、国道で55橋、県道で78橋、市道で414橋架設しているほか、農道や林道にも架設しています。
橋梁の耐震基準は、阪神淡路大震災後に大きく改定され、平成8年以後の基準で架設された橋梁や、河川内に柱のない短い橋梁は耐震化対策済とみなされることから、市道の366橋が耐震化対策済となり、耐震化率は88.4%になります。
本市では、損傷が激しい橋を計画的に補修し、修繕や架け替えなどのコストを平準化する、橋梁の長寿命化を優先して行っています。
また、国から示されている耐震化は、緊急輸送路や高速道路・国道をまたぐ跨道橋の倒壊を防ぐ対策を優先していますので、今後、耐震化対策が必要な橋梁については、国・県と協議しながら進めます。
次に、風力発電施設計画の意見書についてお答えします。
環境基本条例の基本理念では、1つ目に、環境の保全は、健全で恵み豊かな環境を維持し、将来の世代に継承していく。2つ目に、環境の保全は、市、事業者及び市民が自主的かつ積極的に取り組み、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会を構築する。3つ目に、地球環境保全は、全ての事業活動及び日常生活において、積極的に推進されなければならないとされています。
また、第二次出水市総合計画においては、再生可能エネルギーの導入を促進し、普及啓発を進めることになっています。
本市は、環境影響評価法に基づき、県から意見を求められ、関係各課から意見を集約し、本市の意見として回答していますが、環境基本条例の基本理念に基づき、水環境の適正な管理、動物の生態系に影響を及ぼさないよう配慮することなど、環境保全の見地から意見を付しています。
次に、公共施設マネジメントについてお答えします。
まず、屋根付き市民ふれあい広場についてですが、基本構想段階で積算で、大屋根の維持管理費は、年平均390万円となっています。
次に、利用が想定される団体との調整については、道上正己議員の御質問でお答えしたとおり、関係団体等の意見をいただきながら策定しました。
次に、想定されるイベントと使用頻度についてですが、大産業祭やマチテラスなど既存のイベントに加え、鹿児島市の「かんまちあ」での活用事例を参考に、企業主催のお祭りや、マルシェ、車の展示販売会、屋外シネマ、保育園や幼稚園等の遠足や運動会、グラウンドゴルフやフットサル大会など様々なイベントを想定しております。また、民間の方から行政では思いつかないイベントの提案もあると考えています。使用頻度についても、イベント開催等での占用利用がないときは、市民が自由に利用できるため、毎日稼働するものと考えます。
次に、盛土についてですが、県が「米之津川流域に12時間で787ミリの降雨がある」、これは時間雨量で65ミリが12時間降り続けた、現実では考えられないような大変厳しい条件で作成した米之津川の洪水浸水想定区域図ではありますが、建設を予定している総合運動公園芝生広場が0から50センチメートル浸水する可能性があるため、最大で50センチメートルの盛土を行います。なお、このかさ上げについては、昨年7月の豪雨災害で芦北町の復旧・復興計画策定に座長として関わり、屋根付き市民ふれあい広場の検討会に外部専門員として参加していただいた、熊本県立大学の柴田祐教授から、「厳しい条件下で想定する最大規模の浸水想定図であり、現在の計画で十分対応可能」との意見をいただいたところです。
なお、先ほど通告外での質問ではありましたが、花火については、2問目以降で改めてお願いしますが、先の全員協議会でも申し上げましたとおり、検討会には関係団体である出水商工会議所の役員の方にも入ってもらって協議していただいておりますが、最後の検討会で基本構想を御了承いただいたあと、私のほうで直接出水商工会議所会頭を訪ね、その報告と花火についても基本的には現在地での打ち上げを前提として、具体的な検討は今後実施していく旨お話したところであります。
次に、東光山花見山公園計画等についてお答えします。
東光山花見山公園計画については、東光山の西側斜面に、四季折々の草花や花木が楽しめるような魅力的な空間を創出し、新たな観光拠点とするため、今年度、市民や専門家などによる検討委員会を設置して、花木や遊歩道等の配置計画を検討し、策定しているところであります。整備テーマは公募し、検討委員会で審議した結果、「四季の万華鏡東光山」となりました。
また、テーマに基づき、冬から春にかけて開花時期の異なる花木が山すそから頂上に向けて開花する「季節のグラデーション」が楽しめる花見山となるような花木の配置を計画いたしました。
基本的には、桜をメインとし、春は梅や桃、夏はサルスベリやジャカランダ、秋はモミジやキンモクセイなどを配置しています。
また、休憩所や遊歩道も配置し、散策できる計画としています。
整備は、東光山の頂上付近から年次的に山すそに向けて植栽し、おおむね5年で完了する見込みで、令和3年度は、雑木等の伐採後、花木の植栽、遊歩道及び石積花壇の整備を予定しているところです。
○鮫島幸二病院事業管理者 北御門伸彦議員の御質問にお答えします。
新型コロナウイルスのワクチン接種に関する出水総合医療センターの役割については、昨日、橋口住眞議員の御質問に答弁しましたので、重複することを御了承ください。
出水総合医療センターは、基本型接種施設として、ワクチンを受取り、厳重な温度管理を行い、保管する役割を担っております。また、実施施設でワクチン接種を行うほか、市内の医療機関など、サテライト型接種施設及び仮に集団接種を行うとなれば、集団接種会場に必要な量のワクチンを分配することになります。
また、高尾野診療所及び野田診療所もサテライト型接種施設として、ワクチン接種を行う準備をしております。
今後、ワクチン接種連絡調整会議において、接種体制が決定されますので、市や出水郡医師会と連携を図りながら、与えられた役割を果たしていきたいと考えています。
次に、発熱外来の設置場所は、待合室などの院内感染を防止するとともに、患者さんの利便性と職員の動線を考慮して、現在地に決定いたしました。
また、設置した昨年12月21日から2月24日までの統計ですが、この間に213名、1日当たり5.2人の患者さんの診察をしております。
○議長(杉本尚喜議員) ここで申し上げます。北御門伸彦議員より、書画カメラの使用について申出がございました。よって、これを許可してあります。
○5番(北御門伸彦議員) 2問目に入る前にお詫び申し上げたいと思います。ちょっとヒアリングと違うことを聞いてしまったかと思います。御容赦いただきたいと思います。
コロナではないんですが、ちょっと風邪をひいておりまして、ちょっと頭もぼっとしております。ちょっととんちんかんなことを聞くかもしれませんけども、御容赦いただきたいと思います。
2問目に入る前に、失礼しました、今回の大きくリスクマネジメントと、公共施設マネジメントと分けた質問構成について説明させていただきます。
自治体は、自治体経営と言われ、1つの企業にも例えられます。自治体にはリスク管理が必要なことは言うまでもないと思いますが、受け売りで話をしますと、企業経営において損失の生じるリスクを網羅的に把握し、その影響を事前に回避、もしくは事後に最小化する対策を講じる。一連の経営管理手法と言われております。私が昨年9月議会で使いました、危機管理という言葉は、厳密に言うと英語では、「クライスマネジメント」と訳され、リスクが発生した後の対処のことを意味しているそうです。一方、リスクマネジメントは、危機が発生する前にそのリスクを管理し、組織に与える影響を最小限に抑える手法を言います。今回は、まだ起きていない危機を想定し、主にコロナ対策、公共施設等の耐震化、風力発電計画の観点で質問をさせていただきます。
まず、コロナワクチン接種について質問をさせていただきます。
個別接種に積極的な人は、医療センターや接種を引受けてくださる「かかりつけ医」のところに、常に利用していらっしゃる交通手段、例えば、自家用車だったり、バスだったり、タクシーで早目に接種を受けに行くと考えられます。しかし、例えば、自宅での寝たきりの方、認知症の方、精神疾患を持っている方など、自分の意思で接種が難しい方がいると思います。その点についての当局の考え方をお知らせください。
○冨永栄二保健福祉部長 在宅で重度の障害者等の方についての接種の方法の質問だと思います。そういう方についてはですね、訪問診療とかそういうサービスを御利用されている方が多いと思います。ですので、そこあたりをまた医師会さんあたりに、御協力をお願いしながら接種が訪問でできないかというのも今後検討していこうとで考えております。
○5番(北御門伸彦議員) ありがとうございます。よろしく対策をお願いしたいと思います。
次に、地震対策に入ります。
書画カメラをお願いいたします。
これは名古屋市のパンフレットといいますか、案内です。出水の場合、壁をはがして筋交いを補強するような補助だろうと思うんですが、簡易にですね、このシェルター、防災ベッドを設置する方法や、あるいは、その一部屋を補強して対応する。先ほど言いましたように、寝ているときに起きたときが1番危ないということですので、そういう補助方法はいろいろ考えられると思いますが、そういった様々な制度を考えるおつもりはないか。
ちょっと2枚目をお願いします。
アマゾンでひいてみますとですね、二十何万円かでベッドが出ているぐらいです。そういった簡易な方法で耐震化率といいますか、生命を守る最初の方法として利用できるんじゃないかなと思うんですが、それについてのお考え、感想をお聞かせください。
○椎木伸一市長 今、個別のですね、家の中でのそのシェルターハウス等のですね、御紹介いただきました。いろんなこの安心安全を向上するためには有効な手段であるというふう認識しておりますけれども、今後我々も調査研究をしてまいりたいというふうに考えております。
○5番(北御門伸彦議員) ありがとうございます。
次に、風力発電計画について御質問させていただきます。
この風力発電計画については、全国各地で反対運動が起きています。ネットを検索してみて驚いたのが、2009年ですけれども、このあたりで大きなうねりがあったように意識しています。国連環境計画特使の歌手の加藤登紀子さん、呼びかけで全国80の団体、個人が当時の経済産業大臣に事業見直しを求める要望書を提出しております。当時は、お隣の水俣市のように受入れに反対姿勢を打ち出す自治体も現れておりました。要望書を見ると、風力発電は人知でコントロールすることが全くできないという致命的な欠点を持っており、欧米の専門家が指摘するように、出力変動を補うための火力発電所を増やす必要があり、ドイツでは、風力発電施設の増加で何十か所のもの石炭火力発電所が増設されているとの報告もあったようです。
また、5項目の指摘をその中でされていますが、繰り返しの説明になりますが、御容赦いただきたいと思います。
1つ目が「地形の破壊、森林の喪失」建設した結果、土砂崩れ、土壌の流出、飲料水や海水への汚染などの深刻な環境破壊が始まりました。実は、隣の阿久根市で田代地区の4つの集落が反対表明をしたとの情報を得ております。理由は集落に近く、急斜面の上に計画されていること。また、水源がその山に起因していることなどが考えられます。また、地域全体の住民への被害、多様な生物への悪影響、景観の破壊による観光への悪影響などが想定されております。
2つ目が、抑鬱、無気力、極度の不眠、頭痛、血圧上昇、嘔吐、耳鳴りなど様々な健康被害が報告されております。実際に現場を見ない者には想像を絶するストレス源になっていると報告されております。出水の上大川内地区では特に心配される点です。また、今議会で南鶴議員指摘の牛への影響が懸念されております。
3つ目が、当時は事故が頻発していたようです。先月、11名の議員の参加があった議員対象の事業者説明会で耐用年数は20年と言われておりましたが、台風が少なく安定した偏西風が吹くヨーロッパと違い、日本ではブレード(羽)が折れたり、根元から倒壊した事故まであります。また、不要になったときの巨大な処理困難ごみの問題があります。土質が弱いところは30メートル程度の杭を打つとも聞いておりますが、その杭を抜いたら、山の尾根が崩壊すると思います。そうすると、巨大なコンクリートの塊とともに、山に捨て置かれます。
4つ目は、風力は出力変動が大き過ぎる根源的な弱点です。先日、九電の方が「ミックスエネルギー」について説明に来られました。説明の中での切り取りになりますけれども、九電は、福岡県豊前蓄電池変電所を、確か200億円と言われたと思うんですが、建設したと言われました。説明用のパンフレットには、世界最大級の施設と記載があり、さらに、太陽光や風力などの発電量の変動に応じた充放電と記載されております。先日、薩摩川内市の火力発電所を閉鎖するとの報道があったかと思いますが、電力事業所が電力の安定供給のために苦慮している時代だと思います。私は、前回、夢の発電、地上の太陽をつくるプロジェクトの「核融合発電」を少し御紹介しましたが、インドでは、ウランに代えてメルトダウンが起きにくく、廃棄物も毒性が低いトリウム核分裂発電が商用化されております。次世代のエネルギーも徐々に見えてくるとは思うんですが、日本でしばらくはエネルギーミックスでつなぐため、風力に一時的にシフトしているものと考えます。ここ二、三十年のために出水の自然が壊され、廃棄物を後世に残してよいのかと思います。市長、ラムサール条約の登録を目指す観点から、もっと強い意見を発信するおつもりはないか、お尋ねします。
○椎木伸一市長 昨日も橋口住眞議員のほうにもお答え申し上げたところでありますけれども、この環境保全についてはですね、私もその健康被害はじめ、自然破壊、あるいはその災害誘発的なですね、事業については認められるものではないというふうに考えております。その観点から、方法書、準備書等のですね、配慮書もですね、機会あるごとに皆様の御意見等も踏まえながら意見を出しているところでございますけれども、ラムサール条約については、全く別物でありますけれども、環境保全という観点ではですね、非常に市民の安全安心を守る上でも基本的なことであるというふうに認識しておりますので、今後も環境影響評価法に基づく意見等集約しながら、皆様の声も聞きながら対応してまいりたいというふうに考えます。
○5番(北御門伸彦議員) ツルは紫尾山の尾根尾根をすれすれに越えていくというふうに専門家の方から聞いております。バードストライクが起きたときですね、全世界が注目するようなニュースになる可能性だってございます。ぜひ環境を守っていくという、環境基本条例をつくっている出水市でありますし、そういう面からも市長の強い御意見を県のほうに寄せていただくようにお願いしたいと思います。
次に、公共施設のマネジメントの観点で、屋根付き市民ふれあい広場に触れたいと思うんですが、前回の議会で橋口議員が質問されたことです。今回、公共施設マネジメントと質問項目を付けましたのは、先ほども言いましたが、行政は経営と言われ、時代の流れを予測しながら経営していく感覚を持ち合わせていただきたいということで希望しております。
書画カメラをお願いします。平成27年9月策定の公共施設適正配置計画から抜粋しております。前市長がこの前書きに書かれておりますところから引用しますと、高度経済成長期に多くの公共施設が建設され30年以上経過し、耐用年数が切れた施設も増え、大規模改修や修繕、建て替えが必要となっている。日本の経済状況は低迷し、財政や危機的状況となっている。中身を一部紹介しておりますが、この将来の更新費用推計がこのグラフであります。ちょっと見にくいですが、下のほうにオレンジの矢印がありますが、今がここだと思います。これによりますと、これからの10年ぐらいは更新費用の年平均額は33.7億円と書かれております。この試算は今も生きているのでしょうか。この数値の考え方は市の財政計画には反映されているのでしょうか、お尋ねします。
○冨田忍政策経営部長 財政計画のほうには、財政計画は5年度単位で中期的なもので調整をしております。全ての公共工事にかかる維持費等を入れるものではなく、実績等に基づいて、あるいは予定される公共工事等について、各課等から要求等がある、計画があるものを出していただいて、投資事業計画としてとりまとめ、それを財政計画には織り込んでおります。当時の27年度策定の時点での維持更新経費につきましては、現在、全く同じかと言いますと、当然変わってきているかと思います。その詳細が分かればですね、企画政策課長のほうから答弁をさせます。
○松岡秀和企画政策課長 詳細と言いますか、変わってきているところが支所建設に伴いまして、複合化した施設等がございます。そのあたりは以前あった形での補修経費といいますか、更新経費が先ほどの計画には記載されていると思いますので、そのあたりは変わってきていると思います。
先ほどの分は、基本的にそのときにあった施設をそのまま更新をしていくとそれだけかかるという数値というふうに理解をしております。
○5番(北御門伸彦議員) まずは平成27年というとそう前のことではないと思うんですが、このとき30億円を超える維持経費がかかるという試算が東洋大学の教授を招いてですね、この計画をつくられたようなんですが、この大事な計画にもこう整合性をとらないとならないと思います。この屋根付き市民ふれあい広場については、最初の提案のときは、鹿児島市の「かんまちあ」を引き合いに6億円ぐらいと言われたかと思うんですが、もちろんその後、倉庫とか、周りの外構も加わっております。しかし、人口60万人近くを抱える鹿児島市の「かんまちあ」を超える事業になっております。橋口議員が先般、家庭の収入支出の感覚で質問されましたが、コロナ関連予算がない2019年の決算をもとに、昨年の広報いずみ11月号に掲載されたもので考えてみます。
書画カメラをお願いいたします。
ちょっと見にくいと思うんですけれども、収入支出約300万円ちょっとです。この中で広場建設は10万円ぐらいの買い物というふうに私なりに思っていました。実際、これまでローンの返済に25万円、仕送りに33万円ですね。恐らくこれは特別会計への繰出しとかそういうものだろうと思いますが、実質250万円の可処分所得になると思うんですが、ここで10万円の支出をすれば、うちで言えば家内からどやされます。コロナ禍で皆さん苦しんでいるのにこの10億円を使ってまで必要なのかと、家計を預かる女性はそう思うんじゃないかなというふうに思うんです。私は市民の方になかなかこのことはうまく説明できないものです。それよりも、例えばですね、今議会であったように、保育士とか、看護師さんにその職種に慰労金を、例えば、1億円ぐらいでもお支払いしたほうが多くの市民が喜ばれるんじゃないかと思いますし、お金はこの地域で循環して経済波及効果を生むわけですが、建設費に至って想定してみてもですね、特殊な施設なので、基礎や倉庫、外構などは地元に金が落とせるかと思うんですが、恐らく建物のほうは市外の業者にお金を持っていかれると思っています。いつも気になるんですけれども、出水市では、例えば、その道路建設などの場合に、経済波及効果を計算して事業選択をするということがあるのでしょうか。今現在、産業連関表などの取組をされているのは評価いたしますが、事業の優先度などを科学的に判断されることはないんでしょうか、お尋ねします。
○冨田忍政策経営部長 書画カメラの財源のほうで、約10万円という経費について、その費用に関してですね、その10万円という規模に、家庭に比べたときにどうなのかという御意見について、まずお答えをします。
当然、その場合に自前のお金だけで一般財源等で賄うのは厳しいところかと思いますけれども、今回、全員協議会でも説明させていただいたとおり、2分の1の国庫補助が内示をいただいております。設計にいただきましたので、事業実施に当たっても防災安全交付金の国庫補助を活用して整備していくということになっております。その裏につきましては、企業盤ふるさと納税とかを充て、そのほか合併特例債等を含めますと、その交付税措置まで含めますと全体の事業費の75とか、あるいは80近くまでというような国費による補塡をいただける事業計画になっているかと思います。そのお金を他の用途に回した場合に、市内で経済循環、経済の中で循環をされているのか、そういう考えを数字を取り込んでいるのかというお尋ねかと思います。
令和2年度予算をいただきまして、産業連関表とか、そういったものの今勉強を企画を中心にしております。今後、いろんな事業をしていく中で、投資経費に関わる、そこから発生する経済波及効果というものを出しながらやっているかということでございますが、基本的には、今現在の段階ではそこまでは至っておりません。今回の事業については、先に議会の皆様からいただいた御意見、拙速ではないかと、財源がまだ検討してないとか、市民の意見を聞いていないということで御意見をいただきましたので、それらについて、私どもとしては一つ一つ解決をしていくというか、手立てを講じて検討してきたつもりでおります。
○5番(北御門伸彦議員) 国頼みという、まあ地方自治体の悲しいところだろうと思いますが、先ほどの家庭に例えたものでもですね、300万円の中の120万円は国・県からきている予算ということで、この仕送りがなければなっていかないというのは十分理解できるんです。また後でそのことはちょっと触れたいと思います。
私は、この広場の補正提案時に反対いたしました。当初予算では、防災活用ということを条件にして賛成に回ったんですが、これからは施設を造ると仮定した場合の議論になります。候補地7か所の予定地からの選択だということですが、フットサルやグラウンドゴルフ、合宿関係のスポーツ行事や夏祭り、産業祭などの商工関係の大イベントを考えると、確かに適地かもしれません。しかし、防災面で言えば、私は適地と思えません。
書画カメラをお願いいたします。
非常にちょっと見にくいかなとは思うんですが、これはですね、風力発電の学習会案内チラシを市民の方が作ったものをいただいたものです。残念ながらちょっと写真が小さくてですね、予定地は切れているかと思うんですが、左側のオレンジの矢印のあたりに建設になるかと思います。平成18年の豪雨災害のときの写真でございますが、このときは皆様御存じのように反対側の県の合庁の上で越水しました。この土地もですね、先ほどちょっと答弁も先にいただきましたが、越水する可能性はないと言い切れないところです。市外の方から前よく聞きよったのがですね、「出水の総合運動公園は駅からも近く、スポーツ施設がまとまっていてよかな」と言われておりました。新たに建設しないといけない自治体は、よく山の上に建てていらっしゃいます。早くから平地にあってですね、合宿所もあり、大変誇れる施設群だというふうに私も理解しています。しかし、この地域はですね、特に水はけの悪いぬたが多かったところで、土地が買収しやすかったと聞いたことがあります。裏を返せば、水が集まる地域でもあります。たとえ広場が浸水しないとしてもですよ、50センチ程度の盛土をということを言っていただきましたが、文化会館の入り口付近の道路面は川の堤防より低いんですね。越水した場合は、アクセスができなくなるわけです。野球場横からも来れるんじゃないかと言われるかもしれないんですが、ここはまたアクセス、道路が狭い上に一部低いところがやっぱりあります。それを考えると、私は越水の可能性は十分想定しなければならないというふうに思います。せっかく防災拠点として活用しても、洪水のとき、アクセスができない可能性があるところです。むしろ土地の選定で言えば、先ほど道上議員が言われましたけれども、出水駅の近くの芝生広場のほうが市役所が浸かったときも大丈夫でした。私は、市役所に辿り着こうとしたんですが、辿り着けなかったもんで、駅のほうに回りました。鶴丸会館のちょっと確か手前まで水がきてたかと思うんですが、駅は大丈夫でした。防災を考える、防災関係の交付金ですかね、いただかれるということなんですが、災害復旧拠点としてはむしろですね、今後予定されている西回り自動車道の標高もある場所に地域活性化施設ができるわけですが、このままいけばですね、できると思うんですが、それがベストだというふうにも思いますし、申し上げたように水俣駅の横にあるような屋根付き広場の新幹線の駅の市の遊休地を活用してですね、二次的に利用するのは非常に便利だというふうに思っています。予定しているこの施設までのアクセス道路の越水対策まで想定されるか、お尋ねいたします。
○冨田忍政策経営部長 先ほど市長のほうからもありましたとおり、県が12時間で787ミリ、60ミリ以上の雨が12時間続くというような甚大な降雨を想定をした浸水想定区域図であっても、予定地周辺の浸水の深さは浅いか、もしくは浸水しないぐらいということで、先ほど熊本県立大学の専門家の方の知見も御披露させていただいております。浸水があった場合もですね、一時的なものではございます。水が引いたあとはですね、問題なく活用できますし、運動公園南側にある県道沖田新蔵線は、比較的標高が高く、創価学会出水会館のほうから野球場をつなぐ市道八房グラウンド線についても県の浸水想定図では浸水しないとされておりますので、文化会館側の市道等が冠水をした場合でも、南側の県道、市道等からの侵入は確保されるというふうに考えております。
○5番(北御門伸彦議員) そこもですね、飲食店のちょっと下のところは、私が見た感じでは低く感じたところですので、そういう越水対策、アクセスのこともですね、十分考えていただきたいと思います。
あと2分になりましたが、次に、いろいろ注文をつけて本当に申し訳ないんですが、東光山花見公園についてのアイデアは私、支持はいたします。しかし、例えば、事業を着手して一旦マスコミが報道すると、たくさんの見物客が来ます。市は土地を購入するまでは考えていないと聞きましたが、そうすると、道路脇に植えられた花木を見物するとすれば、花見に来た人は道路に駐車してしまうのではないかと思うんですが、駐車場の確保は考えていらっしゃいますでしょうか。
○小原一郎建設部長 駐車場につきましては、今現在の東光山の市道の入り口部分にある駐車場、そして山頂の部分にある駐車場だけをとりあえず計画して、新たにというのはまだ考えていないところです。
○5番(北御門伸彦議員) 非常にちょっと危ういと思うんですね。道路に止めて非常に混乱すると思いますし、トイレも上にしかないわけです。だから、下に降りてくるように計画するならですね、そういったことも十分考えていただきたいというふうに思います。
ここまで大変悲観的な観測を述べてまいりましたが、様々なことを想定すべきものだと思います。アフターコロナでは、国家財政の破綻も視野に入れなければならないと考えます。お隣の熊本県は、地震や豪雨、そしてコロナで財政調整基金がピンチになっております。国はというと、1,000兆円以上の巨大な借金を背負っており、これに関しては断トツ世界1位です。数字をまとめて話をしますと、毎年の支出が100兆としますと、収入は税収で60兆、残りの40兆はほとんど借金で賄っているというのが実情で、これに特別会計を加えると倍以上になると言われているんです。借金の利子だけでいずれ税収を上回る日が来ると言われております。その国から75%ほど財政援助があるから屋根付き市民ふれあい広場を建設したい。また、さらに何年後かには15億円以上かける地域活性化施設を造るわけで、これも75%としても小さくありません。もっと慎重に考えるべきです。財政破綻をした場合、しわ寄せを食らうのは国民、市民です。専門家によれば数年後に財政破綻があり得ると考えている方も複数いらっしゃいます。債務不履行のデフォルトだけでなく、ハイパーインフレ、預金封鎖など視野に入れた対策も想定していかねばならないと思います。リスクマネジメントをしっかりお願いし、質問を終わります。
○椎木伸一市長 いろいろ御提言、御忠告ありがとうございます。私は、最後に考えを申し上げますと、このコロナ禍の中でですね、少子高齢化、そしてコロナがさらにそれを追い打ちをかけるというようなことで、地域の活力が非常に低下しているというふうな時代です。これはいずれもどこも一緒だと思いますけれども、こういうときだからこそですね、我々は一般の家庭の家計とは違うんだという思いがあります。市民の皆さんの安全安心を向上し、子供たちにですね、よりよい未来を引き継がなければならない。そのために、今何をしなければならないかと考えたときに、活力をですね、維持し、あるいは活力を盛り上げていかなければいけない。まさに地方創生であります。地方創生のためには、今、今しなければですね、何もしなければどんどん衰退していくわけであります。ですから、今やりたいという提言をしているわけでございますので、どうかこのタイミングについてもですね、御理解賜りますように心からお願いをいたします。
○議長(杉本尚喜議員) ここで暫時休憩いたします。再開を午後1時といたします。
午後0時00分 休 憩
午後1時00分 再 開
○議長(杉本尚喜議員) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を続行いたします。
次に、髙崎正風議員の質問を許します。
○20番(髙崎正風議員) 通告に従い、地域振興と財政と農業振興について一般質問をいたします。
先ほど来、市長答弁を聞いていますと、屋根付き市民広場については、何でもできる、何でもできますよと御答弁いただきましたので、今度私が質問するのも何でもできますよという御答弁をいただきたいと思っております。
今の社会情勢は、国内外ともに新型コロナウイルス感染症対策が最も重要であり、命を守るため何よりも最優先されるべきであります。こうした中、令和3年度の国の一般会計予算も過去最大で106兆6,097億円が衆議院を通過し、年度内成立が確定をいたしました。本市においても、一般会計予算259億8,200万円が計上され提案されましたところであります。コロナ禍の予算で、国民の負担が強いられることが気になりますとともに、そのしわ寄せが地方自治体に波及されないことを望むものであります。
それでは、地域振興の里道整備について質問をいたします。
前市長のときから数回質問をしておりますが、なかなか地域住民の期待に添えるような答弁をいただいていないところです。再々度質問をいたします。
法定外公共物里道については、平成17年に国から市に譲渡されている道路や水路、または国の管理の状態のままであるのと2通りあります。どちらにせよ、住民の生活に支障のない管理が求められています。地域振興の観点から見て整備が必要であります。そこで里道整備を受益者負担のない整備はできないか。また、その財源にふるさと納税寄附金を活用できないかをお伺いをいたします。
次に、財政について。昨年9月議会で質問いたしました、ふるさと納税については、令和元年度の実績からみると、令和2年度は3倍以上の実績が見込まれています。担当者の職員の努力に敬意を表したいと思っております。
そこで、実績について評価いたしましたが、金額の面から見ると、県内、市町から比べるとまだまだ頑張る必要があります。19市の最下位の順位からは抜け出したような気がしますけれども、ふるさと納税寄附金は、本市にとって貴重な自主財源であることも市長も申し述べられています。自主財源と産業振興のため、地方にとっては有り難い制度であり、この制度を積極的に生かし、本市の経済活動が活性化し、住民福祉の向上につながるものと確信いたしております。
そこで質問に入りますが、ふるさと納税の数値目標はあるのか。また、寄附金を増やすため、仮称でありますが、新たにふるさと納税課を設置する考えはないか。それに、本市の主力商品はどんなものがあるかをお伺いをいたします。
次に、農業行政の多面的機能支払交付金について、この事業は言うまでもなく、今日の農村環境の中ではなくてはならない制度であると認識をしております。行政の曖昧な指導で農家の一部の皆さんが大変な迷惑を被っています。ただ、地区の役員になっただけ、事業費の返還を求められてその責任を取らされることは残念なことであり、二度とこのようなことが起きないように行政指導を望みます。そこで、下原地区管理組合で、平成31年1月29日、溝普請活動が実施されました。出席者には多面的機能支払交付金から日当が支払われ、欠席者からは欠会金が徴収されていますが、この制度的に欠席者から徴収できないことになっていることについてのお伺いをいたします。このことに関連して、市から平成31年4月10日付けの通知で平成30年度決算が適切に行われない場合は令和元年度は認定しないとあるが、下原地区管理組合が認定されたのはなぜか、お伺いいたします。
1回目の質問を終わります。
○椎木伸一市長 何でもできますとは言っておりませんけれども、髙崎正風議員の御質問にお答えいたします。
まず、里道整備についてですが、里道は道路法の適用を受けない法定外公共物であり、財産管理は市が行っていますが、地域の共有財産という側面から地域住民の皆様方に維持管理をしていただいている状況であります。
市としましても、これを補完する形で里道の拡幅・舗装事業等に対する里道等整備事業補助金制度及び建設資材等の支給による里道等整備地域支援事業を実施しています。
市町合併以降、事業の趣旨を理解していただき、これまで多くの里道等が両事業により整備され、制度として定着しているところであります。
里道整備事業は、生活環境の向上を図ることを目的とし、主に地域の集落道路等、受益者が限られる道路等に対して行われる事業ですので、その趣旨を御理解いただき、既存事業の活用により里道等の整備をお願いしたいと考えております。
次に、里道整備の財源に寄附金を活用することについてですが、里道整備は生活環境の向上を図ることが目的であり、ツルと歴史のまち応援基金条例の事業区分には該当いたしません。
また、受益者が限定される事業に寄附金を充当することは、寄附金の使途として適さないと考えております。
次に、ふるさと納税についてお答えします。
まず、ふるさと納税の数値目標についてですが、令和3年度は6億7,000万円としています。令和4年度の目標は、令和3年度の状況を見て設定したいと考えております。
次に、ふるさと納税課の設置についてですが、現在、寄附額は順調に伸びていますが、組織体制上問題はないことから、ふるさと納税に特化した組織の設置は考えていません。なお、今後寄附額の増加等により人員が不足すると判断した際は、増員等による対応を検討してまいります。
次に、主力商品についてですが、現在はハンバーグや鶏肉が多く選ばれています。主力商品は大量の注文に対応できる供給能力が必要ですので、今後も市内事業者にお伺いしながら、随時商品開発を行っていきます。
次に、農業行政についての御質問にお答えします。
多面的機能支払交付金事業の下原地区管理組合の活動についてですが、事業説明会において、溝普請を実施する場合は、欠会費を徴収しないよう各保全会に指導しています。しかしながら、欠会費を徴収しなければ人数確保ができない実状もあることから、各保全会での合意形成を得て、交付金の活動と区分するよう指導していますが、下原地区においては、水田に用水を引くための井堰管理団体の活動と一部混同されていましたので、指導したところです。
次に、下原地区の認定についてですが、平成30年度の決算については、溝普請として日当の支出は確認しましたが、欠会費としての収入については確認できなかったことから、申請書を受理し、その内容を審査したところ、認定要件を満たしていましたので、認定したところです。
○20番(髙崎正風議員) 里道整備については、前市長からずっと質問を重ねております。なかなか、先ほど申し上げましたように、住民の期待に添えるような答弁をいただいていないところでございます。というのも、やはり何かこの、と言いましても、地域活性化さしていくためには、そういうの取り残されているという感じがしてならないわけです。ですから、住民が一番困っていることをば先行してやっていただければと思っているんですけれども、それほど生活に密着したものであるというふうに感じております。ですから、そのことをもうちょっとしっかりとやっていただきたいなと思っているところでもあります。
先ほど屋根付きの市民ふれあい広場、これについては10億円もかかるお金を支出しなければならないということになっておりますけれども、これがそれほど住民に密着したものであるのか。まず先行するのは、住民に密着したものでなければならないと考えております。ということでございますので、このことについては、再度また質問をいただきたいと思います。
○椎木伸一市長 先ほど答弁でも申しましたけれども、受益者が限られている地域の集落道路等でございます。これまでもいろんなその里道等に関してはですね、補助金制度、あるいは資材の供給、支給による整備等を行っていただいているところでありまして、これまでも何回か御質問を幾人からかいただいているところでありますけれども、この補助金交付要綱等もできておりまして、この要件等にですね、叶うようなところを今まで御理解をいただきながら実施しているところでありまして、これからもですね、引き続き、この制度というのは定着しているというふうに認識しておりますので、続けてまいりたいというふうに思っておりますが、屋根付き広場との関係をおっしゃいましたけれども、これについてはですね、不特定多数の市民、あるいは市外の方もそうですけれども、多くの方々の利用を想定している事業でございまして、こういった里道整備との引き合いでですね、検討するということは、私としてはあれが違うのではないかなというふうに思っております。地域振興という大きな観点から考えたときに必要な事業を申し上げているところでありまして、こういった受益者が限られている事業については、制度の要綱等がありますので、それらを踏まえてこれからも実施していきたいというふうに考えております。
○20番(髙崎正風議員) 限られたという御答弁いただきまして、受益者が少ないということは公共性が低いということになってくるわけですけども、しかし、1人のためにもですね、市長は、市民が主人公であるというふうにいつもおっしゃっておりますけれども、今度の施政方針にもその言葉書いてありますけれども、やはり一人一人が大切だと私は思っているんですよ。ところが、大勢の方でやれば何でもいいんだと、一人、二人を見捨てるんだという御答弁のような気がしたんですけれども、やはりこれはもうちょっと真剣に考えてですね、非常に困っている人たちいるわけですから、困っている人を助けるのが市政であると思っております。それを見捨てるようで、大きな広場がみんなで公共性が高いから、10億円もかけてやるということはいかがなものかと思っております。ですから、こういう今の生活道路について、わずかなお金でできるわけですよ。そんなに億も、一千万円もかかる工事もないし、ちょっとした工事で済むわけですけれども、そういう金額を捻出できないというのもちょっとおかしいんじゃないかなと思っております。ですから、ちょっと調べてみたんですけれども、「この条例は、法定外公共物の管理または利用に関して必要な事項の定めをもって、公共の福祉を増進することを目的とする」と書いてあるんです。第1条にうたってあるんですけれども、これは都城市でちょっと調べてみましたら、本市の3条は、法定外公共物のですね、禁止条例になっているんです。しかし、都城市の3条は、「市長は、法定公共物に常に良好な状態に維持し、適正な利用を図られるように管理しなければならない」と。こういうふうに3条でうたってあるし、出水市の場合には、その条項がありません。こういうことを考えると、隅々まで管理をしていきたいという条項じゃないかと考えています。この件についてどうお考えになるのか、御答弁願います。
○小原一郎建設部長 里道につきましても、実際、地域の方々が利用されており、そして、日常管理においても地域の方々で管理をしていただいているところでございます。
今後におきましても、正しい、きれいな管理をしていただければと思います。
○20番(髙崎正風議員) 市長も同じ答弁、部長も同じ答弁をされておりますけれども、可愛そうですよ、実際考えたら。そういうところに手が届くような行政であってほしいと思います。何も法定外公共物だから、それはあれ何ですか、条項にないから駄目だと、そういう考え方じゃなくて、もうちょっと幅広く物事を考えていただいて、隅々まで市民の福祉につながるようなことをやっていただきたいというのが住民の願いだと思っております。ですから、今できないという一点張りでございますけれども、旧高尾野町時代を申し上げますと、平成8年からですね、農村環境整備事業という中で、全部国の事業と合わせて全額で行政が負担をして、補償費も全部払って整備された道路がたくさんあります。ところが、平成17年から合併が始まりまして、18年が合併ですけれども、その以前に、高尾野の場合は、一応17億円だったかな、でしたけれども、その整備事業について、一応採択をしてもらいたいということでお願いしとったんですけれども、その後、18年になってから採択になったんですが、その前、出水市のほうが17年に採択になり、旧高尾野町は不採択になったというような状況でございます。ですから、このような事業に取り組める時期があるわけですから、そういうときに、やはりそれに乗せていくという考えがあって、何もできないということはないわけですよ。農村環境整備事業で、そういうのであればですね。ですから、今、前から申し上げておりますように、この里道についてはもうちょっと真剣に取り組んでいただきたいと。これは私自身でなくて、ほかの議員の方もそういう考えをたくさん持っていらっしゃると思います。前もこのことについて質問された議員がいらっしゃいます。ですから、非常に地域を回って行くこと、これ何とかならないかというのは、必ずみんなその相談を受けると思います。ですから、このことは、公共性が低いからといって、脇に置いといてはいけない問題だと思いますから、もうちょっと真剣に考えていくべきじゃないかと、こういうふうに考えております。どうでしょうか、市長。
○椎木伸一市長 行政は、我々公平公正、適法に執行をしていかなければならないわけですけれども、この農村環境整備事業についても、補助金適化法に見合ったメニューの中で執行されているというふうに認識はしております。
先ほど来、答弁いたしておりますように、この受益者が集落道路をということでですね、公共性、この公道から公道へつなぐようなですね、公共性のあるものについてはですけれども、そこが行き止まりになって複数等の人家があればですね、そこに対してこういった制度を使っていただいてやっていただくという取り決めをしておりますので、今後についてもそのような対応をしていきたいというふうに考えております。
○20番(髙崎正風議員) 市長、考え方を変えないとですね、変わらないんですよ。できない、できないじゃなくて、そういう要望がある。そういう住民の願いがあるということ、ちゃんと汲み取らなきゃ駄目なんですよ。そこを変えるのが行政なんですよ。いつも例がないから、それはお金がないからできないとう答弁ばっかりしてもらったんでは、前に進まないと思います。そういう問題をもうちょっと考えて、切り開いていくのが、やはり行政の力と市長の力であると思います。ただそれがあるからできない、これがあるからできないじゃなくてですね、できるような考え方を持ってほしいと思います。どうでしょうか。
○椎木伸一市長 もともとこの私有地については、補助対象にはならないというのは基本的にお分かりだと思いますけれども、そういった中でですね、公共性が、先ほど言いましたように、公道と公道をつなぐような中にあるような里道については、必要性があるでしょう。しかしながら、その人家にですね、複数といえども受益者が限られているというようなことで、幾らかのこの助成はするわけです。するわけですけれども、それをこの要綱の中でですね、照らしながらやっているわけでございまして、そこの区別はですね、今後もちゃんとしていきたいというふうに考えております。
○20番(髙崎正風議員) その補助要綱を変えたらどうですか。今、一応負担は90%という、助成しますと補助要綱の中にありますけれども、それはクリアできないような状況なんですよ。90%というのは、その中に何が入っているかと、1日80台の車両が行き来しないと駄目だと。そういう里道で80台も行き来する道がありますか、考えたら。何でそういう条項ばつくるのかですね、たまりませんよ。しないという方向で、やれないという方向でつくってある条項だと思います。どうでしょうか。それも、しかも、その地域住民のよその人が80台通るっていう条項なんですよ、どうなんですか、市長、そんな道路が里道にありますか。
○小原一郎建設部長 その80台の要綱をつくった根拠ですけれども、実際の商店街というか、店舗等に行かれる方などが相当多くて、何らか里道整備等でできないかということで、実際に交通量等を調べて、そこの交通量を参考にこういう80台と設定したところでございます。
○20番(髙崎正風議員) その場所はどこにあるんですか。
○小原一郎建設部長 出水病院の前と言いますか、大和に行くところの農道で。農道といいますか、砂利道でございます。
○20番(髙崎正風議員) 一つだけあって、それをば条項に入れると、要綱に入れるというのはおかしいんじゃないかと思う。全体を見て、平均を出していただければわかるんですが、80台て1か所があるからそれをしようというその要綱の取り方というのは、ちょっとできない方向にした要綱だと思います。もうちょっとそれを緩和して、そういう要件を満たさないような要綱のつくり方じゃなくて、ある程度の条件もあるんだと思いますけど、そのハードルを超えるのがもう大変なんですよ。だから、もうちょっとそこを緩和した考え方であれば、90%というのがありますので、何とか理解できるというふうに考えるんですけれども、最初からそういう小さいとこはやらないよという頭から来た。ただ単にその要綱をつくれば、一般質問でうるさく言われるので90%にして今度はハードルを高くしようと、できないようにと。いうのが意図的にされたような感じがするんですけど、どうなんでしょう、その辺は。
○椎木伸一市長 やはり我々は、先ほど言いましたように、公平公正にですね、やるべきだろうということです。公平公正でなくて、例えば、自分の家のきどもしてくれというような話がですね、ややもすると出てくるわけです。そこの線引きはちゃんとしとかないとですね、私有財産とこういった公共性の高いものと、あるいは公共のものとですね、そこの線引きはちゃんとしとかないと公平公正は保たれないというふうに認識しておりますので、ちょうどそこの部分のことをおっしゃっているんだろうなと思いますので、公平性をですね、公平公正性をやはり考慮しながらその公共性もよく議論しながら取り組んでいかなければならないと思っておりますので、これからもこういう取扱いを線引きをしながら、実施していきたいと。何もその何もしないというわけではありませんので、要綱に基づいてですね、70%なり、資材支給とか、いろんなこの事業選択がありますので、地域の皆さんで話し合われて、実績も上がっておりますので、そういった事業を利用していただいて整備していただければというふうに考えているところであります。
○20番(髙崎正風議員) その要綱なんですが、要綱はつくり替えればいいわけですから、それをしようとしないのがおかしいと思うんですよ。そういう住民が困っていることを先にやっていくという考え方を持たない。それはもう行政の在り方だからな、公平公正でないとは言ってない。今の里道つくるのも、公正公平じゃないと私は考えて、公正公平であると思っております。一住民になってもですね、1人のためにやることもやはり公正公平だと思っております。ですから、やはりそのことはじっくりともう1回考え直してですね、新しい要綱をつくって、ぜひ負担のない、里道整備ができるようなことに要綱を変えていただきたいと。一部、内容によっては負担をしなくちゃならないということありますけど、内容によっては、もう負担をしなくていいよと要綱に変えていただきたいというふうに考えておりますが、その辺について、要綱を考える考えてありますか。
○椎木伸一市長 先ほども答弁しましたのであれですけれども、やはりですね、ある程度この私有財産との線引きはちゃんとしとかないと、どこからどこまでを公的な我々が公共工事として担うのか。そこはもう行政の役割の線引きだと思います。そういった中での線引きのために要綱をつくってあるわけでございまして、この要綱について、1人のためにせよということで廃止するとか、見直すとかいうことはする考えはございません。
○20番(髙崎正風議員) やはりですね、そこまで細かいところまで行政のサービスが行き届かないというのはちょっと残念であります。やはりそういうことを考えながら前に進めていただきたいと思っております。
財源としてふるさと納税は馴染まないということでありましたけれども、しかしいろんなやつに、こういうのに使えるようにやるのがふるさと納税の給付金じゃないかと思って、困っているところに税金を使うというのが大事じゃないかと思っております。ですから、大きな大型の、さっき言ったようにですね、屋根付き市民ふれあい広場なんかにはこれをふるさと納税の充てると、寄附金を充てると企業版のやつを充てるという答弁が先ほどありましたけれども、やはりそういう小さいところにこういうのもふるさと納税を充てるのもいかがなものかと考えております。馴染まないということではなくて、馴染ませなきゃいけないと思うんですが、どうでしょうか。
○冨田忍政策経営部長 受益者限定、先ほど市長のほうから受益者が限定される事業に充当することはということでお答えをいたしました。本来の寄附の趣旨、そういったものについては条例等で目的を定めておりますので、やはりそこに従って制度運営していくのが我々の役割かと思っております。
○20番(髙崎正風議員) いつまで話してもらちがあかないので先に進みますけれども。
ふるさと納税についてなんですが、ちょっと聞き漏らしたのか分かりませんけれども、数値目標てあるのでしょうか。
○椎木伸一市長 令和3年度につきましては、6億7,000万円ということで設定をしております。
○20番(髙崎正風議員) やっぱりやればできるんだなと、10億円ぐらいできるんじゃないかという期待もしておったんですけど、数値目標が6億7,000万円出たのは頑張っていただけるなというふうに感じているところですけれども、一応目標が出たということでございますので、それについては何も申し上げありませんけれども、ほかのところの事例を見てみますとですね、平成26年度の南さつま市の事例ですが、548万円です。それから、平成26年の南九州市が576万8,000円、当市が686万4,000円ということで、平成26年度までは一律並んでいるんですよね。その後が問題なんです。その後、令和元年度でみますと南さつま市が46億4,419万9,000円、南九州市が16億4,127万4,742円ですね。本市にとっては8,533万9,500円ということで、非常にまだこれでも先ほど数値目標6億7,000万円と申し上げられましたけれども、到底追い付く数字じゃありません。ですから、もうちょっと頑張っていただきたいというふうに考えておるわけですけれども、どうなんでしょうか。
○冨田忍政策経営部長 先ほど壇上からお褒めの言葉をいただきました。職員一同感謝申し上げます。
6億7,000万円ということで目標を定めております。この6億7,000万円の根拠なんですけれども、6億7,000万円寄附をいただけるということになりますと、地元の特産品の返礼品が3割程度ということになっておりますので、そこからすると地元産品を2億円お買い上げいただけると、そういうような考えから、まずは地元の出品者の方に2億円落ちる、そこを目標にしようということで6億7,000万円を目標にしたところでございます。議員御指摘のですね、他市先行して進んでいるところと比べると少ない金額でまだまだあります。前回の議会でしたか、その前の議会でしたか、議員のほうからも暖かい励ましの御質問もいただきました。そのお蔭をもちまして、今年度は3億円を超えるというレベルにまできておりますので、来年度以降、また改めて頑張っていきたいと思っております。
○20番(髙崎正風議員) 頑張るということでこのような商工会のほうに商工会議所のほうに回されています。確かにやるんだという気持ちは表れてきております。令和2年度の金額ですが、令和3年2月23日時点で3億275万7,000円という数字が出た、実績が出たというふうにして、募られて募集をされております。こういうことで幾らかはやる気が出たんかなというふうな感じがいたしますけれども、しかし、前を遡って調べてみますとですね、平成30年度の寄附金が3,764万6,000円とあるんです。ところが出水市から他の市町に出たやつの税金が幾らかというと、2,699万3,500円、へたするとやり損なうと赤字なんですよ、出水市が。だから頑張れって言っているんですよ。市民の人はそれは感づいている人もいますよ、この時期には。言われましたから。出水市は赤字出しているんじゃないのと、ふるさと納税の寄附金で。これだけ金が出ているんですよ。ですから、頑張らないとマイナスになってしまうと。プラスよりマイナスになるということが言えるわけですから、頑張っていただきたいなと思っております。
それから、ふるさと納税課の課の設置について、私考えないかということなんですが、今のところ特化して考えていないということで、すばらしいなと思いました。ところがこういう事業を20億円も30億円もやる事業になってくると特化しないでどこができるんだと思います。こんな金を一課だけで、企画政策課で扱っただけでできるのか。6億7,000万円の金も到底無理なんでね、だから特化してこういうときは、取り組むときはやらないと駄目だというから、新しい課を設置する必要はないかと私は今申し上げているわけです。いかがなものでしょうか。
○冨田忍政策経営部長 先ほど市長のほうからもありましたとおり、現有の整理部を企画政策課においておりましても、担当者はほぼ専任ということで頑張っております。他市町等をみましてもですね、10億円、20億円売上げているところも観光課の中にあり、あるいは企画の中にありというような状況でございますので、当面、現在のままで努力していきたいと考えております。
○20番(髙崎正風議員) それでできれば私はいいと思いますが、必ず途中で止まってしまいますよ。金額が40億も30億になっていくと。その金額を扱うのに同じ課でできるというのはもうたいしたもんだと、すばらしい能力の持ち主なんだと私は思います。ですから、もうちょっと真剣に考えてですね、やる。長島町あたりはふるさと納税課てありますよね。ですから、長島町の場合には出水市よりもたくさん令和2年度ですか、調べてみたら出水市よりもまだ上ですよ。4億円の売上げ、伊佐市が4億円ですか、の売上げになっております。長島町も出水市よりもたくさんの寄附をいただいているということになっている。まだまだ長島町、伊佐市に負けているんですよ。阿久根市よりはちょっと多くなる見込みです。新年度予算見たときにですね、令和3年度予算計上された数字から引き出すとそういうふうに数字が出ております。だからもうちょっとやり方を変えないと6億7,000万円という数字が出ておりますけれども、ちょっと問題があるんじゃないかということです。やはり特化したもので物事を進めていかないと、20億も30億の数字はちょっと厳しいんじゃないかと、もうちょっと真剣に考えていただきたいと思いますが、市長どうでしょうか。今の企画政策の片手間の仕事でそれができるんでしょうか。私は片手間だと思っているんですよ。すばらしいですよ、片手間でそんな仕事ができれば。
○椎木伸一市長 先ほども答弁で申しましたとおり、今後、寄附額の増加により、人員が不足する、そのような状況があればですね、大変うれしいことなんですけれども、そのときは増員等による対応を検討するつもりでおります。このふるさと納税については、元来、このふるさとから離れた人がふるさとに応援するという税制の趣旨があったわけですけれども、いつしかこの返礼品合戦という名前がありましたけれども、どちらかと言うと、今はもう産業振興施策というふうに捉えられております。出水市も当初はふるさと納税の趣旨を遵守しながら取り組んできたわけですけれども、それではその先ほど髙崎正風議員から御指摘いただいたようにですね、赤字になってしまうというようなこともあり、特産品振興を商品開発も含めてですね、今担当が一生懸命取り組んで2年、3年前の10倍程度になっております。これをまだ倍増しようという思いでですね、担当、非常に一生懸命取り組んでいるところでございますので、我々もそれをバックアップしながら、もしそういった体制がですね、できなくなれば増員をしていきたいというふうに考えております。
○20番(髙崎正風議員) 私はその特化できない理由は何でしょうかというのを聞きたいんですけれども、まずそれから聞いてみましょう。なぜその特別に特化した課を設置できないかという理由を聞きたいです。
○椎木伸一市長 我々いろんなこの業務を抱えております。それをいろんなそのセクションセクション、あるいは係等にですね、割り振って市全体で取り組んでいるわけでございますけれども、そういった意味では、このふるさと納税についても市が行う事務の一つであるわけでございます。その事務量等をですね、毎年政策経営部のほうで査定をしながら人員を配置しているという具体的な話があるわけでございますけれども、その中で今の必要としては、先ほど政策経営部長が申したとおりの体制でやっているということでございますので、それがもしオーバーフローすればですね、髙崎正風議員がおっしゃったように、将来的にはそういった専門のですね、課ができる可能性もないとは言い切れません。ですから、そうなればですね、大変うれしいことでありますので、できるだけ努力しながら、してもらいながらふるさと納税額を増やしていきたいというふうに、職員も含めてですね、私もそのように思っているところでございます。
○20番(髙崎正風議員) 先はそういうことに考えられるということの御答弁ですけれども、令和3年2月の21日の南日本新聞の記事を読まれていらっしゃると思います。誰か読まれた方いらっしゃいますか、お尋ねします。
○松岡秀和企画政策課長 2月21日の南日本新聞のことかと思いますが、はい、一応こちらのほうで確認はしております。
○議長(杉本尚喜議員) 発言は明確にお願いいたします。
○20番(髙崎正風議員) ちょっと読んでたら一番お分かりだと思いますので、質問させていただきますが、大崎町の記事ですね。よろしいでしょうか、大崎町の記事で。ここが莫大な金を集めているんですね。ですから、町長がおっしゃるには、いつまでもこのふるさと納税は続くものではないというような記事が出ておりますけれども、確か私もそういうふうになるんじゃないかなというふうに感じてるところなんですが、やれるうちに、やはり稼げるうちに稼ぐというのが今のふるさと納税寄附金ですね、であるんじゃないかと思っておりますので、勝負はここ二、三年が勝負じゃないかと考えております。ですから、これがずっと地方創生の中でずっと続いていくんであれば、まだじわじわじわじわ考えもありますけれども、やっぱり爆発的にやるとすれば短期間にやるわけですから、一、二年でやっていかないとまた国が首都圏あたりの税収が減ってくると、また問題が出てくるということになりますので、今のうちにやらなきゃいけないからそういう質問をしているわけですが、市長いかがなもんでしょうか。
○椎木伸一市長 以前から言われていた話でありますけれども、ふるさと納税が終了したときにですね、その地場のその物産等を供給していた企業が困らないようにしとかないといけないというような対策で、大崎町あたりもうなぎとかですね、いろいろありましたけれども、自力で、企業が自力でその販売力をですね、維持できるような取組をされているかというふうに思っております。大崎町はですね、一時期すごい勢いで上がっておりましたけれども、そのスピードを緩めてそういった方向にシフトしたというふうに認識しております。また、ほかにも玄海町あたりもですね、早い時期にそういった切り替えをしております。ですから、もともと地場産業振興ということであるならばですね、その道が正しいというふうに私も認識しておりますので、ふるさと納税に頼ることなく自力でPRし、販売が続くようなですね、施策も一緒にこの考えながらやっていかなければならないことだというふうに認識しております。
○20番(髙崎正風議員) 市長が今おっしゃったとおりだとは思いますけれども、結局、大崎町で集めた金というのは46億6,997万円と報じられておりますけれども、非常に、ここは人口が1万3,000人というところでございます。人口ではしないと、ヒアリングのときにそれは人口でしないんだよという話も出てきたんですけど、1万3,000人の人口で46億も稼げるといいますか、ないですよ、この歩留まりがあっても40%歩留まりがあったときに幾らですか、20億近いのが市の財源として残るわけですから、あとは半分以上はいろんな経費とか商品に全部使われるわけですけれども、そういうことでございますので、できるだけこれについてはもうちょっと本腰を入れてやっていただきたいというふうに考えておりますので、御答弁いただきましたので、そういう考えでいらっしゃると思います。また成績が上がらないときにはまた質問をさせていただきたいと思います。
最後になりますけれども、多面的機能支払交付金の事業についてですが、これは前々からいろいろな問題が出ております。残念なことには、さっき申し上げましたように、ただその地域の役員をしたばっかりに余分な返還金を、お金求められたという個人がいます。大変なんですよ、これは。でも行政としてもそれでいいのかというふうに私は感じております。まだ前には進んでいないようですけれども、こういうことはあってはならないということだけはしっかりと言っておきたいと思います。
ですから、今回については、欠会金が取れるという答弁をいただきました。これはちょっとおかしいんじゃないかなと。取れるというふうに聞こえたんですが、取れないんですね。なら取れなかったらどうするんですか。この解決は。
○椎木伸一市長 大変失礼しました。答弁をその部分を繰り返して申しますとですね、欠会費を徴収しないよう各保全会には指導しています。しかしながら、欠会費を徴収しなければ人数確保ができない実情もあることから、各保全会での合意形成を得て、交付金の活動と区分するよう指導していますというような答弁をしたところであります。下原地区においてはですね、水田に用水を引くための井堰管理団体の活動と一部混同されていましたので指導したところですというような答弁をさせていただいております。
○20番(髙崎正風議員) 取れるということですよね、取ったということですよね。どうですか。
○東畠賢一農林水産統括監 情報は髙崎議員も得られていると思いますが、基本的に多面的支払交付金の活動で日当が払われた日の活動時において、溝のいわゆる泥上げ清掃作業時に欠会金を取ったということが問題でございましたので、多面的支払交付金等の事業については、その欠会金は取れないということになっておりますので、そちらの活動と混同をされないように指導をいたしました。欠会金を取った欠会金については、先ほど答弁でもございましたとおり、各地区にあります、こちらの地区には4井堰の組合があるんですけれども、その井堰の組合での欠会金の徴収ということで、そちらの問題については、多面的支払交付金とは切り離して、井堰の問題として解決をしてくださいというふうにお願いをしておりましたので、そちらについては多面的支払交付金の活動ではありました。そこで欠会金取りましたけど、あとの問題については、井堰で解決してくださいねということで処理をしておりました。
○20番(髙崎正風議員) ちょっと今の答弁、市長の答弁も統括監の答弁もちょっとおかしいんじゃないですか。というのは、取れないのは、その協議会では取れますよと。どこにその整合性は出てくるんですかね。片方では取ってはだめだということになっているのに、制度的にはですよ。それで別に話せば取れるんだというのはおかしな答弁じゃないかと思います。いかがなもんですか。
○東畠賢一農林水産統括監 説明上、同じことになると思いますけど、多面的機能支払交付金事業では欠会金は取れませんということで、取ったあとに指導したということでございます。取った当時は、先ほど市長の答弁でもありましたとおり、井堰の活動と一部混同されて取ったというお話でしたので、その後については、そういった活動はできませんよという形での指導をしているところでございます。
○20番(髙崎正風議員) その指導はよく分かるんですけれども、取れないのを取ったということですから、結局、みんな多面的に支払われていなければ問題ないんですよ。その溝普請に対して支払っているわけですから、取った人と取らない人二通りいるわけですから、取られた人と取った人と。ですから、そこが問題があると言っているんですよ。ですから、これが問題があるに関わらず次につながるんですね。そういう会計処理ができていないところに、適切処理ができてないところに認定したということ。だから、前のやつをはっきりしないと、これ認定できないはずなんですよ。どうでしょうか。
○東畠賢一農林水産統括監 これも先ほど市長の答弁でありましたが、最終的に30年度までが5年間の活動期間でございました。この当時は広域組織ということで、先ほど議員のほうからも御紹介があった、役員の問題等があった最終の時期でございます。欠会費として取った方いらっしゃいましたけれども、最終的に多面的支払交付金の収入につきましては、補助金等を充てる。その他収入というのもございますが、基本的には交付金以外の収入を得て活動はされていないということが確認をできましたので、最終的には、令和元年度からの活動については認定をしたということでございます。
○20番(髙崎正風議員) 交付されていないということですか。
○東畠賢一農林水産統括監 交付というか、その欠会金について、多面的支払交付金事業の会計上の処理はされていなかったということが確認できたということでございます。
○20番(髙崎正風議員) ちょっと詳細に調べるとそれは違うと思うんですね。いろいろこの文章は統括監も見られていると思います。これからいくと全く今答弁されたのは違う答弁ですが、いかがなものですか。
○東畠賢一農林水産統括監 昨年来いろいろと髙崎議員のほうに情報を提供されている方のお話だと思います。一方のお話だけを聞いてそのような状況だというふうな判断についてはちょっと厳しいのかなと思っております。実際、もう恐らく最終的には言いたいことは分かっておりますけれども、そういう実態も確認をされております。ただし、その後の確認も私たちもしておりますので、現在のところ問題ないというふうに考えております。
○20番(髙崎正風議員) この文章からいくとですね、欠会金の3月までに返金済みとの報告を偽り報告があったことが令和3年1月11日に明らかになったということの文章があるんですけど、これはいかがなもんですか。
○東畠賢一農林水産統括監 この方にはですね、何回もお会いをして直接お話をしております。先ほど来申し上げているとおり、多面的支払交付金の活動というよりは、井堰の、先ほど説明しました、4つの井堰の管理組合の問題だということで、本人にもその旨お伝えをしております。にもかかわらず、多面的支払交付金の活動の中で、他の団体を干渉しないでいただきたいというお話も全体会でも述べておりますけれども、この方については、そういった他組合、管理組合等の活動に関してもですね、いろいろとリークをされて、市議会議員の方であったり、あるいは県議会の議員であったりですね、九州農政局、それから国のほうにもリークをされていらっしゃいます。そういった状況ですので、そういったもの全てですね、状況を見まして、どうですかという話ですけれども、基本的にはもう管理組合、井堰の管理組合との話でということでお願いをしておりましたので、そういうことでございます。
○20番(髙崎正風議員) 結論から言うと、その活動、溝普請活動のときの出席者に支払われたお金、それから徴収されたお金があるんですけれども、これは相殺されているんですかね。ここが問題なんですよ。
○東畠賢一農林水産統括監 最終的にはですね、こちらの下原の組合のほうからもお話がありましたので、確認をいたしました。返していなかった方についてはですね、領収印等も全て整っておりまして、返還されたものと考えております。
○20番(髙崎正風議員) そういうふうに理解されているとは思うんですけど、実際はされていないという文章なんですよ。偽りがあったと、本人たちがその組合の人たち言っているわけですから、名前は言いませんけれども、そこは問題だから、あんたたちもうちょっとしっかりと調査しなさいと言っているんですよ。どうですか。本人確認されましたか。
○東畠賢一農林水産統括監 今申し上げたとおりですね、お金については、欠会金を払った方の名前、日にち、受領印、全て確認をしております。
○20番(髙崎正風議員) 確認されたということですけれども、我々聞いている話では、確認されていないと。まだもらっていないということですよ、返還されていないということを聞いております。ですから、統括監のほうで確認されたということであればそれは仕方ないことだと思っております。今後こういう問題が起きないような行政運営をしてもらいたいと。もう私も非常に困るんですよ、こういう問題が出てくると。それはなぜかというと、やはりしっかりとした行政指導が足りないということだと思います。先ほど申し上げましたように、返還金求められた、1,600万円ですよ、個人で650万円ぐらいですか。100万円ずつとかて、そんなお金大変なことなんですよ。あんたたちに支払えと言っても支払われないですよ。こういうことが起きるのは行政の指導力不足というふうに思っております。でなければこういう問題も起きてきません。何とかこの辺についてはまださらに解決をしていただきたいと思いますので、私の質問をこれで終わります。
○議長(杉本尚喜議員) 次に、鶴田悌次郎議員の質問を許します。
○13番(鶴田悌次郎議員) 男女共同参画から。
新聞で、出水市の女性管理職数は決して多くはないことが報じられました。出水市の読者や市職員の中には異を唱える人もないわけではないと思いますが、男女共同参画を国が進め、現実に人材不足が指摘されている現状では、日本の男性中心の社会構造を男女共同参画に改め、女性の登用を積極的に実践する以外に解決の道はないことは自明の理です。
そのような社会情勢の中、市民からは広報いずみの1月号表紙の「野田・高尾野支所のオープンのテープカット写真にはなぜ女性が一人もいないのか」と、疑問が投げかけられました。男女共同参画は、我が国の喫緊の課題です。出水市の今後の取組について、具体策をお尋ねします。
まず、市民から指摘があった、広報いずみ1月号の表紙の写真に女性がいないのはなぜかをお答えください。野田支所と高尾野支所の開所式の写真です。1番目の質問です。
次に、2番目の質問ですが、風力発電についてお尋ねします。
風力発電事業者が、巨大な発電設備を出水市内に設置するとして、住民説明会と議員への説明会を開催しました。大型の風車が、特にこれまでにない最大級の大型風車との情報もありますが、広範囲に多数建設される計画であり、住民の生命、財産、生活環境、自然の生態系に多大な影響を及ぼす恐れがあると出水市の市民、また近隣市町のたくさんの住民を不安がらせております。
市長はどのように対応されるおつもりかお尋ねします。
○議長(杉本尚喜議員) ここで暫時休憩いたします。再開を2時15分といたします。
午後2時00分 休 憩
午後2時15分 再 開
○議長(杉本尚喜議員) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を続行し、鶴田悌次郎議員の質問に対する当局の答弁を求めます。
○椎木伸一市長 鶴田悌次郎議員の御質問にお答えします。
まず、男女共同参画についてですが、女性職員の管理職登用については、昨日、中嶋敏子議員へ答弁したとおりですが、現在、管理職は4人おり、平成28年度と今年度を比較すると、課長相当職は1人、課長補佐相当職は3人、係長相当職は6人増加しています。
さらに、女性の管理職登用を進めるために、令和2年4月、今年度から課長補佐制度を導入し、係長の中から6人の女性職員を昇任させ、幅広い経験を積ませているところです。また、係長への登用も積極的に行い、中長期的な視点で女性管理職登用を進めていきます。
さらに、女性職員が活躍するために、男女の区別なく採用時から様々な部署を経験させることでキャリア形成を図っています。
なお、管理・監督職登用が見込まれる中堅の女性職員に対しては、外部研修を実施し、必要なスキルの習得に努めています。
そのほか、今年度は、オンラインによる女性のキャリアデザイン研修も実施しています。
今後も職員本人の希望も踏まえつつ、女性職員の資質向上のための研修の機会をさらに充実させ、女性管理職登用を積極的に進めていきます。
なお、広報いずみ1月号表紙の新支所開所式テープカットの写真は、私や議長、教育長のほか、新支所庁舎に関係する団体の長に列席していただきましたが、皆さん男性でした。今後、それぞれの長を男女に偏りがなく務めるようになることが、真の男女共同参画であると考えております。
次に、風力発電施設の建設に伴う影響への対応についてお答えします。
市は、環境影響評価法に基づき、県から意見を求められますので、騒音及び振動の影響による住民への健康被害が生じないよう配慮し、また、災害については、土砂流出についての適正な管理、沈砂池や調整池等の維持・管理について意見を付して回答しています。
今後も関係各課から意見を集約し、環境保全の見地から本市の意見として回答することとなります。
○議長(杉本尚喜議員) ここで申し上げます。鶴田悌次郎議員より書画カメラ使用についての申出がございました。よって、これを許可してあります。
○13番(鶴田悌次郎議員) 書画カメラ写してください。
今、市長がおっしゃったことは私もですね、大変いいことだと思います。ただ1つですね、大変、私自身が反省しているんです。これが書画カメラですが、これは表紙のごく一部です。全部が映るようにちょっと顔は見えんでもですね、引いて、上下ですね。上も下もですね、上が野田、下が高尾野、両方まあ男の人たちが年配のぞろぞろぞろと並んでいる。ただ私はですね、これを今年の1月号の広報いずみですが、見て、全く違和感感じなかったんです。今、大変恥じております。男女共同参画と言いながらですね、私自身が指摘されて、ああそうかと、私たちはですね、何人も男どもはですね、こういうの見て感じないんだと思います。しかし、職場においても同じようにですね、女性の方はいっぱい感じるところがある。先ほど市長がこうしました、ああしましたって、それは女性の皆さんはですね、それは結構なことだと思っておられるでしょうが、しかし、あの問題も、この問題もまだ何にも解決されていないという、はるかに今市長がおっしゃったよりもたくさんのですね、女性は改善点を持っていると思いますが、市長、いかがですか。
○椎木伸一市長 おっしゃるとおりだというふうに認識しておりまして、日本はやっぱりこのジェンダーと言いますか、それについては非常に遅れているというふうに認識しております。これはもう日本の長い歴史の中での話でありますけれども、今だからこそですね、そういったことを真摯に考えて、社会の中でですね、解決していくべき大きな課題であるというふうに認識しております。
○13番(鶴田悌次郎議員) 大変私も今のを聞いて、心強く男としては思いましたが、女性は思わないと思いますよ、今の回答では。どっぷり私どもは浸かっているんです。例えば、女性の副市長をもってくるとかいうぐらいのことをして改善しないとですね、男の目で幾らやったって女性のいろいろ不満は改善されません。その辺について、今の方をですね、首にしろというんじゃないんですよ。そういうふうなことは市長は考えられたことありますか。
○椎木伸一市長 私は市政を執行する立場でありますので、男女共同参画についてはですね、意識して考えていかなければならないと、積極的に進めなければならないと思っております。今私がどう考えているということは差し控えますけれども、今後はそういうことも十分考えていかなければならないことであろうというふうに認識しております。
○13番(鶴田悌次郎議員) 私がまだ質問しなかったから、市長が今どういうことを考えているというのは差し控えるとおっしゃいましたが、差し控えずに公表できる部分があったらこういうふうなこともできたらと考えているんだというのがあったら御披瀝ください。
○椎木伸一市長 一般的にジェンダーといいますか、社会的なその性差といいますか、そういったものは本当にこのあってはならないという時代になっていると、日本は思います。そういった中ですので、今、職員の登用についてもですね、新規採用職員、この男女関係なく職員の適材を適所にということで、いろんな部署に配置をしております。そういったことも含めて、いろんなスキルをですね、区別なく積んでいただいて、その本人の能力に応じたポストといいますか、仕事にですね、就いていただきたいと思っております。そして、そのことがやがて皆さんも、民間もそうされるでしょうから、やがて若い人たちがですね、成長し、中堅等になられるころにはですね、成果が大きく出てきてくれるようにですね、願っているところでありまして、まずはできることからですね、やっていかなければならないというふうに考えております。
○13番(鶴田悌次郎議員) できることからやっていくと、もうそのとおりで、ぜひやっていただきたいと思うんですが、できることからと言っとったらできないといってですね、ずっと延ばすんですよね。無理してでもやっていかないといけない。もうそこまできているんだと思うんです。私たちは、どんどん高齢化社会を迎えて、現役が減ってきますから。だからぜひですね、できることからじゃない、できないことでもやっていくぐらいの気持ちでですね、取り組んでいただかなければいけない。
それからもう1つですね、これは私自身が反省しているんですけど、女性の目と男性の目ではですね、長く押さえつけられてきた女性の気づくところと、私ども勝手なことを言ってた男性が気づかないところがいろいろあるわけですよ。その辺りが職場によく見られます。市長ももう当然見ておられると思いますが、大変新人、新人て、異動であまりその仕事について御存じなくて、支所なんかでではですね、ところが、隣りにはとってもよく昔からいる分かった女性がいて、そのときの言葉遣いその他ですね、えっと私はびっくりするようなことを言う男性がおりますよ。その辺もですね、やはり役場は、役所は特にですね、まだその辺あたりが裏では、表では出ませんけれども、あるような気がいたします。市長、ぜひこの、これは私自身も理解を込めて申し上げますが、男の目で考えてじゃなくて、女性が自由にものが言える、「市長さん、それちょっとおかしんじゃないですか」と言えるような社会をつくっていくというのが、私1番早道だと思うんですが、そうすると、男の若い人たちも、女性の皆さんからの忠告聞くようになると。今随分、出水市はその点はですね、よくなってきているとは思います。ただ、やっぱり窓口行ったときに、ちょっと感じるところがございます。どうでしょうか。
○椎木伸一市長 私も庁内のことで恐縮ですけれども、職員と語ろ会というものを十数回実施してきました。若い職員から中心にやっているわけでございますけれども、その中で感じるのはですね、我々の世代と比べて、この非常にですね、男女のこの先ほど言いましたようなそのジェンダー的なですね、性差というものはなくなりつつあるというふうには感じております。若い職員は非常に家庭思いというか、そういった方々が多数でございます。そしてまた、女性の方も生き生きと仕事をされながら、また育児もされながらですね、頑張っておられるし、男性職員もそれをフォローしながらやっておられます。そういったことをですね、どんどん進めていかなければならないと思っておりますけれども、むしろ中堅から私どもぐらいの年齢がですね、庁内においては、やっぱり思いを改めていく部分が大きいのかもしれないと、自分も含めてですけれども、思っているところでありまして、また、職員教育等の中でもですね、研修等の中でもそういった研修等も取り入れながら、できるだけのことをしていきたいというふうに考えております。
○13番(鶴田悌次郎議員) ぜひそういうふうな取組をですね、その鹿児島県のどの市町村よりも先駆けてですね、出水の場合は男女の性差というのが職場には全くないというようなふうに、まず仕方がなかったんですけども、今度の写真見て全く違和感を覚えないのは男だけであって、女性はみんなすごい違和感を持っておりますから、その辺りからですね、男女の差がなくなるような形を取っていただけたらと思います。偉そうなこと言っても、家帰るとですね、私も勝手なことをやっているんです。反省しながらですね、なかなか改善はできません。
次にですね、風力発電の問題に移りたいと思います。
風力発電については、もうたくさんの皆さんがいろいろとおっしゃいました。いろいろ質問もされました。ただ今日はですね、市長の基本的な考え方というのが出るだろうと思っておりましたが、その風力発電、今回、設置したいという申込みされている風力発電に対して、市長の考え方はどういうこと。今どういうふうに考えておられるのか、率直にお話を聞かせていただけたらと思います。
○椎木伸一市長 この風力発電については、多くの議員の皆様から御質疑もいただいておりますし、市民の皆様の御意見、要望・陳情等も出ていることも重々把握しております。これまでも回答しておりますように、私は、この風力発電というものはですね、自然再生エネルギー、クリーンエネルギーということで、このSDGsに沿ったような考え方でありますし、このエネルギーの需給率をアップしたり、そういったことについてはですね、いささかもその反論を持つものでもございません。ただ、その皆さんが心配していらっしゃるようなですね、健康への被害、これも環境省からの報告によると、報告事例はないというようなことでございますけれども、そういった人への健康被害、それから、自然の破壊といいますか、動植物も含めてですね、いろんなその自然が壊されてしまうということ。それから、自然災害を誘発する起因にならないかというようなことを懸念はいたしております。これは皆さんも同じようなことだろうというふうに思っております。そういったことでですね、風力発電については、決してそのようなことがあってはならないという思いであります。そういった思いから皆様の御意見や、あるいは各担当課の意見等を集約してですね、必要なものについては条件を、意見を申し上げてですね、配慮書から方法書、準備書、各段階で意見を申し述べられますので、その段階でそれぞれそういった観点からの、環境保全の観点からの意見を申し上げていきたいというような思いであります。
○13番(鶴田悌次郎議員) 今のを聞いておりますと、市長の腹はまあこれは仕方がないよと、風力発電は反対できないと聞こえてくるんですよ。そうでしょうか。私ですね、風力発電に最初は抵抗はそれほど持ってなかったんです。風力が一番いいんじゃないかと。しかしよく考えてみるとですね、昔、原発は絶対に大丈夫だと、もうこれがどうこうなることはないと、私、川内原発なんか建てるときにですね、私、教科書会社にも勤務しておりましたから、その辺少し早く知りました。教科書にも出たんですよ。原子の火がつくというような文書でですね。とても安全でいいんだということでした。しかし、あのときに科学者では反対してた人たちがいるんですよね。これを想定していた人いるんですよ。と同時に、また、もうちょうど今福島に大きな津波が襲ってきた時間帯になってきておりますが、これですね、はっきり人災です。もう予想されておったのに経済が優先して、堤防も上げなかったと。そういうふうなことを、これ同じことが風力発電でも言えます。市長、御存じだと思いますが、その出水の周辺の山は非常に危険な山だと御存じですよね。
○椎木伸一市長 かねて鶴田悌次郎議員のほうからもろい地質で四万十層という土壌なんでしょうか、そういったものであるというふうには聞いております。
○13番(鶴田悌次郎議員) 私、周辺の山、若いころ登りました。全然兎道を登ったんですが、そのあとアスファルトができて、紫尾山にはテレビが映るアンテナができましたけど、その前はもう兎道です。ざらざらざらざら行くんです。これは紫尾山もそうですが、矢筈のほうも登りましたら、一部そういうところがございました。これは地質学者によれば、九州の山々は四国からきているんですが、この四万十帯が特に多いと。で、その四万十帯というのの地図で見ると、ここまで全部延びてきているんですね。こういうところにですね、大型のそれこそすごいでかいのを設置されたらどういうことになるか。私、懸念するのは、一番心配している四万十帯について、設置業者は全く知識を持っておられませんでした。あの方は、その営業の方か何か知らないけど、技術者ではないからという言い訳あるかもしれませんが、私どもは社としてやはり説明に来られて、これに対策はこうとっていますというの期待したら全くない。こういう形でですね、我々のふるさとの山が崩れたら、全く誰が保障してくれるんですか。今の東北の人たちは、いまだに帰れない人たちがいます。それを守っていくのは行政じゃないでしょうか。もう行政がですね、県から言うからそのとおりとかいうような考えでやっとったら市民は誰が守るんでしょうか。今、福島の、昔ですね、私読んだ本ですが、昔ですね、佐藤栄佐久という首相じゃなくて福島県知事がおられました。この福島県知事が出しておられる本を読みますと、もう福島に原発ができてしばらくしたら、何にも報告は来なかったけれども、いろんな小さな事故、事件が起きて、それは福島県には何も報告なくて、ストレートに会社に東京に行ってたんだと。だからこの方は、途中からですね、原発はならんと、もうこれ以上は造らせないということでですね、されたのを、まあ双葉の皆さんには申し訳ないけど、県に言わずにこっそり、一旦お金をもらうとですね、あれはまたもらわないと市町村はやっていけなくなるということで、全ての町会議員が一緒になって、次の原発も造ってくださいと言ったと。その東京電力に。本当にこの県知事さんは怒りまくっておられました。その結果がこれになってきたんです。私たちはですね、もう原発じゃないからと思うかもしれませんが、電力についてですね、もっときちっと考えなきゃいけないんじゃないですか。川内原発があって、我々はリスクにさらされているわけですが、今から十数年前に大きな台風、18号台風だったかな、来て、高尾野町なんかですね、5日間か6日間、電気がきませんでした。女性は、特に赤ちゃんがいるところはおむつがたまって洗濯ができないと、宮之城に行ったら宮之城もいっぱいだったと。その先まで行ったとか。もう大変でした。電柱も18本倒れました。それで分かったんです。原発という、川内の電力、川内のあそこの発電されたものはですね、リスクだけが我々は負担して、我々を迂回して全部都会に売られとったんですよ。我々には電気来なかったんです。だから、我々が怒ったら、紫尾山からこう今新しく鉄塔ができてくれました。結局、営業ですからね、あの人たちは無駄なことはしたくないから、やらないというのは分かります。だけどもですね、この電気がないと我々が困るという状態じゃないんです。今度の紫尾山のこの電気はどこに行くのか御存じですか。
○揚松智幸市民部長 すみません、存じておりません。
○13番(鶴田悌次郎議員) 市長にお伺いします。ここでつくる電気は、私たちに供給されますか。
○椎木伸一市長 風力の話ですかね。風力発電の電力がどこに行くのかということですか。詳しくは存じておりません。
○13番(鶴田悌次郎議員) 詳しくは存じておりませんとおっしゃるが、リスクだけ私たちにきて、それを私たちは許可するか、許可しないかというのの、そのトップがどこへ持って行く電気かも知りませんで済むんですか。もう1回、回答してくだい。
○椎木伸一市長 発電設備を建設するにあたっての条件をいろいろこう我々は各課も含めてですね、付してやっております。そういった中でありますので、詳しくは存じませんけれども、許可権者はですね、私どもではございませんけれども、私どもは出水市民のその自然に対する思いをですね、十分伝えていかなければならない立場でございますので、そういった建設に係るデメリット等をですね、十分考えながら対応しているところでございます。そのリスクだけを背負ってという話でございますけれども、そのリスクを背負ってという話の中でですね、我々はリスクというのがその自然破壊であるとか、健康被害であるとか、そういったことであろうというふうに認識しておりますので、皆さんの意見も聞きながら対応しているところであります。
○13番(鶴田悌次郎議員) リスクですが、これですね、電源立地交付金とかいろいろありますが、これいろいろその後は変わったんですけれども、私いろいろ調べてますと、戦後9電力に整備されたときにですね、それぞれの電力はもっと自分たちの電気を持たないかんというので、大型ダムをあちこち造り始めたんです。大型ダムを造るとですね、下の人たちは、これが崩れてきたときに、我々は何にもいいことないのに、東京なんか持って行く電気のための我々が被害になるじゃないかと反対運動が起きた。それをなだめるために電源立地何とかかんとかでですね、今私どもも若干もらっていますが、あれは黙らせるお金なんですよ。あんなものを私どもはもらう必要ないんです。私たちは、このいい自然をですね、きちっと残していく義務が、子孫に渡す義務があると思うんですが、市長は一番肝心なこと、これ我々の生活にどう関係するのかというのについて、何か分かっているようなさっきことをおっしゃったのに、どこ行くのかも知らないと。どういうここへ機械が座るかもまだ御存じないんでしょう、だったら。
○椎木伸一市長 機械のことについてはですね、いろいろ書類を見ておりますので分かっておりますけれども、その建設自体がですね、市民に与える影響という観点から、あるいは自然保全という観点からの意見等を付すためにいろいろしておりますので、その電気についてはですね、いろいろその配電については今後またいろいろな方向で検討され、配電というのは、その高圧線の配線等もあるでしょうけれども、今後、また検討されていくものというふうには認識をしております。
○13番(鶴田悌次郎議員) 配電を御存じのようですが、これは私たちが使う電気になるんですか。
○揚松智幸市民部長 風力で発電をされたものについては、各電源会社に売り込みをされて、入札の上、売られるものだというふうに認識しております。
○13番(鶴田悌次郎議員) いや、私たちがそのそれをないと困るような状態になるんですか。
○椎木伸一市長 風力発電についてはですね、何世帯分の発電能力とかいうことをよく表示されておりまして、ここの世帯が何世帯なので大体このくらい賄えているんだなという思いはありますけれども、電気というのは、水とは違ってですね、どこかが買って、それをまた配電するというようなことで、発電と送電はまた別物でございますので、その辺はよくはですね、分からないところではあります。そういったことでありますので、あくまでも私どもはその建設に伴って起こると思われるようなですね、危惧しながら意見として付していくというような対応を取っているところでございます。
○13番(鶴田悌次郎議員) 何か曖昧模糊としたコンニャクみたいな回答だったですが、この電気はですね、まあ一応そういう言い方はしておりますけれども、我々のところに供給するためにつくるんじゃありません。それははっきりしています。それは何か特別な事情があったら配線はつながっておりますからあるでしょうけど、目的は我々に持ってくる電気じゃないんです。その辺はもう市長はっきりしてもらいたい。何で私たちがリスクを負わなければいけないんですか。
○椎木伸一市長 私も建設を促進する立場ではございませんので、そういった答弁というか、コメントはできません。
○13番(鶴田悌次郎議員) 建設を促進する立場じゃなかったら、はっきりノーて言えばいいんですよ。
○椎木伸一市長 自然再生エネルギーやクリーンエネルギーをこのエネルギーの自給率を上げることとかですね、日本にとって、今エネルギー問題で非常に重要な課題になっております。これは国策のほうですけれども、そういったメリットもあるわけですね。ですから、そういったことも考えなければならないという観点もあります。ですから、全てがノーというわけではございませんけれども、だからと言って、自然破壊とか、市民の皆さんにですね、健康被害が及ぶようなことがあってはならないという立場で私は意見等を申し上げているところでございます。
○13番(鶴田悌次郎議員) 市長、今電気はどんどん進化しております。発電方法が。この大型の発電方法はですね、近いうちに行き詰まってくると言われております。そして、日本には日本のあった発電方法をやらないと、ヨーロッパでもこんな大きいのは使わないんだそうですけど、しかし、ヨーロッパは風がですね、いつも偏西風が吹いてて、非常に風力発電には向くけれども、日本の場合はそうはいかないというのもはっきりしてきたということなんです。だから、トップとしてはですね、こうしたいとくれば、もうそれははいはいというんじゃなくて、たまにはですね、ノーと言える日本人というのが前あったけれども、ソニーの井深さんが言っとったけどですね、ノーを言わなければ市民は守れませんよ。今の話聞くと、何だかなし崩し的に腹の中は、何でも上から、県から言われりゃ、国から言われりゃOKというふうに私は見えるんですが。少しはその辺りですね、市民目線で考えていただけませんか。
○椎木伸一市長 何も私は、肯定しているわけではございませんので、誤解のないようにお願いしたいんですが、いわゆるそのこの環境影響評価法という法に基づいてですね、事業を推進するという法になっているわけです。発電にしてもですね、先ほど来、これまでも答弁しておりますけれども、国のほうは、もう風力発電の中でもこの陸上発電よりも洋上の風力発電というように舵を切っているわけですね。そういった中で、この事業自体も継続されるのかというふうな疑問も持っております。それでまた、日本はこの四方海でございますので、洋上風力というのも分かるんですけれども、非常にその台風常襲地帯でありますとか、あるいは、浅瀬が少ないとかですね、そういったことも含めて、洋上についてもそれほど簡単にできるものではないというふうな思いがありますけれども、潮流発電にしてもですね、まだなかなかその実用が伴っていないような状況でございます。
いずれにしろ、この安心して使える自然再生エネルギー、化石燃料に頼らない、あるいは原子力に頼らないエネルギーは必要だというふうな認識でおりますので、何が何でも造れないと、造ったらいけないという思いはありませんけれども、ただ、そのことで市民の皆さんに御迷惑がかかるようなことはあってはならないという思いでやっているところであります。
○13番(鶴田悌次郎議員) 市長は、今おっしゃった、それと全く同じ答弁がですね、福島県あたりでは、今から50年前に繰り返されているんですよ。あってはならないと、あったじゃないですか。今、環境評価法どうのこうのおっしゃるけど、それも造るための法ですよ。こうこうやれば造れると、こうしちゃいけないけど、こうこうやれば造れる。造れないという法はないんですよ。だからですね、本当に住民を守るつもりなら、やっぱり自分の方式というのを、こういうことでいくんだと、出水を守るんだという強い信念を持っていただきたいと思いますが、どうですか。
○椎木伸一市長 私もクリーンエネルギーがですね、確立されておればそういったものについては必要ではないというふうに思いますけれども、このいわゆる原子力に代わるものがですね、化石燃料以外に何があるんだろうと思ったときに、現実的に考えますと、風力発電が今も各地にできております。そういったことでありますので、何が何でもその造らせないというようなですね、スタンスまでは取れないところでありますので、そこは御理解いただきたいというふうに思います。
○13番(鶴田悌次郎議員) 風力発電、私、四、五年前まではこれならいいんだと思っておりました。ところがですね、本当に調査を、自分で勉強していきますと、これもまた大変な発電方法で、現状、日本のこの発電ではあとが大変だと。まず、ヨーロッパが大変なことになったんですよ、これで。日本もいずれそういうことになっていくという自分なりの私は勉強しましてですね、市長にももう少し市民を守るサイドからのですね、考え方も持ってもらいたい。国が法をつくったから、それで大丈夫と。国が法をつくってですね、大丈夫なことありましたか。いっつもどこかで漏れたところがあるじゃないですか。だから、もう古い話で、水俣病だけども、あれ、今もうあんなことありませんよとおっしゃるけれども、まだ、100年経ったらまたあのときというのは出てくるんです。それは科学の進歩はやむを得ない部分あると思いますが、今ある程度分かっていることについてはですね、避けていくと。そして、市民を守っていくという、市民を守る観点というのは必要だと思います。
○議長(杉本尚喜議員) 次に、上須田清議員の質問を許します。
○3番(上須田清議員) 皆様、こんにちは。本日、5番目の質問者の上須田でございます。よろしくお願いします。
さて、コロナ感染症が拡大する中、国における緊縮財政が予測され、自治体は交付税の減少も視野に入れる必要があります。これから先は、交付税に頼る自治体は国の動向を留意しながら、行政活動を進めなければなりません。国からの交付税に頼らず、行政活動を進めるためには、自治体が税収を増やすことが必要となります。
そこで、今回は、出水市が税収を増やす工夫をしているのかどうか、という視点で一般会計予算案を見てみたいと思います。将来の税収を増やす事業だと思いますが、未来投資と銘打たれた事業がたくさん計画されていますので、まず未来投資について質問を始めたいと思います。
ところで、投資とは何かということを考えてみますと、将来に資本を投入する活動であると考えます。
まず、未来投資事業の内容について質問します。
一般会計予算で未来投資と銘打った事業が30事業あります。そのうち、未来の税収の増加が期待できる事業について、その投資効果の具体的説明を市長に求めます。
次に、財政調整基金の運用について質問します。
財政調整基金とは、自治体が財源不足や緊急の支出が生じた場合に、貯金として積み立てた基金です。市の財政調整基金、まあ出水市の貯金と申しましょうか、令和元年度末82億4,300万円貯蓄されています。この金額は、鹿児島県においても、鹿児島市、霧島市、薩摩川内市に次いで上位4番目にランクされ、貯蓄額からみれば裕福な自治体と言えます。しかし、令和2年度は、令和元年度に比べ8億円の減少、本年度予算においても財政調整基金から6億円が繰入金として歳入の部に計上してあり、徐々に財政調整基金は減少傾向にあります。この繰入措置は、財源不足を補う繰入金であると思われますが、これから先、税収は減少、交付税は不透明という環境の中で予算が不足するから繰り入れるということでは、この財政調整基金も枯渇することが予測されます。また、この財政調整基金は、緊急の支出も予定されなければならないので、このように財源不足を埋めるようなことを繰り返していると、いざという時に、財源がなくなっているということも想定されます。これからの財政調整基金は、しっかりと使途を決め計画的に使用すべきだと考えますが、市長の見解を伺います。また、これまでのコロナ感染は、緊急の支出が要請される場合であったと考えますが、コロナ対策として、財政調整基金からの支出があったかどうか。支出があったとすれば、使用使途と使用金額について伺います。
以上、登壇しての1回目の質問を終わります。
○椎木伸一市長 上須田清議員の御質問にお答えします。
まず、未来への投資についてですが、本市の持つ観光資源等を磨き上げることにより、さらにその魅力を高める事業、そして、将来の本市を担う子供たちが夢を持ち活躍するための事業、また、高齢者が健康寿命を延ばし、地域社会で活躍するための事業などを未来への投資事業として位置づけております。
議員の皆様にもお配りしました、「令和3年度当初予算(案)の概要」でも、私のマニフェストである「3つの安心」に関連する事業として25事業、第2次出水市総合計画に関連する事業として5事業を「未来への投資」としており、アフターコロナも見据えながら、できるだけ早い地域経済の回復も踏まえた「未来への投資」により、誰もが夢と希望を持ち、いきいきと安心して暮らせるまちを実現することで、地域が元気になり、地域が元気になることで税収の増加につながると考えております。
次に、財政調整基金の運用についてお答えします。
基金の運用については、地方自治法、地方財政法及び出水市資金積立基金の設置、そして、管理及び処分に関する条例に基づき運用しています。
財政調整基金の取り崩しについては、地方財政法第4条の3及び第4条の4において、年度間における財源の不均衡を調整することはもとより、「経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき」や、「災害により生じた経費の財源または災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき」等とされております。
今年度は、新型コロナウイルス感染拡大により、本市においても様々な分野で深刻な影響を受けております。
このような状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策のための諸事業が必要不可欠であり、大規模な自然災害と同様の危機と捉え、財政調整基金をコロナ対策経費の財源として予算措置を行っております。
今回の非常事態に備えるため、これまで基金積立に努めてきており、地方財政法の規定にもあるとおり、今回のような状況であるからこそ、財政調整基金を活用すべきと考えます。
今後も基金残高に留意しながら、予期しない収入減少や支出増加等への対応など、これまでと同様に適切な運用に努めてまいります。
次に、これまでのコロナ対策に係る財政調整基金からの支出等についてお答えします。
コロナ対策については、先ほども申したとおり、非常事態であり、緊急な対策が必要であることから、その時々の状況に応じて、市民の皆様方から現状や御意見等もお伺いしながら、時機を捉えたコロナ対策を講じてまいりました。
新しい生活様式に対応した飲食店や学校、公共施設等の感染防止対策をはじめ、社会経済活動の停滞により深刻な影響を受けている中小企業、個人事業者、農林水産業者等への支援金やコロナ禍を踏まえたGIGAスクール構想の加速化に伴う、小学校1年生から高校3年生までの1人1台タブレットの整備、アフターコロナを見据えた光ブロードバンド整備、地域経済活性化を目的としたプレミアム付商品券の発行などの予算措置をしています。
その財源としては、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用しながら、不足する一般財源については、財政調整基金を活用し対応しています。
財政調整基金繰入金については、随時の補正予算を経て調整しており、基金繰入金の予算計上見込額については、5億6,860万円となり、そのうち、コロナ対策に係る繰入金は約1億9,700万円となっております。
○議長(杉本尚喜議員) ここで申し上げます。上須田清議員より書画カメラの使用について申出がございました。よって、これを許可してあります。
○3番(上須田清議員) それでは、市長に財政調整基金の運用についてお尋ねします。
財政調整基金、すなわち、出水市の貯金の使途は、①一般会計の財源不足を補塡する場合、②緊急の支出の必要がある場合の2つが主な使途であると考えますが、その認識でよろしいですか。
○椎木伸一市長 そのように認識しておりますけれども、地方財政法の中では、経済事情が著しく変動した場合に、財源が不足する場合にその不足額を埋めるための財源とかですね。災害も同じようなことでございます。そして、緊急の実施することが必要となった大規模な土木工事、その他建設工事事業のやむを得ないような理由でですね、充当する場合。それから、長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源ということ。それから、最後にですね、償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるときとかいうようなことが書かれて、そういうときはできるというふうになっておりますので、上須田議員がおっしゃるように、出水市としてはそのように運用しております。
○3番(上須田清議員) 次に、本年度予算の中に6億円が財政調整基金から組み入れられていますが、これは財源不足の補塡であると考えてよろしいでしょうか。
○冨田忍政策経営部長 当初予算の段階では税収等もまだ確定をしておりませんので、そのように、全体を調整した中の一般財源不足ということで捉えていただいて結構かと思います。
○3番(上須田清議員) 次に、予算編成についてですけれども、本来の予算編成は、まず本年度の歳入を見積りながら、必要性、緊急性などの検討を経て歳出の編成を行うのが通常の予算編成だと考えます。財政調整基金の予算編成時での組み入れをしているところを見れば、はじめに歳出があって、その後、歳入を検討したと思われても仕方がないと思われますけれども、いかがでしょうか。
○冨田忍政策経営部長 もちろん予算編成に当たりましては、税務当局等からまず税収等をまずもらった上で交付税と地方財政計画等の譲与税、交付税、そういったものを入れながら、一般財源の中でどれだけの事業がということになります。ただ、今年度は、当初予算の説明でも申し上げたとおり、税収の減収が見込まれると、そういうこともございまして、当初予算で必要な事業の財源として充てるには6億円ほどというようなことで、今計画をしたところでございます。
○3番(上須田清議員) 次に移りますけれども、書画カメラの1をお願いします。
令和3年度当初予算(案)の概要65ページです。4の基金残高推移の基金名、財政調整基金を御覧ください。
平成29年度末から令和3年度末の推移を見ますと、令和2年度末には、前年度から約8億円の減少、令和3年度末には、さらに6億円の減少と平成29年度には約83億円あった出水市の貯金は、令和3年度末には約15億円減少することが予測されます。
そこで市長にお尋ねします。
先ほどコロナ対策の支出は1億9,700万円だとお伺いをいたしました。次に、今の出水市の財政状況を見ますと、これから先、出水市の税収の減少、また、国の財政事情による交付税の交付の減額も予想され、今のように財政調整基金を財政の補塡に使用し続ければ、緊急の場合の対応ができなくなることも予想されますが、市長には、そういう点について危機感はあるでしょうか、お伺いします。
○椎木伸一市長 上須田議員が先ほどからおっしゃっていただいているように、この経済の不況等による大幅な減収でありますとか、災害発生による思わぬ支出の増加、いわゆる、今回の新型コロナウイルスは、まさにそういった状況を勘案しての支出でございます。ですけれども、この地方財政法に書いてあるようにですね、単に当該年度だけではなくてですね、後年度における財政状況も考慮して、健全な運営を行わなければならないということがうたってございます。このようにですね、我々はその安易に支出するということは避けなければならないということは十分認識しております。支出する際もですね、できるだけ精査して、効率的な執行に努めなければならないというふうにも思っているところでありまして、今後はですね、いろんなその防災・減災、国土強靭化計画の予算でありますとか、いろいろこの安全安心の予算等を見ながらですね、そういったものも十分利用しながら、効率的な運営に努めていきたいというふうに考えております。
○3番(上須田清議員) 次に、今は税収不足を理由に財政調整基金を予算に組み入れることを優先するよりも、コロナ禍により市民が経済的にも困っているわけですから、緊急の支出として、優先して財政調整基金は活用すべきだと思いますが、いかがでしょうか。また、これから先、緊急支出として、財政調整基金を使用する予定はあるでしょうか、市長にお伺いします。
○椎木伸一市長 大きな災害がまた起きれば、そういった対応も考えなければなりませんけれども、新年度においてはですね、令和3年度においては、引き続き、この新型コロナの影響でのコロナ禍への対応をですね、時機を逸することなく、やはり市民の皆さんの意見を十分に聞きながら対応していかなければならないというふうに考えておりますので、令和2年度に引き続きですね、必要な際は活用をさせていただきたいというふうに考えております。
○3番(上須田清議員) 次に、未来投資を事業とした担当各課への質問です。
投資という言葉の意味は、辞書を引きますと「利益を見込んで事業に投資すること」とあります。すなわち、未来の利益を見込んで、今予算化したのが未来投資だと考えます。
では、行政における未来の利益とは何かということ考えてみますと、最終的には、未来の税収の増加に係る事業だと思います。その視点から、各課未来投資の事業を俯瞰してみますと、全て税収の増加につながる事業のはずですが、事業の必要性、緊急性での両面から見ても、事業内容から見ても具体性がなかったり、数字の裏付けがないことが懸念されます。このような具体性がない事業内容では、来年度決算において、事業をしたのか、しなかったのか投資効果が分かりません。予算執行の無駄が当然のように発生すると思います。
そこで、担当各課に事業の具体性、そして、その事業が将来に出水の税収の増加にどのような形で現れるのか、次の2事業について質問します。
まず、都市計画課にお尋ねします。
未来投資の中に、屋根付き市民ふれあい広場整備事業があります。この質問については、予算審議の中でも質問させていただきますけれども、事業の内容を考えたとき、必要性、緊急性がありますか。コロナ感染症の終息が見えないこのコロナ禍の中、必要、緊急な事業ですか。
次に、この事業が未来投資とありますが、出水市の税収の増加にどのように寄与するのですか。
次に、工事費の予算額、出水市の負担部分について、どのような資金を投入するのですか。財政調整基金を充当するつもりですか。
次に、平成27年9月作成の出水市公共施設適正配置計画によると、基本指針として、基本方針②において、統廃合等を除き、原則として、新規建設はしないとしていますが、この事業が例外である理由は何ですか。
○議長(杉本尚喜議員) ここで暫時休憩いたします。再開を3時30分といたします。
午後3時15分 休 憩
午後3時30分 再 開
○議長(杉本尚喜議員) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を続行し、上須田議員の質問を許します。
○3番(上須田清議員) 先ほどは大変失礼いたしました。夢中になって一問一答を忘れておりました。申し訳ありません。
もう1回質問させていただきます。
未来投資の中の屋根付き市民ふれあい広場整備事業について質問します。
この質問については、予算審議の中でも質問させていただきますが、事業の内容を考えたとき、必要性、緊急性がありますか。コロナ感染症の終息が見えないこのコロナ禍の中、必要、緊急な事業ですか。
○椎木伸一市長 先ほどもほかの議員のときにもお答えしましたけれども、重要な事業については必要性、緊急性、その重要性というようなことを勘案するわけですけれども、今回のこの屋根付き広場についてはですね、これまでの少子高齢化での活力の低下、そして、またそれを追い打ちをかけるように、長引く新型コロナウイルスによる、感染症によるコロナ禍によって非常にこの経済も停滞し、活力も低下しているというようなことから、それらからのですね、活力を向上し、あるいは、元気を創出し、早期のこの脱却した経済振興、そういったもののためにですね、地方創生の拠点としたいということ。それから、度重なるこの自然災害そういったものからもですね、安心安全を確保していく必要があるというような重要性、そういったところに鑑みてですね、今回、こういった提案をさせていただいているところであります。
○3番(上須田清議員) 私としては、余裕があるんであれば、コロナ感染症の先行きが見えてないので、そちらのほうに、例えば、看護師の危険手当とか、いろんな設備関係とか、喫緊の支出が必要になってくると思います。そこのほうに充当していただきたいと思います。
次に、この事業が未来投資とありますけれども、出水市の税収の増加にどのように寄与するのですか、担当課にお尋ねします。
○椎木伸一市長 税収の増についての御質問ですけれども、私のほうから答弁をさせていただきます。
その前にですね、先ほど後段でおっしゃった、今しなければならないかということですけれども、先ほども申しましたように、この低迷の中でですね、今何もしなければますますこの活力がなくなってしまうという思いがありまして、今だからこそ手を付けていかないといけないという思いがあります。そして、コロナ禍で苦しんでいる方々にはですね、その都度、市民の皆様等の意見を聞きながら、必要なときに必要な対策を打っていきたいというふうに思っております。これはもうこれまでも行ってきたとおりでございます。そういった思いでありますので、御理解を賜りたいと思います。
それから、税収についてはですね、今回、このいろんなこの未来への投資予算ということで、投資という言葉を使わせていただいておりますけれども、いわゆるその経営上の投資、見返りがあってのということも全体的にはあるのかもしれませんけれども、私としてはですね、人材育成であるとか、経済の振興であるとか、活力の向上であるとかですね、地方創生、いわゆる元気創出のためのですね、地域の活力の向上のためにやることをですね、この未来への投資予算というふうに思っているところでございまして、そのことで、全てが、全てというか、いろんな活力向上になればですね、いろんなところからのその税収等も伴って、上がってくるのではないかというようなことでございまして、具体的な税収の指標をもって当初予算等組んでいるわけではございませんので、そこについても御理解を賜ればというふうに思います。
○3番(上須田清議員) 次に、この事業の出水市の負担部分については、どのような資金を投入されるのか。財政調整基金を充当されるおつもりでしょうか。
○椎木伸一市長 財政調整基金ではなくてですね、補正予算債を考えているところでございます。すみません、補正予算債の詳細については、政策経営部長のほうから答弁をさせます。
○冨田忍政策経営部長 今回、19号補正に計上しております予算に対する財源措置でございます。国庫補助金が2分の1充当されますので、残り2分の1につきましては、補正予算債、その補正予算債でございますが、国が補正予算を編成をする際にですね、伴って支出を要する地方の支出分については、地方財政対策を講じることになっておりますので、その中で、充当率100%で50%の交付税措置のある起債の発行が今回の事業には、補正予算で計上する事業には認められるということでございます。
○3番(上須田清議員) 次に、平成27年9月作成の出水市公共事業適正配置計画によると、基本指針として、基本指針②において、統廃合を除き、原則として、新規建設はしないとしていますが、この事業が例外である理由は何でしょうか。
○椎木伸一市長 公共施設等総合計画の中でですね、おっしゃるように、原則として、新規の建設は認めないという方針に確かになってございます。ただ、今回、この屋根付き市民ふれあい広場はですね、同様な機能を持つ施設はこれまでもなく、また、社会情勢の変化、いわゆるこの少子高齢化や、あるいはその新型コロナウイルス感染症による経済への影響等々ですね、非常にこの状況は変化しておりまして、その中で、先ほど申しましたように、必要性等を感じて、思って対応をしたいというようなことでございますので、新たな市民ニーズの中での施設というふうに考えておりまして、この計画の基本方針や既存施設の削減目標を維持しながらもですね、整備する必要があるというふうに認識してのことでございます。
○3番(上須田清議員) 今日の質問は未来投資という項目であげていますので、これぐらいにして、次の質問に移りたいと思います。
シティセールス課にお尋ねします。稼げる観光地づくり事業について、この事業には、毎年投資をし続けているようですが、今まで、市民に目に見えて分かるような、どういう成果がありましたか。
○椎木伸一市長 稼げる観光地づくり事業はですね、私が就任して以来お願いをしている部分でございまして、いわゆる産業として成り立って行く観光業を育成しようという思いで取り組んでおるわけでございます。その具体的な中身はですね、個々には申し上げませんけれども、例えば、ラムサール条約への登録、このことによって、このいろんな産業振興に役立てようという思い、それから、都市計画課のほうで昨年の8月に実施しました、武家屋敷麓一帯のですね、部分的な都市計画用途の変更、これもいわゆる空き家等がどんどん増えていく中でですね、それを空き家を増やさない、あるいは、空き家を活用した観光振興ができないかということで、具体的には宮路邸等を活用した民泊施設をつくって、いろんな外からのお客さんを増やし、また、出水市のグレードを上げていこうということ。そして、観光協会と特産品協会のいわゆる合併によりまして、観光推進母体をつくっていこうと。そして、その母体によって出水市も当座は人、人的な支援や予算的な支援もいたしますけれども、そういったことで、その稼げる観光地のですね、中枢になってもらおうという思いがありまして、そのような諸々の事業にですね、観光振興、新たな観光振興ということで取り組んでいただいているところでございます。
○3番(上須田清議員) 今の稼げるっていう答弁をいただきましたけれども、具体的にはそのどのように稼げるのか、教えていただきたいんですけど。
○椎木伸一市長 これもですね、これまでも質問いただいたこともあったと思いますけれども、金銭的にですね、商売の中での稼ぐというよりも、いわゆる観光産業全体として、産業として成り立っていける人の流れをつくりたいという思いでの稼げる観光地づくりでございます。例えば、ラムサール条約登録されますと、ツル観光に関わらずですね、非常にこの水鳥のたくさんいる出水地区でございます。全国で確認された600種の中の300種が確認されるというような非常に優れたところだそうです。そういったところに長期のいわゆる平日型、滞在型観光客を呼び込もうということ。そして、そのことでホテル産業等もですね、この潤うのではないか。あるいは、バス、タクシー、そういった観光関連産業も潤うのではないかということ。
それから、これまで麓に来てもですね、みやげ品も買えない、あるいは食事もできないというようなところが、そういったこと、先ほど申しました、都市計画の変更等によって景観市有地は保存しながら、そういった規制をやや緩和することでですね、そういったところでのいろんな小売業、商店業等もですね、収入が得られるというようなことでございまして、そういうことを総括して、私はそういった表現でですね、稼げるということを申し上げているわけでございまして、決して儲かるということではございませんので、どうかよろしくお願いいたします。
○3番(上須田清議員) 次に、ツル観光戦略事業、麓武家屋敷観光戦略事業、地域食文化活用観光戦略事業の3事業について、簡単で結構です。事業の具体策を御説明お願いします。
○春田和彦産業振興部長 申し訳ございません。もう1回事業名をお知らせください。
○3番(上須田清議員) ツル観光戦略事業、麓武家屋敷観光戦略事業、地域食文化活用観光戦略事業。
○議長(杉本尚喜議員) 上須田議員にちょっと確認しますけども、通告はこれはされていますか。
暫時休憩いたします。
午後3時44分 休 憩
午後3時45分 再 開
○議長(杉本尚喜議員) 再開いたします。
○春田和彦産業振興部長 稼げる観光地づくり事業の中で取り組む観光戦略事業のことかと思います。
まず、ツルの部分ですけれども、先ほど市長が申し上げました、ラムサール条約登録後のツルの見せ方であったり、そういったところの研究であったり、取組でございます。
それから、武家屋敷の戦略、観光戦略につきましても、今、先ほど申し上げました、宮路邸を活用した民泊、それから、今後その出水麓の地域が都市計画の用途見直しもありまして、おみやげ屋さんであったりとか、食堂というか、食事処でもできるようになりました。そういうところも含めて、今、民間で取り組もうとされている方がいくつかございます。そういったところとの連携により、武家屋敷での散策も含めた滞在型の観光です。
地域食文化につきましては、出水地域のいろいろ食材がございます。鶏もございます。あとジビエ、あと出水の海苔、そういったもの、いろんな優れた食材がございますので、そういったところのまずはレシピを作ったりして、宣伝をしていくということでございます。
○3番(上須田清議員) 大変失礼しました。未来投資の項目を見てて、その中から抜粋をして、これはいいなと思って聞いてみたいと思って質問をしました。答えていただいてありがとうございます。お礼を申し上げます。
本日、歳入、歳出の両面から質問をしてまいりましたけれども、これからは、再々国の借金の問題が出ておりますけれども、天文学的な日本の借金であります。その中で、予算編成をしていくわけですけれども、予算編成が、いわゆるできなくて、さらに借金を重ねていくと。借金を返すために借金をしていく。じゃあ最終的にどうなのかなというのを考えますと、先行きは不透明だと。そうなりますと、これからは国からのいわゆる補助金等々交付金、いわゆる本当に緊縮財政なのかなと思います。そうした中で、これからの税収不足の対応が今後の出水市にとって最大の課題だと思います。
最後になりますけれども、今は財政調整基金を取り崩して税収を補塡していても、財政調整基金という出水市の貯金は将来的には枯渇します。財政調整基金は、今回のコロナ禍のように、緊急の支出に備えるために使うべきで、よっぽどのことがない限り、歳入不足の補塡として使うことは将来的に見ても好ましくはないと考えます。歳入不足は、あくまで自治体の自助努力により解決する必要がございます。そういう意味では、本予算における未来投資という事業は、自助努力の一環として将来の出水市の自主財源を生む大事な事業だとも考えております。
事業の中には、未来投資とは趣旨が異なると思われる事業もところどころ見られます。また、市長がおっしゃるように、人の投資とか、いろんな、いわゆる税収につながらない投資もございます。しかし、事業というのは、事業を具体化することで事業推進が明確になり、成果が現われてまいります。
来年の決算に関する議会においては、個々の未来投資事業について、税収の増加に寄与する具体成果があったとか、いわゆるその事案での大きな成果があったという御報告がなされることを期待をいたしております。
以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。
○議長(杉本尚喜議員) 以上で、本日の一般質問を終結いたします。
-------------------------------------------------------
△ 延 会
○議長(杉本尚喜議員) お諮りいたします。本日の会議はこれで延会したいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(杉本尚喜議員) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会いたします。
第5日の会議は、明日10日に開きます。御苦労様でした。
午後3時51分 延 会
-------------------------------------------------------
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
出水市議会議長
出水市議会議員
出水市議会議員
出水市議会議員
- 260 -