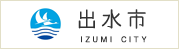令和2年出水市議会第2回定例会会議録第2号
-------------------------------------------------------
令和2年6月11日
-------------------------------------------------------
会議の場所 出水市議会議場
-------------------------------------------------------
出席議員 19名
1番 南 鶴 洋 志 議員
2番 橋 口 住 眞 議員
3番 上須田 清 議員
4番 日 髙 信 一 議員
5番 北御門 伸 彦 議員
6番 枦 山 卓 二 議員
7番 吉 元 勇 議員
8番 土 屋 工 吉 議員
9番 鶴 田 均 議員
10番 田 上 真由美 議員
11番 杉 本 尚 喜 議員
12番 出 水 睦 雄 議員
14番 中 嶋 敏 子 議員
15番 宮 田 幸 一 議員
16番 道 上 正 己 議員
17番 榎 園 隆 議員
18番 垣 内 雄 一 議員
19番 築 地 孝 一 議員
20番 髙 崎 正 風 議員
-------------------------------------------------------
欠席議員 1名
13番 鶴 田 悌次郎 議員
-------------------------------------------------------
地方自治法第121条の規定による出席者
椎 木 伸 一 市長
吉 田 定 男 副市長
冨 田 忍 政策経営部長
山 元 周 作 総務課長
戸 﨑 基 夫 くらし安心課長
駒 壽 ひとみ くらし安心課課長補佐兼コミュニティ推進係長
宮 﨑 毅 財政課長
大 田 直 子 財政課課長補佐兼財政係長
松 岡 秀 和 企画政策課長
宗 像 完 治 企画政策課秘書監(課長補佐)
川 畑 正 樹 企画政策課課長補佐兼行政改革係長
田 中 一 将 情報課長
大 森 聡 情報課情報係長
冨 永 栄 二 保健福祉部長
田 口 保 福祉課長
揚 松 智 幸 市民部長
松 原 淳 市 市民生活課長
森 山 佐 知 市民生活課住民年金係長
長谷川 健 市民生活課課長補佐兼健康保険係長
春 田 和 彦 産業振興部長
東 畠 賢 一 農林水産統括監(参与、農林水産整備課長事務取扱)
酒 本 祐 喜 農林水産整備課技術主幹兼基盤整備係長
小 村 郁 則 シティセールス課長
堀 昌 伸 シティセールス課特命統括監(参事)
堂之上 健 二 シティセールス課課長補佐兼観光交流係長
松 下 誠 シティセールス課産業支援係長
小 原 一 郎 建設部長
山 村 祐一郎 道路河川課長
永 山 勝 久 道路河川課課長補佐兼建設第一係長
松 木 健 治 道路河川課課長補佐兼建設第二係長
池 田 幸 弘 高尾野支所長
山 口 徹 野田支所長
鮫 島 幸 二 病院事業管理者
髙 橋 正 一 出水総合医療センター事務部長
﨑 迫 真 也 出水総合医療センター総務課長
東 陽 一 出水総合医療センター総務課調整監(係長)
大 平 伸 章 消防長
溝 口 省 三 教育長
溝 口 雄 二 教育部長
田 中 真一郎 学校教育課長
諏訪園 直 子 学校教育課学校教育係長
小 田 大 吉 生涯学習課長(生涯学習課読書推進室長兼補)
中 村 宗 義 生涯学習課参事兼指導主事
岩 本 秀 一 生涯学習課生涯学習係長
酒 本 めぐみ 生涯学習課読書推進室次長(主幹)
-------------------------------------------------------
議会事務局
畠 山 義 昭 局長
華 野 順 一 次長(課長補佐級)
浦 﨑 紀 光 主任主査
中 村 勇 士 主査
野 﨑 育 美 主査
-------------------------------------------------------
付議した事件
一般質問
午前10時00分 開 会
△ 開 議
○議長(杉本尚喜議員) おはようございます。ただいまの出席議員は19名であり、定足数に達しております。これより令和2年出水市議会第2回定例会第2日の会議を開きます。
鶴田悌次郎議員から、本日の会議に欠席する旨の届け出が出ております。
-------------------------------------------------------
△ 議 事
○議長(杉本尚喜議員) これより議事日程により、議事を進めます。
-------------------------------------------------------
△ 日程第1一般質問 上程
○議長(杉本尚喜議員) 日程第1、一般質問を議題といたします。
本定例会の質問通告者は14名であります。
これより一般質問に入りますが、質問者の発言並びに当局の答弁は、できる限り重複を避け簡明・的確に、また通告外の質問や品位の保持等については遵守されるよう望みます。なお、再質問からは一問一答方式とし、各議員の質問時間は20分以内といたします。
質問順に従い、宮田幸一議員の質問を許します。
○15番(宮田幸一議員) おはようございます。
世界中で猛威を振るっているCOVID-19と名づけられた新型コロナウイルスの世界全体での感染者は、アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の5月23日午後3時時点の集計で、アメリカ158万8,322人、ロシア32万6,448人、ブラジル31万87人、イギリス25万5,533人、スペイン23万4,824人など、世界全体で515万9,674人が確認され、亡くなった人は、アメリカ9万5,276人、イギリス3万6,475人、イタリア3万2,616人、スペイン2万8,628人、フランス2万8,218人を初め、全体で33万5,418人となっています。同日の日本国内の感染者は、クルーズ船を除いて1万6,543人で、死者は814人と発表されています。
そのような状況下で、日本政府は、国の一般会計や特別会計からの支出に、政府系金融機関などを通じて民間に資金を供給する財政投融資などを加えた財政支出72兆7,000億円を含む、新型コロナウイルス感染拡大に対応する緊急経済対策の事業規模117兆1,000億円程度になる31兆9,114億円余りの第2次補正予算案を、5月27日、閣議決定しましたが、不足する財源は、赤字国債をさらに追加で発行して賄うことになり、発行する国債の内訳は、赤字国債が22兆6,124億円、建設国債が9兆2,900億円となり、当初予算と第1次補正予算を含めた今年度の国債の新規発行額は、過去最大の90兆2,000億円に達し、歳入の56.3%を国債に頼ることになります。世界経済の急激な減速と、世界一の借金大国日本の財政事情を考え合わせると、新型コロナウイルス感染収束後の日本国民の大幅な税負担、並びに自主財源の脆弱な出水市への地方交付税の激減を憂いながら、質問をしてまいります。
まず、小水力発電事業の売電収益の基礎についてお伺いいたします。
今月6月2日に式典が行われた高川ダム小水力発電事業は、平成21年度小水力発電工事等技術強化対策事業鹿児島地区の3地点、宇検村アランガチの滝、霧島町田口用水路、出水市高川ダムの1つとして、平成21年に事業採択、補助金交付決定を受けた事業であります。
出水市は、平成24年に出水市高川ダム小水力発電施設検討協議会設置要綱を策定し、渋谷俊彦市長のもと、鹿児島県土地改良連合会、九州農政局、鹿児島県農政部、出水市職員、出水平野土地改良区理事長、広瀬川漁業協同組合組合長、市長が必要と認めた人たちからなる協議会を立ち上げて、この事業に取り組み、足かけ8年目での完成となります。その間、行政もできなかった難事業を成功に導いたのは、野中正己理事長と川崎勝副理事長に、今は退職されている柿野担当職員でありました。上京し、当時の農林水産委員長、野村哲郎参議院議員、森山裕農林水産大臣、金子万寿夫地方創生本部長補佐、尾辻秀久参議院議員、経済産業委員野間健衆議院議員の国会議員の先生方には、それぞれの立場で多大なる御尽力を賜りましたこと、この場を借り、出水市の農家の方々を代表して心から厚く感謝・御礼申し上げます。また、当時の農林水産省、三浦農村振興局長様には、小水力発電はもとより、応急対策事業の手順や取り組み方、出水平野土地改良区組合員農家の負担軽減、並びに日本政策金融公庫より、償還期間据え置きの一番長くて一番金利の安い資金調達まで御協力をいただき、お礼の申しようもありません。本当にありがとうございました。
さて、高川ダム小水力発電施設は、年間約178万キロワットの発電量で、売電収益はおよそ年間5,000万円となりますが、高川ダム管理施設等で年間約900万円ほど使用しますので、4,100万円の収益が推定されます。日本政策金融公庫の償還も含め、売電収益の使途について伺います。
次に、国営基幹水利事業応急対策事業は、どのような手順で進めていかれるのかお尋ねいたします。
以上、2問の質問を、高川ダム小水力発電施設の完成を見ることなく故人となられた、難事業の高川ダム小水力発電施設整備と応急対策事業を、成功に向かい全身全霊で戦ってきた戦友・同志、野中正己氏にささげる質問といたします。
以上です。
○椎木伸一市長 おはようございます。宮田幸一議員の御質問にお答えします。
小水力発電設備につきましては、先ほどお話がありましたように、前理事長であられる野中正己氏の非常な御尽力のたまものと、心から敬意を表し、感謝を申し上げ、御逝去に対しまして哀悼の意を表したいと思っております。
小水力発電設備については、本年5月の工期をもって完成し、先日、発電式が実施されたところであります。これまで、この事業実施に当たり御尽力いただきました農林水産省、鹿児島県、関係議会議員、工事施工関係者の皆様には感謝申し上げます。また、出水平野土地改良区におかれては、組合員の皆様方の負担軽減はもとより、さまざまな事業推進に取り組んでいかれることを期待し、出水市としても、老朽化した施設改良等の事業推進を図りたいと考えています。
御質問の小水力発電事業の売電収益の使途についてですが、発電した余剰電力を電気事業者に売電した収入の充当先は、施設において必要な電力の購入に係る費用、発電施設の運営に必要な費用、発電施設にかかわる水路・取水施設等の維持管理費、発電施設を維持するための積立資産等、土地改良施設全体の維持管理費となっています。売電収入が土地改良施設全体の維持管理費に充てられることにより、維持管理費の負担が軽減され、組合員から徴取している賦課金の一部を水利施設の更新事業積立金とすることで、今後の大規模な土地改良施設を更新するための費用に充てる計画です。
次に、国営基幹水利事業応急対策事業についてですが、基幹水利施設の多くが、整備から約40年経過し、老朽化が急速に進行するなど、今後、突発事故の増加や機能低下が懸念されています。このようなことから、基幹施設の機能診断により緊急性が高い施設については、早急に取り組める事業等があれば積極的に要望し、実施に向けて、県、国、関係機関と協議を進めていきたいと考えています。
○15番(宮田幸一議員) 今、答弁を聞いていまして、売電収益の使途は出水平野土地改良区全体の維持管理ということで、そのとおりの答弁だとしたら、現在まで行われている基幹水利施設管理事業で実施されている国営施設の維持費は、二重の補助金を適用していることにはならないのでしょうか。
○椎木伸一市長 二重の補助金を適用しているのではないか、というようなことでございますけれども、売電収益の使途については、先ほど答弁で申し上げましたように、今回の収入については、将来の水利施設の更新事業の積立金とすることで、賦課金の一部からの積み立てということでございますので、収入については維持管理に使うというようなことでございます。これは、そのような使途でいいというような解釈になっておりますので、あくまでも、将来的に更新するような積立金については賦課金の一部を充てるというような考えでございまして、補助金の二重受け取りというようなことにはならないというふうに考えております。
○15番(宮田幸一議員) 先ほど市長は、出水平野土地改良区全体の維持管理費にも売電収益を使うと言われました、だから、私はこれを聞いているんですが。いいですか、現在、国営施設は、基幹水利事業を通して、国30%、県30%、出水市20%の補助金をいただいて運営されていることは御存じですよね、そうすると二重になりませんか。
○椎木伸一市長 負担割合はそのとおりになっていると思いますけれども、詳細につきましては農林水産統括監のほうから答弁をさせます。
○東畠賢一農林水産統括監 宮田議員おっしゃるとおり、基幹水利事業については、国から補助金をいただいて運営をしております。その観点からいきますと、補助金の二重取りになるか、ならないかというお話ですけれども、今後、基幹水利、国から補助金をいただいて運営をしております分については、国からいただいている運営費の中から、基幹水利のほうの施設についての改修等はしていくと。その関係で、小水力発電の運用益については、直接、基幹水利の国営の施設には使えないということになっております。
○15番(宮田幸一議員) 今、東畠さんの答弁が一番、市長より正確なんですが。だとしたら、既存の基幹水利事業のお金と、小水力発電による売電収益のお金の使い分けというか、すみ分けが必要だと思うんですよ。だから、その辺を答弁していただきたかったんですが、いかがでしょうか。
○椎木伸一市長 先ほど統括監のほうから詳細について説明があったとおりでございまして、発電事業を実施することで、おっしゃる売電収益で維持管理費の負担が軽減されるわけでございまして、土地改良区では、大規模な土地改良施設を更新するための費用としてその賦課金を更新の積立金とするということで、売電収入は応急対策事業等に充てることはしないというような使い分けをしていかなければならないと思っているところです。
○15番(宮田幸一議員) 私がこの質問をした真意は、全体の小水力発電の事業費用の50%を国が、そして県は15%、出水市は12.5%負担したにもかかわらず、事業費用の22.5%を負担した出水平野土地改良区が売電収益の全額を使用できることへの感謝を忘れることなく、組合員農家への賦課金の増加にならないための戒めになればと念じて質問をしているわけでございますが、このことに対しての市長の御意見、御見解をお願いいたします。
○椎木伸一市長 賦課金については、おっしゃるとおり、こういった収入の施設もできているわけですので、そういったものを将来の事業をする積立金に充てるわけですけれども、賦課金の一部を事業積立金に充てるわけですけれども、そういったことで収入を農家負担の軽減につなげる、そのことが出水市の農業振興につながっていくというような考えのもとに、出水平野土地改良区におきましても、農家負担の軽減ということが大きな目的であるということは念頭に置きながら事業実施をしてまいりたいと考えております。
○15番(宮田幸一議員) 次の質問に移ります、時間が20分ですので。国営基幹水利事業応急対策事業の質問をこれから進めていく上で、理解を深めることが必要だと私は考えますので基礎的なことをお尋ねいたします。市長、水利権は幾つあるんでしょうか。
○椎木伸一市長 水利権の詳細等についての御質問ですけれども、農林水産統括監のほうから答弁をさせます。
○東畠賢一農林水産統括監 水利権の関係でございます。高川ダムと五万石頭首工に水利権がございまして、こちらが国営の施設となっております。水利権については、国が持っているということだと思います。
○15番(宮田幸一議員) 私は、水利権には幾つあるんですかと聞きました。質問する人が答えていいのかどうかわかりませんが、水利権は2つしかございません。慣行水利権と許可水利権です。出水市が今もらっているのは、許可水利権だということであります。
そこでお尋ねしますが、では、東畠さんが答えられましたけれども、出水市での基幹水利事業の水利権者はどなたでしょうか。
○東畠賢一農林水産統括監 水利権者は九州農政局となっております、国営施設についてはですね。あと、県施設については鹿児島県ということで理解をしております。
○15番(宮田幸一議員) 正確に言いますと、国営基幹水利事業の水利権者は、ちゃんと国にも確認しました、農林水産大臣殿です。そして、県の、例えば沖田大井手頭首工、六月田左岸の頭首工の水利権者は、鹿児島県知事であります。
それでは、水利権を得るには、河川法で定めた関係者との同意が必要なことから、応急対策事業を実施するにも関係者との協議が必要だと思いますが、市長の御見解をお願いいたします。
○椎木伸一市長 協議すべき事項は、協議することが必要であると考えております。
○15番(宮田幸一議員) 1回目の壇上での答弁で、市長が、国と県と協議していくと言われたから、ちょっと私も質問したんですが。
それでは、さらにお尋ねします。椎木市長になってから、県の担当課に出水市からの相談は全くないと聞き及んでいます。きのうも県庁に行ってまいりました。市長も御承知のとおり、出水市が直接農林水産省に事業申請はできないことになっています。事業申請は、県が申請し、国が採択する仕組みになっておりますので、応急対策事業が令和3年度で期限切れとなりますので、他の事業で国営基幹水利事業の老朽化した施設の機能を長期的に保全する事業を探したら、国営施設機能保全事業がありましたので、よくよく持ち帰って関係書類を勉強してみましたところ、受益面積が3,000ヘクタール以上の規定にぶつかりました。出水平野土地改良区は、農地をだんだんだんだん宅地に、4条申請、5条申請が可決されて広がっていったために、まことに残念ながら現在の出水平野土地改良区の受益面積は3,000ヘクタールを切っていることから、この事業は国の事業採択案件を満たさないことが判明いたしました。
そうなると、当然、農地の受益面積が減るわけですから、水利権の決めてある水利使用規則の水利の使用量も減らされることになりますが、市長は、このような状況下でどのようにして国営基幹水利事業、並びに国営基幹水利の長寿命化対策事業に取り組んでいかれるのでしょうか。
○椎木伸一市長 先ほどおっしゃった事業については、3,000ヘクタール以上の受益がないとできないということで伺っております。大隅半島等で実施されている事業であったかというふうに認識しておりますけれども、応急対策事業等については令和3年度で終了いたします。以前、答弁した経緯がありましたけれども、私どもとしては、令和4年度以降の事業の詳細等を見極めながら、はっきり内容等がわかる段階で、現在、期成会等をつくっておりますので、そちらの団体等を通じ、県に申請を要望をまずはして、そのあとで県との協議を重ねながら申請、それから県のほうから国に申請してもらうという手はずで事業を実施していきたいと思っておりますけれども、それまでの間はいろんな事業を探しながら対応せざるを得ないと考えているところです。
○15番(宮田幸一議員) 市長は、多分そう答弁されるだろうと思って、きのう、実は、農地整備課の中にいらっしゃる国営事業対策監ともよく話をしてきました。先ほど私が言いました、応急対策事業にかわる国営施設機能保全事業を勉強するために、実はおっしゃるとおり大隅半島笠野原土地改良区に行ってこういう事業をやったということで、そこは応急対策事業でなくて、私が先ほど申しました国営施設機能保全事業で、これはもうまもなく終わるところです。そういう事業をされています。
そこで、市長が先ほど言われましたように、令和3年度で応急対策事業は切れるけれども、私、直接農林水産省本庁にも聞きました、今後どうなるんですかと聞きましたら、応急対策事業は令和3年度で切れるけれども、それからさらに延長するか、もしくは違う事業名でこの事業ができるようにするか、今審議中であって、令和3年度末には答えが出ます、ということでしたので、その答えを持って、きのう、県の農地整備課の国営事業対策監とお話ししました。そうしたら、いずれにしても準備期間に相当かかるし、先ほど市長も言われましたけれども、まず、出水市が直接農林水産省に事業申請することはできない仕組みに法律でなっていますから、県を通じなくてはいけない。だったら、県と早めに協議をして、令和4年度から始まる事業をスタートしないと間に合いませんよね、というのが県の対策監のお話でした。
その辺について、出水市は今何もしてないということですが、それで本当に、私の質問じゃないですが、以前の質問で、出水平野土地改良区さんとは緊密に連携をとりながら、必ずこの事業はやっていきます。と、どなたかの質問に対して答弁されているんですが、それでは、今何もほったらかしてしていない中で、令和4年度からどういう事業ができるのでしょうかお尋ねいたします。
○椎木伸一市長 おっしゃるとおり、申請をする段階からしますと、3年以上かかるように聞いております。ですから、先ほど答弁いたしましたように、そこまでの間は、いろんな事業を充てながら維持管理をしていくというように考えているところでございます。
詳細については、農林水産統括監のほうから答弁をさせます。
○東畠賢一農林水産統括監 県庁の坂口対策監とお話をされたということで、先ほど紹介いただきました事業についてはおっしゃるとおり、出水平野には該当しないということでございます。
それから、応急対策事業についても令和3年で切れますけれども、今後、このまま補助率等を引き継いで新しい事業にいくのか、さらに新しい事業で、補助率が変わるのか、そのあたりを研究をしていきたいというふうに考えております。
さらには、国営の事業については、まず国が100%の予算で調査をし、計画等を立てたものを、先ほどおっしゃったように、出水市のほうから県のほうに計画等の申請をして、最終的に確定をするという事業になっておりますので、現在、九州農政局のほうでも、前に調査をしました長寿命化の施設等の再調査等をしていただいております。ちょっと、コロナの関係で調査等とまっておりますけれども、今後、そちらのほうが随時進んでいくようであれば、そちらの国の中身を見ながら、早めに申請できるものについては申請をしていきたいというふうに考えております。
○15番(宮田幸一議員) ちょっと僕の聞き方が悪かったのかな。結局、それまでの間にできる仕事っていっぱいあるんですよ。だから、私、きのう行ってきたんです、県に。もともと言うと、国の調査によって応急対策事業の本当に出水市にある国営基幹水利事業に必要な金額は、今申し上げますけど、60億円の事業でした。ところが、これはどうしても受益者負担が伴うために、出水平野土地改良区さんにそれだけの受益負担金を払うだけの経済的力がないだろうということで、国が見直して40億円の、当時の応急対策事業となって、その計画を立てて、その上でこの小水力発電に持ち込んでいろんなことをやったというのが実状です。
ですから、おっしゃるとおり、国は1回調査をしておりますので、再調査をしているのは知っています。なぜかと言うと、熊本地震の影響で出水の高川ダムにどれだけの影響があったのかということが、まだ調査が済まれていないので、その部分はわかります。でも、その間にしなければいけない書類的な手続、事務的な手続というのがいっぱいあるのも、私は承知しております。ですから、本来ならば、県に出向いて、県を通じないと申請できませんから、それで、今、どの辺までいっているか、どうなのか。そして、応急対策事業が、また引き続き事業延長をされるのであれば、そこについてはこういう手続が必要だね、でも、名前を変えて、同じような国庫の補助率で、もう御存じだと思いますが、応急対策事業は国が60%基本的に、あと加算率というのがありますが、農地の条件について、60%、国が補助金を出す事業だということは、市長は御存じなくても東畠さんは御存じだと思います。ですから、その辺のことをかみ合わせれば、当然、今、既に協議を県としないと、じゃあ、いざ国の制度が決まった、スタートといったときは、私は大変遅くなるんじゃないかと思いますが、その辺を聞いています。その間にいろんな事業を使って、椎木市長はするんだと言われましたが、じゃあ、例えばどういう事業で、国営基幹水利施設の老朽化したところをどんな事業名を持ってやられるのか教えていただけませんでしょうか。
○東畠賢一農林水産統括監 新たな事業というのは、先ほど宮田議員も御紹介いただきましたとおり、この応急対策にもちろん間に合えば一番いいんですけれども、加算率等があるということで、60%以上の補助金が国から来るということでございました。
新たな事業というのは、国営の場合は、先ほどから申し上げているとおり、国が調査をして、県に市が上げていくということになりますので、今のところ、その他の大きい補助事業というのは現在見つかっておりません。ということで、宮田議員がおっしゃるとおり、県のほうとの協議については、今後もさらに充実させていきたいというふうに考えております。昨年度は、何回かこちらにも来ていただきました。施設等も見ていただきましたけれども、直接、県の本庁に行ったのは1回か2回、別件も含めて行かせていただきましたけれども、今年の新しい対策監とはまだお話ができていない状況でございますので、今後については、県とも十分協議を進めていきたいというふうに考えております。
○15番(宮田幸一議員) 私は名前を出さなかったけれども、あなたが名前を出されたから言いますけど、私が聞いて回ったのは、今はあなたがおっしゃる坂口対策監です。その前は西園対策監です、その前は山下対策監です、この三者に、大分前から私はこのことを聞いておりますけど、1回も相談にいらっしゃったことはないと答えています。ですから申し上げたんですが。
市長も答弁で、何も知らない人が聞いていると、さも何か、その間に何か違う事業でやると言われたんですが、それはできないことになっています。前、大橋副市長が、他の議員の質問のときに、それは、出水の農家の方、農協を入れて、出水平野土地改良区何とか協議会をつくって、と言われましたが、それも国に確認しました。その事業では、国営水利の事業はできないそうです。だから、国営基幹水利というのは、それだけに重みがあって、国営ですから、それだけのもので、その他の事業では適用できないということです。
それで、ちなみに、御存じかどうかわかりませんが、国営基幹水利事業というのは、要するに国営基幹水利を持っているところ、鹿児島県内にどれくらいあるか御存じでしょうか。
○東畠賢一農林水産統括監 済みません、全体像については調べておりません。
○15番(宮田幸一議員) もう御存じだと思いますけれども、南薩にもあります、先ほど市長が言われた大隅、要するに笠野原ですが、土地改良区、そこもありますし、鹿児島県の場合、離島が多いです、奄美大島の中の喜界島とかいろいろそういうところにありますから。国会議員の先生方は自分の選挙区なので、必死になってそこあたりは取り組んでいらっしゃるということを申し上げると同時に、もう少し早いアクション、行動を起こして、出水の農家が安心するようなことをしていただきたいというふうに切に要望しておきます。
それでは、野中正己氏の安らかな眠りを祈りつつ、私の質問を終わります。
○議長(杉本尚喜議員) 次に、垣内雄一議員の質問を許します。
○18番(垣内雄一議員) 世界中に大流行した新型コロナウイルスでありますが、去る5月25日、緊急事態宣言が解除されております。しかしながら、依然として世界の国々においては感染者また死亡者も後を絶ちません。これまで亡くなられた方々に対し、心より御冥福をお祈り申し上げます。なお、療養中の方々に対しましても、一日も早い回復を願うものであります。
本市には、現在のところ感染者も出ていないところでありますが、さらに危機意識を持ちながら邁進してまいりたいと考えます。これらの対策等につきましては、国・県のさまざまな制度、あるいは対策が打ち出されております。出水市におきましてもいち早く受けとめて、スピード感を持って対処されておりますことに感謝申し上げたいと存じます。市長を初め職員の皆様に対し御慰労申し上げ、通告に従い質問をいたします。
まず、新型コロナウイルス対策の中で、特別定額給付金の支給状況についてでありますが、昨日も対策会議の結果が報告があったところでもございます。これは、1人10万円を、家計の支援として給付するものでございまして、本市においても早々と申請請求の運びとなり、約1週間ぐらいで口座振込が終わり、市民の方々の反応も極めて良好だと伺っております。心配しておりました高齢の方の申請ミス、あるいは金融機関等の口座等の問題などの点で不安要素もあるのではないかと想定しておりましたが、5月11日より本庁で、また、5月25日より市内自治会での出張申請を実施されております。それらを含めて、今日までの支給の状況と、トラブル等の発生は生じていないのかについて、まずお伺いをいたします。
次に、教育行政についてでありますが、コロナウイルスが発生して以来、児童・生徒に関する情報並びに学校関係の現状等については、市の感染症対策本部会議より結果報告がその都度ございまして、ある程度のことは理解をいたしております。特に春期休業期間中における児童・生徒の家庭内での過ごし方や家庭学習のあり方など、また心身の健康保持増進に努めるなど、大変だったろうと考えております。その後、5月11日より、全市立幼稚園や小・中、義務教育学校、出水商業高校の教育活動を再開することになり、幾らか安心したところでもございます。しかし、児童・生徒の中には、部活動あたりの取り組みも満足いくものではなく、大きな大会等の中止により目標を失い、精神的ショックは計り知れないものであろうかと考えます。もろもろ、感染症拡大の状況に目をとめながら、変化していく日々を複雑な心境で見守ることしかできないものでしょうか。児童・生徒の心中を察し、適切なアドバイスを提供できるようになればと考えるところでもあります。
そこで、次の4点についてお伺いをいたします。
まず、学校の休業により授業日数が減少しておりますが、どのように考えているのかお伺いをいたします。
2点目として、中体連・高体連にあっては、各種大会等が軒並み中止になっておりますが、教育的見地からどのように対処されるのかお伺いをいたします。
3点目として、今日のような緊急事態は、今後もあり得ると考えます。そこで、これからの教育に求められるものとして、家庭の中での授業、つまりオンライン方式について、どのように考えているのかお伺いをいたします。
4点目、家庭学習と読書の重要性についてどのように捉えているのか、さらに、読書活動の今日の成果は向上しているのかどうかについてお伺いをいたします。
次に、大きな3点目でございます。出水総合医療センターについてお伺いをいたします。
去る3月いっぱいで退職をされました今村前事業管理者が、4年間の在任中に大変御尽力をいただきました。本当に御苦労様だったと思っております。さて、4月1日付の新たな人事異動によりまして、新しく、鮫島幸二事業管理者を迎えることになり、大いに期待をし、また感謝申し上げたいと存じます。前任者も、赤字部分の大変大きい中に飛び込んでいただきました。今回は、それに加えて新型コロナウイルスの真っただ中に就任をされ、ひときわ御苦労もあるんじゃないかと考えます。しかし、出水市民が最も頼りにしているのが出水総合医療センターでございます。この非常事態であればこそ、鮫島新事業管理者を初め病院のスタッフ一同と市民とともに、また、私ども議員も一緒になって、この難局を乗り切っていけるように力を尽くしていくべきかと思っているところであります。
そこで、次の2点につきお伺いをいたします。
まず、コロナウイルス発生後の今日の入院、手術、外来患者等の動向、収支について、どのように推移しているのかお伺いをいたします。合わせて、医療用備品、マスク、ガウン、消毒液等は充足しているのかどうかお伺いをいたします。
2点目として、医師招聘、看護師確保の取り組みの状況についてお伺いをいたしまして、壇上からの質問といたします。
○椎木伸一市長 垣内雄一議員の御質問にお答えします。
戦後最大の生活・経済危機とも言われている新型コロナウイルス感染症の影響に対しては、迅速で時期を逸しない対応が最も重要なこととの認識のもとに、市職員一丸となって市民生活を守るための施策を講じているところです。
特別定額給付金事業については、国の予算が成立した翌日、5月1日に申請書を発送し、同11日から給付を開始しました。受付は郵送を原則としまして、本庁多目的ホールに受付窓口を設置したほか、御案内のとおり、市内180カ所の自治公民館で出張受付を実施しました。その間、1日当たり最大80人の職員体制で申請内容の審査やデータ入力などを行い、できるだけ早急に給付するよう努めてまいったところであります。
御質問の給付状況ですが、6月10日、昨日現在ですけれども、全世帯の約97%に当たる2万4,651世帯に約52億円を給付しているところです。なお、これまでの迅速な対応に対して、市民の皆様から多くの感謝の言葉を頂戴しました。本市がここまで早く実施できたのは、税務経験者でつくる特別班を中心に、部局を超えた職員が休日・夜間を問わず業務に当たったこと、独自にソフトを構築することができるスキルを持った情報課職員がいたこと、そして何より、職員一人一人が市民生活を守るという強い使命感で業務に当たった結果であると考えております。
今後については、受付期間終了となる8月7日まで、防災行政無線等を活用した広報を行うなど、給付率の向上に努めていきます。
次に、教育行政の家庭でのオンライン方式での授業に係る、その前提条件となる市全域でのインターネット環境の整備状況について、私のほうからお答えし、後ほど教育長から、教育行政における具体的な取り組みについて答弁させていただきます。
家庭でも授業が受けられるオンライン方式を導入するためには、まず、出水市全域で光ファイバー網を使用できる環境を整備する必要があると考えます。高速通信基盤は、スマート農業や学校教育、定住促進、企業誘致、経済活動、地域バランスのとれた地域振興などさまざまな分野でICTを利活用する上で必要不可欠なものです。例えば、道路や橋梁など社会基盤と同様に、重要な社会インフラであると認識しています。しかしながら、本市の光ファイバー網の整備状況は、世帯数で見ますと94.7%となってはおりますが、未整備地区の大川内地区及び江内地区内等の小学校4校、中学校2校を光ファイバー整備地区の学校と比べますと、通信環境が劣る状況となっております。
市民がICTを利活用するためには、市全域での光ファイバー網整備が必要であることは認識しており、財源等で有利な条件がないか、これまで国の動向を注視しておりました。今般、国は新型コロナウイルス感染症への対応を進めるため、新たな日常に必要な情報通信基盤の整備が急務と位置づけており、また、国の補正予算での整備を予定していることから、まずは情報通信格差解消に向けた未整備地域への光ファイバー網の整備を進めてまいりたいと考え、今年度中の予算化に向け、国の事業採択等へ向けて準備に取り組んでいるところです。
私からは以上です。
○溝口省三教育長 おはようございます。垣内雄一議員の御質問にお答えをいたします。
まず、学校の臨時休業による授業日数の減少への対応についてですが、今回の新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業の期間は、昨年度が3月3日火曜日から3月25日水曜日まで、今年度は4月22日水曜日から5月10日日曜日まででございました。臨時登校日や卒業式、終業式等の日を除くと、昨年度が14日程度、今年度が7日程度の授業日数の減少になっています。
3月の学習内容については、学年末の復習が中心であったことから、臨時休業中に課題プリントを配布して、家庭学習として取り組ませるとともに、新学年の4月当初に授業で確認したり、補充指導を行ったりして対応をしてきたところです。また、今年度の臨時休業の補充については、行事の精選や中止などによって授業日数の確保に努めております。小学校6年生や中学校3年生については、特に学習の遅れが生じないように補充指導等を充実させながら対応しているところです。
今後、地域内で新型コロナウイルスの感染が確認された場合などは、再び学校の臨時休業を実施しなければならないことも想定されます。子供たちの学力を保障するという観点から、長期休業の短縮等も含め、授業日数をどのように確保していくか検討してまいります。
次に、各種大会が軒並み中止になっていることへの対応についてお答えをいたします。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、全国・九州レベルの各種競技大会の中止が決定され、鹿児島県においても県中学校総体及び高校総体が中止になりました。特に、この夏の大会を集大成と位置づけ、日々、仲間と切磋琢磨し、部活動に取り組んできた3年生にとっては、新型コロナウイルス感染拡大防止とはいえ、目標を失い、持って行き場のない複雑な気持ちであろうと思います。そこで、中学校においては出水地区の2市1町で協議をし、全国・県の各種競技大会、協会・連盟等の方針を踏まえるとともに、開閉会式の中止や試合方式の簡素化、選手・観客の人数制限、3密を防ぐ会場設営など、できる限りの感染防止策を講じた上で、地区大会としての陸上競技を7月2日に、その他の競技を7月22日と28日に実施することを決定しました。また、出水商業高校においては、種目に応じて、近隣の二、三校での練習試合や県高体連の指定する少数の学校での交流試合、部活動内での紅白試合など、3年生の引退試合として企画し、6月中に実施することになっております。中・高の3年生が、これらの大会・試合を1つの区切りとして、これまでの部活動で培ってきたさまざまな力や人間性・社会性を、新たな目標に向けて発揮してくれることを期待しております。
次に、家庭でのオンライン方式による授業についてお答えをいたします。
今後、新型コロナウイルス感染症の第2波、第3波の発生が懸念され、再び臨時休業を実施しなければならない状況も考えられることから、オンライン方式による授業を実施できる環境の整備は必要であると考えます。しかし、現在の本市のICTの状況では、オンラインによる双方向での授業の実施や、学習課題等の配布は難しい状況にあります。
そこで、本市においても、現在国が進めているGIGAスクール構想を推進し、校内LANの整備や全小・中学生が1人1台の端末を使用できる環境を整備したいと考え、6月の補正予算に計上したところでございます。
GIGAスクール構想は、児童・生徒一人一人の教育的ニーズや理解度に応じるとともに、コンピュータをツールとして、考え、表現し、友達と考えを伝え合う、個別最適化された学びを実現することを目的としております。児童・生徒が、家庭でオンライン授業を受けるためには、端末とインターネット環境が必要となります。端末については、GIGAスクール構想により1人1台端末が配備されることから、その端末の貸し出しによる家への持ち帰りや、各家庭におけるインターネットの環境整備も必要になるという課題があります。加えて、オンライン授業を効果的に行うための教員の研修も早急に進める必要があります。来年度は、GIGAスクール構想の実現に向けICT利活用に係る研修を、年間を通じて重点的に進めてまいります。
今後、災害や感染症等により臨時休業を余儀なくされた場合の学力保障のため、オンライン環境の整備を早急に進めてまいります。
次に、家庭学習と読書の重要性と活動の成果についてお答えをいたします。
まず、学校休業中における家庭学習支援の取り組みとして、市ホームページに家読推薦図書の一覧やALTによる英語活動動画、学習資料等を掲載し、家庭教育の支援を行ってきました。読書活動推進の成果としては、昨年度、高橋松之助記念「朝の読書大賞」を、全国の高等学校の中から、唯一出水商業高等学校が受賞し、西出水小学校が優秀校を受賞しました。また、平成18年度からこれまでに、市立図書館、2つのボランティアグループ及び5つの学校が文部科学大臣賞を受賞しました。本年度は、おはなしボランティアグループ「紙ふうせん」が文部科学大臣賞を受賞しております。
また、市立図書館の利用については、新型コロナウイルス感染症拡大防止による全館休館日数が合計で27日となります。3月と4月は、特例として貸出期間を最大3週間とし、貸出冊数を無制限にしました。昨年同時期と比較すると、児童・生徒の貸出冊数は17%の減少となったものの、開館日における1日当たりの貸出冊数は18%の増加となりました。なお、出水商業高等学校の学校図書館利用については、開館日数が5日間減少したにもかかわらず、1人当たりの貸出数が2倍ほど増加しております。新聞報道によると、全国では休業中の過ごし方でふえた時間は、テレビやビデオ視聴80%、インターネット動画視聴62%、ゲーム52%で、読書の時間がふえた報告はありませんでした。しかし、市立図書館や学校図書館が閉まっていても、出水の子供たちの読書量が大きく減っていないということは、児童・生徒が本に親しみ、読書を楽しむ手だてがなされているからだと考えられます。読書を楽しむうちに、感動する力を培い、語彙力や表現力、思考力を高め、主体的に生きていく力を養うことは、将来の人づくり、ふるさとづくりにつながります。新しい生活様式を踏まえた取り組みをしていかなければならないこのようなときだからこそ、子供から大人までの読書活動の取り組みは、子供たちにとっても、家庭教育にとっても意義のあることです。
今後も、家庭教育の充実を図るとともに、読書活動日本一のまちづくりを推進するために、幼稚園や保育園を初め各学校、関係団体、関係機関及び図書館等と連携を図り、新しい生活様式を踏まえた読書活動の推進に努めてまいります。
○鮫島幸二病院事業管理者 おはようございます。垣内雄一議員の御質問にお答えします。
まず、出水総合医療センターにおける新型コロナウイルス感染症発症後の入院、手術、外来患者等の動向及び収支状況の推移についてですが、入院患者数が、前年同月と比べ、3月は特に影響はありませんでしたが、4月は延べで約300人減少したことによりまして入院収入が減少しております。一方、手術件数や外来患者数は、前年同月より若干増加しております。なお、入院患者数につきましては、5月中旬まで減少傾向にありましたが、その後、徐々に回復の兆しを見せ始めております。医療用消耗品等については、全国的にマスクが入手困難となった3月ごろは、1カ月分程度の保有数となっておりましたが、現在では、市や幾つかの企業から提供を受けたり、国からの配布などもありまして充足されつつあります。
次に、医師招聘についてですが、3月から、麻酔科は医師1人が増員して2人体制になり、4月から、整形外科が2人増員し3人体制となりました。さらなる医師招聘に向けて、大学医局を訪問したいところでありますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、現在自粛しているところです。徐々に移動制限が緩和されつつありますので、今後、早い段階で医師招聘活動に取り組んでまいります。
次に、看護師確保については、南館3階第2病棟の再開に向け精力的に取り組んできた結果、採用見込みを含めて17人の増員となり、ほぼ充足する見込みとなっています。
○議長(杉本尚喜議員) ここで暫時休憩いたします。再開を11時15分といたします。
午前10時57分 休 憩
午前11時15分 再 開
○議長(杉本尚喜議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。垣内雄一議員の質問を許します。
○18番(垣内雄一議員) それぞれ御答弁ありがとうございました。あと、二、三お伺いしたいと思っております。
定額給付金の支給の期限は、8月7日だというふうに記憶いたしておりますが、あと残り、およそ2.5%ちょっとであります。私は、このことにつきましてはやっぱり100%達成できるように、ぜひひとつお骨折りいただきたいというふうに考えております。もう御承知のとおり、このことによって地域経済に幾らかでも消費が拡大されまして潤いが出ればというふうに考えておりますので、どうかひとつその点を十分加味していただきながら、最後まで周知徹底方よろしくお願い申し上げたいとこのように思っております。
それから、教育行政についてでございますが、教育長のほうからるる御答弁をいただきました。今年は、出水の子供たち、生徒だけでなく、全国、これは関連するんですけれども、受験生にとっては、特に今年は不利な条件下に立たされているんじゃないかというふうにも思っておりますが、このことについて教育長の何か見解があればお聞かせいただきたいと思います。
○溝口省三教育長 先ほども申し上げましたように、国のほうも、特に小学校6年生、中学校3年生、もちろん高校3年生もそうですが、その授業日数については大変危惧されておりまして、鹿児島県の場合、特に出水市の場合は、先ほど申しましたとおり、昨年度が14日程度、今年度が7日程度でございますので、それぞれ今から、3月の14日の場合は、授業がほとんどある程度終わって、復習の段階に3月は入っているわけなんです。しかしながら、やっぱりそれを引きずる学年もございます。そういうことを考えますと、今後、その時間をやっぱりある程度補っていかないとならないということで、長期休業中等、どのような形で授業を行うのか、行わないのかというのは、今、校長等と話し合いをしているところで、特に受験生については、全ての内容が本年度中に終わるように努力をしてまいりたいと考えております。
○18番(垣内雄一議員) 2点目の、中体連、高体連の件でありますが、徐々にいろいろ新聞・テレビ等を見ておりますと、各種の大会が、各県によって、あるいは九州全体によって、いろんな緩和されつつございます。けさの新聞を見ておりましても、選抜の32校が甲子園大会へ交流試合をやるという、大変楽しみな喜ばしいニュースが入ってまいりました。
そこで、1つ御紹介しておきたいことがあるんですが、実は、我が出水市にも関連をいたしますけれども、6月5日の「編集局日誌」という南日本新聞の記事が小さく載っておりました。「信頼の置ける指導者」ということで、今年は御承知のとおり、新型コロナウイルスの影響で競技大会中止が相次ぎ、進路を決定する上でいろんな判断材料がほとんどない事態に見舞われていると。そんな中、出水体操クラブ監督の松本監督が、選手の夢を壊すまいといち早く行動に出た。例年ならば、九州、全国と大学側にアピールできる舞台であったはずだが、それがなくなった今、選手の力を少しでも示そうといろんな技を試技を動画で撮って、大学側に送っているそうでございます。目標としていた大会がなくなっても、選手は冷静に受けとめ、次に向かって、現在も練習に励んでいると。できることはやってあげたい、と話す監督の松本さんでございますが、そういった選手の可能性を広げられるということに非常に、苦楽をともにしてきた、いわばお互いが信頼できる間柄だなというふうに感じたところですけれども、教育長はこれについてはどのように感想をお持ちか、よかったらお聞かせをいただきたいと思います。
○溝口省三教育長 出水商業高校の体操の同好会につきましては、圭成さんのお父さんである俊一さんも何回も来られまして、ぜひ出水商業高校でやりたいということで話を持ち込まれました。その熱意といいますか、ただ者ではないなと、私は感じました。それは、子供たちをどうされるかというと、ただ、体操で強くなるというのではないと、私は子供たちに、本当に生きるための生き方や人生観を教えたいと、だから、寮を持っているけれども、その寮の中でも宿題が終わらなければ練習はさせないとか、成績表も必ず提出をして、成績が落ちるようであれば練習をやめさせるとかという話をされて、それから何年かたったわけですけれども、その成果が令和元年度だけでも、県高校体操競技大会では男子団体優勝とか個人優勝、2位、3位と、そして九州大会2位とか全国大会13位とか、県新人大会等でも同じような成績を残されて、私は、やっぱりトップのアスリートを育てる指導者というのは、それなりの力量というか、あるいは人を人として育てるということが大事だということを言われまして、非常に感服して、出水商業で頑張っていただくことを大変ありがたく思っております。
○18番(垣内雄一議員) ほかにもいろんな、各少年団体の監督さん、コーチさんいらっしゃるかと思うんですけれども、やはりそういう方々と、学校、あるいは教育委員会一緒になって、いろんな生徒さんの悩み、しっかり寄り添っていただければなというふうにお願いをいたしておきたいと思います。
それから、オンライン方式についてでありますが、今後第2波、第3波のことも考えますと、先ほど市長も教育長も申されますように、早く通信環境を整えて取り組みたいと。私も心配しておりましたのが、やはり光ファイバーの回線の整備状況が、大川内、江内地区、もう早くから言われておりますけれども、なかなかこれが進んでいなかったというのは承知しております。ですから、今年度中に予算化をするという意気込みでございましたので、大変この点については、私も喜んでいるところでございます。そういうところに、しっかりと行政がてこ入れをして、全生徒にこれが行き渡るようなそういう体制づくりをぜひ実行していただきたいというふうに思っておりますけれども、市長、もう一回その辺の決意のほどをお願いしたいと思います。
○椎木伸一市長 詳細については、教育長からありましたようにGIGAスクール構想ということで今回の補正予算にお願いをしてございます。1人1台の端末を実現できるように、ある程度の期間がかかりますけれども、早速取りかかりたいと思っております。
それから、光ファイバー網の整備につきましては、御案内のとおり、大川内、江内の系統が未整備ということになっておりまして、先ほど申しましたように、いろんな事業を展開するにしても、定住促進をするにしても、企業誘致をするにしても、やはり基本的な整備、社会基盤の1つであろうと思っております。総務省が、今回、今準備をしているそうですけれども、通信事業者が主体となって実施する整備についての補助制度が前倒しでできるようでございますので、出水市のほうが負担金を払って一緒に取り組むというような事業でございますが、今後、そういった内容等が整い、補正等の状況がわかり次第、議会のほうに上程をさせていただいてお願いをしたいと思っております。GIGAスクール構想と光ファイバー整備の事業が同時並行して進んでいければというふうに考えているところです。よろしくお願いしたいと思っております。
○18番(垣内雄一議員) ぜひ、早期に実現できますようにお願いをいたしておきます。
それから、家庭学習と読書の関係でありますが、もうこれについては教育長の申されたとおりであろうかと思っております。子供たちが家の中に閉じこもって、果たしてどういう生活をしているのか、いろいろ考えさせるところがあろうかと思いますし、また、親御さんもいろんな面で大変心配な点もあろうかとも考えます。そういった中で、やはりゲームにだけ集中するということになれば、また偏ってしまいますので、児童・生徒の精神的な落ち着きを取り戻していくという点からも、先ほどありました家読の推進というものを、やはりやっていくべきが本当かなと、このように思っております。そういうことで、今後もこちらのほうにもぜひ力を入れていただきたい。幸い、御紹介ありましたとおり、図書館の開放も早めにやっていただいておりますので、お父さん、お母さん方が、そちらのほうも子供と一緒に利用できるように、そういうこともしっかり考えていただいて、家読の推進にもぜひ力を入れて盛んにしていただきたいと、このように考えております。
それから、総合医療センターにつきまして、鮫島事業管理者から御答弁をいただきました。あと1つ、2つお願いしたいと思うんですが、先般、この感染症が発生いたしましてから、医師招聘の件でございますが、県外からこっちに来られる先生方の件について、若干、こういう不測の事態だから勤務を見合わせようかなというのが記事にありましたけれども、現在、その点についてはどういうふうになっているのか、わかっていたらお聞かせください。
○鮫島幸二病院事業管理者 新型コロナウイルス感染症が拡大しました4月下旬から5月連休明けにかけまして、一応感染防止対策としまして、常勤医師については県をまたぐ移動は禁止させました。特に県外から来られている非常勤の医師については、原則診療を中止せざるを得ないという状況でしたけども、中にはやっぱり外来患者さんの治療上、診療をどうしても継続しないといけない診療科もありましたので、そういう診療科につきましては、医師と患者さんの間にシールドを設置したり、あるいは極力離れて診療ができるような体制をとって診療を行いました。
現在は、医師については全員健康チェックを義務づけて行いつつ、通常診療のほうに、非常勤、常勤医師とも戻っているところでございます。
○18番(垣内雄一議員) それから、医師招聘ということは、これはやはり病院の経営改善あるいは収益の増を見る上において一番のポイントだというふうに、今日まで伺っております。そういった中で、先ほど御紹介がありましたように、整形外科の先生が3人体制になられました。私ども、大変このことについては期待もありますし、喜んでいるところでございます。3人体制になられますと、手術の件数も幾らかまたふえてくるでしょうし、また、そうなりますと、今度はリハビリのほうもかなり、やっぱりそれに付随して患者の方もふえてくるんじゃないかということも考えられますけれども、その辺についての見解はいかがなものでしょうか。
○鮫島幸二病院事業管理者 手術件数のほうは、やはり整形外科が新しく3人になったことによって手術件数自体がふえておりまして、当院でリハビリ、あるいは整形外科の患者さんに限らずリハビリを受ける患者さんも、今はふえてきているところで、その体制づくりを今進めているところです。
○18番(垣内雄一議員) では、最後に1つ、せっかく事業管理者がおいでいただきましたのでお願いしたいと思うんですが、これから世の中の人口動態を見ておりますと、だんだん、だんだん高齢化率が上がってくる。私もその域に達しているんですけれども、やはりこれからの医療というものが医療と福祉、やはりこれも切っても切り離せないものもあろうかと思っております。あわせて、今回、鮫島事業管理者がおいでいただきました小児科でございます。現体制は、小児科3人の常勤医師だというふうに伺っております。これにまた、産婦人科がうまく加わってきますと、医療と福祉、あるいは小児科、産婦人科、この辺がしっかりとかみ合ってくれば、私はやはり将来の医療センターの構想として、かなりまたいい方向に転じていくんじゃないかなというふうにも考えておりますので、どうかひとつ、これから、鮫島事業管理者の頭の隅に入れていただいて、ぜひ今後とも御検討されまして、いい病院経営になりますように御努力いただければと思っております。
以上で、質問を終わります。
○議長(杉本尚喜議員) 次に、鶴田均議員の質問を許します。
○9番(鶴田均議員) それでは、通告に基づき市長に質問します。
先ほど垣内議員の質問と同じでございますが、今一番気になる新型コロナウイルス感染について、国や県により多くの対策、支援が示されています。出水市も、これらの対策に合わせて、さらに市独自で支援、助成が示されています。今回、新型コロナウイルス感染は、世界人類全ての生命、生活を脅かしております。出水市も、感染の危険性があるとして、その対策と支援の方向性が示されました。これらの感染症から市民の生活の安全、安心、安定は、行政の役割として緊急に支援する必要があることは御承知のことと思います。そして、これらは、業種によって死活の問題であり、経営そのものが成り立たないと心配もします。特に飲食店などについて、経営支援の陳情もなされているが、それはこのままでは経営継続が困難で、再起不能が多数出てくるのではないかと心配します。市としては、感染症の修復後に、店などの改修費の30%、30万円以下を限度として助成するとなっていますが、改修する余力がある店はできたとしても、自転車操業などで経営している店は人件費や家賃など必要経費がかかり、営業計画も厳しくなるために経営支援の助成が必要ではないでしょうか。北薩随一の繁華街、川端通りは出水市の風物詩として、北薩の天文館と私は言っていますが、人々のにぎわいや癒やしやおもてなしの交流の場所として、出水市の観光を含め繁栄のシンボルであり、極めて重要な役割があります。そこで、これらの経営の安定を図り、存続できるように力強く支援できないでしょうか、伺います。
次に、指定管理者制度により協定を締結して管理している業者において、当初の協定に準じた運営はできなく、イベントや施設使用料の現状、スポーツ大会やコンサートなど開催できなく、不利益が生じていると思います。そこで、協定における協議の必要性や、経営における自主事業が困難であったと思うが、それらに対応する助成はどのようになっているのでしょうか伺います。
次に、新型コロナウイルス感染症で、出水市の観光業を初め、会社や事業者を倒産させないための手法はないのでしょうか。昔、米沢藩の大飢饉で、米沢藩主みずから、領民の食糧不足のために貯蓄米を解放し餓死をなくした。今回の新型コロナウイルス感染症は、人類歴史上、最大の天災に匹敵するのではないでしょうか。これは、企業や個人の経営問題ではなく天災として、国や県の支援が足りなかったら市が全力で支援を図り、市民の生活基盤を守り、育てるのが行政として一番大事なことではないでしょうか。
市長は、出水市の最高責任者として市民の生活を守り抜き、出水市からこの感染症で倒産はさせないとして、米沢藩の貯蓄米ではないですが、市の財政調整基金を活用して判断、決断、実行し、市民の生活を救うことができるのだと思います。市長の意見を伺います。
以上で、壇上からの質問を終わります。
○椎木伸一市長 鶴田均議員の新型コロナウイルス感染症に関する市の緊急対策についての御質問にお答えします。
市では、独自の取り組みとして、飲食店等緊急支援事業などさまざまな支援を行っています。市の単独事業としては、まず、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた飲食店、または宿泊業を営む事業者が、この時期を利用して店舗等の改修工事、あるいは感染防止のための備品等の購入など感染拡大防止対策を行った場合の対象経費の30%、最大で40万円を助成する飲食店等改修支援事業に取り組んでいるところです。このほかにも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている飲食店等を含めた事業者への緊急対策としては、一月の売上が前年同月比で20%以上減少した市内事業所に対し、10万円を支給する中小企業等支援金、4月25日から5月6日までの間、県から要請を受けて休業や営業時間短縮に協力した市内事業所に対し、法人には10万円、個人事業主には5万円を、県の給付に上乗せ給付する中小企業等休業協力金、5月7日から5月14日まで、県から要請を受けて休業したスナックやバーなど4業種を営む市内事業所に対し、5万円を支給する中小企業等休業協力経営支援金、そのほか、インターネットを利用して、事前に食券を販売する購入型クラウド・ファンディング、テイクアウト情報を掲載した「キバレ出水市飲食店チラシ」の市内全世帯への配布、市役所庁舎を利用した出水テイクアウト市場の出店支援など、市単独事業でのさまざまな支援を行ってきました。
また、県においては、一月の売上が前年同月比で80%以上減少した事業者に対し、最大20万円支給する事業継続支援金など、国においては労働者の雇用を維持した場合の休業手当を助成する雇用調整助成金などの給付を行っており、今月からは家賃支援給付金の申請受付も始まるとのことです。
次に、指定管理者への助成についてお答えします。
指定管理者へは、協定に基づき各施設の管理をお願いしているところです。国からも感染拡大防止に向けた対応等による減収等については、各地方公共団体と指定管理者との間で締結した協定等に基づき対応するよう通知がありましたことから、本市においても、指定管理者への減収の補填については各施設の協定等に基づき対応し、必要に応じ指定管理者と協議を行っていきたいと考えます。なお、新型コロナウイルス感染症対策として、市の判断で公共施設を休館したり、利用を制限したことに伴い利用料金収入が減収となる一方、利用者数が減少することで管理費も減少することから、収支両面の影響を見極めて対応する必要があると考えています。
今後も、施設の管理運営及び感染症対策については、指定管理者と十分連携をとり、市民サービスの低下を招かないよう努めていきたいと考えます。
次に、コロナ倒産をさせないための手法についてお答えします。
先ほど垣内雄一議員の御質問でお答えしましたが、戦後最大の生活・経済危機ともいわれている新型コロナウイルス感染症の影響に対しては、迅速で時期を逸しない対応が最も重要なこととの認識のもと、市職員一丸となって市民生活を守るための施策を講じているところです。新型コロナウイルス感染症は、感染拡大防止のため、全国を対象として発出された緊急事態宣言は解除されたものの、市民生活や経済活動に、これまでにない重大な影響を及ぼしています。
このため、市においても、先ほど述べたとおり、経営が悪化した事業者に対して適宜支援等を行っているところです。また、継続的な支援が必要であることから、市民や観光客の移動手段を確保するため、本市に、本社または本店を置く観光バス及びタクシー等事業者に対して、バス・タクシー等を維持するための車検代など固定費等の一部の支援や、感染拡大により影響を受け減収となった農林水産業者に対する支援を含む、追加の補正予算を準備しているところです。
このような支援策を含め、新型コロナウイルス感染症対策に係る予算措置については、これまで令和元年度の補正予算に加え、本年度においても必要な補正予算を国の予算成立前から編成し、その財源として財政調整基金等を活用しています。今後においても、市民の命や健康を守ることを最優先に、事態の変化を注視しながら適時適切に時期を逸しない対応をちゅうちょすることなく講じていきたいと考えています。
○9番(鶴田均議員) 先ほど市長の答弁を伺いました。それぞれ、さまざまな分野で支援の計画があるということは十分わかります。この中で、先ほども言いましたとおり、自転車操業などをしているような飲食店とかいろいろあるわけですが、これについて一番大事なのが賃金とか、あるいは、さっき言われました家賃ですね、テナントで借りているところがあると思いますが、これについて支援をする方向性があるような話をちょっと伺いましたが、この点についてもう一回、回答していただければいいと思います、家賃についてはちょっと話されましたので、それを聞かせてください。
○椎木伸一市長 飲食店等の非常に緊急な対応が必要なところについては、適宜支援を計画して実施させていただいているところであります。家賃については後段で申し上げましたけれども、今月から家賃支給給付金、国においての申請受付が始まるということでございます。私どもとしては、飲食関係の方々と早期に協議をいたしまして、どのような支援が必要かという御意見等も聞きながら対応してきたところでありますけれども、運転資金等については、速やかに資金等を得られる方法としてクラウド・ファンディングを提案し、実施に移していただき、もうしばらくで締め切りになりますけれども、目標の2.5倍を超える御賛同をいただいてしているところでございまして、組合等の中で資金運用については責任を持って対応していただくと、そのファンディングの中からですね、そういったことをしております。また、御存じのとおり、庁舎内でも現在も行っておりますけれども、テイクアウト市場を実施しまして、非常に市民の皆様の御理解と御協力のもとに、当初は市の職員を対象としておりましたけれども、それに頼ることなく、市民の皆様が多く御来店いただいておりまして、心から感謝を申し上げたいと思います。
○9番(鶴田均議員) 今話を伺いましたが、国とか県とかさまざまな分野で家賃とかそういうのも手だてがあるような話を聞きましたが、やはりそういうのを勘案しながら、さらにまた必要な分については、出水市も上乗せしたりとかいろいろ考えて進めていっていただきたいというふうに思います。
それと、現在、国では中小法人等200万円以下とか、個人事業者には100万円以下とか持続化給付金の支給という形で示されておりますが、これについて市の対応は、今どういうふうになっているんですか。
○椎木伸一市長 市民の皆さんに、できるだけ、いわゆる自治体がどこが担当しているのか、どこの窓口に行けばいいのかというような広報を市のほうではしております。全世帯に配布しましたけれども、こういうチラシをつくりまして、市の対応、国の対応、県の対応等を一覧表にしましてわかりやすい周知を、一部広報紙にも載せましたけれども、月に1回の広報でございますので、こういったものも適時つくり、あるいはホームページに掲載しながら、いろんな救済措置ができるだけわかりやすく受けられるように努力をしているところであります。
○9番(鶴田均議員) いずれにしても財源が必要だと思います。現在、出水市の財政調整基金どれぐらいあるのか、また、令和元年度、その基金に回すのはどれぐらいあるのか、わかれば教えていただきたいと思います。
○椎木伸一市長 財政調整基金、いわゆる財政調整積立金でございます。こういった、いわゆる災害の発生、災害と同じような状況でございますけれども、思わぬ支出の増加、あるいは経済不況による大幅な税減収時に備えて基金をつくっているわけでございますけれども、現在の状況、それから今回の対応等の状況については、政策経営部長のほうから答弁をさせます。
○冨田忍政策経営部長 まず、財政調整基金、元年度末での残高を申し上げますと82億4,260万円の残高でございました。本年度、現段階で9億3,610万円ほどの取り崩しになろうかと考えております。年度末、このまま現在の状況でいくと、現段階では2年度末の見込みが約73億円程度になろうかと思います。コロナ関連も含めまして、当初の段階から一般財源不足についても取り崩しをしておりますので、年間で約9億円程度取り崩す、現段階の見通しでございます。
○9番(鶴田均議員) わかりましたが、やはり財政調整基金というのは、市長に言いますけど、出水市民自体が非常に大変な今回のこういう災害に見舞われたときに、自信を持って拠出していただきたいと思います。非常に、やはり市民の生活を守るのがやっぱり行政としては一番ですので、そのあたりは十分考えて、市長も財政調整基金は運用していただきたいというふうに思います。それと、市長は、稼げる観光ということを施政方針で提案されております。それについては、やはり何と言いましても、観光関係といいますと観光バスとか、あるいはホテルとかこういうところが、市長が言う稼げる観光とするなら非常に大事な分野です。ですから、これらに対しても、それぞれまた、今、支援の方針を話をされましたけど、やはり、コロナが収束していけばいいんですけど、これが長引けば大変になってくる面があります。そういった場合の対応とか、先ほども状況によっては考えていくような話をされましたが、もう一回その点についてお知らせください。
○椎木伸一市長 観光産業は総合産業といわれるように、経済に及ぼす影響というのは非常に大きなものがあると思っております。これだけの経済打撃を受けますと、なかなか長期に及んでしまうということでありますので、本日、報道等にもありましたけれども、県のほうで「ディスカバー鹿児島キャンペーン」ということで、2回に分けて、県民限定で県内宿泊の促進をするということです。そのあとにまた、国が同じような事業を打ち出しておりますけれども、私どもも地域内の宿泊旅館業については、非常にこの県の対策、あるいは国の対策ではなかなか出水まで影響、効果が出るのかどうか非常に危惧しておりまして、独自の支援が必要だろうということで、現在、担当課のほうでいろいろその辺のことを協議しながら対応しております。そういった効果が大いに発揮されるような事業を、今後取り組んでいかなければならない、また、継続的に取り組んでいく必要があると思っております。そしてまた、観光関係で移動手段である観光バスやタクシー、あるいは代行さんも含めて、そういったところにも今後、計画ができ次第、今議会に提案できればすぐにでも提案したいと考えておりますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
○9番(鶴田均議員) 今さまざま伺いましたが、一生懸命努力されているとは思います。ですから、市長の強い熱意の中で、出水市から倒産するところはつくらないよという強い意志を持って政策を進めていっていただきたいと思います。
今後、これが収束がどういう形になっていくかわかりませんけれども、やはりそれに合わせながら、出水市に合った方法、アイデアを出しながら進めていっていただきたいと思います。
以上で終わります。
○椎木伸一市長 議員がおっしゃるように、1社も1事業者もそういったことがないように、迅速な対応をしていかなきゃならないということはもとよりですけれども、職員に、今年の初めから申しておりますように「5S」で頑張ろうということを申し上げておりましたけれども、まさに「SPEED UP」、「SERVICE UP」、「SECURITY UP」、それから「SAFETY UP」、「SUSTAINABILITY」という「5S」を掲げておりましたけれども、職員が一生懸命このことも念頭に頑張ってくれておりますので、引き続き、そういったことを含めて職員一丸となって取り組んでまいりますので、皆様の御理解と御協力を今後ともどうかよろしくお願いを申し上げます。
○議長(杉本尚喜議員) ここで昼食のため休憩いたします。再開を午後1時といたします。
午前11時56分 休 憩
午後1時00分 再 開
○議長(杉本尚喜議員) 会議を再開いたします。
次に、土屋工吉議員の質問を許します。
○8番(土屋工吉議員) けさほどから久しぶりに田畑を潤す大雨に、本当に我が地域にあります浦田川水域が川藻が繁茂してどうしようもないということで、早速市の担当課の方が準用河川の清掃をしていただきました。本当に市民が安心して暮らしていると思います。ありがとうございます。
今回は市民の皆様の暮らしの安心、特に新型コロナウイルス対策の質問多うございます。医療、介護、飲食店等、世の中を取り巻く全ての生活環境まで変えてしまう感染症対策、心から、市当局を初め、特に医療関係者、また市民の皆様への御苦労に対し敬意を表するとともに、また、お見舞い申し上げます。新聞紙上では43年間、我が子の祖国への帰りを待ち、全国へ周知されながら亡くなられた横田めぐみさんのお父さん、安倍総理への感謝の言葉、本当に脳裏に刻まれました。また、先日、「鶴瓶の家族に乾杯」に出演していた青森県鰺ヶ沢町の愛犬わさお、いろんな時の流れを感じさせられます。きょうは一番打者で宮田議員の5,400組合農家のために、売電計画、基幹水利、応急対策事業に新しい夢と課題をいただきました。感謝いたします。先の見えるものに対し、我々もしっかりと努力してまいりたいと考えます。
それでは、通告に従い、私はいのちの安心、令和2年度当初予算の概要10ページの国の交付金事業を財源とする新規事業2,200万円、農業用水路等長寿命化・防災減災事業の目的は何か伺います。
また、洪水等からの安全確保となっているようだが、全体計画として何カ年を見込んでいるのか伺います。
また、土地改良事業組合員の賦課金を主力財源とする維持管理事業費等を耳にしますが、非常に当組合のほうは厳しい状況の中にありますが、地元の負担としてはいかほどか伺います。
調査しながら事業化されると思うが、今後どのように実施されるのか伺います。
次に、これは何回もやっていますが、平成18年度地域校区自治会要望を何回となく、私、質問してまいりましたが、道路改良工事に対し、市道上村六月田線と県道沖田新蔵線との交差点改修の進捗状況はどうなっているのか伺います。
最後に、文化会館及び音楽ホールの命名権料が本年度から予算化されておりますが、その財源を生かして、両ホールの改修をスピードアップされる考えはないか伺い、登壇しての1回目の質問といたします。
○椎木伸一市長 土屋工吉議員の御質問にお答えします。
まず、農業水路等長寿命化・防災減災事業の目的についてですが、農業の持続的な発展を後押しするため、農業生産の基盤となる農業水利施設の機能の安定的な発揮に必要な、機動的かつ効率的な長寿命化対策及び防災減災対策を推進するとともに、農業水利施設の効果を最大限に発揮するために行っています。この事業は、平成30年7月豪雨において多くのため池が被災したことを受け、緊急時の迅速な避難行動やため池の適切な保全管理など、ため池の保全・避難対策を実施することによって災害の未然防止を図ることを目的としています。
また、事業計画ですが、本市には農業用ため池が25カ所あり、そのうち、下流に住宅や公共施設等が存在し、施設が決壊した場合に人的被害を与えるおそれのあるため池17カ所を、防災重点ため池と位置づけています。平成28年度は、団体営震災対策農業水利整備事業でハザードマップを1カ所作成しました。昨年度は、団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業で7カ所作成し、今年度は9カ所作成する予定であり、本事業としては2カ年計画になります。本事業は、国庫100%の定額助成となっていることから、防災重点ため池については、今年度までに16カ所全てを国に要望し、事業採択を受けているところです。
次に、土地改良事業の負担率については、農業農村整備事業は種類が多くあり、事業の内容や要件によって負担率が異なります。市としては、最適な事業を選定し、事業化をするため関係機関と調整を図っています。また、計画事業化については、要望地区での検討会等を行いながら、地元要望のとりまとめを行い、国や県に要望し事業化を図りたいと考えます。
次に、市道上村六月田線と県道沖田新蔵線との交差点改修についてお答えします。
御質問の交差点については、市道上村六月田線側は買収した用地の除草を行い、交差点の安全確保に努めています。また、市道津山西1号線側の買収予定地については、昨年から県外在住の土地所有者と協議を行い、用地買収の準備をしています。今後、補償契約等の手続が完了次第、交差点改良に着手していきたいと考えています。
○溝口省三教育長 土屋工吉議員の御質問にお答えをいたします。
文化会館及び音楽ホールの改修についてですが、文化会館は昭和49年に竣工され、平成21年度から22年度にかけて大規模改修をしております。音楽ホールは平成4年に竣工された施設で、経年劣化による老朽化は否めないところです。改修については、現在、状況に応じて、指定管理者と所管課である生涯学習課との間で協議の上、50万円未満は指定管理者で、それ以上の金額は所管課で修繕等を実施しております。なお、大規模な案件は、投資事業5カ年計画をもとに、計画的に進めているところです。両施設は、昨年度、ネーミングライツパートナーを募集し、株式会社マルマエ様が命名権を取得されました。その結果、本年4月1日から10年間の契約で、文化会館はマルマエホール出水、音楽ホールはマルマエ音楽ホール出水という愛称に、それぞれ決定したところです。出水市ネーミングライツ導入に関するガイドラインでは、市が得た命名権料については、原則ネーミングライツを導入した施設の整備や管理運営に使用すると規定しております。当該施設の命名権料が今後10年間見込めることから、命名権料をいただいているネーミングライツパートナーに対するメリットにも配慮しながら、より有益な改修内容を指定管理者と協議する予定です。あわせて、御提案の内容も含めて、利用者のためになるような改修や物品購入を検討し、より親しみのある施設にしたいと考えております。
○議長(杉本尚喜議員) ここで申し上げます。土屋工吉議員より書画カメラの使用の申し出がありました。よって、これを許可してあります。
○8番(土屋工吉議員) 2回目の質問になるんですが、今、市長のほうから答弁の中で16カ所ため池等の施設改修計画があるということで伺いました。非常に安心して、農家の方も給水等も漏水のないため池が望めるんじゃないかと思いますが、例えば、農業集積等で大型農家へ委託できる地域と、また最近は、小規模でもいいから、例えば家族農業をしたいという方もいらっしゃいます。また、山間部に行きますと、どうしても大型農家がなかなか難しいということで、鳥獣被害等ありますので、特に大川内山間部等では、できれば元気のある自治会が自治会で農業をしておいしい農産物を全国に売ろうじゃないかという話も出ております。いろいろそういった中で、長寿命化・防災減災事業についていろんな形で対応されると思いますが、特に、今、農水省のほうでは出水西部地区で野田、高尾野の改修をやっているということも聞きます。いろんなそういう中でちょっと冒頭お話しました、青森県の鰺ヶ沢町のわさおの町なんですが、ここは湿地の地域を暗渠排水等をいろいろ完備しながらそういった東北の寒い中で、地球温暖化で、米も今、北海道が一番いいという時の流れになってまいりましたけれども、そういったものをいろんな全国のそういういい参考例をして、この事業にどうしても、農産物の独特のブランドをつくるという形のものも必要だと思いますが。要するに、出水市は基幹産業は農業だということから、そういった、今、ため池の計画がありましたけども、2年間ということですので、なかなか一挙にというのは難しいんですが、具体的にまだ、来年度はこういうことも考えてますよということがあればお示しいただきたいと思います。
○椎木伸一市長 長寿命化・防災減災事業につきまして2年間ということで、今年度までの事業を紹介いたしましたけれども、来年度以降の事業等の考えについては農林水産統括監のほうから答弁をさせます。
○東畠賢一農林水産統括監 あくまでも長寿命化対策事業でございますけれども、危険度が増しているため池の防災のためのマップをつくるための事業でございます。ソフト事業ということで、昨年度と本年度が最終年ということで、全部で17カ所のハザードマップがまずできあがるという事業でございます。このハザードマップができあがると同時に、県のほうでは、さらにため池の耐震度合い、それから、いわゆるどこか崩れているところがないかとか、そういった調査点検につきましては、今後、県が行っていって、その結果、危険度があるところについては新しい事業を入れまして改修なり、もう使われていないということであれば、ため池の持ち主の許可をいただいて壊すとか、そういった方向に進んでいく事業でございます。いろんな農業の大型、小規模の農家のお話でございますけれども、農業農村振興の事業につきましては、主に集落基盤整備型と農業生産基盤の整備の事業がございますけれども、主に農道の整備であったり、国とか県営にかかわらない用水路の整備とかを実施していく事業となっております。農地集積のほうは、また農政課の所管になりますけれども、そういった事業については、また農政課とも協議をしながら、今後、事業については取り組んでいきたいと考えております。
○8番(土屋工吉議員) 今、ハザードマップの作成ということなんですが、さつま町あたりは結構ため池等がいろいろな場所にあるというのをよく見ますけども、出水地区においてもため池、その地域地域によって違うと思うんですが、そこら辺のハザードマップをつくって、いざ農家の方に活用していただくというか、その配布はどのような形でされるということでしょうか。
○東畠賢一農林水産統括監 それぞれのため池のハザードマップを作成をいたしまして、それぞれのため池のある関係自治会においては、作成されたハザードマップを全戸配布、それから、大きなハザードマップをつくりまして、自治会の公民館に掲載をしたりというふうな形で、最終的には成果物ができたときにはそのようなことを行っております。業者委託になりますので、委託先の業者がこのマップを作成するまでの間、市の職員も入りまして、自治会や消防団等を集めまして、こういったことでマップをつくっていきますよということで地元も中に入れて、話し合いをしながら作成をしていくという事業になっております。
○8番(土屋工吉議員) 上水道でもそうなんですが、いざ災害時にタンクが使い物にならないということで、耐震対策でいろんなステンレス製と、管路もそういった耐震性の管路を設けて市民にいつでも水が供給できるということをやっていますが、そこら辺も農家の方と十分協議されながら活用できるようお願いしまして、次の質問に入ります。
それでは、ちょっと見にくいあれですが、1のあれをお願います。(議場内ディスプレーへの資料表示)ちょっとけさ、雨が降る前に書いたものですからちょっと見にくいんですが、特に、次の道路改良工事の出水平野の中に西回りと3号線が青、縦のあれが国道447号なんですが、どうしても西回りの出水インターができてから、赤い商業地域になりつつある328号沿いと六月田から沖田線にかけては渋滞というのは、皆さん御存じかと思います。その中でも、やはり上村西の交差点というのは、我々が社会に出ていく昭和49年前後から、鹿児島NECの水俣から来る勤務者、いろいろな方の非常に過密すぎるぐらいの交差点なんですよ。今、現在は、出水インターから降りられる方の、この前も申し上げましたけども、沖田新蔵線の県道を利用したり、近辺の市道を近回りして信号のないところを、混まないところを走ろうということで非常に込んでいます。だから、要するに、用地買収も2年前に協力いただきながら、前回は部分的にも改修できないかということで私質問したわけですが、基本設計が大体用地買収が完了しないとできないふうな形になっています。いろいろと現場経費等分散すれば、高価になりますが、やはり地域の方が、用地買収はしてもらって、部分的にしたんですけど、動く姿が見えないというんですよ。だから、今、市長の答弁に用地買収が完了次第、基本設計できていますので、工事に入りますということなんですが、やはり、どうしても、今使える道路としては非常に重要な交差点でありますが、いかがなものでしょうか。もう一度答弁をお願いします。
○椎木伸一市長 以前から何回も御質問いただき、この交差点を利用される方の人数も多く、早急な改良が必要だということは十分認識しておりまして、これまでも、用地買収を含め、今回買収予定の反対側の角も解体等を行ってもらい、樹木の伐採等も行ってもらい、今、大分、以前よりも見通しがよくなったところであります。先ほど答弁しましたように、県外の在住者の方と、今、用地の協議をお願いしておりまして、その辺の状況、今後の予定等についての詳細については、建設部長のほうから答弁をさせます。
○小原一郎建設部長 今の交差点の用地買収の状況について御説明いたします。
県外の方と何回か交渉を行っているところなんですが、今現在としまして、前向きな回答もいただいているところでございます。契約締結等がスムーズに行きましたら、工事のほうに進めていきたいと考えているところです。
○8番(土屋工吉議員) 今、用地買収等を具体的にお示しいただきましたけども、地域の方が、行政のほうが行けなかったら我々でも行きますよということなんですが、いや、いや、待ってくださいと、当局も一生懸命やってますからと、そういう形で、何年たったらできるという品物じゃないかもしれませんけども、やはり用地買収もある程度めどをつけて、今年は何とかするぞというぐらいの気持ちを持っていただいて、地権者がいろんな方々いらっしゃいますので、やはりそういった形でなかなか難しいと思いますけども、ぜひ、今まで半世紀も使った道路ですから、NEC鹿児島工場があったころは非常ににぎやかな交差点ですよ。事故もありました。用地買収を一部していただいて本当にやさしい交差点、見通しのいい交差点になって、幾らかは減りつつはありますけども、やはり地域の方が一番望むのは、せっかく、昔のにぎやかな県道沿いがこんなになっていいのかということをいわれますので、ぜひ、そこら辺をお願いしたいと思います。土木費の平成31年度の構成比率からいいまして5.7%、令和2年の歳出予算の構成比からいって、下水道の持ち出しとかいろいろあって6.5%として、伸びはしてますけども、やはり出るところがいろいろあってなかなか難しいなというのを感じます。ぜひ、そこら辺をお願いしたいと思います。
道路改良についてはお願いして、次に文化会館の、最後になりますが、7番議員の外木場スタジアムはホームベース上でワンバウンドになりましたけれども、何とかネーミングで命名権料が本年度から予算化されております。本当にありがたいものでございます。御協力いただいた企業への感謝しながら施設の改修について質問いたします。
写真の2番をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)特に我々が部分的に、改修もそうなんですが、確か、教育長の答弁ありましたように、昭和49年、我々が成人式を第1回目にさしていただいたのが文化会館です。東京に行けば東京中野のサンプラザ、出水に帰れば、同じ三角のかっこいい文化会館ができたのを覚えております。そのときに、色黒の3人男が税所市長と並んで成人式の写真を田舎から同級生が送ってくれたのを思い出します。そういった老朽化した施設なんですが、やはり障害者に優しい施設、例えば、この写真はスロープなんですが、スロープが大体、次の写真をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)今の車椅子の寸法とスロープの寸法が1.1メートルぐらいなんですよね、ここら辺もできれば、階段付近の踊り場も洗い出しで、つぶつぶの砂が足にざらざらするぐらい傷んでおります。そういったものをもうちょっと、極端にいえばホールの入り口まで救急車でも行けるそういう施設を、もうちょっとやさしい施設にしたらどうかと思いますが、いかがでしょうか伺います。
○溝口省三教育長 土屋工吉議員の御質問ですけれども、そのようなことも考えながら、先ほど言いましたように、ありがたいことでネーミングライツパートナーの募集に対しまして、マルマエホール出水、あるいはマルマエ音楽ホール出水が命名権をとっていただきましたので、その導入の趣旨というのは施設の整備や管理運営に使用するということで、改めて前にも出されておりますので、今のようなところは成人式のたびに感じるところですから、努力をしたいと思います。
○8番(土屋工吉議員) 写真の5番をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)今、教育長のほうから、各施設も指定管理者と一緒に協議しながらやっていくということをいただきましたので期待し、これはちょうど、今のスロープの横の階段の蹴上げのところのタイルなんですが、ここら辺もめくれて非常に危ないと。スロープを広げれば、高齢者もつえをつきながらでも歩けるなという状況にあります。この階段の蹴上げの上なんかはどうしても洗い出しのつぶつぶがなくなってしまって、非常に国体を迎えるにはちょっと恥ずかしいなというところもあります。そういったところで、ぜひお願いしたいと思います。5番をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)次に、いろいろと命名権で10年間そういった予算を協力いただく中で、これは音楽ホールのシートの状況です。シートがどうしても破れたり、下のほうは汚れた状況なんですが、ここら辺もやはり、たまに音楽ホールへ行きますと非常に子供たちも音楽祭で一生懸命やっているその中で、命名権があれば、例えば全部取りかえというのは非常に大きな規模になりますので、例えばカバーを被せて、そのカバーに命名権の会社のマークとか、いろいろと子供たちが喜ぶそういうマスコットを刺しゅうしてやるとか、カバーを設けていかがなものかと思いますが、どうでしょうか。
○溝口省三教育長 音楽ホールは先ほども申し上げましたように、平成4年度に竣工された施設でございます。それから、文化会館は昭和49年ですけれども、平成21年から22年にかけまして大規模改修をしております。今お示しいただいたように、確かに音楽ホールの場合は、そのようなシミが入ったり、汚れたりしている部分がございます。それを精査をしながら、そのようなネーミングライツの契約のお金でできるのか、あるいは50万円以内でできるのか、私どものほうでまた考えてみたいと思っております。
○8番(土屋工吉議員) 規模的にシートを全席につけるだけでも、指定管理者の50万円では到底難しいと思います。今年度予算でも、非常電源等改修で1,600万幾らか予算化されていますので、あまり無理は申しませんが、やはり我々が文化会館に行って、例えば八代亜紀の歌を聴いて、出てくるときはスターなんですよね。本当に健康で文化的な生活をさせていただいたなという間隔がありますので、ぜひこういう文化施設も改修をお願いして私の質問を終わります。
○議長(杉本尚喜議員) 次に、南鶴洋志議員の質問を許します。
○1番(南鶴洋志議員) 本日、最後の質問者となります。今しばらくおつき合いください。
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。また、感染拡大の防止に御尽力されている医療関係者を初めとした多くの皆様に、心から感謝申し上げます。
それでは、通告に従い質問いたします。
今回は、コロナ対策に関する質問が多いため、視点を変えてお伺いいたします。1つは、自治会がコロナ禍で新たな役割をつくれないかということ、2つ目には、行政事務連絡員の見直しにより今後の自治会のあり方についてお伺いいたします。
5月25日、全県で緊急事態宣言が解除され、世間の自粛ムードも少しずつ緩和されてきました。しかしながら、一部の専門家も指摘しているように、新型コロナウイルス感染の第2波は必ず来るものと考えていたほうがいいでしょう。約100年前に日本を襲ったスペイン風邪も、2年間に3回の波があり、第2波で多くの死者が出ました。今回の新型コロナも秋以降に来るであろう大きな波が、ウイルスは変化していく特性があるので、より凶悪化していくおそれもあります。
では、次に来る大きな波のために、私たちはどう心がければいいのでしょう。やはり、今回経験して得たことが基本です。手洗い、マスク、そして3密を避ける、ソーシャルディスタンスを保つ、不要不急の外出をしないことではないでしょうか。3密や不特定の人との接触を避けるためには、昔あった御用聞きのようなシステムがあれば理想ですが、現代であれば電子マネーでの支払いやネットで注文して店舗で受け取るだけのシステムなども、これを機に試して慣れておくべきかと思います。しかし、スマホやパソコンに疎くなりがちな高齢者には簡単なことではありません。デジタルデバイドとは、コンピュータ-やインターネットといった情報技術、IT技術を利用できる人とそうでない人の間に生じる格差のことです。デジタル技術の習得は、今や完全な社会参加には欠かせない鍵となっており、もし高齢者にこのテクノロジーの利用法やトレーニングを提供できないのであれば、その人たちを社会から締め出すことになり、既に問題化されている高齢者の孤立化や孤独を増長してしまうことになります。
そこで、自治会、特にいきいき自治会への、今回の災害を機にオンライン端末を導入してみてはいかがでしょうか。オンライン診療、買い物支援、テイクアウト予約、乗合タクシー予約、生涯学習関係では読み聞かせ、出水論語塾、その他介護料理教室など、関係施設に行かなくても済むようなさまざまなオンラインサービスが考えられます。将来的には、各家庭で個人で端末を操作できるよう、まずは自治会にて端末を導入することによって少人数の方が集まり、教え合い、トレーニングをしてもらう、その中で会話が生まれる。これまで公民館の利用が少なかったものが、新たな様式により変わっていきます。住民の生活様式が変わりつつあります。自治会も、昭和時代からほとんど変わらないやり方を変えるべき、新たな様式、スタイルに見直す転換期に来ているのではないでしょうか。また、自治会に入っても何のメリットもないという未加入者への加入促進のツールになるかとも思います。市長の見解をお伺いいたします。
次に、(2)の行政事務連絡員の見直しによる自治会のあり方について質問いたします。
本年4月から、行政事務連絡員の見直しにより、自治会に転入・転居される方の情報が、本人の同意がないと自治会に情報提供されなくなりました。自治会とは、地域に住む一人一人が自分たちの地域のことを考え、お互いに協力し合い、住みよい地域社会を形成するため、住民相互の親睦や共同作業、相互扶助などを図ることを目的に、自主的に組織された任意の団体です。地域住民の皆様が一番身近な地縁型コミュニティの中心的な存在です。少子高齢化等に伴う地域社会の弱体化が大きな問題となっている昨今、自助・共助・公助によるまちづくりの重要性が増しています。その中で、自治会は住民同士の親睦、生活環境の維持等の活動のほかに、高齢者の見守りや子供の安全対策等に取り組み、住みよいまちづくりを進める中心的な役割を担っています。しかし、近年、社会経済情勢の変化に伴い、地域社会に対する住民の関わり合いが、ともすると希薄化し、日常生活における人と人とのふれあいの場が少なくなるなど、地域社会を取り巻く環境も著しく変化してきています。こうした状況の中で、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などでは、地域における防災活動の重要性、自治会等や自主防災組織による共助の重要性について貴重な教訓を得ました。最近では、地震災害だけではなく、平成30年7月に起こった西日本豪雨災害や台風21号など風水害による被害も年々増加しており、地域の防災力の強化、充実の必要性が高まってきています。
市長は、令和2年度施政方針説明にて、自主防災組織の結成について、組織率100%を目指すと言われました。しかし、形だけの組織ができあがっても、自治会に情報が把握できない方の安否確認等はどうするのか、対応に苦慮しているところです。個人情報は、上手に使えば顔の見える関係づくりに役立ちます。お互いの顔や名前を知り合うことで信頼関係や支え合いが育ち、安心して暮らせる地域社会の実現につながります。個人情報の保護は必要ですが、過度の対応は、地域のつながりを弱くし、地域の活動の災害時の助け合いなどに支障を来します。個人情報は正確な管理を行うとともに、いざというときのため有効に活用することが必要です。自治会の運営のためには、会員情報の把握は欠かせないものと思います。
そこで、本年4月以降の情報提供に同意されない転入・転居者の状況についてお伺いいたします。
次に、地域活動への参加意識の低下とともに、自治会加入者及び参加者が減少している中、今後の自治会のあり方についてお伺いして、壇上からの質問を終わります。
○椎木伸一市長 南鶴洋志議員の御質問にお答えします。
まず、新型コロナウイルス感染症の第2波に備えた、自治会へのオンライン端末の導入についてお答えします。オンライン端末の導入に当たっては、垣内雄一議員の御質問でもお答えしたとおり、市内全域で光ファイバー網を使用できる環境を整備する必要があると考えます。本市においては、大川内地区、江内地区において光ファイバー網の整備が遅れている状況です。まずは情報通信格差解消に向け、未整備地区への光ファイバー網の整備やGIGAスクール構想の実現に向けて取り組んでまいります。御提案いただいたサービスについては、今後、情報通信環境が整えば活用できるものもあるかと思います。また、今後、コロナ禍に合わせて生活様式も大きく変わり、社会のあり方も大きく変容すると思われます。新たな需要が生まれることも考えられることから、社会情勢の変化に合わせて検討することも必要であり、将来に向けての大きな課題であると認識しています。
次に、行政事務連絡員の見直しにより、情報提供に同意されない転入・転居者の状況と、今後の自治会のあり方についてお答えします。
まず、自治会長への情報提供に同意されていない方の状況については、同意を求め始めた本年4月から5月末までの2カ月間で330世帯の転入・転居があり、このうち同意されなかった世帯は150世帯でした。年代別の傾向として、同意されない世帯が多いのは単身世帯の10代、30代、50代となっており、2人以上の世帯では全ての年代で同意されない世帯は少ない傾向にあります。
次に、今後の自治会のあり方についてお答えします。自治会は、地域活動を通して連帯感を深め、住みよい地域をつくっていくための最も身近なコミュニティ組織で、議員御披瀝いただいたように任意団体であることから、市が自治会加入について強制することは大変難しい課題であると認識しています。東日本大震災以降、自助・共助の重要性は特に認識されるようになりましたが、この共助の精神も、地縁団体である自治会によって育まれてきたものであると思います。しかしながら、近年、社会情勢が大きく変化する中で、仕事と家庭生活に追われ、地域行事に参加できない方が多いのも実状となっています。自治会加入者が減少している中ではありますが、地域の課題や実状は多様であり、その地域課題解決についても、また、いつ発生するかわからない災害時においても、自治会における役割は大きいものと認識しています。行政としても、地域に合った自治会運営ができるように、これまで同様に支援してまいります。
○議長(杉本尚喜議員) ここで申し上げます。南鶴洋志議員より書画カメラ使用の申し出がございました。よって、これを許可してあります。
○1番(南鶴洋志議員) 早速ですけど書画カメラの1番をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)壇上で申し上げた内容について、一応、図でお示しさせていただきました。ここ3、4カ月で、皆さん方もそうだと思うんですけれども、生活がさま変わりしました。私もスカイプとかZOOMとか使ってオンラインの会議に出席したり、今週の月曜日、火曜日も日本経済新聞主催の世界デジタルサミット2020というのがありまして、それのオンラインライブとかも見ました。かなり最初は抵抗があったんですけれども、やってみると、結構使えるね、便利だねというのがあります。したがいまして、こういったのを、先ほどお話もしたんですけれども、例えば買い物支援とかテイクアウト予約、乗合タクシーとか使えるのが多々、市役所との連携でできると思います。例えば、自治会で子ども会育成会が活動しているんですけれども、その中で読み聞かせを一緒にオンラインで見れて、かつ、そこで一緒に子ども会の行事をするとか、例えば壮年部の会合とかもあります。そういった中で介護の料理教室とかも一緒にすると、今までは現場に行って料理教室を見るという方、男性方というのはなかなかできないところがあるんですけれども、こういったオンラインで見れば、利用価値がかなり高まってくるのではないかなと思います。あと、オンライン診療についても、都心部ではオンラインで診療というのがありますので、これも徐々に地方に深まっていくと思いますので、ぜひ、先ほど垣内議員の質問でもありましたとおり、ネットの環境が整備されればこのような環境ができるんではないかと思いますので、進めていっていただければと思います。
そこで、先ほどの話の中で、いきいき自治会をできれば最初、利用者がなかなか勉強ができないコンピュータ-、パソコンに詳しくない方がいらっしゃるので、自治会の中でまとまって勉強し合うという話をしましたけれども、いきいき自治会数と高齢化率の推移について、よろしければ教えてください。
○椎木伸一市長 南鶴洋志議員におかれましては、自治会活動等、非常に熱心に、会長も含めて務めていただき、取り組んでいただいております。国道3号線沿いの花いっぱい運動とか、NPO法人と協力してひまわり等を相当数植えていただいておりまして、この場を借りて御礼を申し上げます。
いきいき自治会の数、あるいは高齢化率については政策経営部長のほうから答弁をさせます。
○冨田忍政策経営部長 平成29年度以降のいきいき自治会の認定数と高齢化率ということで申し上げます。平成29年度が40自治会で、高齢化率56.75%、平成30年度が同じく40自治会で57.96%、令和元年度が43自治会で57.7%、令和2年度が49自治会で57.68%となっております。
○1番(南鶴洋志議員) 御答弁いただいたように、徐々にふえていっているのがわかるかと思います。ここで、書画カメラの2番をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)これは、5月29日に公表の総務省が発表された通信利用動向調査の結果です。右端2つが、一番右端が80歳以上、その隣が70から79歳です。青で示しているのが令和元年度のインターネットの利用状況、パーセントであらわしていますけれども、これは都心部も含めての値なので、地方になると当然2割ほど下がるんではないかなと思います。徐々に上がってはきているんですけれど、前年度はかなり低い、70歳以上の方は利用されていないということがわかるかと思いますので、ぜひ、こういったのを公民館、自治会で学び合うということが大切なのかなというふうに思います。
時間もないので、1番については前向きに考えていただけるようでございますので、ぜひとも自治連とも交渉して、前向きに進んでいただければと思います。オンライン会議が実際話題になっているんですけれども、こういったのを含めれば、オンライン井戸端会議みたいなのが高齢者の中でできれば、本当に夢のような形でいけるのかなというふうに思っております。
1番は終わりまして、2番のほうに行きたいと思います。加入率の推移について、もしわかれば教えていただきたいんですけれども、お願いします。
○冨田忍政策経営部長 自治会加入率についてお答えいたします。
過去3年間で申し上げます。いずれも11月1日現在の数字で申し上げます。平成29年度が78.51%、平成30年度が77.45%、令和元年度が76.21%となっておりまして、この3年間で2.3%減少をしております。直近で申し上げますと、令和2年6月1日現在でございますが、75.25%になっています。
○1番(南鶴洋志議員) これは平均値なので、当然加入率が高いところもあれば低いところもあると思いますが、加入率の低いところの自治会を教えてもらえなければ校区だけでも結構です、教えてください。
○冨田忍政策経営部長 自治会ごとの加入率につきましては、今、手元に資料を持っておりませんので、後ほどお答えしたいと思います。(後日資料配付)
○1番(南鶴洋志議員) では、傾向的にどこの区が多いとか、どういった地域だから加入率が低いんだとかいうのはわからないですか。
○冨田忍政策経営部長 大まかに申し上げますと、アパート、マンションの立地が多い地域、そこについては加入率が低いというように感じております。
○1番(南鶴洋志議員) それでは、書画カメラの4番をお願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)まず、最初に市民生活課で、転居・入居された方が来られて手続をとるわけですけれども、一番最初にするのが住民異動届でございます。これのどこで識別するかというと、左下のところで自治会長への情報提供に承諾します、署名というところに書いていただくと、自治会長に情報提供をされるという仕組みになっています。
このやり方についてどうこう言うわけではございません、これは5枚つづりになっていて、必要な部署に回るというシステムなので、これについてはどうこう言うつもりはないんですけれども、この手続のやり方、住民異動届を書いてくださいということになるんですけれども、そのときにどのようなお話、説明をされているのかをお聞かせください。
○椎木伸一市長 転入届等の場合の自治会長への情報提供の意思の確認の仕方の具体については、市民部長のほうから答弁をさせます。
○揚松智幸市民部長 まず、この同意をいただく、いただかないというのは個人さんのあれがあるんですけれども、御同意があれば、当然そのまま自治会長さんに御案内をするということを言います。同意がない場合にも、ごみステーションの関係とかいろんなものがありますので、加入促進チラシと一緒に自治会長さんのお名前をお伝えしていると、連絡先をお伝えしているというような状況です。
○1番(南鶴洋志議員) こちらが、自治会の加入に関するアンケート調査集計結果というのが、昨年末に議員の方にも配られていると思います。昨年、自治連と市と共同で調査をされた結果なんですけれども、この中で問7で「自治会がどのような活動を行っているのか御存じですか」という質問がございます。「あまり知らない」「知らない」をあわせると69%、約7割の方がよくわかっていないというのがわかります。例えば、先ほどおっしゃったごみステーションのほうもそうなんですけれども、防犯灯についても市からの補助もあるんですけれども、維持管理というのは自治会がやっています。こういったところも、多分、一般の住民の方は御存じないと思うんですけれども、そういったところも、慌ただしい手続の最中なのでなかなかその説明ができないんですけれども、もうちょっとした工夫というのはできないかをお伺いいたします。
○揚松智幸市民部長 確かにおっしゃるとおり、いろんなことが説明をできればいいんでしょうけれども、今の現状況でどういう活動をされているかというのは、もちろん自治会でも違いますでしょうし一概には言えないと思うんですが、自治会さんによっては、独自につくられたチラシなどもこちらに持ち込んであることもあります。そういうのは促進チラシと一緒に送っておりますので、また、確かに防犯灯であるとかそういったものは、関係部署とも協議して、簡単なものがつくれるかどうかは検討させてください。
○1番(南鶴洋志議員) ありがとうございます。いずれにせよ、情報提供されないという方は自治会長が把握できないまま、その地域に住まれているわけです。その中で、こちらから自治会加入へのお願いをするわけですけれども、いつ入ったかというのがなかなか識別判断ができない。一軒家だったらどうにかわかるんですけれども、アパートに住んでいらっしゃる方というのは非常に判断がしづらいところがあるんですけれども、その辺はどのように思われていますか。
○椎木伸一市長 非常に難しい課題だと思います。自治会長さんの立場から言うと、詳細に知って自治会としての手助け、あるいは自治会に加入してもらうことにより地域の活性化を図りたいということであります。先ほど申しましたように、単身世帯の方が非常に加入に同意されない率が高いという傾向もあります。政策経営部長からありましたように、アパート、マンションが多い地区が加入が低い状況もあるというようなこともあります。自治会は任意団体であるというようなこともありますけれども、本来ならば、皆さんにそういった、南鶴議員がおっしゃったようないろいろな自治会に入ることによって、あるいは自治会活動がどういったものだと、どういったことで市民の生活に貢献いただいているんだというようなことをよく知っていただいて、確認していただく、同意していただくということが非常に大切なことではないかなというふうに思っております。そういったことが確認できない状況にあるということは大変残念なことでありますけれども、先ほど申しましたように、私どもとしても自治会活動がよりすばらしい活動となるように支援していきたいと思っておりまして、同意いただけるような工夫ができるものについては取り組んでいきたいと思っております。
○1番(南鶴洋志議員) 先ほど登壇したときに質問したんですけれども、自主防災組織について、自治会に加入されてない方、加入されている方、自主防災組織には自治会に加入されている方が動くわけですけれども、実際に加入されていない方、安否情報の確認とかそういったのは、もう切り分けるべきなんでしょうか。もし、市長が市長を退かれて、もしかしたら自治会長になるかもしれません、そういった場合にどのようにこの難局は乗り越えられるかをお伺いします。
○椎木伸一市長 自治会長になった立場で考えてみますと、今、自主防災組織もほぼ100%になっておりますけれども、冒頭おっしゃったように、形式だけの自主防災組織ではいけないわけでありまして、地域内に居住されていらっしゃる、いわゆる災害弱者、高齢者でありますとか、体の御不自由な方、そういった方々をつぶさに把握し、誰がどのように対応するか、昼間、夜間、そういったものを取り決めておくことが非常に重要なことであろうと思います。そのような中で、そういった方の確認がまずは必要であると思っておりますけれども、その自治会に入っているか、いないかとか、詳細のことについてはくらし安心課長のほうから補足があれば答弁をさせます。
○戸﨑基夫くらし安心課長 ただいま自主防災組織の御質問が出ましたので、お答えいたします。
現在、自主防災の組織率が97.42%ということで確認をしているところでございます。市の目標として100%というところがございますので、今後も鋭意、自主防災組織率の向上に向けて進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○1番(南鶴洋志議員) それでは、書画カメラの5番お願いします。(議場内ディスプレーへの資料表示)これはコロナ禍で自治会に関する記事をちょっと集めてきました。1つは、南日本新聞の記事と東洋経済オンラインという記事の内容です。いずれにしても、どちらも、こんなコロナ禍であっても自治会というのは大切なんだよというのを言っていたかと思います。
自治会ではまだまだ、きょう申し上げた以外にもいろんな課題があります。鹿児島市では、今回触れることをしませんでしたけれども、自治会が所有、管理する防犯灯の損害賠償責任保険に公費で加入するということが本年度から決まっております。この問題についても、本市でもぜひ取り組んでいきたいというふうに感じておりますので、ぜひよろしくお願いします。
これで、私の質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
○議長(杉本尚喜議員) 以上で、本日の一般質問を終結いたします。
-------------------------------------------------------
△ 延 会
○議長(杉本尚喜議員) お諮りいたします。本日の会議はこれで延会したいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(杉本尚喜議員) 御異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会いたします。
第3日の会議は、あす12日に開きます。御苦労様でした。
午後2時00分 延 会
-------------------------------------------------------
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
出水市議会議長
出水市議会議員
出水市議会議員
出水市議会議員
- 136 -